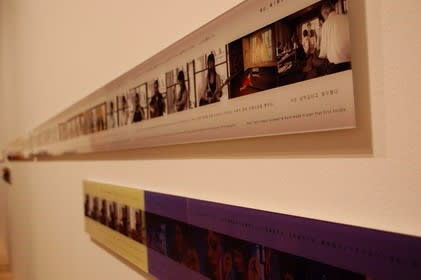遊歩道さんのブログに触発されて、
ワーグナー『ニーベルングの指環』全曲のCDを買ってしまいました。
クラシック歴は永いですがオペラはどうも不得手で、なかなか手を出せませんでした。
しかし『ニーベルングの指環』は、やはり「クラシック音楽」の一つの頂点であり、
「いずれ必ず」という思いもありました。
昔はCDにして12~14枚、時間にして14~15時間、
という長大さ(とCDの値段)に恐れをなしていましたが・・・。
でも、今やハイドン先生の交響曲全集と弦楽四重奏曲全集を制覇?し、
コンサートでもバッハ大先生のマタイ受難曲、マーラーの交響曲第3番を経験したので
もはや怖いものなし!
・・・怖いものなしですが、一応、廉価版の一番安い全集を買いました。
ギュンター・ノイホルト指揮
バーデン州立歌劇場管弦楽団
(1993~95年のライブ)
CD14枚組で、値段は2,290円です。
1枚あたり163円。もう100円ショップの世界です。
こんな値段で「クラシック音楽の頂点」を聴いていいのでしょうか?
色々なレビューを見ますと「値段の割には・・・」という評と
「聴く価値なし」という評が混在していますね。
まあ超初心者の私にはどちらでもあまり関係ないのですが・・・。
併せて、ショルティ指揮の「ライトモティーフ集」(2枚組)も買いました。
もともと同指揮者の「指環」(世界初の全曲スタジオ録音!)に「おまけ」?として
ついていたものの分売のようです。
マーラーの交響曲第10番の補筆版で知られる、デリック・クックが監修しています。
『ニーベルングの指環』は「ライトモティーフ」によって組み立てられた「言語」のようですが、
難しいことは考えず、石川遼君おススメの「スピードラーニング」方式で
とりあえず何度も聴き流してみようと思っています。
追記
これをエントリー中に1枚目のCD(第2幕まで)を聴き終わりました。
完全にBGMと化していました。しかしこれが「スピードラーニング」。
ある日突然、会話?が聴き取れるようになる・・・
ワーグナー『ニーベルングの指環』全曲のCDを買ってしまいました。
クラシック歴は永いですがオペラはどうも不得手で、なかなか手を出せませんでした。
しかし『ニーベルングの指環』は、やはり「クラシック音楽」の一つの頂点であり、
「いずれ必ず」という思いもありました。
昔はCDにして12~14枚、時間にして14~15時間、
という長大さ(とCDの値段)に恐れをなしていましたが・・・。
でも、今やハイドン先生の交響曲全集と弦楽四重奏曲全集を制覇?し、
コンサートでもバッハ大先生のマタイ受難曲、マーラーの交響曲第3番を経験したので
もはや怖いものなし!
・・・怖いものなしですが、一応、廉価版の一番安い全集を買いました。
ギュンター・ノイホルト指揮
バーデン州立歌劇場管弦楽団
(1993~95年のライブ)
CD14枚組で、値段は2,290円です。
1枚あたり163円。もう100円ショップの世界です。
こんな値段で「クラシック音楽の頂点」を聴いていいのでしょうか?
色々なレビューを見ますと「値段の割には・・・」という評と
「聴く価値なし」という評が混在していますね。
まあ超初心者の私にはどちらでもあまり関係ないのですが・・・。
併せて、ショルティ指揮の「ライトモティーフ集」(2枚組)も買いました。
もともと同指揮者の「指環」(世界初の全曲スタジオ録音!)に「おまけ」?として
ついていたものの分売のようです。
マーラーの交響曲第10番の補筆版で知られる、デリック・クックが監修しています。
『ニーベルングの指環』は「ライトモティーフ」によって組み立てられた「言語」のようですが、
難しいことは考えず、石川遼君おススメの「スピードラーニング」方式で
とりあえず何度も聴き流してみようと思っています。
追記
これをエントリー中に1枚目のCD(第2幕まで)を聴き終わりました。
完全にBGMと化していました。しかしこれが「スピードラーニング」。
ある日突然、会話?が聴き取れるようになる・・・