先日、近所の古書店Y書房さんに久々にお邪魔して、ご主人と本のことや働き方のことなど、たっぷりお話しすることができました。
そのときの盛り上がった話題のひとつが、これまで時代を築いてきた地域の郷土史家が相次いで亡くなると、どこの家でもその貴重な蔵書の処分に困っている例が最近とても多いという話でした。
本来であれば、このときまず第一に考えるのは、図書館への寄贈です。第二に、古書店への売却、そして第三に、同業者など同じ分野の人への譲渡などが考えられますが、このところこのどれもが、なかなかスムーズにはおこないえない傾向にあります。
第一の図書館への寄贈ですが、残念ながら多くの公共図書館が単純には寄贈図書を歓迎しない傾向があります。タダで寄贈されるものであっても、その登録・管理の手間を考えると、本来はそんなことが理由になるはずもない価値あるものであっても、必ずしも喜んでは受け入れてもらえないのです。
公共図書館が、地域固有の情報センターとしての役割を発揮する方向に、行政機構のなかの位置づけができていない例が現状ではとても多いのです。
第二の古書店への売却ですが、これも同様に古書店もその土地固有の古書を力を入れて扱える店が激減してきています。残念ながら、チリ紙交換同様の処分しか出来ない場合が多くなっているのです。
ローカルな情報は、その土地を離れてしまうと、どんなに価値あるものでも結局市場価値はなくなってしまうからです。
第三の場合は、私的贈与や売却の問題になるのですが、ある郷土史家は、個人的に譲り受けてしまうと、あとで遺族との間で問題が発生することがあるので、絶対に受けないようにしていると言っていました。その理由は、邪魔になっているときは無料でも引き取ってもらいたいものですが、あとになって価値がわかったりしたものが出ると、遺族との間で大きなトラブルに発展してしまうことがあるからです。
ここでこれらの個々の問題に深入りはしませんが、いづれにしても価値ある個人蔵書をその本人以外が価値を認めて引き継ぐことは、極めて多くの困難がともなうということです。
この厳しい現実をよくみると、これは特殊な蔵書家に限った問題ではなくて、元をたどると本という情報のもつ性格そのものが、情報の価値としては本来、公共性の高い資産であるはずなのですが、現実の価値となると結局はその本の所有者個人の固有の文脈でこそ価値があるもので、その所有者の視点を離れても普遍的価値をもつ情報などというものは、そうあるものではないということです。
いや、すぐれた本であれば決してそんなことはないとも言われそうですが、つきつめるとこれは、蔵書というまとまりでなく1冊の本の価値で考えた場合にもこれは言えると思います。
かつて私は、職場でこの本は必要だから会社のお金で買って共有してはどうかと、何度か予算をもらって必要図書を購入したことがありました。
ところが、その後の実態は、その本の価値がわかる人は、たいてい自分の金で買う、あるいは自分で選ぶ。また、価値のわからないひとは、無料であっても読まない。
だからこそ、そこを橋渡しする媒介者の仕事が確かに大事なのですが、上記の基本は変わりません。
ここで気づいたのです。
機会を増やすために、より多くの蔵書をもち、また図書館などで共有できる環境づくりは不可欠で重要であることに異論はありませんが、より重要で力を入れなければならないのは、与えられる環境を使いこなし使い倒すような個人の側の問題意識や課題に対する個人の情熱のようなものこそ大事に育てられないと、どんなに豊な環境が与えられてもそこに生命が吹き込まれることはないとうことです。
その生命の本質を見ればみるほど、それは「公共」的価値よりも、まず「パーソナル」なものでなければならないということです。
かつての工業化社会を突き進む大量生産、大量消費の時代では、このパーソナルな価値は邪魔もの扱いにされることの方が圧倒的に多く、より均質なものでのレベルアップこそが求められていました。
でも、そうした時代はもう過去のものになりだしています。
総じて効率の悪い職人的仕事は、時代の流れについていけない過去のものとして見捨てられるのが常ですが、いま、ほんとうの価値の実現が問われる時代になりはじめると、製品の品質を高めることは不可欠ですが、その先にさらにパーソナルな体験や価値が積み重ならないと、ほんとうの価値実現には至り得ないことがみえてきたのです。
この意味で、さきの個人蔵書の処分という問題も、蔵書のもつ普遍的価値を保持するための図書館への寄贈や市場への売却、あるいは特定個人への譲渡も可能であれば必要と認めながらも、本筋では他人へは容易に伝え難いそのひと固有の文脈をともなってこそ、その本(蔵書)の価値は貫徹することができるのではないかということです。

ここから私は、
かつてはアウトサイダーであることの表明にしか聞こえなかった「オレの仕事は俺一代」という言葉が、アウトサイダー側の言葉ではなく、人の仕事を貫徹するならば、むしろ普遍的に求められる言葉なのではないかと思うようになりました。
一代限りで終わるような仕事は、成功者とはいえないようなイメージもありますが、ほんとうにそうでしょうか。
考えてみれば、よく商売は3代もつことは少ない、3代目がつぶすなどと言われますが、これは商売に限らずどんな分野でも共通していえることです。
3代以上にわたって安定した継続をはたせている例は、ごく一部の老舗企業や名家以外では、そもそも徳川家と天皇家くらいのものといっても過言ではないほど、例は少なく現実にはマレなことです。
だからこそ、安易な継承に期待することよりも、そもそも良い仕事や生き方をすればするほど、その仕事はそのひと一代であるべきだとはじめから覚悟すべきなのではないでしょうか。
2代目、3代目がつぶす以前に、創業者の破綻や失敗の数は富士山の裾野の広がりどころか、圧倒的な量の屍を累々と積み重ねているものです。
また、仮に末永く事業を継承することを考えた場合でも、それぞれの環境や時流にあった活動をその時代を生きる者として一代限りの覚悟と努力をすることこそが重要なのではないかと思うのです。
もはや時代は、一代限りの仕事や生き方を追求するほうが、付加価値も増し、結果的に事業継承だけに依存しない生命の継続がはかれる社会になりはじめているのだと私は思います。
自分の蔵書のゆくえ、自分の仕事の遠い将来のゆくえを考えると、なんとも儚い想いにもかられますが、先に「オレの仕事はオレ一代」と腹をくくると、自信ををもって自らの人生をより深く掘り下げていける気がします。
上記写真『俺の仕事は俺一代』は、藤原集落で暮す人々の生きざまをまとめた素晴らしい本で、私のお気に入りの1冊(絶版)ですが、このような視点で振りかえってみると、あらためてこれからの時代にも通用する評価ができる大事な本にみえてきました。













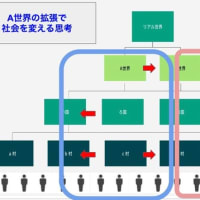

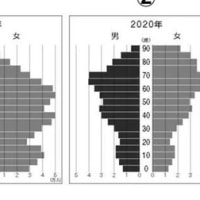











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます