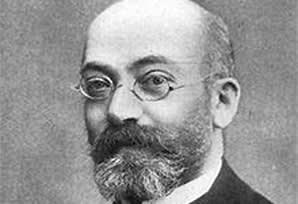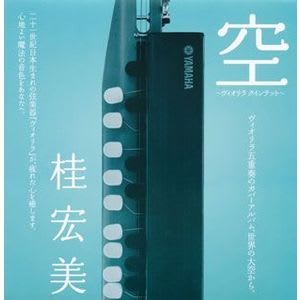2025年も3カ月経過。この2025年は何かと区切りの年のよう。
ラジオ放送が始まって100年
終戦(敗戦)から80年
オウムサリン事件から30年
You Tube 設立から20年・・・
米国の動画サイトYou Tubeの出現はネット社会の中でも大きな影響をポポロ(人びと)に与えたと思う。
私は比較的早くYou Tubeのアカウント登録をし動画のアップを行った。
SANYOのXacti=写真=というハンディ動画カメラを使って演奏会や高校野球などをアップした。編集機能もそこそこで、単純に撮ったものを載せていただけ。個人情報の承諾なども気にせず良き時代だった。それでいて今は、自撮りで動画を頻繁に発信する人も多い。「You Tuber」という言葉も職業も無かった。
この4月、ピカピカの小学一年生になる孫が、一人でYou Tubeを器用に検索しているのには驚いた。いくつかのひらがな入力で、マンガアニメを楽しんでいる。この子たちの将来はどんな社会になるのだろう。横で見ていてたのもしい反面、ハラハラもする。
これからは情報リテラシー教育をしっかりしないと、と強く思う。
25年度から中学校で使われる道徳の教科書に、人気ユーチューバーのヒカキンさんが登場するという。どんな内容なのか見てみたいものだ。
ラジオ放送が始まって100年
終戦(敗戦)から80年
オウムサリン事件から30年
You Tube 設立から20年・・・
米国の動画サイトYou Tubeの出現はネット社会の中でも大きな影響をポポロ(人びと)に与えたと思う。
私は比較的早くYou Tubeのアカウント登録をし動画のアップを行った。
SANYOのXacti=写真=というハンディ動画カメラを使って演奏会や高校野球などをアップした。編集機能もそこそこで、単純に撮ったものを載せていただけ。個人情報の承諾なども気にせず良き時代だった。それでいて今は、自撮りで動画を頻繁に発信する人も多い。「You Tuber」という言葉も職業も無かった。
この4月、ピカピカの小学一年生になる孫が、一人でYou Tubeを器用に検索しているのには驚いた。いくつかのひらがな入力で、マンガアニメを楽しんでいる。この子たちの将来はどんな社会になるのだろう。横で見ていてたのもしい反面、ハラハラもする。
これからは情報リテラシー教育をしっかりしないと、と強く思う。
25年度から中学校で使われる道徳の教科書に、人気ユーチューバーのヒカキンさんが登場するという。どんな内容なのか見てみたいものだ。
太田高校応援団(校歌) in 前橋