ずっと昔に投稿したブログ「五味康祐」さんのクラシックベスト20」だが、現在でも記事へのアクセスがちらほら垣間見える。
この稀代の音楽愛好家に対していまだに関心があることが興味深いが、このベスト20にはバッハの作品がやたらに多いことにお気づきだろうか。
たとえば「平均率クラヴィーア曲集」をはじめ「無伴奏チェロソナタ」「3つのピアノのためのコンツェルト」「パルティータ」などがそうで、しかも大半が上位に食い込んでいる。(ちなみに第1位はオペラ「魔笛」である! 五味さんの耳を信用する第一の理由である)
実を言うと、クラシック歴およそ60年以上になろうかというのにバッハの音楽にはいまだに馴染めないままでいる。モーツァルトやベートーヴェンの音楽はスッと胸に入ってくるのに、バッハだけは手こずっているというか、もう縁がないととうの昔に諦めの境地に入っている。
自分だけかもしれないがバッハの音楽には同じクラシックの中でも孤高というのか、ひときわ高い山を感じる。したがって「バッハが好きです」という音楽愛好家には「この人は本物だ!」と始めから一目も二目も置いてしまう(笑)。
こう書いてきて何の脈絡もなしにふっと思ったのが、「バッハ」と「ドストエフスキー」は似たような存在ではなかろうか。
片や音楽界の雄、片や文学界の雄である。
ドストエフスキーの文学も容易に人を寄せ付けない。「カラマーゾフの兄弟」「罪と罰」「白痴」「悪霊」などやたらに長編だし、とっかかるだけでも億劫さが先に立つ。
両者ともにその分野で絶対的な存在感を誇り、何回もの試聴、精読に耐えうる内容とともに、後世に与えた影響も測り知れない。
バッハは周知のとおり「音楽の父」と称されているし、ドストエフスキーに至っては「20世紀以降の文学はすべてドストエフスキーの肩に乗っている」(「加賀乙彦」氏)と称されているほどだし、「世の中には二種類の人間がいます。カラマーゾフの兄弟を読んだことのある人と読んだことのない人です。」と、宣うたのは「村上春樹」さんだ。
ただし、ドストエフスキーはその気になれば何とか付いていけそうな気もするが、バッハだけはどうも苦手意識が先に立つ。つまり理屈を抜きにして「線香臭い」のがそもそも嫌っ!(笑)。
こういう ”ややっこしい” バッハの音楽についてモーツァルトの音楽と比較することで分かりやすく解説してくれた本がある。
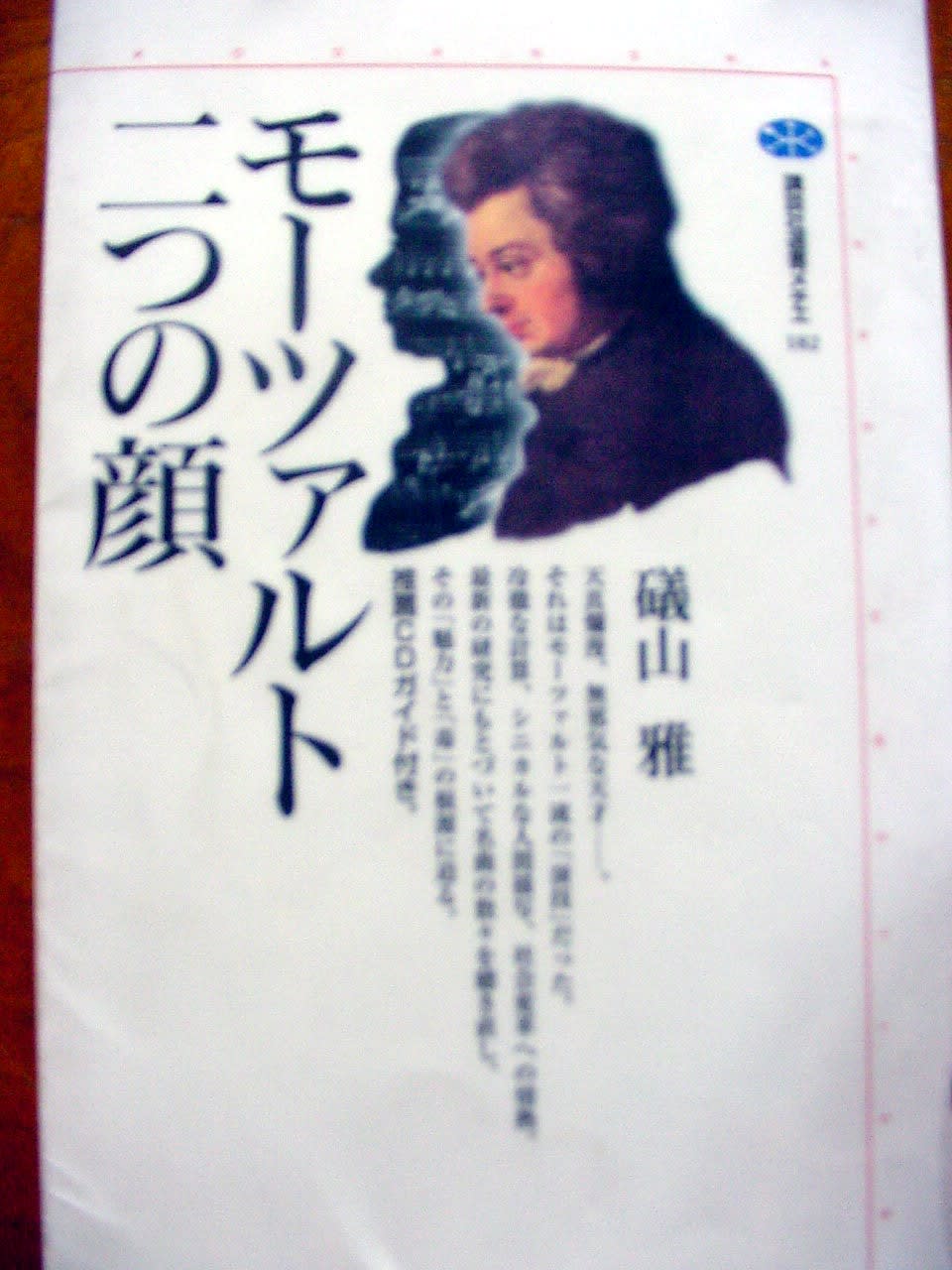
著者の磯山雅氏(1946~)はバッハ研究を第一とし、モーツァルトの音楽を愛される学識経験者。
本書の第9章「モーツァルトとバッハ」で、イメージ的な私見とわざわざことわった上で両者の音楽の本質的な違いについて、独自の考察が展開されている。
以下、要約。
☆ モーツァルトのダンディズム
バッハは真面目かつ常に正攻法で誠実に問題に対処する。一方、モーツァルトは深刻さが嫌いで茶化すのが大好き。
いわば問題をシリアスに捉えてはいるのだがそう見られるのを好まないダンディズムがある。
※ 私見だが、モーツァルトの音楽にはひとしきり悲しげでシリアスな旋律が続いたと思ったら突然転調して軽快な音楽に変化することが度々あって、たしかピアニストの「青柳いずみ子」さんだったか「な~んちゃって音楽」と言ってたのを思い出す。ただしオペラは例外~。
☆ 神と対峙するバッハ
バッハの音楽には厳然たる存在の神が確立されており、音楽を通じて問いかけ、呼びかけ、懺悔し、帰依している。「マタイ受難曲」には神の慈愛が流れ出てくるような錯覚を抱く。
モーツァルトにはこうした形での神の観念が確立していない。その音楽の本質は飛翔であり、疾走である。神的というより霊的と呼んだ方がよく、善の霊、悪の霊が倫理的規範を超えて戯れ迅速に入れ替わるのがモーツァルトの世界。
以上、「ごもっとも!」という以外の言葉を持ち合わせないほどの的確なご指摘だと思うが、バッハの音楽はどちらかといえば精神的に ”タフ” な人向きといえそうで、これはドストエフスキーの文学にしてもしかり。
道理で、両者ともに自分のような ”ヤワ” な人間を簡単に受け付けてくれないはずだとイヤでも納得させられてしまいました(笑)。
クリックをお願いね →
「クラシック音楽がすーっとわかるピアノ音楽入門」(山本一太著、講談社刊)を読んでいたところ、「ベートーヴェン晩年のピアノ・ソナタ」について次のような記述(95~96頁)があった。

~以下引用~
『ベートーヴェンは、1820年から22年にかけて「第30番作品109」、「第31番作品110」、「第32番作品111」のピアノ・ソナタを書き、これらがこのジャンルの最後の作品となった。
この三曲をお聴きになったことのある人なら、これが現世を突き抜けた新しい境地で鳴り響く音楽だとして理解していただけると思う。
とにかくこういう超越的な音楽の神々しさを適切に美しく語ることは、少なくとも著者には不可能なので、簡単なメモ程度の文章でご容赦ください。 ベートーヴェンの晩年の音楽の特徴として、饒舌よりは簡潔、エネルギーの放射よりは極度の内向性ということが挙げられる。
簡潔さの極致は「作品111」でご存知のようにこの作品は序奏を伴った堂々たるアレグロと感動的なアダージョの変奏曲の二つの楽章しか持っていない。ベートーヴェンは、これ以上何も付け加えることなしに、言うべきことを言い尽くしたと考えたのだろう。
こんなに性格の異なる二つの楽章を、何というか、ただぶっきらぼうに並べて、なおかつ見事なまでの統一性を達成しているというのは、控え目にいっても奇跡に類することだと思う。
もっとも、この曲を演奏会で聴くと、何といっても第二楽章の言語に絶する変奏曲が私の胸をしめつけるので、聴いた後は、第一楽章の音楽がはるかかなたの出来事であったかのような気分になることも事実だが。』
以上のように非常に抑制のきいた控え目な表現に大いに親近感を持ったのだが、「音楽の神々しさを適切に美しく語ることは不可能」という言葉に、ふと憶い出したのがずっと昔に読んだ小林秀雄氏(評論家)の文章。
「美しいものは諸君を黙らせます。美には、人を沈黙させる力があるのです。これが美の持つ根本の力であり、根本の性質です。」(「美を求める心」より)
いささか堅苦しくなったが・・(笑)、自分も「作品111」についてまったく著者の山本氏と同様の感想のもと、この第二楽章こそ数あるクラシック音楽の作品の中で「人を黙らせる力」にかけては一番ではなかろうかとの想いは20代の頃から今日まで一貫して変わらない。
とはいえ、ベートーヴェン自身がピアノの名手だったせいか、ハイドンやモーツァルトの作品よりも技術的には格段にむずかしくなっているそうで、標記の本では「最高音と最低音との幅がドンドン大きくなっている」「高い音と低い音を同時に鳴らす傾向が目立つ」といった具合。
言い換えるとピアニストにとっても弾きこなすのが大変な難曲というわけで、聴く側にとっては芸術家のテクニックと資質を試すのにもってこいの作品ともいえる。
以前のブログでこの「ソナタ作品111」について手持ちのCD8セットについて3回に分けて聴き比べをしたことがある。
そのときの個人的なお気に入りの順番といえば次のとおり。
1 バックハウス 2 リヒテル 3 内田光子 4 アラウ 5 ケンプ 6 ミケラジェリ 7 ブレンデル 8 グールド

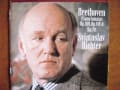

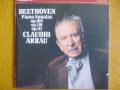

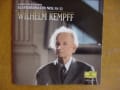


ちなみに、天才の名にふさわしいピアニストのグールドがこのベートーヴェンの至高のソナタともいえる作品でドンジリというのはちょっと意外・・。
しかし、これは自分ばかりでなく世評においてもこの演奏に限ってあまり芳しくない評価が横行しているのだが、その原因について音楽好きの仲間が面白いことを言っていた。
『グールドはすべての作品を演奏するにあたって、いったん全体をバラバラに分解して自分なりに咀嚼し、そして見事に再構築して自分の色に染め上げて演奏する。
だが、この簡潔にして完全無欠の構成を持った「作品111」についてはどうにも分解のしようがなくて結局、彼独自の色彩を出せなかったのではないだろうか。』
グールドの演奏に常に彼独自の句読点を持った個性的な文章を感じるのは自分だけではないと思うが、この「作品111」にはそれが感じられないので、この指摘はかなり的(まと)を射たものではないかと思っている。
天才ともいえる演奏家がどんなにチャレンジしても分解することすら許さない、いわば「付け入る隙(すき)をまったく与えない」完璧な作品を創っていたベートーヴェンの晩年はやっぱり凄いと思う。
クリックをお願いね → 
我が家では「好きな音楽」を「いい音」で聴きたい一心なので「音楽とオーディオ」がおおよそ一体化している積りだが、いったい「いい音って何?」と考えさせられたのがこの本だ。

著者は「片山杜秀」(かたやま もりひで)氏。巻末の経歴欄によると1963年生まれで現在、慶應義塾大学法学部教授。
過去に「音盤考現学」「音盤博物誌」「クラシック迷宮図書館(正・続)」などの著書があり、「吉田秀和賞」をはじめ「サントリー学芸賞」「司馬遼太郎賞」など数々の賞を受賞されている。
本書では様々な作曲家や演奏家について取り上げている。たとえば
1 バッハ 精緻な平等という夢の担い手
2 モーツァルト 寄る辺なき不安からの疾走
3 ショパン メロドラマと“遠距離思慕”
4 ワーグナー フォルクからの世界統合
5 マーラー 童謡・音響・カオス
6 フルトヴェングラー ディオニュソスの加速と減速
7 カラヤン サウンドの覇権主義
8 カルロス クライバー 生動する無
9 グレン・グールド 線の変容
といった具合。
この中で特に興味を惹かれたのが「フルトヴェングラー」と「グレン・グールド」の項目だった。
前者では「音は悪くてかまわない」と、小見出しがあって次のような記述があった。(137頁)
「1970年代以降、マーラーの人気を押し上げた要因の一つは音響機器の発展があずかって大きいが、フルトヴェングラーに限っては解像度の低い音、つまり『音がダンゴになって』聴こえることが重要だ。
フルトヴェングラーの求めていたサウンドは、解析可能な音ではなくて分離不能な有機的な音、いわばオーケストラのすべての楽器が溶け合って、一つの音の塊りとなって聴こえる、いわばドイツの森のような鬱蒼としたサウンドだ。したがって彼にはSP時代の音質が合っている。」
これはオーディオ的にみて随分興味のある話で、そういえば明晰な音を出すのが得意な我が家の「AXIOM80」でフルトヴェングラーをまったく聴く気になれないのもそういうところに原因がありそうだ・・。
通常「いい音」とされているのは、「楽器の音がそれらしく鳴ってくれて透明感や分解能に優れ、なおかつ奥行き感のある音」で、いわば「解析的な音」が通り相場だが、指揮者や演奏家によっては、そういう音が必ずしもベストとは限らないわけで、そういう意味ではその昔、中低音域の「ぼんやりした音」が不満で遠ざけたあの「スピーカー」も、逆に捨てがたい味があったのかもしれないとちょっぴり反省(笑)~。
ずっと以前のブログで村上春樹さんの「バイロイト音楽祭」の試聴記を投稿したことがあるが、その会場ではオーケストラ・ピットが沈み込んでおり、その音が大きな壁に反響して「音が大きな一つの塊のようになって響く」とあったのを思い出した。
そういえばフルトヴェングラーが指揮したあの感動的な「第九」(バイロイト祝祭管弦楽団)がまさしくそういう音で、こういう「鬱蒼とした音の塊」からしか伝わってこない音楽があることも事実で「いい音って何?」、改めて考えさせられる。
次いで、グールド論についても興味深かった。
稀代の名ピアニスト「グレン・グールド」(故人、カナダ)が、ある時期からコンサートのライブ演奏をいっさい放棄してスタジオ録音だけに専念したのは有名な話でその理由については諸説紛々だが、本書ではまったく異なる視点からの指摘がなされており、まさに「眼からウロコ」だった。
まず、これまでのコンサートからのドロップアウトの通説はこうだ。
☆ グールドは潔癖症で衛生面からいってもいろんなお客さんが溜まって雑菌の洪水みたいな空間のコンサート・ホールには耐えられなかった。
☆ 聴衆からのプレッシャーに弱かった。
☆ 極めて繊細な神経の持ち主で、ライブ演奏のときにピアノを弾くときの椅子の高さにこだわり、何とその調整に30分以上もかけたために聴衆があきれ返ったという伝説があるほどで、ライブには絶対に向かないタイプ。
そして、本書ではそれとは別に次のような論が展開されている。(188頁)
「グールドによると、音楽というのは構造や仕掛けを徹底的に理解し、しゃぶり尽くして、初めて弾いた、聴いたということになる。
たとえばゴールドベルク変奏曲の第七変奏はどうなっているか、第八変奏は、第九変奏はとなると、それは生演奏で1回きいたくらいではとうてい分かるわけがない。たいていの(コンサートの)お客さんは付いてこられないはず。
したがって、ライブは虚しいと感じた。よい演奏をよい録音で繰り返し聴く、それ以外に実のある音楽の実のある鑑賞は成立しないし、ありえない。」
以上のとおりだが、40年以上にわたってグールドを聴いてきたので “いかにも” と思った。
「音楽は生演奏に限る・・、オーディオなんて興味がない。」という方をちょくちょく見聞するが、ほんとうの「音楽好き」なんだろうか・・。
さらにオーディオ的に興味のある話が続く。
「その辺の趣味はグールドのピアノの響きについてもつながってくる。線的動きを精緻に聴かせたいのだから、いかにもピアノらしい残響の豊かな、つまりよく鳴るピアノは好みじゃない。チェンバロっぽい、カチャカチャ鳴るようなものが好きだった。線の絡み合いとかメロディや動機というものは響きが豊かだと残響に覆われてつかまえにくくなる。」といった具合。
グールドが「スタンウェイ」ではなくて、主に「ヤマハ」のピアノを使っていたとされる理由もこれで納得がいくが、響きの多いオーディオ・システムはたしかに心地よい面があるが、その一方、音の分解能の面からするとデメリットになるのも愛好家ならお分かりだろう。
結局、こういうことからすると「いい音」といっても実に様々で指揮者や演奏家のスタイルによって無数に存在していることになる・・、さらには個人ごとの好みも加わってくるのでもう無限大といっていい。
世の中にはピンからキリまで様々なオーディオ・システムがあるが、高級とか低級の区分なくどんなシステムだってドンピシャリと当てはまる音楽ソースがありそうなのが何だか楽しくなる、とはいえ、その一方では何となく虚しい気持ちになるのはいったいどうしたことか・・(笑)。 
クリックをお願いね → 

図書館の「新刊コーナー」でたまたま見つけたのが「交響曲名盤鑑定百科」という本。
「交響曲」でいちばん好きなのは「第39番K543」(モーツァルト)なのでどういう鑑定をしているのか、真っ先に目を通してみたところガッカリ・・、肝心の「第4楽章」に言及していない。
50年以上も前に読んだ「モーツァルト」(小林秀雄著「無私の精神」所蔵)では、この4楽章についてこう書かれている。
「部屋の窓から明け方の空に赤く染まった小さな雲の切れ切れが動いているのが見える。まるで「連なった♪」のような形をしているとふと思った。
39番のシンフォニーの最後の全楽章が、このささやかな16分音符の不安定な集まりを支点とした梃子(てこ)の上で、奇跡のようにゆらめく様はモーツァルトが好きな人ならだれでも知っている」
以上のような表現だが、この「揺らぎ」こそモーツァルトの音楽の真骨頂なのに、これに触れないなんて音楽評論家としてあるまじき行為だと思うよ~。
腹が立ったので、もう読まずに返却することにした(笑)。
もう一冊・・。
「宗教音楽の手引き」に目を通していたら、次のような箇所があった。(60頁)。
「クリスマスが近づいてきました。一時代前の日本ではクリスマスというと顔を真っ赤にして酔っ払ったご機嫌の紳士がケーキの箱をぶらさげて きよしこの夜 を歌いながら千鳥足で歩く姿をよく見かけたものでした。
それでも普段キリスト教に関心を持たない日本人が年に一度でもキリストの誕生を祝う気持ちになるならそれはそれでいいことだと思っておりましたが、どうも話はそう簡単ではなかったようです。
その頃たまたまテレビを見ておりましたところ、若い芸能人たちが「連想ゲーム」をしていました。「クリスマス」という題を出されて、それぞれ「プレゼント」「シャンパン」「パーティ」などと言い合っています。その中で一人だけ気の利いた若者が「キリスト」と言ったとたん「バカァー、お前、何言ってんだョー」「何の関係があるんだよョー」と一斉にののしられ、当人も自信をなくして「アア、そうか」と引き下がってしまったのです。
なるほど、これが日本の現実かとわたくしはしばらく考え込んでしまいました。」
そして、各国のクリスマスの祝い方に移り「アメリカは商業的」「ヨーロッパは地味で静かで、フランスは聖夜のミサが秘かに捧げられ教会堂から流れ出る鐘の音がいかにもそれらしい雰囲気を醸し出す、もっとも好ましいのはドイツで質実剛健で浮かれ上がったところが無く堅実で素朴です」といった具合。
ブログ主は「クリスマス」に限らず、外国の風習を安易にとり入れる日本独特の浮かれ方について、苦々しく思っているうちの一人です。
あっ、そうそう、ふと思い出した・・、何かの雑誌に書いてあったことだが、「イブともなると若者たちで都会のラブホテルが満員になる、聖なる夜をみだらな性欲で汚さないで欲しいと外国人が嘆いていた」というお話。アハハ、と笑い話で済ましていいのかどうか・・。
皆さまはどう思われますか?
さて、本論に移ろう。
宗教曲といえば死者の霊魂を天国に送る「レクイエム」、正式には「死者のためのミサ曲」に代表される。日本でいえばお坊さんの念仏みたいなものですかね~。
本書では「レクイエム」の代表曲として「ガブリエル・フォーレ」と「モーツァルト」が挙げてあったが、まったく異論なし~、「ヴェルディを忘れちゃいかん!」と怒り狂う方がいらっしゃるかもねえ(笑)。
前者には「クリュイタンス」盤が推薦してあったが、「ミシェル・コルボ」盤を忘れてはいませんかと言いたくなる~。
後者では「ワルター」盤と「ベーム」盤が推してあったが、ちょっと古いかなあ・・、近代の名演をご存知の方があればご教示ください。
クリックをお願いね →
前々回のブログ「理系人間にクラシック好きが多い理由」の続きです。
大好きな音楽を聴くときに「数学」を意識する方はまずいないと思うが、じつはその底面下にはそれが秘かに横たわっているというお話。
本書を読んでみたが、なにぶん自分の読解力では荷が重すぎたようで完全に理解するにはほど遠かったが、概ね理解できたエキスだけを記して恰好だけつけておこう(笑)。
「古代ギリシャでは数論(算術)、音楽、幾何学、天文学が数学の4大科目とされていた。そのうち音楽は数の比を扱う分野とされ、美しい音楽は調和のとれた音の比によって成り立っており、それこそが美の原点と考えられた。
もっともよく協和する二つの高さの音は1対2の関係(つまり1オクターブ)により作られているというように、ここでは常に音は数と対応して考えられ、また美しい数の比は美しい音楽を表すとも考えられた。
そもそも音楽は数学とは切っても切れない関係にあり、メロディーもビート(拍)も和音も、数の並びそのものである。つまり書かれた音符は数の並びなのである。数として認識された音は、身体的行為としての演奏を通して音楽になる。
したがって、私たちは何気なしに音楽を聴いているが、それは無意識のうちに数学にふれていることにほかならない。
「音楽を考えることは数学を考えることであり、数学を考えることは音楽を考えることである」
とまあ、簡単に噛み砕くと以上のような話だった。
どんなに好きな音楽であろうと長時間聴くと自然に(頭が)疲れてしまう経験もこれで説明がつくのかもしれない。
とにかく、本書は超難しかったけど音楽と数学とは切っても切れない縁を持っており、これで理系人間に音楽好きが多い理由が、何となく分かってもらえたかな~?
「ど~もよく分からん、もっと詳しく知りたい」という方は、直接本書を読んで欲しい(笑)。
さて、実はこのことよりも、もっと興味のある事柄がこの本には記載されていたのでそれを紹介しておこう。こういう思わぬ“拾いもの”があるから濫読はやめられない。
第3章では数学家(桜井氏)と音楽家(坂口氏)の対談方式になっており、数学の観点から「アナログのレコードとCDではどちらの音がいいか」について論じられた箇所があった。(158頁)
数学家「これは数学と物理学で説明できます。デジタルを究極にしたのがアナログです。レコードの音はアナログだから時代遅れだと思う方がいるかもしれませんが、数学を勉強した人は逆なのです。アナログの音が究極の音なのです。
CDは1秒間を44.1K(キロ)、つまり4万4100分割しています。その分割した音をサンプリングと言って電圧に変換してその値を記録する。これをA/D(アナログ→デジタル)変換といいますが、このCDになったデジタルデータはフーリエ変換によってアナログに戻されます。
しかし、レコードの原理はマイクから録った音の波形をそのままカッティングするので原音に近いのです。だから究極では情報量に圧倒的な差があるのです。CDは情報量を削っているから、あんなに小さく安くなっていて便利なのです。」
音楽家「ただし、アナログで圧倒的にいい音を聴くためには何百万ものお金が必要になりますよね(笑)」
数学家「それなりのリスニングルームとそれなりの装置と、そこに費やされる努力はいかほどか・・・。だから趣味になってしまうんです。それはやはり究極の贅沢みたいなことになります。そんなことは実際に出来ないということでCDができて、さらにiPodができて、どんどんデジタルの音になっています。」
音楽家「結局、それで一つの文化というものが作られました。アナログの時代には“オーディオマニア”という人種がいたのだけれども、今、そういう人種はいなくなってしまいましたね。ほんのわずかに残っているみたいですが。」
その「ほんのわずかに残っている人種」のうちの一人が自分というわけだが(笑)、いまだに続いているアナログとデジタルの優劣論争においてこの理論は特に目新しくはないものの、いざ改めて専門家からこんな風に断定されると、「ハイレゾ」をどんなに詰めてみても所詮「アナログには適わない」ということを頭の片隅に置いておいた方が良さそうだ。
我が家のケースではもう20年以上も前にワディアのデジタルシステムを購入してアナログとあっさり手を切ったわけだが、それではたしてよかったのかどうか?
その後にはさらにエスカレートして「ワディア」から「dCS」に乗り換えてしまったがこれらの機器の値段を書くと「お前はバカの上塗りか!」と言われそうなので差し控えるが、これだけのお金をアナログに投資する術もあったのかもしれない。

つい最近も仲間のお宅でレコードの音を聴かせてもらったが実に自然な「高音域」が出ているのに感心した。
いまだにアナログに拘る人の存在理由を現実に思い知らされるわけだが、貴重なレコード針が手に入りにくくなったり、ターンテーブルの高さやフォノモーターの回転精度、アームの形状で音が変わったり、フォノアンプの性能に左右されたり、有名盤のレコードがたいへんな値上がりをしていたりと、いろいろ腐心されていたのでレコードマニアにはそれなりの悩み(楽しみ?)もあるようだ。
また、DAコンバーター、真空管プリ・パワーアンプ、あるいはスピーカーなど周辺システムに細心の注意を払ったCDシステムと、幾分かでもそれらに手を抜いた場合のレコードシステムのどちらが「いい音」かという総合的な問題も当然残る。
結局のところ、俯瞰(ふかん)しないと、その優劣について何ともいえないのがそれぞれの現実的なオーディオというものだろう。
まあ、CDにはCDの良さもあって、前述のようにソフトの安さ、取り扱い回しの便利さなどがあるわけだし、今さらアナログに戻るのはたいへんな手間がかかるし、第一、肝心のレコードはすべて処分してしまっている。
もはや乗ってしまった船でオーディオ航路の終着駅もぼちぼち見えてきたので、CDで「潔く “まっとう” するかなあ」と思う今日この頃~。
あっ、そうそうこのところ聴いてる音楽ソースといえば 昔好きだった希少な曲目をタダで聴ける、そしてリモコン一つで簡単に聴ける 「You Tube」オンリーになっているが音質にまったく不満はないので大いに重宝している・・、「悪貨は良貨を駆逐する」(グレシャムの法則)のかな~(笑)。
クリックをお願いね →
「音楽、特にクラシック好きは理系人間に多い」これは争えない事実だと思う。
実際に身辺を見回してもお医者さんあたりに該当者が多いし、ちょくちょく我が家にやって来る高校時代の同級生(福岡在住3名)だってそう。
いずれも理系出身で、卒業後の進路は建築科、機械科、電気科と見事に色分けされるし、自分だって理系の “端くれ” なのでいわば4人すべてが理系を専攻している。
”たまたま” かもしれないが、「4人そろって」となると確率的にみてどう考えても意味がありそうである。
全員がオーディオというよりも音楽の方を優先しているタイプで音楽を聴くときに、より興趣を深めるために仕方なくオーディオ機器に手を染めているというのが実状である。
これは、なかなか興味深い事象ではなかろうか。
周知のとおり、ほとんどの人が高校時代に大学受験のため「文系と理系のどちらに進むか」の選択を迫られるが、これはその後の人生をかなり大きく左右する要素の一つとなっている。そのことは、一定の年齢に達した人たちのそれぞれが己の胸に問いかけてみるとお分かりだろう。
「自分がはたして理系、文系のどちらに向いているか」なんて、多感な青春時代の一時期に最終判断を求めるのは何だか酷のような気もするが、生涯に亘る総合的な幸福度を勘案するとなれば、なるべくここで誤った選択をしないに越したことはない。
現代でも進路を決める際の大きな選択肢の一つとなっているのは、おそらく本人の好きな科目が拠り所になっているはずで、たとえば、数学、理科が好きな子は理系を志望し、国語、英語、社会などが好きな子は文系志望ということになる。もちろんその中には「数学は好き」という子がいても不思議ではない。
それで概ね大きなミスはないのだろうが、さて、ここからいよいよ本論に入るとして、なぜ、音楽好きは理系人間に多いのだろうか。
その理由について実に示唆に富んだ興味深い本がある。

音楽と数学の専門家によって書かれた本書の序文の中で音楽と数学の関わり合いについてこう述べられている。
「私たちは、数の世界の背後には深い抽象性があることを、ほとんど無意識で感じています。音楽によって与えられる快感は、ときにはこの抽象世界の中を感覚的に漂う心地よさで高まり、それは広がっていく心の小宇宙に浮遊し、魂が解放されるような感動まで到達することがあります。~中略~。音楽は数の比によって成り立っており、それを考える数学の一分野です。」(抜粋)
抽象的だけどなかなか含蓄のある文章だと思うが、要するに音楽は数の比によって成り立っており数学の一分野というわけ。
以下、さらに分け入ってみよう。
続く。
クラシック愛好家なら「ワグネリアン」という言葉をご存知のはずですよね!
とはいえ、読者の中にはジャズ愛好家もいらっしゃることだろうし、確率は五分五分くらいかな~。
一言でいえば「リヒャルト・ワーグナー」(1813~1883年)の音楽が好きで好きでたまらない連中を指す。
昨日(1日)のこと、梅雨真っ只中の鬱陶しい気分を吹き飛ばそうと久しぶりに「ワルキューレ」(ショルティ指揮)を聴いてみた。
すると「威風堂々と辺りを睥睨(へいげい)する」かのような独特の音楽に大いに痺れてしまった。
平たくいえば、自分がまるで天下の英雄になったかのような痛快な気分とでもいおうか・・、なるほどとワグネリアンの心境の一端が分かるような気がした。
そういえば第二次世界大戦のさなか、あの「ヒトラー」(ドイツ)が聴衆を鼓舞するのにワーグナーの音楽をよく利用していたことは有名な話。
たとえ一時的にせよ「こういう錯覚」を起こさせてくれるのだから「凄い音楽」である。
これまでにもたびたびワーグナーの音楽に親しんできたがこういう気分になったのは初めてで、これは明らかにオーディオ・システムのおかげ・・、というか豊かな低音域を誇る「ウェストミンスター」(改)の面目躍如といったところかな~(笑)。
あの「五味康佑」さんの言葉・・、「オートグラフはワーグナーを聴くためにつくられたスピーカーだ」と、一脈通じるものがあると思いますよ~。
というわけで、いつものように「熱に浮かされるタイプ」(博多弁でいえば「逆上(のぼ)せもん!」ですな)なので次から次にワーグナー三昧。

聴けば聴くほどに凄い音楽ですよ~(笑)。
で、そのうちいつものように「欲」が出てきた・・、もっとスケール感が出るといいなあ。
というのも、ワーグナーを聴いている限り、通常の音の「彫琢とか艶とか奥行き感」などの「”ちまちま”した音質」の心配は吹っ飛んでしまう、というか、もう ”そこそこ” でいい(笑)。
とにかくマッシブで雄大で力強い低音が出てくれればそれで十分な気になるのが不思議。こればかりはもう「ワーグナーの魔法」にかかったとしか言いようがない。
で、この低音域に相応しいアンプをあてがうとなると、我が家の9台のアンプの中では「EL34プッシュプル」アンプにとどめを刺すといっていい。
我が家では一番の「力持ち」だが、やや繊細さに欠けるところがあって、日頃はめったに登板の機会が無いアンプ・・。
こうして「ワーグナー」さんのおかげで、眠っていた「アンプ」が見事に蘇ってくれました~、メデタシ、メデタシ。
以上、音楽ソースに振り回される「悲しいオーディオ」の顛末でした(笑)。
クリックをお願いね → 
今朝、起床した時(4時30分)の気温は27℃だった、窓を開け放した状態でこれだから今年いちばんの高温・・、いよいよ本格的な夏の到来ですか~。
さて、一年ほど前のブログで「百花繚乱のソプラノ歌手たち」と題して投稿したことをご記憶だろうか・・。
そして、つい最近、新たなソプラノ歌手を発掘したので一部重複するけど改めて記録しておこう。
テレビの故障による買い替えに伴い、内蔵された「You Tube」にリモコンで簡単にアクセスできる様になってからおよそ一年、あらゆるクラシック音楽が手軽に聴けるようになって、ちょっと大げさだが「狂喜乱舞」状態になり、今でもその余波が続いている(笑)。
たとえば、昔から大好きなモーツァルトの宗教曲「踊れ、喜べ、汝幸いなる魂よ K165」は「ソプラノ歌手と小編成の管弦楽団」という素朴な組み合わせだが、日本ではそれほどポピュラーな曲目ではなくどんな演奏会でもプログラムに入っているのをこれまで見たこともないし、聞いたこともない・・。
ところが、「You Tube」のテレビ画面でこの曲を検索してみると、ずらりとこの曲のアルバムが登場してくるから驚く。
欧米ではこういう曲目が中世風の素敵な小ホールで、まるで当たり前のように数限りなく演奏されていることに少なからずショックを受ける。日常的に宗教音楽がとても身近に鑑賞されているのだ!
延々と続いてきた伝統に深く裏打ちされた西欧の「精神文化」は、急に成金になった国々や科学技術がどんなに進展した国であろうと、 揺るぎない堅城を誇っている ような気がする。
で、たくさんのソプラノ歌手たちの歌唱を次から次に楽しませてもらったが、その中でも特上だと気に入ったのが次の2名の歌手。
「Stefanie Steger」(ドイツ)
はじめて聴く歌手だったが、声の張りといい、伸び具合といいたいへんな逸材ですね、おまけに見てくれもいい。もう、ぞっこんです(笑)。
そして、次は「Arleen Auger」(アーリーン・オジェー)
いかにも落ち着いた佇まい、自信に満ち溢れた表情のもと、その揺るぎない歌唱力に感心した。こんな歌手がいたなんて・・、大発見である。
急いでネットでググってみると、エ~ッ、1993年に59歳で鬼籍に入っていた! ガンだったそうでまだ若いのに・・。
ほかにもありまっせ~。
歌劇「死の都」(コルンゴルド作曲)はそれほど有名ではないが、その中の曲目「マリエッタの歌~私に残された幸せは~」は名曲中の名曲で、何度聴いても胸が熱くなる。
この一曲だけで「死の都」の存在価値があると思えるほどで、ほら、歌劇「カバレリア・ルスティカーナ」だってあの有名な「間奏曲」で持っているのと同じようなものかもね~。
で、「マリエッタの歌」も演奏会のプログラムに頻繁に登場しているようで、次から次にいろんな歌手が楽しめる。
シュワルツコップ、ミゲネス、オッター、そして日本人の「中江早希」も十分伍しているので楽しくなる。
名前は不詳だがこの歌手も大変良かった。
こうして、次から次にお気に入りのソプラノ歌手たちがタダで発掘できるのだから、もう時間がいくらあっても足りない(笑)。
そういえば、昔の演奏会のプログラムは「ソプラノ」が中心だったんですよねえ。
裏付けるために、「クラシック名曲全史」にあったプログラムを引用しよう。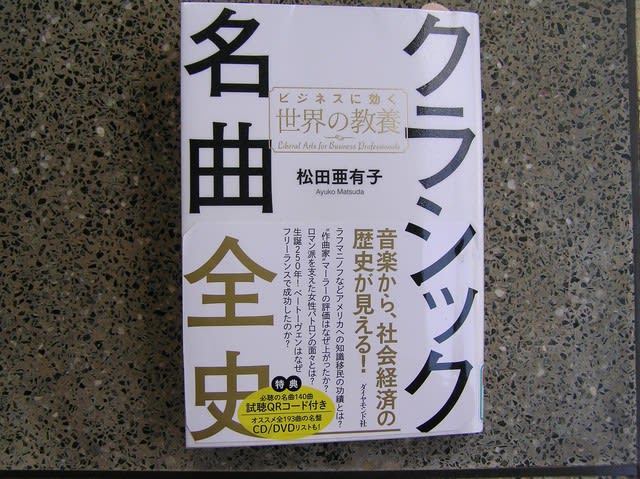
✰「1783年のモーツァルトの音楽会のプログラム」
いわば240年前の「音楽会」の演目なので極めて珍しいが、モーツァルトは1791年に35歳で亡くなったので、換算すると27歳のときの演奏会になる。
ウィーンで開かれたそのときの演奏会のプログラムの内容はこうだ。
1 序曲「ハフナー」交響曲
2 オペラ「イドメネオ」よりアリア(ソプラノ)
3 ピアノ協奏曲K415(モーツァルト演奏)
4 オペラのシェーナK369(テノール独唱)
5 「ポストホルン」セレナードの協奏曲楽章
6 ピアノ協奏曲K175(モーツァルト演奏)
7 オペラ「ルーチォ・シッラ」よりアリア(ソプラノ)
8 モーツァルトのピアノ独奏
9 オペラのシェーナK416(ソプラノ独唱)
10 終曲(序曲の終楽章)
解説によると、当時の音楽会の目玉演目はいつも声楽であり、注目されるのも声楽家たちだった。
1番と10番はオーケストラだけの演奏で、まだ電気も発明されておらず普及していない時代なので1曲目の序曲は開幕のベル代わりであり、最後の10曲目にあたる終曲は終了の合図だった。
つまり交響曲はベル代わりで「前座」のようなものでありコンサートの華は歌曲だった。
とまあ、コンサートの華が歌曲だったということに大いに興味を惹かれる。人の声(ボーカル)は昔も今も変わらない「最高の楽器」なのでしょうね。
我が家の音楽鑑賞においても中心となるのはやはりボーカルだが、その再生は簡単そうに見えて実はオーディオ機器の弱点を洗いざらい白日の下にさらけ出す手強い難物でもある(笑)。
そして、つい最近発掘したのが「レグラ・ミューレマン」(スイス)で、グリーク作曲「ソルヴェイグの歌」(歌劇ぺールギュント)が惚れ惚れするほどいい! ほかにも「モーツァルト」の歌曲なども れっきとしたレパートリー と来ている!!
今や各種演奏会に 引っ張りだこ だそうだがたしかに非の打ち所がない歌唱力と容姿に毎日ウットリ~(笑)。
それにしても、ひところでは夢想だにしないほどの「音楽をタダで聴ける夢のような時代」が実際に現実のものとなりましたね。
これも「You Tube」のおかげです・・、仕組みを考え付いた人たちに足を向けて寝れませんな(笑)。
おっと、最後に・・、オーディオのことだけど「192KHz」のハイレゾで「You・・」を聴いてるけど、CDと何ら遜色(そんしょく)を感じませんよ~。
クリックをお願いね → 
図書館で新刊本の「ノーベル文学賞」というタイトルの本をざっと立ち読みしたところ、近年の選考基準は既に世界的に著名な作家、いわばポピュラーになった作家には与えない方針とかで、昔は既に有名になっていた「ヘミングウェイ」なども受賞しているのに、まことに手前勝手な都合のいい話だが何とも仕方がない。
これまで有望とされてきた作家の村上春樹さんはもはや有名になり過ぎたので、その目はもう無くなったというのが大方の見方だろうか・・、ただし村上さんは「エリーティズム」には程遠い作家なので、ノーベル文学賞を受賞できなくてもおそらく何ら痛痒を感じていないことだろう。
音楽好きで知られる彼の著作は希少なので見逃せない存在だが長編については、このところ根気がなくなってしまいなかなか読む気にならない・・、ただしインタビュー形式のエッセイは率直な語り口で非常に面白いので、機会あるごとに目を通している。
最近では、「村上春樹インタビュー集」~夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです~が面白かった・・、何と19本のインタビューが紹介されている。

つい読み耽ってしまったが、185頁に音楽ファンにとっては実に興味のある問答が収録されている。
「20世紀の偉大な文学作品の後にまだ書くべきテーマがあるでしょうか?文学にはもはや書くべきテーマも、言うべきものごともない、という意見に同意されますか?」
と、外国の愛読者が発する問いに対して村上さんはこう答えている。
「バッハとモーツァルトとベートーヴェンを持ったあとで、我々がそれ以上音楽を作曲する意味があったのか?彼らの時代以降、彼らの創り出した音楽を超えた音楽があっただろうか?それは大いなる疑問であり、ある意味では正当な疑問です。そこにはいろんな解答があることでしょう。」
とあり、以下長くなるので要約すると「音楽を作曲したり物語を書いたりするのは”意味があるからやる、ないからしない”という種類のことではありません。選択の余地がなく、何があろうと人がやむにやまれずやってしまうことなのです。」とあった。
文学的には、村上が理想とする書いてみたい小説の筆頭は「カラマーゾフの兄弟」(ドストエフスキー)で、小説に必要なすべての要素が詰まっているそうで、そのことを念頭に置いて解答しているわけだが、興味を引かれるのは音楽的な話。
「バッハ、モーツァルト、ベートーヴェンの3人組に対して、はたして他の作曲家の存在意義とは?」
これはクラシック音楽において常に問われる「旧くて新しい」テーマではないだろうか。
ほかにも「ブラームス、ワーグナー、マーラー、ブルックナーなどが居るぞ」と声高に叫んでみてもこれら三人組の重量感にはまったく抗しようがないのも、なんだか虚しくなる事実である。
とりわけ我が家では作曲家たちを「大木」に例えると、太い「幹」に当たる部分がモーツァルトでほかは「枝葉」に過ぎない・・、なんだよねえ~(笑)。
本書には、もうひとつ音楽に関して興味あることが書かれてあった。(312頁)
村上さんは映画が好きで青春時代に台本(シナリオ)を読み耽ったそうだが、それが嵩じてそのうち自分なりの映画を空想の中で組み立てていくクセがついてしまった。
それは、近代音楽の雄であるアーノルド・シェーンベルクが「音楽というのは楽譜で観念として読むものだ。実際の音は邪魔だ。」と、言っていることと、ちょっと似ているとのこと。
「実際の音は邪魔だ」とは実にユニークな言葉である。
「楽譜を読みながら音楽を頭の中で想像する」ことが出来れば実にいいことに違いない。第一、それほど広くもない部屋の中で我が物顔で大きなスペースを占めているオーディオ・システムを駆逐できるのが何よりもいい(笑)。
「文学」は文字という記号で行間の意味を伝える仕組みになっているが、音楽だって音符という記号で情感を伝える仕組みだから同じようなものかもしれない。
もしかして、楽譜が読める音楽家がオーディオ・システムにとかく無関心なのもその辺に理由があるのかもしれないですね。
人間が勝手に描くイマジネーションほど華麗なものはないので、頭の中で鳴り響く音楽はきっと素晴らしいものに違いない。
これから音楽を聴くときはできるだけ頭の中で想像しながら聴くことにしようと心掛けたいところだが、この歳になるともう無理だよね~(笑)。
道徳的なクリックを求めます → 
日本歌曲といえば「島田祐子」さんで決まりと思っている。その声を聴いているとまるで母親の胎内で羊水に浸っているような懐かしい感覚を覚えるのだから不思議(笑)。
CD全集(5枚組)も持っているが、このところ手っ取り早く「You Tube」で楽しんでいる毎日だが、ふと「歌が巧くて素敵な声の持ち主には共通点があるのではないか」と思い至った。
たとえば顔の造作について。



左からずらっと並べたのは「美空ひばり」、「五輪真弓」、そして「島田祐子」さんで、歌唱力に定評のあるこれら3名の共通点として気付くことはどちらかといえば、ややエラが張った幅の広めの顔の持ち主ばかりだとは思いませんか?
こういう顔立ちは歯並びが良くて「咀嚼力」(ものを噛む力)が強いだろうし、咽頭部が丈夫そのもので「声帯」も強靭で大きそうな気がする・・・。
そういえば世紀のソプラノ歌手(コロラトゥーラ)として名を馳せた「エディタ・グルベローヴァ」(当たり役はオペラ魔笛の「夜の女王」)だって同じような顔立ちに見える。

ちなみに、政治家でも一般的に細面よりも幅の広い顔の方が「向き」とされているが、見た目の安心感とともに安定した声が有権者の心を獲得しやすいのかもしれない。
まあ、これは例外もあるしすべての歌手に該当する話でもないがご参考までに提示してみた。
それはさておき、島田祐子さんの声があまりにも素晴らしいので、我が家の近くにお住まいで「歌心」の有る知人の「I 」さんにCDを貸してあげたことがある。
「I」さんは生粋の地方政治家だが、7年ほど前にご自宅の80坪ほどの集会用の地下室に置くために我が家の余ったオーディオシステム一式を貸し出している。
グッドマンのエンクロージャーに入った「フィリップスのフルレンジ」(口径30センチ:アルニコマグネット)が朗々と鳴っており、貸した後で「しまった!」と臍(ほぞ)を噛んだ(笑)。
余談になるが「いずれ回収しないと・・」と内心密かに思っているが、どちらが先に くたばるか 生存競争の様相を帯びているのが実状だ(笑)。
で、そのときに広い部屋で鳴らすのと狭い部屋とでは音質に雲泥の違いがあり、「色の白いは七難隠す」ではないが「部屋の広いは七難隠す」ことを痛感したことだった。
その「I 」さんからメールが届いた。
「島田祐子さんのCDありがとうございました。さっそく聴かせていただきましたが、まるで心が洗われるようで日本人に生まれて良かったとつくづく思いましたよ。それにどの曲も詩的でとても言葉が美しい。とりわけ”あざみの歌”には感激しました。ぜひ他の4枚のCDも貸してください。」
「あざみの歌」は戦後の昭和25年、信州の諏訪湖畔で暮らした横井弘が人生観を「あざみの花」に託した歌詞に「八州秀章」が作曲したものであるとライナーノートに記されていた。
スコットランドの国花「あざみ」 → 
それでは、その美しい歌詞の余韻に浸りつつ終わりとしよう。
山には山の 愁いあり 海には海の 悲しみや ましてこころの 花園に 咲きしあざみの花ならば
高嶺の百合の それよりも 秘めたる夢を ひとすじに くれない燃ゆる その姿 あざみに深き わが想い
いとしき花よ 汝(な)はあざみ こころの花よ 汝(な)はあざみ さだめの径(みち)は 涯(は)てなくも 香れよせめてわが胸に
道徳的なクリックを求めます → 
音楽評論家の「宇野功芳」氏といえばご存知の方が多いと思うが、あの独特の断定的な物言いがとても個性的で有名だ。
たとえばこういう調子。(「クラシックCDの名盤」から、デュ・プレが弾くエドガーの「チェロ協奏曲」について)
「67年、バルビローリの棒で入れたライブが最高だ。人生の憂愁やしみじみとした感慨に彩られたイギリス音楽に共通する特徴を備えるこの曲を、22歳になったばかりのデュ・プレが熱演している。第一楽章から朗々たる美音がほとばしり、ポルタメントを大きく使ったカンタービレは極めて表情豊か、造詣はあくまで雄大、ロマンティックな情感が匂わんばかりだ。」
こういう表現って、どう思われます?(笑)
クラシック通の間では評価が二分されており、「この人、またいつもの調子か」と やや嘲り をもって受け止める冷静派と、むしろ憧憬の念を持って受け止める熱情派と、はっきりしている。
自分はどちらかというとやや冷めたタイプなのでこういう大げさな表現はあまり肌に合わない。したがって前者の派に属しているが、まあ「死者に鞭打つ」ことは遠慮した方がよさそうだ。
「宇野功芳」さん「ご逝去」の報に接したのは8年前のちょうど6月頃だった。

享年86歳、しかも老衰が原因となると「天寿」をまっとうされたのではあるまいか。合掌。
その宇野さんの遺作となったのが「私のフルトヴェングラー」(宇野功芳著)。

我が音楽人生の中でフルトヴェングラーには深い思い出があって、20代前半の頃はそれこそフルトヴェングラーに のめり込んだ ものだった。ベートーヴェンの「第九」「英雄」、そしてシューベルトの「グレート」・・・。
本書の15頁に次のような記述がある。
「今や芸術家たちは技術屋に成り下がってしまった。コンクール、コンクールでテクニックの水準は日増しに上がり、どれほど芸術的な表現力、創造力を持っていてもその高度な技巧を身に着けていないと世に出られない。フルトヴェングラーなど、さしずめ第一次予選で失格であろう。何と恐ろしいことではないか。
だが音楽ファンは目覚めつつある。機械的なまるで交通整理のようなシラケタ指揮者たちに飽き始めたのである。彼らは心からの感動を求めているのだ。
特にモーツァルト、ベートーヴェン、シューベルト、ブラームスなどのドイツ音楽の主流に対してもっと豊饒な、もっと深い、もっとコクのある身も心も熱くなるような演奏を期待しているのだ。
だからこそ死後30年も経ったフルトヴェングラーの音楽を必死になって追い求めるのである。実際に舞台姿を見たこともない、モノーラルレコードでしか知らない彼の音楽を熱望するのである。」
といった調子~。
クラシックのオールドファンにとって、黄金時代は「1950年代前後」ということに異論をさしはさむ方はまずおるまい。
綺羅星の如く並んだ名指揮者、名演奏家、名歌手、そして名オーケストラ。
随分昔のブログになるが「フルトヴェングラーとカラヤン」でも紹介したが、ベルリン・フィルのコントラバス奏者だったハルトマン氏がこう語っている。
「カラヤンは素晴らしい業績を残したが亡くなってまだ30年も経たないのにもうすでに忘れられつつあるような気がする。ところが、フルトヴェングラーは没後60年以上経つのに、未だに偉大で傑出している。<フトヴェングラーかカラヤンか>という問いへの答えは何もアタマをひねらなくてもこれから自ずと決まっていくかもしれませんよ。」
だがしかし・・。
本書の中で、フルトヴェングラーがもっとも得意としていたのはベートーヴェンであり「モーツァルトとバッハの音楽には相性が悪かった。」(23頁)とあったのに興味を惹かれた。
そういえばフルトヴェングラーにはモーツァルトの作品に関する名演がない!(強いて言えばオペラ「ドン・ジョバンニ」ぐらいだろう)
あの わざとらしさ がなく天真爛漫、 天馬空を駆ける ようなモーツァルトの音楽をなぜフルトヴェングラーは終生苦手としていたのか、芸風が合わないといえばそれまでだが・・・。
「モーツァルトを満足に振れない指揮者なんて認めない」というのが永年の持論だが、はてさてフルトヴェングラーをどう考えたらいいのだろう。
どなたか ご教示 をいただくとありがたいのですが・・。
道徳的なクリックを求めます → 
このところドップリ嵌っているのがブルッフの「ヴァイオリン協奏曲」・・、演奏者はあの「ヒラリー・ハーン」、そして音源は「You Tube」。
使用スピーカーは「AXIOM80」・・。
起きてすぐに1回、午後に1回、寝る前に1回と1日のうちで3回も聴いているほどの凝り性ぶり~(笑)。
もちろん演奏も特上だが、筆舌に尽くし難いほどのヴァイオリンの音色と響きが深く心に沁み入ってくる。
やはり楽器の王様は「ヴァイオリンに尽きる」との思いを改めて確認したが、彼女ほどの達人が弾いているヴァイオリンとなると、おそらく「ストラディヴァリ」に違いない。
現代の技術をもってしても再現できないヴァイオリンの名器として、つとに有名だが、そのことから ふと高校時代の同級生「O」君のメールを思い出した。
「O」君は桐朋学園大学を卒業して指揮者として武者修行のため渡欧した音楽家(現在は福岡で音楽アカデミーを開設)。
「私の留学はザルツブルグ・モーツアルテウム音楽院の夏期講習から始まったのですが、ザルツブルグ音楽祭を初めて聴いたのがカラヤン指揮の<アイーダ>でした。(幸いなことに、宿の主人がチケットをゆずってくれたのです)
全ての点で余りにもスゴくて《ブッ飛ばされた》ことを覚えています。この時、舞台上で演奏された(古代の)トランペットがYAMAHA製だと聞きました。ヤマハが管楽器を手がけた最初の事例でしたが、結果は良かったと思います。
この時、ヤマハはヨーロッパの金管楽器の名器を入手して、全ての部分の厚みの変化や、金属の質などをコンピューターで分析しながら開発したと聞きました。この方法で、それ以後のヤマハの金管は優れたものを作っています。
その後、ウィーンの指揮者スイートナーのクラスで学んだのですが、あるとき日本から帰国したばかりのスイートナーがヴァイオリンを抱えて教室にやってきました。
“使ってみて欲しいと言われて、ヤマハから預かって来た”と言って楽器を生徒に見せ、ヴァイオリンの生徒が弾いて“うん、いいイイ”と言っていました。
後で聞いた話ですが、ヴァイオリンの銘器をコンピューターで詳しく分析して、そのように作ろうとしたそうです。しかし、どうしても本物に近い楽器にまでは作れなかったようです。金属では成功したのですが、(自然の)木が相手ではコンピューターも分析しきれなかったように思います。
また、ヤマハの工場に行った時、聞いた話ですが、スタインウェイを入手して、全てバラバラに分解してから、組み立て直すと<ヤマハの音>になってしまったそうです・・・やはり職人(名工)の『感性』が重要な鍵を握っているのでしょうか。」
そういえば、人間の感性技が重要なカギを握っている例としてオーディオ機器も例外ではない・・、たとえば往年の名器とされる「マランツ7」にまつわる話がある。
「マランツ7」といえば、1950年代の初めに市販のアンプにどうしても飽き足りなかった大の音楽好きのデザイナー「ソウル・B・マランツ」氏(アメリカ)がやむなく自作したプリアンプの逸品である。
デザイン的にも日本のオーディオ業界に多大の影響を与えたことが知られている。
そこでの話だが、ある専門家がそっくり同じ回路と同じ定格の部品を使って組み立ててもどうしてもオリジナルの音の再現が出来なかった曰くつきの名器だと、ずっと以前のオーディオ誌で読んだことがある。
感性技が求められるオーディオ機器の典型的な例として挙げてみたわけだが、このことから一つの課題らしきものが導き出される。
それは「オーディオ機器の製作に携わる方は少なくとも音楽的感性に満ち溢れた人であって欲しい!」
大学の電子工学関係科を卒業したというだけで音楽に興味を持たない人たちが(メーカーで)機器づくりに携わることは、まるで「仏(ほとけ)作って魂入れず」で、使用する側のマニアにとってはもはや悲劇としか言いようがない・・。
その事例を代表するメーカーといえば、やたらに高価なあの〇〇〇かな~、物議をかもすので具体名は控えておこう・・、このブログの読者ならもうお分かりですよね(笑)。
道徳的なクリックを求めます → 
ドナルド・キーンさんの著作「オペラへようこそ!」を読み終えたところ、オペラに対する情熱にすっかり感化されてしまい、何だか始めからオペラファンだったような錯覚を覚えてしまった(笑)。
それほど本書にはオペラに対する熱情がほとばしっている。何事につけ人の胸を打つのは最後は「情熱」ということを改めて思い知らされたましたぞ。

それではまず、キーンさんの大好きなオペラ「ベスト10」を挙げてみよう。
1位 ドン・カルロス(ヴェルディ) 2位 トラヴィアータ(椿姫:ヴェルディ) 3位 神々の黄昏(ワーグナー) 4位 カルメン(ビゼー) 5位 フィガロの結婚(モーツァルト) 6位 セビーリャの理髪師(ロッシーニ) 7位 マリーア・ストゥアルダ(ドニゼッティ) 8位 湖上の美人(ロッシーニ) 9位 エヴゲーニイ・オネーギン(チャイコフスキー) 10位 連隊の娘(ドニゼッティ)
偏ることなく、とても幅の広いオペラファンであることが伺えるが、惜しいことに自他ともに認めるオペラの最高峰「魔笛」(モーツァルト)が入っていない!
5位の「フィガロの結婚」(モーツァルト)もいいけど、それよりは上だと思うけどなあ(笑)。
このことで、キーンさんのオペラへの嗜好性が垣間見えた気がした。
おそらく魔笛を外された理由は「ドラマ性」が物足りないといったことだろう。
周知のとおり「魔笛」は荒唐無稽の「おとぎ話」の世界だからストーリー性は皆無といっていいくらいだが、その反面、音楽の美しさといったらもうこの世のものとは思えないほどだ。
その辺りに自分のようにクラシック部門から分け入ったオペラ・ファンと、キーンさんのようにオペラ・オンリーの生粋のファンとの本質的な違いがあぶり出されてくるような気がした。
ところで上記のベスト10には指揮者が特定されていないのが残念。あえて無視されたのかもしれない。
そのかわり、「思い出の歌手たち」の一項がわざわざ設けてあった。
✰ キルステン・フラグスタート(キーンさん一押しのソプラノ歌手)
✰ エリザベート・シュワルツコップ(類い稀な美人かつ際立った声の個性)
✰ ビルギット・ニルソン(ついにフラグスタートの後継者が登場)
✰ マリア・カラス(スーパースターが持つ独特の雰囲気を発散)
✰ プラシド・ドミンゴ(パバロッティを上回る魅力的な声を持つテノール)
ほかにもいろんな歌手が登場するがこのくらいに留めておこう。
さて、キーンさん一押しのソプラノ「フラグスタート」だが、幸いなことに手元にフルトヴェングラー指揮の「トリスタンとイゾルデ」(ワーグナー)のCDがある。

これまで「フラグスタート」をそこまで意識して聴いたことがないが、稀代のオペラファンが絶賛するのだからいやが上でも興趣が募る。
まず、ネットでの履歴を紹介しておこう。
「1895年7月12日、ノルウェーのハーマル生まれのソプラノ歌手。1962年12月7日、オスロにて没。父は指揮者、母はピアニストという恵まれた音楽環境の中で育ち、オスロのヤコブセン夫人の下で声楽を学ぶ。
1913年、同地の歌劇場でデビューしたが、30年代に入ってバイロイトに招かれ、ジークリンデ役で大成功を収める。その後も、ブリュンヒルデやイゾルデなどの歌唱で高く評価され、ワーグナー歌手としての名声を不動のものにした。
その声量は極めて豊かで、膨大なオーケストラの強音をも圧して響き渡ったにもかかわらず、清澄な美しさを失わず、劇的表現と気品に満ちたもので、ワーグナー・オペラのヒロインとして理想的であった。
また、R.シュトラウスの歌曲の歌唱においても、歴史的名歌手として名を残している。」
以上のとおりだが、気の遠くなるような長い前奏の後でようやくフラグスタートが登場してくれた(笑)。
後継者とされる「ブリギット・ニルソン」と比べると、やや声質が柔らかくて軽やかで高音域への伸びが一段と際立っているような印象を覚えた。さすがキーンさん一押しのソプラノです~。
ちなみに「You Tube」で、「フラグスタート」とググるとズラッと出演したオペラが出てきました!
CDよりも音質が落ちるけど、当時は録音状態が悪いのでこれで十分かもね~。興味を覚えた方はぜひご一聴を・・。
道徳的なクリックを求めます → 
フランスの女流作家「フランソワーズ・サガン」に「ブラームスはお好き」というタイトルの小説がある。
バッハやモーツァルトとは違って、わざわざ「お好き?」と訊くところに、西欧音楽界における「ブラームス」の微妙な位置づけを現わしているように思える。
そして「チャイコフスキーがなぜか好き」(PHP新書)という本がある。

「なぜか好き」という言葉に、ブラームスと同様の屈折した匂いを感じる(笑)。
著者は前東京外国語大学の学長の亀山郁夫氏。ロシア文学者として近年、「カラマーゾフの兄弟」をはじめロシアの文豪「ドストエフスキー」の一連の著作の新訳で著名な方。
文学のみならずクラシックにも興味をお持ちとは、ほの暖かい親しみを感じさせてくれるが「チャイコフスキー」となるとちょっと異質かな。
もちろんロシア出身という要素もあるのだろうが、クラシック通の間で「チャイコフスキーが好き」なんて広言することは何だか「はばかられる」感じを持つのは自分だけだろうか。
親しみやすいメロディが多いのはいいけれど、何回も繰り返しての鑑賞に堪えるには少し物足りない音楽という印象が個人的にはずっとしている。
したがって、チャイコフスキーと聞くだけで初心者向けの軽いイメージが先立ってしまう。
ふと、関連して以前のブログの中で「ショパンは二流の音楽」と記載したことを思い出した。
ショパンの音楽も親しみやすさという点ではチャイコフスキーと似たようなものだが、いくら筆の勢いとはいえ歴史に名を刻む大作曲家を二流といって一刀のもとに切り捨てる資格は自分ごときにあるはずがないという反省心のもとで亀山さんの率直な物言いがもろに心に響いてくる。
結局、作曲家の位置づけなんて個々の心情の中で相対的に決まるものであって、そっと心の中に秘めておけばいいものをというのが現在の心情である。
「雉も鳴かずば撃たれまいに」(笑)。
ところで作曲家に一流とか二流とかのレッテル貼りは不遜にしても世間一般のランク付けというのはあるのだろうか。
実は本書の30頁に興味深い記事があった。ロシアの作曲家たちがクラシックの世界でどのような位置づけにあるのかという視点から著者がウェブで調べた結果が次のとおり。(抜粋)
「今日、世界のコンサート会場で演奏される曲目の国別統計を取るとしたらどの国の作曲家が最高位にランクされるのだろうか。そんな非音楽的な好奇心に駆られてウェブ上に情報を求めた結果統計は見つからなかったがその代わりに「百人の音楽家たち」と題するランキング表が出てきた。
タイトルは「100 Greatest Classical Composers」とあり、もうけられた基準は「彼らのイノベーションや影響力だけでなくその美学的な重要性と歴史的な意味の重さ」とある。
そして出てきたのが次のランキング。
全文英語なので、これが日本のみならず世界的にグローバルな「ものさし」だといえよう。
第1位 ベートーヴェン 以下2 モーツァルト、3 バッハ 4 ワーグナー 5 ハイドン 6 ブラームス 7 シューベルト 8 チャイコフスキー 9 ヘンデル 10 ストラヴィンスキー 11 シューマン 12 ショパン 13 メンデルスゾーン 14 ドビュッシー 15 リスト 16 ドヴォルザーク 17 ヴェルディ 18 マーラー 19 ベルリオーズ 20 ヴィヴァルディ
これまで自分の好み次第で作曲家のランクを勝手に決めつけていたもののこのランキングでいろいろ考えさせられた。
まず上位4名の顔ぶれは妥当なところという気がする。もはや時代遅れと思っていたベートーヴェンが1位とはさすがだが、「第九」という十八番(おはこ)の影響もあるのかな~。そして、近年コンサートを席巻しているマーラーが18位とは後ろ過ぎて意外。
逆に、今回俎上にのぼったチャイコフスキーが8位、ショパンが12位というのもちょっと上位過ぎる感がする。
やはり一度聴いただけでも親しみやすい「アイスクリームのような音楽」というのが有利なのだろうか(笑)。
最後に、チャイコフスキーの音楽について著者の友人「音楽評論家」のコメントが印象に残った。(141頁)
「私はチャイコフスキーの音楽(メロディ)に いじわる なものを感じます。とてつもない自己愛から来るもの。だからチャイコフスキーの奇跡のように素晴らしい音楽にはものすごく興奮し、感動もするけれど、慈愛を感じない。
作曲家はみんな自己中心的でナルシストだけれど、創作しているうちに、音楽への愛が自己愛を上回る瞬間というのが必ず来ると思う。チャイコフスキーの場合はたぶん、音楽より自分の方が大好きだったのではないか、と思えるんですね。そう、あの人の音楽、聴いても何か癒されない・・・・・・。」
言い得て妙だと思います!
本格的に鑑賞するのに何がしかの物足りなさを感じていた原因はそこにありましたか!
文中の「チャイコフスキー」を「ショパン」に置き換えても同じことが言えそうな気がするけどはたして読者の皆様はいかがでしょう・・、
「チャイコフスキーとショパンはお好き?」(笑)
道徳的なクリックを求めます → 
村上春樹氏に関する新刊「村上春樹研究」を一読したところ、ご本人のジャズへの傾倒ぶりがひとしきり記載されていた。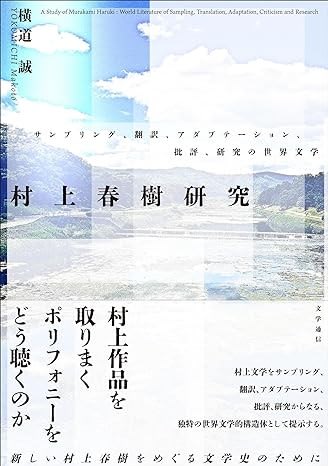
肌合いが違う作家なので小説の方はあまり読む気がしないが、エッセイなどにおける「音楽についての的確な表現力」については、一目を置かざるを得ないので常に気になる存在ではある(笑)。
そして、この人はいったいクラシック派なのか、ジャズ派なのかずっと気になっていたが本書により氷解した。
圧倒的なジャズ派なんですねえ~。
手持ちのレコードはジャズが7割を占めているそうだし、文章を書く時にも一にリズムを重視し、次がハーモニー、そして即興性を盛り込むようにして完結させているとのこと。
クラシック愛好家として言わせてもらうと、音楽の3要素の一つとして欠かせないメロディ(旋律)ではなくて即興性というところに良きにつけ悪しきにつけ彼の本質が垣間見えるような気がする・・。
仮にクラシックが「ウェット」でジャズを「ドライ」だとすると、彼の小説も本質的には「ドライ」なので肌合いが違う原因がようやく分かった・・、もちろん私見ですよ~。
(以下、クラシック愛好家を「ウェット派」、ジャズ愛好家を「ドライ派」と呼称しよう)
さて、ときどき、このブログの読者層が「ウェット派」か「ドライ派」かを想像してみることがある。
現在の読者を1日当たり仮に1000人だとするとそのうちウェット派は200人ぐらい、ドライ派が500人ぐらい、そして音楽なら何でも好きという日和見タイプが300人といったところかな。つまり「2:5:3」というわけ。
もちろんあくまでも想像の域を出ないが、搭載しているブログの内容に応じたアクセス数から推し量ったものだから全然根拠が無いわけでもない。
言い換えると、このブログのセールスポイントは「実践的なオーディオ実験」にあるとみている・・、もちろん、大した内容ではありませんよ~(笑)、で、ドライ派はウェット派に比べて圧倒的にオーディオ愛好家が多いのでこの5割説の根拠にもなろうというものです。
そういうドライ派の中で息の長い交流をさせていただいているのが「I」さんである。
折にふれ、ブログのネタにさせてもらいたいへん感謝しているが、このたびジャズのアーチストについて興味深い情報を得られたのでご了解のもとに掲載させてもらおう。
実を言うと、これまでジャズは芸術よりも娯楽に近い存在だと思っていたが、少なくとも認識を改めようと思った次第(笑)。
それでは以下のとおり。
「ジャズの話題に便乗して、好みのジャズ(奏者)について白状させてください。
学生運動最後の時代が自分の大学時代と重なり、その頃にジャズを聴き始めています。思想的にジャズが扱われる時代でしたが、そのようにジャズを聴いたことはありません。もっと個人的な芸術表現として聴いてきました。
娯楽でなく芸術として聴いていますので、ジャズ奏者に求めるものは、けっして偉そうに言うわけではないのですが「創造性・・探求性?」そして「矜持」です。
好きな(リスペクトする)奏者
<ピアノ>
バド・パウエル(比類なきドライブ感)
セロニアス・モンク(笑みがこぼれます)
ウィントン・ケリー(最高のハードバップピアニスト)
ビル・エバンス(ジャズピアノの・・・何と言ったらいいかわかりません)
<トランペット>
マイルス・デイビス(ウエイン・ショーターが参加する前までが帝王)
ブッカー・リトル(夭折が本当に惜しい)
ウィントン・マルサリス(批判にめげず頑張ってほしい)
<アルトサックス>
エリック・ドルフィー(早死にが悔しい。少なくともあと数年だけでも生きていてほしかった)
オーネット・コールマン(1964年のヨーロッパ・ツアーまでが眩しい)
<テナーサックス>
スタン・ゲッツ(うまい!それだけで凄い)
アーチー・シェップ(70年以降もいい演奏をしている稀有な存在)
<ベース>
ポール・チェンバース(はずせない)
(以下3人は白人。表現力が尋常ではない)
スコット・ラファロ、ニールス・ヘニング、ウルステッド・ペデルセン ジョージ・ムラーツ
<ドラム>(ドラムには関心が薄いのですが、強いて言えば)
フィリー・ジョー・ジョーンズ(上質な縁の下の力持ち)
ジミー・コブ(上に同じ)
トニー・ウイリアムス(超人なのに縁の下の力持ち)
偏ってますねえ(笑)
時代は1950、60年代がほとんど。楽器はアコースティック。ジャズ史的にいうと、ハードバップ・モード・フリー・ウルトラモダンになります。
ジョン・コルトレーンとソニー・ロリンズが入っていないのが不思議に感じられると思いますが、この二人へのコメントは不遜になりますので差し控えます。
以上のとおりだが、「I」さんのジャズとオーディオへの熱意にはいつも敬意を抱いている。
ところで、クラシックの場合は作曲家をはじめ指揮者や演奏家など好みの対象が広範囲に広がるが、ジャズともなると演奏家だけに収斂されていくのが特徴のようだ。
それだけ許容範囲が狭くなるというのか、ジャズファン同士の「口角泡を飛ばす」議論の要因にもなりそうな気がしている(笑)。
ちなみに、我が家ではときどきコルトレーンを聴いてみるのだが、どうもサッパリで皆が言うほどピンとこない。

素人なりに、この疑問を率直に「I」さんにぶつけたところ次のような返信があった。
以上、ドライ派は「演奏家」に対する熱の入れ様が一段と「ヒート・アップ」しているような気がします~。
最後に、「村上春樹研究」を通じて、ウェット派はとうていドライ派になれそうもないことを改めて痛感した・・、音楽における「旋律」だけはどうしても譲れないところだからね~、小説だってホロリと琴線に触れる ところがなくちゃねえ・・、と思うんだけどどうかな~(笑)。

道徳的なクリックを求めます →

















