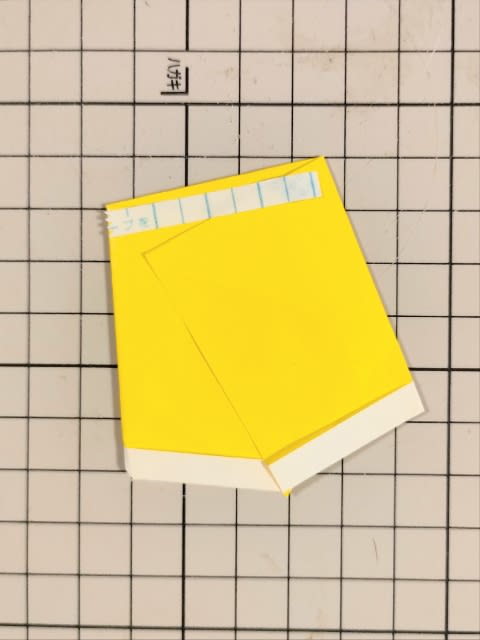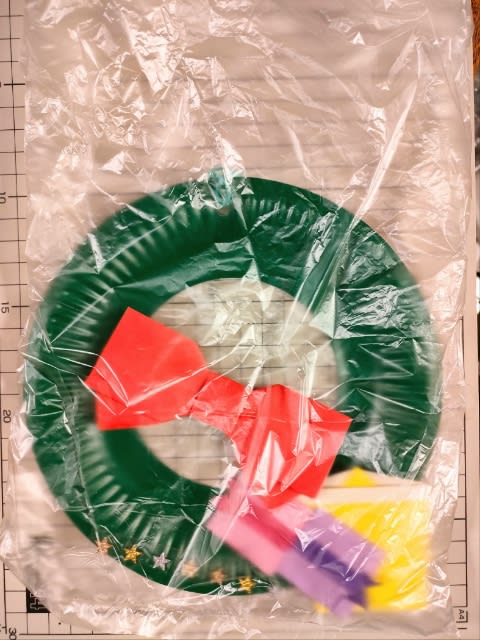今日は、11月とは思えないほど暖かくなりました。用心のためにとっておいた半袖が活躍するとは思いもしませんでしたが、立冬過ぎだと思うと何だかゲンナリさせられます。
ところで。今日11月17日は《スラヴ行進曲》が初演された日です。《スラヴ行進曲 変ロ短調 作品31》は、
 ピョートル・イリイチ・チャイコフスキー(1840〜1893)が作曲した演奏会用行進曲です。
ピョートル・イリイチ・チャイコフスキー(1840〜1893)が作曲した演奏会用行進曲です。
1876年6月、オスマン帝国軍によってセルビアのスラヴ人キリスト教徒が多数殺害されました。この事件に際して多くのロシア人は殺害されたスラヴ人たちに同胞としての同情を感じ、セルビアへは義勇兵が援軍として赴きました。
モスクワ音楽院初代院長であり、チャイコフスキーの親しい友人でもあったニコライ・ルビンシテイン(1835〜1881)はチャイコフスキーにこの事件の犠牲者たちの追悼演奏会のための作品を依頼し、愛国心に駆られたチャイコフスキーは《セルビア=ロシア行進曲》と題された作品をわずか5日間で作曲しました。この作品はモスクワで初演された後に改稿され、現在の《スラヴ行進曲》の原型となりました。
葬送行進曲のような重々しい低音に始まり、セルビア民謡『太陽は明るく輝かず』の持つ哀調溢れる旋律がヴィオラとファゴットで悲しげに奏でられるところから曲が始まります。中間部に入ると、同じくセルビア民謡の『懐かしいセルビアの戸口』からの快活なメロディ、続いて同じくセルビア民謡の『セルビア人は敵の銃を恐れない』からの勇壮なメロディが繰り出されていきます。
その後、曲の冒頭で登場した主題が情熱的に再現されます。終盤に入ってからは帝政ロシア国歌『神よ、皇帝を護りたまえ』が力強く歌い上げられ、勝利を暗示するかのような祝祭的な響きに包まれながら曲が締めくくられます。
《スラヴ行進曲》は1876年11月5日、グレゴリオ暦では11月17日にモスクワで開催された『ロシア音楽協会第1回交響楽演奏会』で、ルビンシテインの指揮で初演されました。これにはチャイコフスキーも出席し、後に
「先週の土曜日、ここでセルビア・ロシア行進曲(後のスラヴ行進曲)が初めて演奏された。それは愛国的熱狂の完全な嵐を巻き起こした。」
と妹に書き送っています。
またこの演奏会の様子を書き留めた文章が保存されていて、それには
「行進曲の演奏のあと、場内に起こった人々の叫び声は筆舌に尽くしがたい。全聴衆は立ち上がり、ブラボーの叫びの中にウラー(万歳)の叫びが入り混じった。」
「行進曲は再演され、再び嵐が巻き起こった。これは1876年の最も感動的瞬間のひとつであり、場内では多くの人々が泣いた。」
と記されています。
この作品には帝政ロシア国歌『神よ、皇帝を護(まも)りたまえ』が引用されていることから、旧ソ連時代にはオリジナルでの演奏が禁止されていました。ソ連崩壊後はロシアでもオリジナル通りに演奏されるようになりましたが、ロシアによるウクライナ侵攻後は
「ロシアを賛美する音楽は如何なものか」
という一部の意見により、今度は日本でロシア国歌のメロディを含む《スラヴ行進曲》と《大序曲『1812年』》が自主規制的にプログラムから外されています。
時勢を思えば致し方ないのかも知れませんが、あえて言わせていただくなら
『あくまでもチャイコフスキーの芸術作品なのだから、四の五の言わずやりたければやればいい』
と個人的には思っています。何事か起こる度に芸術作品が真っ先に槍玉に挙げられ忖度の対象となるのは、絶対に間違っています。
そんなわけで、今日はチャイコフスキーの《スラヴ行進曲》をお聴きいただきたいと思います。アレクサンドル・スラドコフスキー指揮、タタールスタン国立管弦楽団の演奏でお楽しみください。