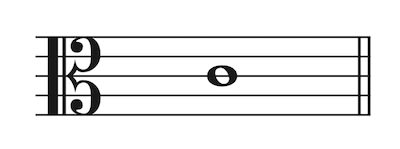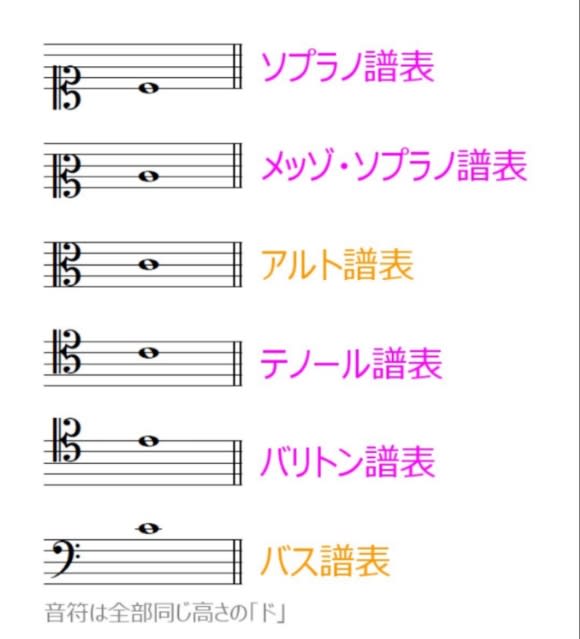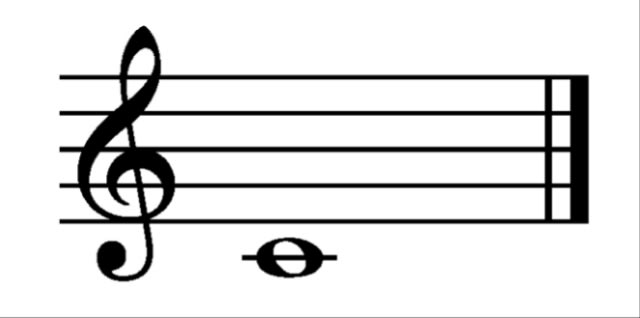今日はかなり暖かな陽気となりました。この勢いだと桜の蕾も膨らんでしまいそうですが、週明けからまた冷え込みが戻ってくるようなので、ことはそう安々とは進まないようです。
ところで、今日2月16日はゴセックの祥月命日です。

フランソワ=ジョゼフ・ゴセック(1734〜1829)は、フランスで活躍したベルギー出身の作曲家・指揮者です。
『…誰?』
と思われる方もおいでかと思いますが、

ヴァイオリンのための愛らしい小品《ガヴォット》の作曲家といえば、分かっていただける方も多いのではないでしょうか。
現在はこの《ガヴォット》1曲のみによって知られているゴセックですが、実は交響曲の大家で30曲近くの交響曲を書きました。パリ音楽院創立の際には作曲の分野における教授として招かれていて、共和政・帝政時代の革命歌の作曲家としても歴史的に名を残している人物です。
ゴセックは95年という当時としては異例とも言える長い生涯を過ごし、大雑把に言えばバロック音楽の終焉から初期ロマン派音楽の勃興までに遭遇した稀有な人物でした。同じような時期を過ごした長寿の作曲家といえば

フランツ・ヨーゼフ・ハイドン(1732〜1809)が有名ですがそれでも77年の生涯ですから、ゴセックが如何に長生きしたかが分かるかと思います。
多くの交響曲を作曲したゴセックでしたが、次第に交響曲の作品数を減らしていってオペラに集中するようになると、1784年に『エコール・ドゥ・シャンÉcole de Chant (唱歌伝道所)』を設立し、フランス革命の際には作曲家エティエンヌ・メユール(1763〜1817)とともに救国軍の楽隊指揮者を務めました。1795年にパリ音楽院が設立されるとルイジ・ケルビーニ(1760〜1842)やメユールとともに視学官に任命され、フランス学士院の最初の会員に選ばれるとともに、レジオンドヌール勲章を授与されました。
しかし、1815年にワーテルローの戦いでナポレオンが敗北するとパリ音楽院はしばらく閉鎖に追い込まれ、当時81歳のゴセックも引退を余儀なくされてしまいました。その後は音楽院近くで年金暮らしを続けながら、最後の作品となる3曲目の《テ・デウム》の作曲に1817年まで取り組んでいました。
ゴセックはフランスの外ではほとんど無名であり、おびただしい数の作品は、宗教音楽も世俗音楽もともに同時代のより有名な作曲家の陰に隠れていってしまいました。そして1829年の2月16日、ゴセックはパリ郊外のパシーに没しました(享年95)。
そんなゴセックの祥月命日である今日は、《レクイエム》をご紹介しようと思います。
18世紀の後半になると、フランスではレクイエムに大きな変化が現れていました。それはオペラ的要素が加わったばかりでなく曲全体が長大となり、特にセクエンツィアの〈怒りの日〉が楽曲の大きな部分を占めるようになっていったのですが、この作品はその顕著な例となっています。
1760年3月に、当時のパトロンであったコンデ公の妻シャルロット・ド・ロアンが亡くなるとゴセックはその追悼のために《レクイエム》を作曲し、同年5月に初演しました。この曲は演奏に1時間半を要する大作で、オラトリオ以外の宗教音楽としては当時異例の長さでした。
ゴセックはこの《レクイエム》で、最初の大成功を収めました。中でも『トゥーバ・ミルム(妙なるラッパ)』部分の管弦楽法は当時としては驚くべきもので、ゴセック自身によれば
「〈怒りの日〉の3章と4章で3本のトロンボーン、4本クラリネット、4本のトランペット、4本のホルン 、8本のファゴットが教会の見えない場所や、高いところから最後の審判を告げたので、聴衆は恐怖に包まれた。その時オーケストラの全部の弦楽器がトレモロを弾き続けたのは、その恐怖の表現だったのである」
と言っています。
また、京都ノートルダム女子大学元学長の相良憲昭氏(1943〜2020)はゴセックの《レクイエム》の先進性について
「ゴセックの《レクイエム》は、おそらく当時のもっとも前衛的な曲の一つだったのではないだろうか。バッハが死んで十年、ヘンデルの死の翌年にこのような曲が生まれたのは驚くばかりである。」
「勿論、対位法の用い方にはバロック音楽の体臭を濃厚に感じとることができるが、大胆なオーケストレーションや壮麗極まりないホモフォニックな旋律などは古典派の全盛期の例えば、ハイドン晩年の『ミサ曲』やベートーヴェンのオペラ 『フィデリオ』、さらにはベルリオーズの『レクイエム』すらを予見させるものがある」
と評しています。
この作品を称賛したモーツァルトは、1778年のパリ滞在中にゴセックを訪ねました。そして、
「とてもいい友人になりました。とても素っ気ない人でしたが。」
という会見記を父レオポルトに書き送っています。
そんなわけで、今日はゴセックの《レクイエム》をお聴きいただきたいと思います。フランソワ=グザヴィエ・ロト指揮による演奏で、現在では愛らしい《ガヴォット》のみで知られるゴ豪華で壮麗な鎮魂歌をお楽しみください。
因みに、この動画の『トゥーバ・ミルム』は21:05から始まります。バルコニーの上から降り注ぐ、最後の審判のラッパの迫力も聴きどころです。