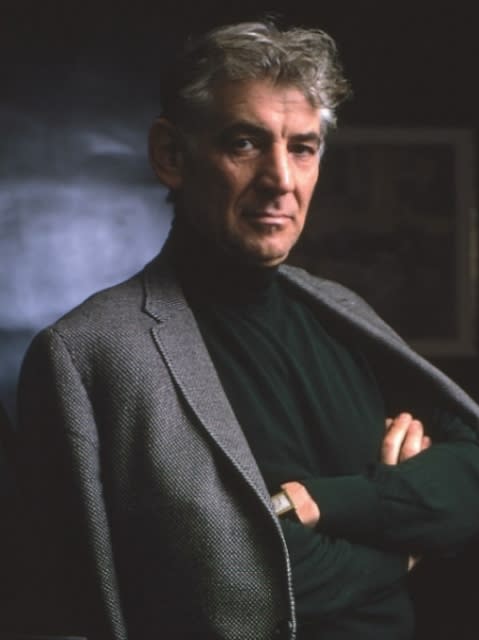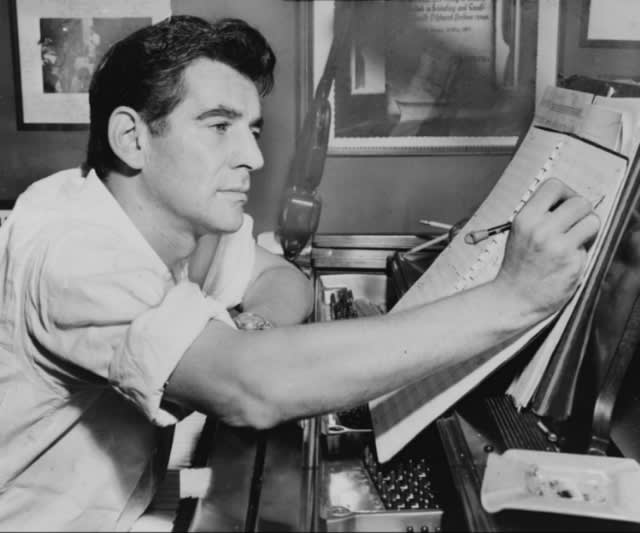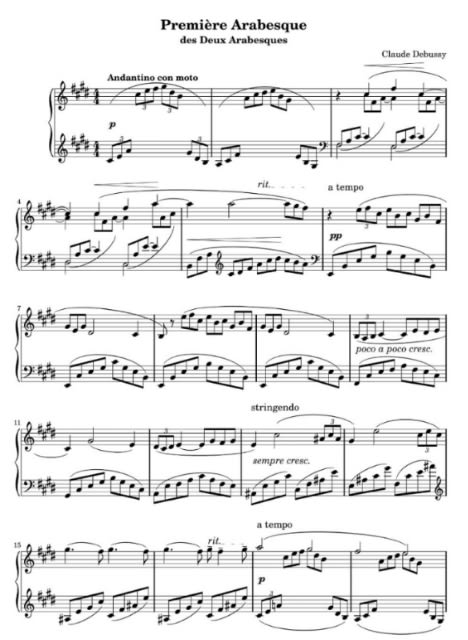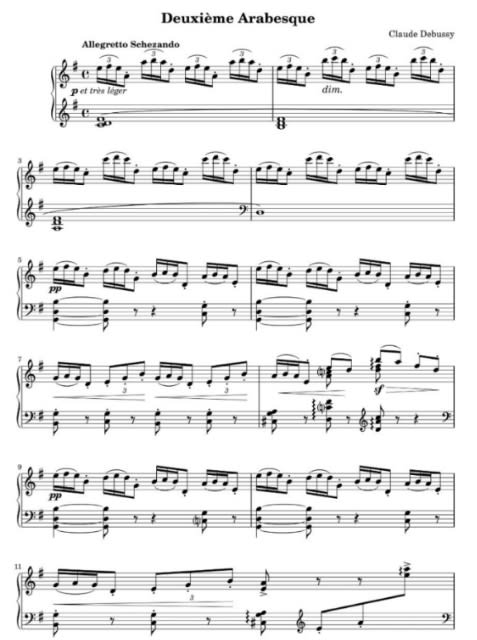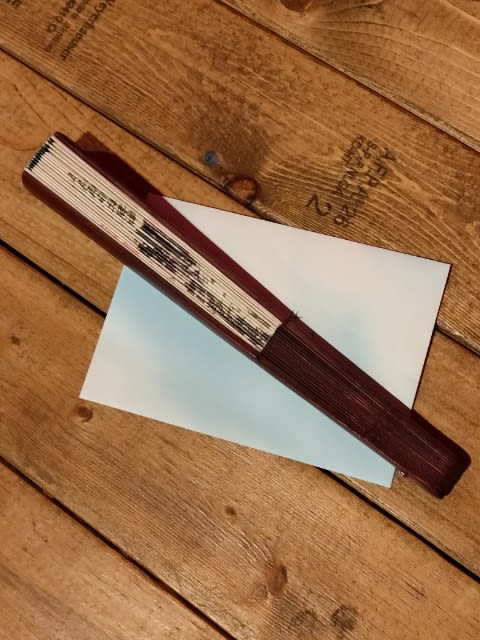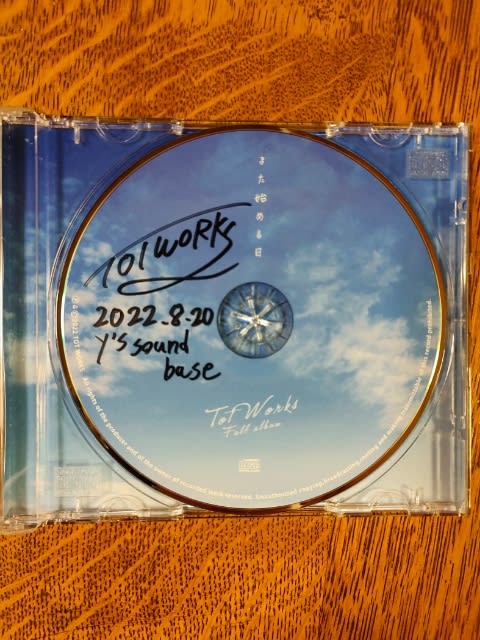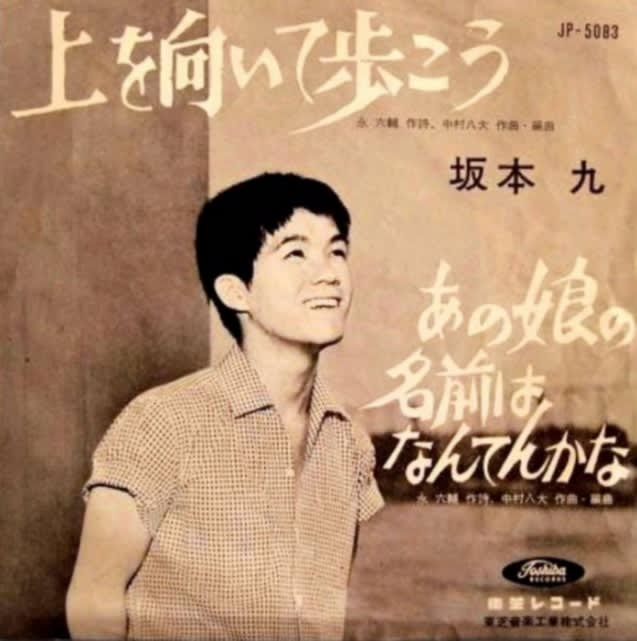今日の厚木市は、滝のような凄まじい豪雨で明けました。窓の外には向こう側が白く煙るほどの雨が降りしきり、道行く人が傘などさしても全く役立たない様子でした。
そんな豪雨も少しずつ弱まってきたので、間隙をついて本厚木駅まで出かけ、小田急線に乗り込んで一路東京・上野を目指しました。そして上野公園を横切って、東京藝術大学大学美術館に向かいました。
現在、こちらでは

特別展《日本美術をひも解く〜
皇室・美の玉手箱》という展覧会が開催されています。この展覧会は明治以降に様々なところから皇室に献上されたものや、明治天皇や旧宮内省が、日本の伝統技術の継承を図ったり、パリの万国博覧会に出品させるためだったりといった様々な目的で作らせた工芸品など、皇室に伝えられた品々を収蔵する宮内庁三の丸尚蔵館の名品、優品約90件で日本美術をわかりやすく紹介しているものです。
この展覧会は前期と後期で展示替えがあり、9月4日までが前期展示となっています。どちらも興味深い作品が展示されているのですが、とりあえず前期展示で印象深かったものを取り上げてみたいと思います。
先ずは何と言っても注目なのは、会場に入ってすぐのところに展示されている
『菊蒔絵螺鈿棚(きくまきえらでんだな)』です。これは明治天皇が日本の工芸技術の継承を目的として東京美術学校(現在の東京藝術大学)に図案を依頼し、皇居内に設けられた製作所に登場一級の指物師や蒔絵師、彫金師、螺鈿細工師らを集めて約9年の歳月をかけて完成させたもので、日本ならではの優美で繊細な感覚と、熟達した伝統技術が細部に至るまで結集された完成度の高い作品です。
棚の天板や扉、縦横に渡された柱に至る全ての部分に金蒔絵が施され、扉の留め金には皇室の紋章である菊と五七の桐が彫金の透かし彫りで表されています。そして螺鈿で表された菊の花や小鳥たちの輝きはそれは見事なもので、見る角度を変えると赤や黄色、青や碧や紫へと刻々と色を変えて輝きます。
360度どこからでも観賞できる展示なので裏側に回ったり、しゃがんで観たりといろいろな角度で観賞しましたが、どこから観ても全く飽きません。高さや角度を変えながら繊細な金蒔絵と華やかな螺鈿の輝きに見入っていたら、気づくとこの棚だけで1時間近く時間を使ってしまっていました(汗)。
次に印象深かったのは、

鎌倉時代に制作された絵巻物《蒙古襲来絵詞(もうこしゅうらいえことば)》です。この作品は日本史の教科書の元寇のところにも載っているので、御存知の方も多いのではないでしょうか。
これは肥後国の御家人竹崎季長(たけざきすえなが)が、元寇における自分の戦功を描かせた絵巻物です。現在は宮内庁三の丸尚蔵館の所蔵となっていて、昨年9月に国宝に指定されています。
季長は自身の元寇での働きを鎌倉幕府に伝えて恩賞を得るために、この絵巻物を作らせたと伝わっています。それ故に戦闘シーンはかなりの迫力で描かれていて、文永の役・弘安の役が如何に過酷な戦いであったかを垣間見ることができます。
興味深いのは日本の武士と元軍の武具や武器の違いで、日本の武士の甲冑姿に対して元軍の装束はかなり動きやすそうなものとなっています。そして、戦いに使用されている弓矢にも形状の違いが見て取れます。
そして一番特徴的なのが

『てつはう』と書かれた元軍の武器です。平仮名だけ見ると鉄砲のように思いますが、実際には鉄球に火薬を詰めて投げつける手榴弾のようなものだったようです。
戦にあたっては「やあやあ我こそは〜」と名乗りを上げてから戦い始める日本の武士たちにしてみたら、元軍からこんな飛び道具がいきなり飛んでくるのですからたまったものではなかったことでしょう。それ故に戦功を挙げた季長としては、恩賞を得るために如何に自身が過酷な戦闘を生き抜いてきたかを鎌倉幕府に猛烈にアピールする必要に迫られていたわけですから、この絵巻の制作には並々ならぬ思いがあったことでしょう。
この《蒙古襲来絵詞》は江戸時代に大規模な修復が施され、上下2巻に分けられました。その時にいろいろと改竄もされてしまったようですが、それでも
◎絵の中に日元双方の軍船が描かれていて、中には武士の他に漕ぎ手の水夫が乗っている場合と、水夫がおらず雑兵が舟を漕いでいる場合とがあること。
◎日本軍は陣鐘も陣太鼓も用いていないのに対して、元軍では既に鳴り物を用いた集団戦法が発達していること。
◎日本軍と元軍の弓矢の形状の違い。
◎元軍は投げ槍を多く使っているのに対して日本軍では殆ど用いられておらず、長刀を使っているのは雑兵に限られていること。
といった歴史的資料としての価値が高いといわれています。
次に印象深かったのは《唐獅子図屏風(からじしずびょうぶ)》です。これまた教科書に掲載されていることが多い作品なので、御存知の方も多いかと思います。
《唐獅子図屏風》は安土桃山時代の絵師である狩野永徳による作品で、永徳による代表作かつ最も著名な作品です。この作品は元々城の障壁画として描かれたもので、

このように平らな形だったようです。それを後の時代に屏風に仕立て直したことで

こうした姿となり、明治21(1888)年に毛利家から皇室に献上されました。
この屏風の特徴は、とにかくデカいことです。写真のショーケースとの対比でもお分かりいただけるかと思いますが、右隻の大きさは縦223.6×横451.8cm、左隻の大きさは縦224.0×横453.5cmもある巨大なものです。
その巨大さ故に、この絵は豊臣秀吉が建てた大阪城や聚楽第にあったものではないかとも言われていますが、詳細は分かっていません。また、どういった経緯で毛利家に伝わったのかも不明なようです。
因みに狩野永徳が描いたのは右隻の方だけで、左隻の方は17世紀になって永徳の曾孫の狩野常信(つねのぶ)が曽祖父の作品に合わせて新たに描いたものです。こちらも昨年9月に国宝に指定されています。
青い体の雄獅子と黄色い体の雌獅子とが仲睦まじく歩く姿は雄々しいながらもどこか愛らしく、後に常信によって描かれた左隻の子獅子の姿は勇壮ながらもどこか無邪気さを感じさせます。こんな巨大な屏風を背にして座っていたら、さぞかし威厳に満ちて見えたことでしょう。
他にも、尾形光琳が琳派の祖である俵屋宗達の作品を模写した《西行法師絵巻》や
 琳派の画家酒井抱一が月毎の花鳥を描いた《花鳥十二ヶ月図》全12幅、
琳派の画家酒井抱一が月毎の花鳥を描いた《花鳥十二ヶ月図》全12幅、

葛飾北斎の肉筆画《西瓜図》や、明治期に
パリ万国博覧会に出品するために作られた金工や象牙の置物、有線七宝の花瓶といった日本の工芸技術の粋を集めた工芸品が展示され、訪れた人たちはその収蔵品の多様さに見入っていました。
この展覧会は、9月5日から後期日程に入ります。その時には伊藤若冲の大作《動植綵絵(どうしょくさいえ)》全10幅が展示されるなど見どころ満載なので、その時にまた改めて来てみようと思います。