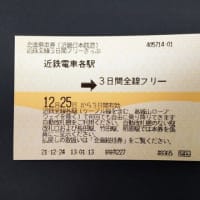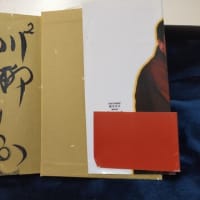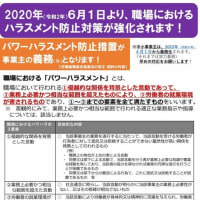# 「現代落語論」(談志)読了。
近年の談志の記述と比べると多少違いがあり、
より寛大で「様々な落語を認めよう」という感じがする。
しかし、このレベルの本が
真打に昇進して2年やそこら、
年齢的にも30歳前後で出版されているのは、
やはり凄いことだなあ。
昨日は本町の自社に戻って少し事務的な作業を片付け、
19時頃に出てタクシーで「繁昌亭」へ。
「三喬・南左衛門ふたり会」。
南左衛門は確か「大銀座落語祭」で見たが、
三喬はかなり長い間見ていない。
繁昌亭に入ると、南左衛門の1席目「お紺殺し」のマクラの途中。
タクシーを飛ばしてきた甲斐があったというもの。
「お紺殺し」(南左衛門):○+
やはり、この人、声が素晴らしい。
この声を聞くだけで金を払う価値がある、と思う。
男の声に陰影があり、
口ではどうにか宥めようとしつつ、
腹では「弱ったな」と思っていることが感じ取れた。
一度、男の言い訳を受け入れて積年の恨みが晴れた後で、
だまされて殺される、という流れから、
さらに恨みを募らせる、といった構造は
よく出来ている話だと思う。
ただ「怪談」としては、
お紺が殺された怨みを晴らすあたり、
もっと手替え品替え次第に積み上げていっても良いのでは、と感じた。
あっさり男を殺してしまった感じ。
「荒大名の茶の湯」(南左衛門):○
よく演っている話。「大銀座落語祭」でも喰らった覚えがある。
まあ、下品でよくウケる話。
茶を飲んでいく場面で、
一度隣の大名の視点でツッコミが入った後、
元の大名が口を拭ってから廻す、と言うのが
科白廻しとして少し分かりづらい。
一瞬、名前をトチったのかと思う。
あと、個人的には「茶碗を回す」場面は不要で、
正則が「バリバリ茶菓子を食べる」ところで
「こんな面白い茶会」として終わっても良いのでは、と感じた。
しかし個々の大名の雰囲気が出ていて結構。
「住吉駕籠」(三喬):△+
出囃子が、今は亡き文紅の「お兼晒し」。
好きな曲だから良いのではありますが。
マクラは見台膝隠しの話から乗り物の話。
今の乗り物は「戻ってこない」という視点は面白かった。
ネタは、今までになく、松喬の匂いを感じるものだった。
(私はこの人に、師匠の影響をあまり感じていなかったのだが)
アホの口調の作り方とか、酔っ払いの喋り方とか。
ただそのあたり、徹底していなかった感じはする。
よくウケていたのだが、
ところどころ設定に矛盾を感じる。
例えば、茶店の主には「こいつ昨日この界隈に降ってきた」と言い訳しつつ、
最後の場面(三喬オリジナルだと思うが)で
「東京の街道筋でずっと流していた」(一緒にやってきた感じがする)と
言うとか。
台詞廻しにやけに熟語が混じり、
まあそれでウケをとる訳だが
それは普通は落語の登場人物が使う言葉ではないよな、と思ったり。
あと、「手尽くし」の客を出すならば
その嫁さんも出すのが良いと思う。
オリジナル?のサゲは初めて聞いたが、
持っていき方をくどく感じること、
サゲの設定が浮いている(付け足しっぽい)ところ、
特に良いとは思えんなあ。
終わって後輩と軽く飲んでおしまい。
近年の談志の記述と比べると多少違いがあり、
より寛大で「様々な落語を認めよう」という感じがする。
しかし、このレベルの本が
真打に昇進して2年やそこら、
年齢的にも30歳前後で出版されているのは、
やはり凄いことだなあ。
昨日は本町の自社に戻って少し事務的な作業を片付け、
19時頃に出てタクシーで「繁昌亭」へ。
「三喬・南左衛門ふたり会」。
南左衛門は確か「大銀座落語祭」で見たが、
三喬はかなり長い間見ていない。
繁昌亭に入ると、南左衛門の1席目「お紺殺し」のマクラの途中。
タクシーを飛ばしてきた甲斐があったというもの。
「お紺殺し」(南左衛門):○+
やはり、この人、声が素晴らしい。
この声を聞くだけで金を払う価値がある、と思う。
男の声に陰影があり、
口ではどうにか宥めようとしつつ、
腹では「弱ったな」と思っていることが感じ取れた。
一度、男の言い訳を受け入れて積年の恨みが晴れた後で、
だまされて殺される、という流れから、
さらに恨みを募らせる、といった構造は
よく出来ている話だと思う。
ただ「怪談」としては、
お紺が殺された怨みを晴らすあたり、
もっと手替え品替え次第に積み上げていっても良いのでは、と感じた。
あっさり男を殺してしまった感じ。
「荒大名の茶の湯」(南左衛門):○
よく演っている話。「大銀座落語祭」でも喰らった覚えがある。
まあ、下品でよくウケる話。
茶を飲んでいく場面で、
一度隣の大名の視点でツッコミが入った後、
元の大名が口を拭ってから廻す、と言うのが
科白廻しとして少し分かりづらい。
一瞬、名前をトチったのかと思う。
あと、個人的には「茶碗を回す」場面は不要で、
正則が「バリバリ茶菓子を食べる」ところで
「こんな面白い茶会」として終わっても良いのでは、と感じた。
しかし個々の大名の雰囲気が出ていて結構。
「住吉駕籠」(三喬):△+
出囃子が、今は亡き文紅の「お兼晒し」。
好きな曲だから良いのではありますが。
マクラは見台膝隠しの話から乗り物の話。
今の乗り物は「戻ってこない」という視点は面白かった。
ネタは、今までになく、松喬の匂いを感じるものだった。
(私はこの人に、師匠の影響をあまり感じていなかったのだが)
アホの口調の作り方とか、酔っ払いの喋り方とか。
ただそのあたり、徹底していなかった感じはする。
よくウケていたのだが、
ところどころ設定に矛盾を感じる。
例えば、茶店の主には「こいつ昨日この界隈に降ってきた」と言い訳しつつ、
最後の場面(三喬オリジナルだと思うが)で
「東京の街道筋でずっと流していた」(一緒にやってきた感じがする)と
言うとか。
台詞廻しにやけに熟語が混じり、
まあそれでウケをとる訳だが
それは普通は落語の登場人物が使う言葉ではないよな、と思ったり。
あと、「手尽くし」の客を出すならば
その嫁さんも出すのが良いと思う。
オリジナル?のサゲは初めて聞いたが、
持っていき方をくどく感じること、
サゲの設定が浮いている(付け足しっぽい)ところ、
特に良いとは思えんなあ。
終わって後輩と軽く飲んでおしまい。