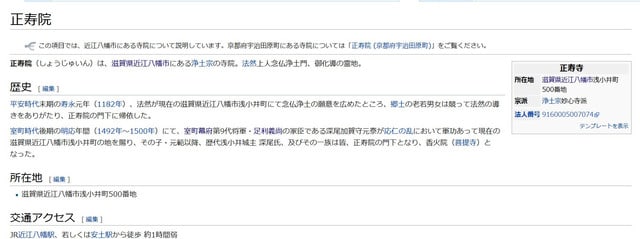加地信実の娘が浅小井泰長の妻になっている。ということは、加地実秀の姉か妹である。
そして浅小井氏には加地佐々木氏が入っているということになる。
浅小井泰長の系図の註には「深尾次郎 右衛門尉 飛騨守 文暦卒」とある。
泰長の息 家長の註「深尾太郎 式部太輔 佐々木右衛門尉 母加地太郎信実 定綱四男左衛門定高成猶子號佐々木」とあるではないか。調べてみると式部太輔の他のメンバーを見ると「大江・中原・菅原・大中臣…」のような文官系と思われるのだが、右衛門尉である。
浅小井氏の始まりが行実で母親が紀氏である。その息【盛実】が佐々木宮神主とある。
そのあたりで、やはり祭祀等を行う血脈なのかもしれない。
この盛実は、三上新太夫=浅小井盛実であろうとの意見もあり(佐々木哲学校のコメント欄)、ますます神社とのつながりの強さを感じる。
佐々木行実ー盛実ー家実ー長家ー清長ー泰長ー家長ー公宣ー氏輝(重宣)…というのが浅小井深尾氏の嫡流。
清長には清家と、後に奥島氏となる義長。
清長の息には泰長の他に安顕・義清がおり、義清の息が山田氏となる。
さて、家長の註「母加地太郎信実 定綱四男左衛門定高成猶子號佐々木」の部分だが
定綱の四男定高とある。他の系図では三男定高である。
公卿類別譜には定高━定時━定清(右衛門尉、或左衛門尉)とある。
家長はその定時にあたるのだろうか???
定時は本名:太郎時定とある。また、別の系図では「沢田氏」となっている。
姓氏家系大辞典では、
澤田氏【安倍氏族、佐々木氏流】尊卑分脈に「佐々木定綱―定高(澤田)―定時(本時定)―定淸」、また淺羽本佐々木系図に「時定(澤田太郎左衛門)定淸(澤田源太郎左衛門)」と見える。・・・とある。
また、「六角家臣団」のwebページにも澤田氏が出ていた。
よくわからないが、佐々木定高は土佐に配流にされていること(建久二年の強訴)と、母を同じくする盛綱の元暦元年(1184年)12月、平氏追討の為備前国児島に在り、息:信実の娘が後に児島にあって道乗を産むことにつながっていく。
そのことと何かが絡んでいくように思えるのだが…
その信実の姉妹か本人が浅小井家長を産む。
~~~*~~~
感じであるが、「中条家長」???とつながっていく???
その周辺がwebにあるのだが、「東寺長者道乗は父頼任親王、母を、加地信実の女で、祖父北条時政としていた。」とある。確かに「阿波局」は時政の娘にもいる。が、義時の母も「阿波局」(加地)なのだ。
加地信実の娘の息=信実の孫「道乗」の妻となるのが上沢中条家長の娘となるようだ。
道乗の義父が家長ということになる。
浅小井家長と中条家長とは、別人であるが近い所にいるようだ。浅小井家長の母親の年代に中条家長がいる。
もう一度年代も含めて考えてみると、
頼仁親王(よりひとしんのう、建仁元年7月22日(1201年8月22日) - 文永元年5月23日(1264年6月18日)
道乗は1220年位の生まれと仮定する。
その妻は1225年位とする。
家長は(1165年-1236年)
一方の浅小井家長は1220年生まれ位と思われる。
加地信実の娘でweb上にあるのは「阿波局」である。北条泰時(1183年~1242年)の母となる人物である。
泰時を産んだのが1183年ということは、泰時の母と「道乗の母・浅小井の母」とは別人と思われる。
道乗の母と浅小井の母とは同一人物かもしれない。姉妹かも知れない。
中条家長は(1165年~1236年)鎌倉時代の武将。義勝法橋盛尋(中条兼綱)の子である。・・・とある。
家長の叔母は宇都宮宗綱に嫁いで八田知家(1142年~1218年)を生んだ女性で、頼朝の乳母の一人としても知られる近衛局であった。・・・とある。
上沢家長は中条家長であり、同時に宇都宮・八田氏の養子となる。つまりは中原氏でもあるのだ。
…とすれば、式部太輔もあり得るように思えてくるのである。
~~~*~~~
かなり複雑で…もっとすっきりと書きたい!