2012年10月2日に東京都台東区上野の国立科学博物館の日本館講堂で開催された公開ワークショップ「生物多様性を規範とする革新的材料技術」を拝聴した話の続きです。
全体で10件程度発表された講演の中で、一番インパクトを感じたのは、北海道大学大学院教授の長谷山美紀さんが説明した、技術革新の着想が得られる発想支援型データベース開発に着手している話です。
長谷山さんは「生物学と工学の連携基盤になるバイオミメティクス・データベースを構築します。このデータベースでは、技術革新の着想が得られる発想支援型の仕組みを組み込んだ“知の構造化”を実現します」と発表しました。
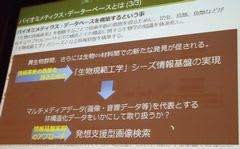
文部科学省が平成24年度(2012年度)の科学研究費の新学術領域として設けた「生物多様性を規範とする革新的材料技術」プロジェクトは、3つのグループで構成されています。中核となるのは、生物規範設計を実際に担当する「B01」グループです。具体的には、生物が持つ機能などを解明して革新的材料技術を産み出す研究グループです。
生物規範設計を担当する「B01」グループに、新しい発想を産み出すツールとなるデータベースを提供するのが、長谷山さんが所属する「A01」グループです。生物規範の基盤となるデータベースを構築するのが目標ですが、「専門分野が異なる研究者に対して、形式知になっていない暗黙知のクラスターを提供し、暗黙知クラスターから形式知を見いだす“気づき”を提供することを目指しています」と説明します。分類されたデータを提供するのではなく、新しい発想を提供するツールとなる生きているデータベースだそうです。
長谷山さんの研究グループは、科学技術振興機構(JST)の研究ファンドを受けて、既に先行研究を始めているそうでうす。10月2日の講演では、発想支援型仕組みを盛り込んだバイオミメティクス・データベースの先行事例として、昆虫の身体の微細構造を示す、走査型電子顕微鏡(SEM)の画像データベースを発表しました。この画像データベースから関連するクラスターを作成した際に、予想したクラスター以外に、別のクラスターがつくられている実例を示しました。「用いた画像データには簡単なタグ(基本情報)しか付けていないが、異種データベースを横断検索すると、暗黙知クラスターを作成する能力を持っている」と説明します。
日本には大学などの学術組織が作成したさまざまなデータベースが多数あります。ところが、これらを横断的に検索し、本当にほしいデータや、予想もつかなかったデータを提供するスーパーデータベースはまだ発展途上です。まさに、“ビッグデータ”をどう使いこなすかという根本的な課題になります。
生物規範設計を担当する「B01」グループの技術シーズを受けて、3番目の生物規範社会学を担当する「C01」グループは、生物規範工学を、社会に安全かつ効果的に普及させる役割を担うそうです。この中では、TRIZ法という発想術を用いた革新的問題解決法などを確立する研究も実施される計画だそうです。

人間は、昆虫などの多様な生物から多くのことを学ぶ時代を迎えています。その生物が持つ多様性から形式知を抽出するツールとなるデータベースの構築は、始まったばかりです。今後は、予想もしなかった知識が産まれてくる可能性があると、なんとか学びました。専門用語の海で、おぼれかけましたが。
全体で10件程度発表された講演の中で、一番インパクトを感じたのは、北海道大学大学院教授の長谷山美紀さんが説明した、技術革新の着想が得られる発想支援型データベース開発に着手している話です。
長谷山さんは「生物学と工学の連携基盤になるバイオミメティクス・データベースを構築します。このデータベースでは、技術革新の着想が得られる発想支援型の仕組みを組み込んだ“知の構造化”を実現します」と発表しました。
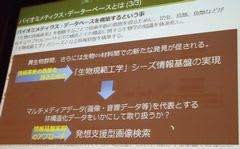
文部科学省が平成24年度(2012年度)の科学研究費の新学術領域として設けた「生物多様性を規範とする革新的材料技術」プロジェクトは、3つのグループで構成されています。中核となるのは、生物規範設計を実際に担当する「B01」グループです。具体的には、生物が持つ機能などを解明して革新的材料技術を産み出す研究グループです。
生物規範設計を担当する「B01」グループに、新しい発想を産み出すツールとなるデータベースを提供するのが、長谷山さんが所属する「A01」グループです。生物規範の基盤となるデータベースを構築するのが目標ですが、「専門分野が異なる研究者に対して、形式知になっていない暗黙知のクラスターを提供し、暗黙知クラスターから形式知を見いだす“気づき”を提供することを目指しています」と説明します。分類されたデータを提供するのではなく、新しい発想を提供するツールとなる生きているデータベースだそうです。
長谷山さんの研究グループは、科学技術振興機構(JST)の研究ファンドを受けて、既に先行研究を始めているそうでうす。10月2日の講演では、発想支援型仕組みを盛り込んだバイオミメティクス・データベースの先行事例として、昆虫の身体の微細構造を示す、走査型電子顕微鏡(SEM)の画像データベースを発表しました。この画像データベースから関連するクラスターを作成した際に、予想したクラスター以外に、別のクラスターがつくられている実例を示しました。「用いた画像データには簡単なタグ(基本情報)しか付けていないが、異種データベースを横断検索すると、暗黙知クラスターを作成する能力を持っている」と説明します。
日本には大学などの学術組織が作成したさまざまなデータベースが多数あります。ところが、これらを横断的に検索し、本当にほしいデータや、予想もつかなかったデータを提供するスーパーデータベースはまだ発展途上です。まさに、“ビッグデータ”をどう使いこなすかという根本的な課題になります。
生物規範設計を担当する「B01」グループの技術シーズを受けて、3番目の生物規範社会学を担当する「C01」グループは、生物規範工学を、社会に安全かつ効果的に普及させる役割を担うそうです。この中では、TRIZ法という発想術を用いた革新的問題解決法などを確立する研究も実施される計画だそうです。

人間は、昆虫などの多様な生物から多くのことを学ぶ時代を迎えています。その生物が持つ多様性から形式知を抽出するツールとなるデータベースの構築は、始まったばかりです。今後は、予想もしなかった知識が産まれてくる可能性があると、なんとか学びました。専門用語の海で、おぼれかけましたが。









