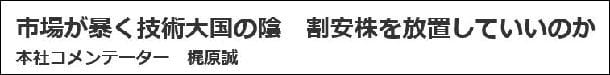2019年10月24日から東京モーターショー2019が東京都江東区有明の東京ビッグサイト(国際展示場)などで始まりました。
今回は、会場が東京ビッグサイトと青海展示棟の2カ所に分かれて開催されています。青海展示棟部分では、体験乗車できるコースを設けたために、2カ所に分かれたようです。
その青海展示棟に設けられたトヨタ自動車の展示会場では、未来の移動社会をイメージしたコンセプト車を公開しています。
未来の移動社会では、日ごろの移動手段としては、無人運転車になるとアピールしています。自動運転電気自動車(EV)の「イーパレット」は無人運転車ですが、移動店舗にも使えるという仕様です。
イーパレットの小型版「マイクロパレット」は、病院に向かう途中の車内で医者から問診を受けることを前提としていて、移動中に問診を済ませのために、病院に着いた瞬間から診察が始まるという仕様です・


1人乗りの自動運転車などでは、自分の好みに合わせて仕様をつくり込んだ内装を想定し、移動中に、それを利用します。
トヨタ自動車の豊田章男社長は「人を中心とした未来のモビリティー社会を体験してほしい」と説明しています。

豊田社長は「今回のトヨタブースには来年発売される車はひとつもない。未来の社会とまちで移動サービスを提供するモビリティーばかり置いている」と説明しました。
このトヨタブースにはスポーツコンセプトEV車「イーレーサー」(e-RACER)も展示されています。




未来のモビリティー社会が自分で運転しない無人運転車になると、逆にプライベートな時間では、自分で運転するスポーツカーがほしくなり、所有すると説明しています。
以前にテレビコマーシャルで豊田社長は「馬車などに使うウマはいなくなったが、競走馬は残った」と語り、個人がスポーツ目的で乗る個人用カーは生き残ると説明しています。
トヨタ自動車の展示会場では、未来の移動社会をイメージしたコンセプト車だけですが、もちろんトヨタ自動車系のレスサスの展示会場では、発売予定の電気自動車を展示しています。
レスサスの展示会場では電気自動車のコンセプトカー「LF-30 Electrified」を公開しています。


この電気自動車では、各ホイールにモーターを配置した“インホイールモーター”方式を採用しています。4つのホイール・タイヤが一つひとつ独立して動き、自由に駆動力を制御ことができるという仕様です。“インホイールモーター”方式はコンセプトカーでは実際に使われていますが、市販車では初めての採用です。
この電気自動車「LF-30 Electrified」は市販される予定です。
今回は、会場が東京ビッグサイトと青海展示棟の2カ所に分かれて開催されています。青海展示棟部分では、体験乗車できるコースを設けたために、2カ所に分かれたようです。
その青海展示棟に設けられたトヨタ自動車の展示会場では、未来の移動社会をイメージしたコンセプト車を公開しています。
未来の移動社会では、日ごろの移動手段としては、無人運転車になるとアピールしています。自動運転電気自動車(EV)の「イーパレット」は無人運転車ですが、移動店舗にも使えるという仕様です。
イーパレットの小型版「マイクロパレット」は、病院に向かう途中の車内で医者から問診を受けることを前提としていて、移動中に問診を済ませのために、病院に着いた瞬間から診察が始まるという仕様です・


1人乗りの自動運転車などでは、自分の好みに合わせて仕様をつくり込んだ内装を想定し、移動中に、それを利用します。
トヨタ自動車の豊田章男社長は「人を中心とした未来のモビリティー社会を体験してほしい」と説明しています。

豊田社長は「今回のトヨタブースには来年発売される車はひとつもない。未来の社会とまちで移動サービスを提供するモビリティーばかり置いている」と説明しました。
このトヨタブースにはスポーツコンセプトEV車「イーレーサー」(e-RACER)も展示されています。




未来のモビリティー社会が自分で運転しない無人運転車になると、逆にプライベートな時間では、自分で運転するスポーツカーがほしくなり、所有すると説明しています。
以前にテレビコマーシャルで豊田社長は「馬車などに使うウマはいなくなったが、競走馬は残った」と語り、個人がスポーツ目的で乗る個人用カーは生き残ると説明しています。
トヨタ自動車の展示会場では、未来の移動社会をイメージしたコンセプト車だけですが、もちろんトヨタ自動車系のレスサスの展示会場では、発売予定の電気自動車を展示しています。
レスサスの展示会場では電気自動車のコンセプトカー「LF-30 Electrified」を公開しています。


この電気自動車では、各ホイールにモーターを配置した“インホイールモーター”方式を採用しています。4つのホイール・タイヤが一つひとつ独立して動き、自由に駆動力を制御ことができるという仕様です。“インホイールモーター”方式はコンセプトカーでは実際に使われていますが、市販車では初めての採用です。
この電気自動車「LF-30 Electrified」は市販される予定です。