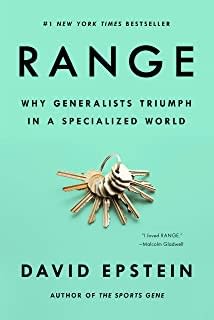
Chap5.Thinking outside experience
経験を超えて考える
①この章
関連:ビジネスエリートのためのリベラルアーツ 哲学
哲学:世界の有意味化30
デリダの脱構築100
脱構築:一から作り直すこと
構造物を解体し,構築し直しすという意味。単に解体するだけではなく,構築し直す。101
第5章は経験を超えて考えるには?
ということ。
ポイントは、類推力。
どことなく、デリダの脱構築にリンクする。
そして、ダニエルカーネマンを呼んでみたくなる、
0-0-0書き出し
★ ★★★★「よく整理された問題は、半分解決されたようなものである。」〜JohnDewey
よりよく問題解決を行うものは、戦略立案の前に,問題に秘められた深い耕造の把握から始める者である。115
幅広い思考が必要な世界においては,戦略を複数発見できる思考の源泉が必要であるということ。
そのためには、未知に直面したときに類推により決断をスタートさせるということが求められるということである。119
予期せぬことがまだ観ぬ広大な新しい世界への発見のスタートとなるということ。117
未知へ遭遇した時の類推力とはゆっくりとした経験によりなされるということ。119
◇ 経験が生かされない領域:wicked domain理不尽な領域
において、
ひとつの領域の経験に頼るということは可能性を制限するということだけではなく,大惨事を招きかねないということ。107
★ ★★★★抽象的領域,もしくは関係性における類似性を見いだすことが求められているということ。君がクリエイティブな存在でありたければあるほどこの類推思考が重要となってくるということ。104
★ 今を生きるということはそれほど簡単なことではない。過去の経験が役立たなくなっているからだ。
今までにであったことがない問題を解決するための戦略を練ることが求められているということ。
17世紀は挑戦の世紀であった。
宇宙というものは言い表しようのない精神により支えられた安定した地球の周りを回る天体であると捉えられていた。
17世紀にはポーランド人であるコペルにクスが実際は地球が太陽の周りを各天体が回っていると解いたがメジャーにはなっていなかった。
プラトン、アリストテレスの時代からこれは2000年も変わらぬ事実と冴えて来た。
しかし、カシオペアが新たな衛星を獲得してから、変わらぬ宇宙という幻想は打ち砕かれつつあった。
Keplerは惑星がヨーロッパの空を横切るのを目がけてアイデアを変えていこうとしていた2000年も変わらなかった。
やがて彼の運動もあり,コペルニクスの考えが支持されるようになって来た。
彼には新たな疑問が沸き上がって来た。
【ドイツ人宇宙学者Johannes Keplerの類推】
②-a類推思考とは?
◎analogical thinking類推思考
多様な領域の中に共通する概念を見いだすこと
表面的に違うように見えるものの中に共通点を見いだすこと。103
脱構築的考え:
表面的に違うように見える問題の根底に流れる共通の構造を見いだすこと。107
◎ 類推の力
◎ 類推力とは問題解決の燃料である。
3人集まれば文殊の知恵
3つの異なる分野からの類推で大きな問題解決に当たることで,問題解決の力はブーストする。106
▼
relations 関係性を見いだすということが人間を人間たらしめていることでもある。
◎ think outside the box
⇒知っている領域の外への類推を働かせるということ。
Cfジョハリの窓
Keplerの類推からの蓄積が後に宇宙物理学の礎となった。
◎ 類推⇒論証⇒新しい類推
新しい疑問が浮かぶたびにこれまでの類推は容赦なく尋問し、あらたな類推を作り出すこと。101
◎ 惑星が動くことに対する類推analogy:
世界中から解き放たれ、かつどこにも存在せず、稼働可能なエネルギーがあるのではないか?という類推。100
▼
Keplerはそれまで魂、スピリッツと神話的に捉えられていたものをパワー、力を物理学の世界に持ち込んだ。
▼
結果として,重力という存在への興味を世間を向かわせた。
▼
彼の仮説であった惑星は太陽からは馴れるほどゆっくり動くということは徐々に証明されていった。
「なぜ太陽から遥かに離れた惑星は太陽よりゆっくりと動くんだろう?
おそらく、太陽から離れるほど動きはゆっくりになるんだろう。
ではなぜ?」と。
Keplerの仮説は太陽から放たれるエネルギーは離れるほど弱くなるからではないか?というものであった。
②-bダニエルカーネマン 脱構築のプロセスとして★★★★★
◇ inside view outside view
ダニエルカーネマン
inside view「内なる視点」:経験から導き出される直感
⇒認知バイアス
詳しく知っていることほど、自ら想定する結果が起こると思ってしまう。110
▲
核心:
詳細を分かったつもりでいるほど、過激な決断を下しがちになってしまうということ。110
知っていることに関しては,好意的な判断を下しがちになってしまう。
outside view「外からの視点」:直面する問題と別の問題の構造的な類似性を見いだす思考。
◎ 深い部分での共通した構造を見いだすということ。114
◎ アメリカでは理系の学際的つながりにより、これまで見えなかった別の分野感の共通点を探すという試みもされている。
⇒
◎ 慣れ親しんだ思考から幅広い思考へとスイッチを切り替える思考
◎ ネットフリックスレコメデーションの精度を上げるために同じくoutside viewを用いている。
多くの視聴履歴から何を次に進めるべきか?を分析する変わりに、視聴者がいいねをした結果からレコメデーションを行っている。
興味を示したカテゴリーから興味を示すであろうカテゴリーをAIが学習しているということ。111
経験を超えて考える
①この章
関連:ビジネスエリートのためのリベラルアーツ 哲学
哲学:世界の有意味化30
デリダの脱構築100
脱構築:一から作り直すこと
構造物を解体し,構築し直しすという意味。単に解体するだけではなく,構築し直す。101
第5章は経験を超えて考えるには?
ということ。
ポイントは、類推力。
どことなく、デリダの脱構築にリンクする。
そして、ダニエルカーネマンを呼んでみたくなる、
0-0-0書き出し
★ ★★★★「よく整理された問題は、半分解決されたようなものである。」〜JohnDewey
よりよく問題解決を行うものは、戦略立案の前に,問題に秘められた深い耕造の把握から始める者である。115
幅広い思考が必要な世界においては,戦略を複数発見できる思考の源泉が必要であるということ。
そのためには、未知に直面したときに類推により決断をスタートさせるということが求められるということである。119
予期せぬことがまだ観ぬ広大な新しい世界への発見のスタートとなるということ。117
未知へ遭遇した時の類推力とはゆっくりとした経験によりなされるということ。119
◇ 経験が生かされない領域:wicked domain理不尽な領域
において、
ひとつの領域の経験に頼るということは可能性を制限するということだけではなく,大惨事を招きかねないということ。107
★ ★★★★抽象的領域,もしくは関係性における類似性を見いだすことが求められているということ。君がクリエイティブな存在でありたければあるほどこの類推思考が重要となってくるということ。104
★ 今を生きるということはそれほど簡単なことではない。過去の経験が役立たなくなっているからだ。
今までにであったことがない問題を解決するための戦略を練ることが求められているということ。
17世紀は挑戦の世紀であった。
宇宙というものは言い表しようのない精神により支えられた安定した地球の周りを回る天体であると捉えられていた。
17世紀にはポーランド人であるコペルにクスが実際は地球が太陽の周りを各天体が回っていると解いたがメジャーにはなっていなかった。
プラトン、アリストテレスの時代からこれは2000年も変わらぬ事実と冴えて来た。
しかし、カシオペアが新たな衛星を獲得してから、変わらぬ宇宙という幻想は打ち砕かれつつあった。
Keplerは惑星がヨーロッパの空を横切るのを目がけてアイデアを変えていこうとしていた2000年も変わらなかった。
やがて彼の運動もあり,コペルニクスの考えが支持されるようになって来た。
彼には新たな疑問が沸き上がって来た。
【ドイツ人宇宙学者Johannes Keplerの類推】
②-a類推思考とは?
◎analogical thinking類推思考
多様な領域の中に共通する概念を見いだすこと
表面的に違うように見えるものの中に共通点を見いだすこと。103
脱構築的考え:
表面的に違うように見える問題の根底に流れる共通の構造を見いだすこと。107
◎ 類推の力
◎ 類推力とは問題解決の燃料である。
3人集まれば文殊の知恵
3つの異なる分野からの類推で大きな問題解決に当たることで,問題解決の力はブーストする。106
▼
relations 関係性を見いだすということが人間を人間たらしめていることでもある。
◎ think outside the box
⇒知っている領域の外への類推を働かせるということ。
Cfジョハリの窓
Keplerの類推からの蓄積が後に宇宙物理学の礎となった。
◎ 類推⇒論証⇒新しい類推
新しい疑問が浮かぶたびにこれまでの類推は容赦なく尋問し、あらたな類推を作り出すこと。101
◎ 惑星が動くことに対する類推analogy:
世界中から解き放たれ、かつどこにも存在せず、稼働可能なエネルギーがあるのではないか?という類推。100
▼
Keplerはそれまで魂、スピリッツと神話的に捉えられていたものをパワー、力を物理学の世界に持ち込んだ。
▼
結果として,重力という存在への興味を世間を向かわせた。
▼
彼の仮説であった惑星は太陽からは馴れるほどゆっくり動くということは徐々に証明されていった。
「なぜ太陽から遥かに離れた惑星は太陽よりゆっくりと動くんだろう?
おそらく、太陽から離れるほど動きはゆっくりになるんだろう。
ではなぜ?」と。
Keplerの仮説は太陽から放たれるエネルギーは離れるほど弱くなるからではないか?というものであった。
②-bダニエルカーネマン 脱構築のプロセスとして★★★★★
◇ inside view outside view
ダニエルカーネマン
inside view「内なる視点」:経験から導き出される直感
⇒認知バイアス
詳しく知っていることほど、自ら想定する結果が起こると思ってしまう。110
▲
核心:
詳細を分かったつもりでいるほど、過激な決断を下しがちになってしまうということ。110
知っていることに関しては,好意的な判断を下しがちになってしまう。
outside view「外からの視点」:直面する問題と別の問題の構造的な類似性を見いだす思考。
◎ 深い部分での共通した構造を見いだすということ。114
◎ アメリカでは理系の学際的つながりにより、これまで見えなかった別の分野感の共通点を探すという試みもされている。
⇒
◎ 慣れ親しんだ思考から幅広い思考へとスイッチを切り替える思考
◎ ネットフリックスレコメデーションの精度を上げるために同じくoutside viewを用いている。
多くの視聴履歴から何を次に進めるべきか?を分析する変わりに、視聴者がいいねをした結果からレコメデーションを行っている。
興味を示したカテゴリーから興味を示すであろうカテゴリーをAIが学習しているということ。111










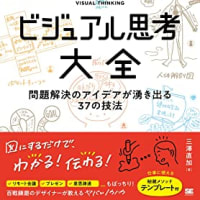
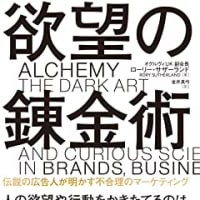
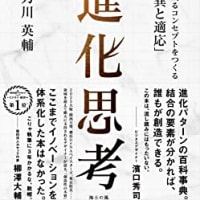
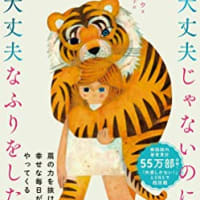
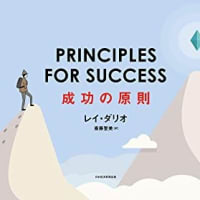
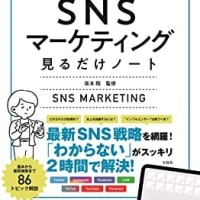


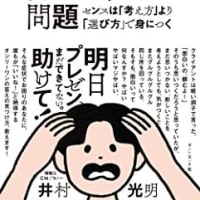
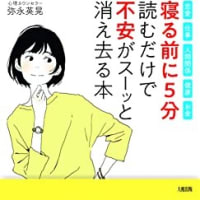






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます