
村上春樹氏の短編集です。
怪談好き、不思議な話好きのぼくにとっては、このタイトルはとってもそそられるものでした。でも、いわゆる「怪談・奇談」を期待して読むと、ちょっとがっかりするかもしれません。
帯には『不思議な、あやしい、ありそうにない話』とありますが、不思議な話はあくまで物語の入り口にすぎないような気がします。
導入部の「自分のリクエストしたい曲と、ピアニストの選曲が偶然にも一致した」、というエピソードが肩に入った力をほぐしてくれ、あとはすんなり物語に入ってゆけました。
登場人物たちは、「とるにたらないけれども不思議なできごと」を端緒として、心にそっと置いたまま向き合うのを避けていた事柄に視線を向けるようになります。彼ら・彼女らの心の内を読み解いていくと、自分の価値観を再確認できるのかもしれないですね。ちょっと抽象的かな・・・。
ぼくはもともと村上春樹氏の文章が好きで、とくにエッセイは愛読してきました。ほのかにユーモラスなところ、知的な雰囲気のする適確な言葉の選び方、適度に力が抜けているところ(リラックスはしているが、決して行儀の悪い座り方はしない、というような)などがぼくの好みに合っています。
ちょっと不思議な空気を感じながらも、肩から力を抜いて読むことができた短編集だったように感じます。
人気blogランキングへ←クリックして下さいね
怪談好き、不思議な話好きのぼくにとっては、このタイトルはとってもそそられるものでした。でも、いわゆる「怪談・奇談」を期待して読むと、ちょっとがっかりするかもしれません。
帯には『不思議な、あやしい、ありそうにない話』とありますが、不思議な話はあくまで物語の入り口にすぎないような気がします。
導入部の「自分のリクエストしたい曲と、ピアニストの選曲が偶然にも一致した」、というエピソードが肩に入った力をほぐしてくれ、あとはすんなり物語に入ってゆけました。
登場人物たちは、「とるにたらないけれども不思議なできごと」を端緒として、心にそっと置いたまま向き合うのを避けていた事柄に視線を向けるようになります。彼ら・彼女らの心の内を読み解いていくと、自分の価値観を再確認できるのかもしれないですね。ちょっと抽象的かな・・・。
ぼくはもともと村上春樹氏の文章が好きで、とくにエッセイは愛読してきました。ほのかにユーモラスなところ、知的な雰囲気のする適確な言葉の選び方、適度に力が抜けているところ(リラックスはしているが、決して行儀の悪い座り方はしない、というような)などがぼくの好みに合っています。
ちょっと不思議な空気を感じながらも、肩から力を抜いて読むことができた短編集だったように感じます。
人気blogランキングへ←クリックして下さいね










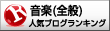
















こんばんは。
コメント、失礼致します。
この村上春樹氏の短篇小説集『東京奇譚集』は気になっている作品で、近々読んでみたいと思っております。
僕は村上春樹氏の長篇小説は、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』(‘85年)、『ノルウェイの森』(‘87年)、『ダンス・ダンス・ダンス』(‘88年)、の頃の方が大好きで、近作では、小説の形ではない作品の村上春樹氏の素顔が垣間見れる『「そうだ、村上さんに聞いてみよう」~』(‘00年)やシドニー・オリンピック観戦記『シドニー!』(‘01年)が特に好きです。
また遊びに来させて頂きます。
ではまた。
あ、ぼくも「そうだ、村上さんに聞いてみよう~」、好きですよ
「村上朝日堂」シリーズが好きで、何度も繰り返して読みました。肩こらないし、といって軽くもないし。
なんか不思議な静けさと温かみのある文章だな~、なんて思ってます。
お久しぶりです。
これ、まだ読んでないんですよね。
楽しみにしてるんです。
「適度に力が抜けている」というの、よくわかります。
行儀の悪い座り方はしないというのもいい表現ですね。今度パクろう。
>今度パクろう
そのかわり、今度西米良付近で迷ったらノロシ上げますから、助けに来てくださいね(笑)
この本、秋の夜長に雰囲気が合っているような気がしましたよ。ぼくは布団にもぐって、枕元の蛍光灯の灯りだけで読みました。読書の秋、って感じがしました~
不思議でありえなさそうで
でもすんなりその世界に入っていける
春樹さんの文章センスはすごいですよね。
エッセイは春樹氏の現実世界への眼差しが
感じられて小説とはまた違っておもしろいです。私も近いうち読もうーっと!
いつも覗いてますよ~
>文章センス
同感です。練り上げられているようでもあり、自然体でもあり。そして読み手のぼくがすんなり入って行くことができる文章なんです。
小説は「Haruki's Wonder World」っていう気がしますね。エッセイは、自然体で、かつリベラルな視点が好感持てますよね。