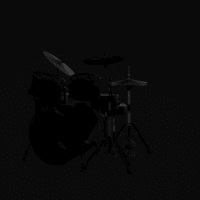今回は、映画記事です。
このジャンルでは、ゴジラ作品について記事を書いていました。前回はいったん中断しましたが、ふたたびゴジラシリーズに戻りましょう。
順番にしたがって、シリーズ第11作にあたる『ゴジラ対ヘドラ』です。
公開は、1971年。
東宝特撮のゴッド的存在である円谷英二がこの世を去り、邦画の斜陽という時代もあいまって東宝特撮自体が風前の灯火となるなか、いったんは予算切れで制作中止に追い込まれながらなんとか完成にこぎつけたといういわくつきの作品です。
その予告の映像が東宝の公式チャンネルにあったので、それを貼り付けておきましょう。
【公式】「ゴジラ対ヘドラ」予告 根強い人気の公害怪獣ヘドラとの闘いを描いたゴジラシリーズの第11作目。
ゴジラは常に時代性を背負うことを宿命づけられている、と以前このブログで書きましたが……この作品のテーマは、環境問題です。
ヘドラはヘドロから生まれた怪獣であり、核実験から生まれたゴジラが核の恐怖を象徴していたように、ヘドラは環境問題の象徴なのです。
前作でも公害問題に言及するようなシーンがちょっとありましたが、『ゴジラ対ヘドラ』では、それをさらにテーマとして掘り下げています。
直接的には、田子ノ浦のヘドロ問題をモチーフにしているそうです。
高度経済成長の負の側面として公害問題が深刻化しつつあった頃。
公害対策基本法ができたのは1967年。そうしたことが背景にあるでしょう。また、レイチェル・カーソンの『沈黙の春』の影響もあるといいます。
監督は、坂野義光氏。
ゴジラ作品で、同氏がメガホンをとった作品はこの一作のみ……というより、坂野氏が正式に監督をつとめた映画作品は、この『ゴジラ対ヘドラ』しかないようです。
この監督の個性ゆえに、本作はシリーズの中でもきわめつけの異色作として知られるものとなっています。
具体的には、サイケデリック趣味や、マルチスクリーン、時折挿入されるアニメーションなど、実験的な手法が随所に取り入れられているのです。
海面を漂うヘドロの画像や、ヘドラの発する硫酸ミストで骨だけになった死体など、無気味な映像も出てきます。「怪獣によって殺された人間の死体」というのはなかなか怪獣映画で直接描かれることのないものと思いますが、この映画ではそれをやります。皮膚がただれて死んでいく姿などは、かなりグロテスクです。
そうした表現は、ある意味では、時代に先駆けたセンスだったのかもしれません。
前作から、ゴジラ映画には新たな表現がみられるようになったとこのブログで指摘しましたが……『ゴジラ対ヘドラ』は、そういう方向性を急速に推し進めたものともいえるでしょう。
実験的な手法がほとんど常にそうであるように、こうした表現は賛否を呼んだようです。
興行としてはそれなりに成功したということですが、酷評にもさらされたといいます。
ウィキ情報によると、あるとき「世界の最悪映画50本」というような企画があり、そのなかに本作が選ばれたのだとか。そこでは、「Z級の愚作」と酷評されたそうです。
私自身は、このカルトな感じが結構気に入ってますが……ただ、好きであるにせよ嫌いであるにせよ、この作品がゴジラシリーズ全作品のなかでも際立った個性を持っているというオンリーワン性は誰にも否定しえないところでしょう。
私がリスペクトする映画評論家の町山智浩さんは、この映画にかなり強く衝撃を受けたそうで、「人生において重要な意味を持つ映画」だといっています。
その町山さんによれば、『ゴジラ対ヘドラ』はカルト映画として町山さん世代の人たちに大きな影響を与えているんだそうです。
それは映画関係者だけでなくミュージシャンなどもふくまれていて、たとえば怒髪天の増子直純さんや、チェッカーズのリーダーだった武内亨さんなども『ゴジラ対ヘドラ』が大好きなんだそうです。
たしかに、アングラ 酒場で、魚人間たちが踊る場面で流れる音楽は、いかにもサイケデリックロックっぽくてかっこいい。そういうところが、ミュージシャンの琴線にも触れたわけでしょう。
世界最悪の映画とされたものが、ある人にとっては名作となる……こういう構図は、映画にかぎらず、音楽、絵画などいろんなジャンルで見受けられます。このブログでも、いくつかそういう例を紹介してきました。
画期的な作品というのは、しばしばそういう毀誉褒貶を受けます。
そういう意味でも、『ゴジラ対ヘドラ』は、ゴジラ史に残る作品になっているのだと思います。