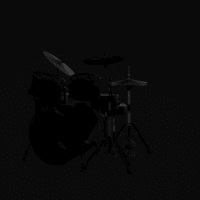今邑彩さんの『卍の殺人』を読みました。
これは、鮎川哲也賞のはじまりとなった作品です。
本格ミステリの牙城ともいえる鮎川賞は、もともとは東京創元社が主催したミステリーの公募企画でした。鮎川哲也御大が推理小説シリーズ「鮎川哲也と十三の謎」を刊行する際に、その最終巻を公募したもの……そこでこの作品が「十三番目の椅子」を獲得。これがきっかけとなって、鮎川哲也賞という賞が誕生したのでした。
内容は、鮎川賞前夜にふさわしい本格ミステリとなっています。
卍型の屋敷で起こる殺人……いわゆる“館モノ”の範疇に含めてよいでしょう。特殊な構造を持った屋敷で次々と奇怪な事件が起こるという、ミステリーとしては古式ゆかしい舞台設定です。
ネタバレになるので詳細は書けませんが、ちょっとだけ内容を書くと、二重の解決になっています。
いったん謎が解けたかにみえた後、さらにどんでん返しがあるという趣向……
それ自体は珍しいものではありませんが、この作品ではその仕掛け方がすごい。
ミステリを読みなれていれば、残りのページ数でそういう展開が待っているんだろうなという予想はつくものですが、しかし、ここからどうやってどんでん返しするのか、できるのか……と思っているところへ、鮮やかにどんでんを返してきます。どうしたってそれ以外の解決はありえないだろうというぐらいに固めておいてから、それを覆す……その志の高さと、高く設定したハードルを超える実力。たしかに鮎川の系譜につらなる職人肌のミステリーという感じです。
しかしながら、刊行当初はずいぶん辛口の評価も受けたようです。
私が読んだ中公文庫版のあとがきでは「褒めているのは、お義理で出版社から頼まれた評論家だけ。ミステリーファンの間では酷評に近かったんじゃないかな」と本人が回顧しています。
この点について、その当時のいわゆる「新本格ブーム」に便乗するようなかたちに見られたためではないかと本人は分析しています。まあ、その新本格ブームの本流に位置する作家たちにしても、デビュー当初酷評を受けたという点は変わらないわけなんですが……ただ、そういう事情があったので、今邑彩さんはその後ちょっと作品の傾向を変えていきました。ただ、“職人肌のミステリー”という点は、変わっていません。今邑彩という人は、たしかに鮎川哲也が用意した十三番目の椅子にふさわしい作家だったといえるでしょう。