
今回は、ひさびさに小説記事です。
このカテゴリーでは、ミステリーの古典を読もうというキャンペーンをやってますが、その一環として、コナン・ドイルの『四つの署名』について書きましょう。

コナン・ドイルといえば、ミステリーの元祖と目される作家の一人であり、いうまでもなくシャーロック・ホームズの生みの親。
……というわけで、前回映画記事で紹介した『シャーロック・ホームズ』からのつながりでもあるのです。
※以下、ネタバレになる部分もあるので、未読の方は注意。
『四つの署名』は、そのシャーロック・ホームズシリーズの中の一作。
第一作は、以前の映画記事でも言及した『緋色の研究』です。
これを自信満々で発表したドイルですが、思ったほどの評価は得られませんでした。
そう、これまでこのブログで紹介してきたロックの名曲の多くがそうであったように、ホームズも最初は評価されなかったんです。
この文庫本についている訳者解説によれば、評価を得られなかったドイルは、失意のあまり、もうホームズ物は書かないことにしようとまで思っていたそうですが、そんななかでアメリカの雑誌から依頼があり、『緋色の研究』発表からおよそ2年後に執筆したのが『四つの署名』です。
内容は、ある女性から依頼を受けたホームズが探偵活動の過程で殺人事件に遭遇し、そのなぞを解いていくというもの。
宝の地図なるものが出てきて、足跡や臭いで犯人を突き止めていく、古き良き古典ミステリーといったところでしょうか。
扱われているのは“密室”といえないこともない状況で起こる殺人事件ですが、どちらかといえば、密室どうこうというよりも(という以前に、この時代にはまだ“密室”という概念自体固まっていないと思いますが)タイトルにある“四つの署名”の謎がキモでしょう。まあそれも、ロジックとかトリックとかいう話ではないんですが。
ただ、私がもっとも興味深く読んだのは、終盤の犯人の告白部分です。
犯人は、かつてインドで兵役に従事していた過去があり、そこでの出来事が事件に深く関与しています。
その、インドで過去にあったことに関する話が、じつに興味深い。おそらくセポイの乱と思われる反乱のことを描いているんですが、そういう歴史上実際にあった事件と絡んでいるところが、いかにも19世紀の冒険小説という感じで面白いわけです。もっともそこに、植民地主義的な視点が潜んでいることも認めないわけにはいきませんが……
思えば、ワトソンにはアフガン戦役帰りという設定もあって……世界中に植民を持っていた大英帝国という土台の上に、シャーロック・ホームズの物語を作られているんだということを実感させられます。
事件の解決でしゃれているのは、宝物の行方ですね。
マクガフィン的な役割を果たす“アグラの大宝物”は結局とりもどすことができないんですが、その取り戻せないことがワトソンにとっては幸運になる……という結末。
このちょっとしたロマンス的な部分が、絶妙の隠し味になっているという印象でした。
このカテゴリーでは、ミステリーの古典を読もうというキャンペーンをやってますが、その一環として、コナン・ドイルの『四つの署名』について書きましょう。

コナン・ドイルといえば、ミステリーの元祖と目される作家の一人であり、いうまでもなくシャーロック・ホームズの生みの親。
……というわけで、前回映画記事で紹介した『シャーロック・ホームズ』からのつながりでもあるのです。
※以下、ネタバレになる部分もあるので、未読の方は注意。
『四つの署名』は、そのシャーロック・ホームズシリーズの中の一作。
第一作は、以前の映画記事でも言及した『緋色の研究』です。
これを自信満々で発表したドイルですが、思ったほどの評価は得られませんでした。
そう、これまでこのブログで紹介してきたロックの名曲の多くがそうであったように、ホームズも最初は評価されなかったんです。
この文庫本についている訳者解説によれば、評価を得られなかったドイルは、失意のあまり、もうホームズ物は書かないことにしようとまで思っていたそうですが、そんななかでアメリカの雑誌から依頼があり、『緋色の研究』発表からおよそ2年後に執筆したのが『四つの署名』です。
内容は、ある女性から依頼を受けたホームズが探偵活動の過程で殺人事件に遭遇し、そのなぞを解いていくというもの。
宝の地図なるものが出てきて、足跡や臭いで犯人を突き止めていく、古き良き古典ミステリーといったところでしょうか。
扱われているのは“密室”といえないこともない状況で起こる殺人事件ですが、どちらかといえば、密室どうこうというよりも(という以前に、この時代にはまだ“密室”という概念自体固まっていないと思いますが)タイトルにある“四つの署名”の謎がキモでしょう。まあそれも、ロジックとかトリックとかいう話ではないんですが。
ただ、私がもっとも興味深く読んだのは、終盤の犯人の告白部分です。
犯人は、かつてインドで兵役に従事していた過去があり、そこでの出来事が事件に深く関与しています。
その、インドで過去にあったことに関する話が、じつに興味深い。おそらくセポイの乱と思われる反乱のことを描いているんですが、そういう歴史上実際にあった事件と絡んでいるところが、いかにも19世紀の冒険小説という感じで面白いわけです。もっともそこに、植民地主義的な視点が潜んでいることも認めないわけにはいきませんが……
思えば、ワトソンにはアフガン戦役帰りという設定もあって……世界中に植民を持っていた大英帝国という土台の上に、シャーロック・ホームズの物語を作られているんだということを実感させられます。
事件の解決でしゃれているのは、宝物の行方ですね。
マクガフィン的な役割を果たす“アグラの大宝物”は結局とりもどすことができないんですが、その取り戻せないことがワトソンにとっては幸運になる……という結末。
このちょっとしたロマンス的な部分が、絶妙の隠し味になっているという印象でした。










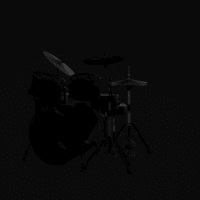









たしかにありますね、「ルパン対ホームズ」……恥ずかしながら私は読んでないんですが。
海外では、人物設定を借りて別の作者が話を書くというスタイルが慣行としてあるみたいですね。もちろん払うべきものを払ったうえでですが。日本でいうと、ルパン三世対コナンみたいな感覚じゃないでしょうか。
そういえば、日本のミステリー作家のなかにも、ホームズを登場させて自作の探偵と対決みたいな話を書いている人はいました。
やっぱりシャーロック・ホームズといえば名探偵の元祖的な存在なんで、ドリームマッチをやってみたいというふうになるんでしょう。
作者は「ルパンシリーズ」のモーリス・ルブランでした。
どういう経緯でルブランが書いたのかはわかりませんが・・・。