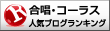その他、コンクールに関しては、全国大会出場を逃した悔しさが格別なこととして、今でも残っている年度がある。一つは、1981年~庄司寛部長(札幌市、自由曲は「都会」)、もう一つは、1986年~横山琢哉部長(函館市、自由曲は「オンゴーオー二」)である。この2回は、審査員のミスジャッジではないか(笑)とさえ思うほどに自信があった(それがコンクールなんだよね!)。さあ次がある、と言える私でさえ悔しかったのだから、最後の年にかけていた3年生の悔しさはいかばかりか?の繰り返しがコンクールであった。何と言っても、岩見沢東高校合唱部の思い出の一番は、定期演奏会である。1974年~出口敬智部長時代から始まった定期演奏会は、やがて岩見沢市民会館のホールで行うことになり、毎年多くの人に聞いてもらった。そして、岩東合唱部志願の中学生が入部してくれるようになり、部員数最高は84名という年もあった(全校生800名中、約1割が合唱部員)。よい生徒に恵まれた岩見沢東高校での15年間は、たくさんの思い出が残る至福の時であった。
そして、1986年4月、当時の静修短期大学に赴任した。突然の要請に応じたものであり、まさに青天の霹靂であった。要請を受けてから、1週間以内の返答を求められていたので、色々迷いながらも「えいっ、や!」の決断であった。特に、心残りであったのは、当時、2学年の学級担任であったので、彼らの卒業までを全うできないこと、そして、合唱部のことであった。最終的には、いずれは転勤というときが来る。それが今であり、請われて行く幸せを大切にしよう!となったのである。