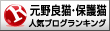今回の話は「大家族の日常」ではなくて「大家族の非日常」です。
"家族"として暮らしているワンニャンたちが被災した時に遭遇する悲劇。
このブログでも度々書いてきました。
・「被災して命を落としたワンニャンたちの、無念の涙を忘れない」2021.3.10
・「被災した猫たちは」2024.1.16 等。
もし大地震に襲われたら、まず何もできないだろう。津波はどうかと言うと、やはり避難の緊急性が高いからできることは限られる。しかしそんな中でも最低限決断しなければならないことがあります。家族同然のワンニャンを連れ出す余裕が時間的にない場合(直ちに確保できない場合)、彼らの逃げ道として窓を開放(リードを解放)するかどうかだ。それは家が倒壊するかどうか、津波がどのくらい大きいのかの判断によって変わるだろう。ただ抱くことができるのであれば、後のことをネガティブに考えないで、とりあえず一緒に避難するのが鉄則だ。
東北大震災には原発事故という特異的な災害が重なった。多くの人がすぐに戻れると考えて猫を閉じ込め、犬を繋いだまま指示に従って避難した。よもや年単位で戻れないとは思いもよらず。それが餓死という悲惨な結果を招き、何とか逃げ出したワンニャンも、誰も人がいない街でその大半が飢え死したのでした。

未だに近寄れず、本気逃げか攻撃もしてくるケン
こんな悪夢のような原発事故はもう2度と起こらないと思いたい。津波の場合はどうか。事前避難を要するほどの大津波であれば、ワンニャンの解放もやむを得ないのではないか。ただし木造と鉄筋では強度が違うし、よほど大きな津波でない限り2階まで水没することはないだろうから、その判断は難しい。
わが家の場合、避難指示がでる可能性があるとすれば火事による延焼リスクが生じた時だ。先日の愛媛の山火事の際、避難先から戻ると家が全焼していたという人を取材していた。(3/27ニュースゼロ) その人は焼け跡で"家族"の猫を探していた。1匹は大やけどを負いながらも外に逃れ、1匹は焼死、残る1匹を探していたのです。生前の元気な姿の写真とともに紹介された猫たち。その人のやるせない思いが身に染みた。大船渡や岡山も含め、こんな話がたくさんあったに違いない。
自分は心に決めています。延焼リスクで避難指示がでても自分は逃げません。何故なら避難指示というのは人命しか考えてないからです。わが家の猫たちは自分にとってまさに家族。その命を預かっているのは役所ではなく、自分だからです。

「撫でて~」と寄って来るけど、抱こうとすると逃げまくるキー
延焼リスクというのは地震や津波と違って多少は間的余裕がある。火事が近づいてきたら猫たちの箱詰めを始めます。(キャリーが2個しかないので。) まずは抱ける6匹。次に半馴れの4匹。続いて家庭内ノラの5匹。もし隣の家に火が付いたら生活必需品と一緒に車に詰め込み、最後の捕獲を続けます。いよいよ自宅に火が付いて燃え広がったら、逃げる前に窓を開けて残った猫たちを開放します。それが、保護者として猫たちにできること。わが家が火元で手に負えなくなった場合は、時間的余裕がないので直ちに猫たちを開放します。
なので、猫たちには連絡先の付いた首輪が必須。家が燃えてしまった後に猫たちを探して回るのは考えただけでも本当につらい。でも、生きてさえいれば、何とか生活を再建できる可能性がある。だから誰も死なせない。自分としてはその一言に尽きると思っています。避難の際に使用する空箱を用意しておくこと。家具を壁に固定して家の強度を増すと同時に、倒壊した際の空間が確保できるようにすること。それがわが家の災害対策です。

抱っこ大好きだけどパニックになると逃げまくるチキン
(パニックになる前に確保要)