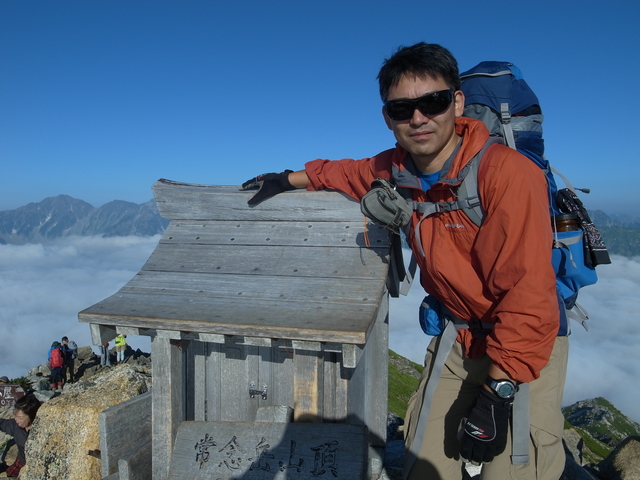3月14日、雪が降って、夜更けに雨に変わった。山下達郎の逆だ。
東京は3月の終わりに、冷たい雨が降ることが多い。そんな冷たい雨に降られると、いつも思い出すことがある。
高校を卒業し、東京に上京してきて、社会人を経験した。ただ、僕はどうしても大学に行きたかった。
しかし、実家からの援助は期待できない。大学に行くとすれば、自分で学費を稼ぎ出すしかなかった。
読売新聞に奨学制度があることを知り、それを利用することにした。狭い部屋だが、一応、寮もあった。そこで僕は新聞配達をしながら、大学に通うことになった。
普通の人が卒業するような歳に、大学に入学した。希望と不安の入り混じった複雑な気持ちだった。自分のやっていることに、イマイチ自信が持てなかった。味方してくれる人もいなかった。すごく孤独だった。
僕の持っていたものは、ちっぽけな希望だけだった。そんなものは現実の厳しさの前では、すぐに打ち砕かれてしまう。
毎朝、三時前に起きる。正確に言うと朝ではない。まだ夜だ。
3月の終わり頃、大学の入学式の前で、店に入って、数日しか経っていなかった。
その日は、朝から雨だった。
新聞配達は、雨が降ると、普通の日の三倍くらい神経を使うし、疲れる。僕はまだその大変さを知らなかった。
まだ配達のルートを教わっているときだった。自転車の前のカゴと後ろの荷台に100部ほどの新聞が積まれてあった。
僕たちは、必要な部数をもって、エレベーターでマンションの上の階に上がっていった。
マンションから戻ってくると、自転車がひっくり返っていた。自転車に積まれていた新聞がすべて道路に散乱していた。新聞は雨に濡れて、もう使い物にならなくなっていた。
僕はダメになった新聞を呆然と見ていた。はあ、やっちまったなと深い溜め息をついた。
冷たい雨に濡れながら、僕は平謝りに謝った。しかし、彼の怒りは収まらなかったようだ。
「だから、壁に自転車を寄りかけておかないとだめだって言っただろ。店に戻って新しいのと変えないとだめだ。何時に終わると思ってるんだ。今日は苦情の嵐だよ」と。
いろんな人に迷惑をかけながら、その日はなんとか終わることができた。
しかし、配達が遅いという苦情の電話が鳴り止まなかった。
その日は、すごく疲れたし、惨めで恥ずかしかった。孤立無援で、僕の味方はいなかった。
僕は打ちのめされ、精神的にどん底にいた。僕はゼロだった。
これから四年間やっていけるのだろうか、そう思っていた。
泣きそうな気分だった。しかし、泣かなかった。
ボロボロの気分だったけど、胸の奥にある火は、まだかすかに消えていなかったからだ。
僕はファイターだ。打たれて打たれても、倒れても倒れても、立ち上がる。
だから、これから戦っていくためには、この小さな火を消さずに、大切にしなければならなかった。
僕の持っているものは、その小さな種火だけだったからだ。
3月の雨に降られると、打ちのめされ、孤独だった、どん底の絶望を思い出す。
そして、そこから立ち上がってきたことも。