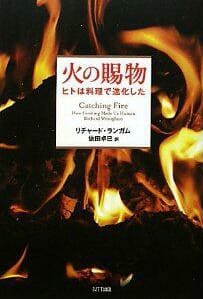朝、植木に水をあげていたら、遠くから
「キョロ、キョロ、キョロ、キョロン 」と声が聞こえてきました。
」と声が聞こえてきました。
あれっ、ガビチョウじゃないな。。キビタキとか??
とにかく何かの夏鳥のような、、、、。
夏鳥到来…というよりは夏鳥通過かな。
早速、双眼鏡を持って、家から50メートルの雑木林へ。
ヒヨドリが騒がしい。
コナラの芽吹きがはじまり、クヌギの花が満開。

何度か遠くで同じ鳴き声がしたけど、姿は見えず。
20~30分、バードウォッチングをして帰ってきました。
●見た鳥
ヒヨドリ
キジバト
カワラヒワ
シロハラ
ガビチョウ
アオゲラ
●声だけ聞こえた鳥
ウグイス
シジュウカラ
コゲラ
コジュケイ
謎の夏鳥?
明日は朝早くいってみるかな。
「キョロ、キョロ、キョロ、キョロン
 」と声が聞こえてきました。
」と声が聞こえてきました。あれっ、ガビチョウじゃないな。。キビタキとか??
とにかく何かの夏鳥のような、、、、。
夏鳥到来…というよりは夏鳥通過かな。
早速、双眼鏡を持って、家から50メートルの雑木林へ。
ヒヨドリが騒がしい。
コナラの芽吹きがはじまり、クヌギの花が満開。

何度か遠くで同じ鳴き声がしたけど、姿は見えず。
20~30分、バードウォッチングをして帰ってきました。
●見た鳥
ヒヨドリ
キジバト
カワラヒワ
シロハラ
ガビチョウ
アオゲラ
●声だけ聞こえた鳥
ウグイス
シジュウカラ
コゲラ
コジュケイ
謎の夏鳥?
明日は朝早くいってみるかな。