A級MissingLink 第22回公園
『くらげなす、流体力学の基礎知識』
*********
思えばあの頃は夢があったと思います。
技術的楽観主義とでも申しましょうか、
ネットさえあれば人間は平等になるし、
資源配分は効率的になるし、
私的所有も戦争もなくなってみんなハッピーになるんだ。
僕たちはわりと本気でそう思ってました。
*********
始まりは、「運転席と助手席」×2
同時進行? それとも過去現在?
(こういう奇妙性がこの劇団の特徴だね)
。。。。。暗転。。。。。
そして、素振り「西野」、素振り「山瀬」、素振り「オレ!」
廃れた商店街を盛り上げるための対立、
女の嫉妬や母娘対立、嘘つき男や旅好きな女、
エアーガンをもつ風変わりな男などの喜怒哀楽が
スパイスとして話は面白可笑しく進んでゆく。
・
・
・
最終オチは嘘つき男と娘の駆け落ち!
・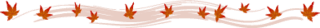
あらっ、今回はお話がずっと続いている!
一般の方々にはこういう方がわかり易いのよね。
何も考えずに済むから話の筋だけが脳に残る!
だから感動の余韻が長く続くのね。
わが親族のおじさんおばさん連中受けは
めっちゃよかったですよ~♪
主なる舞台は一つの部屋!
それがいくつもの別な部屋に早変わり!
左右の出入り口を上手く使いこなしている。
川向こうの近くて遠い騒動は、
突然のマンションの非常ベルを思い浮かべた
誰も外へ出てこないのだ・・興味がないから。
本当は危険がせまっているかも知れないのに・・・
この世って、人間の喜怒哀楽を囲みながら、
ある時は暗闇を探りながらふらふらと徘徊し、
ある時は水の中をゆらゆらと気持ちよく浮遊するようなもん。
まあ、いつも気持ちよいとは限らないけどね・・
そうだよね~、全ての人がそんな経験あるんじゃあないかな、
ってこの演劇を観て感じましたョ。
これぞ、「くらげなす、流体力学の基礎知識」かあ・・
な~るほど、上手いタイトルをつけたもんだ!
(10月31日 3時開演の部を観賞でした)
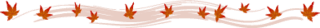
最後に、「くらげなす」
ん? くらげとナスビ? こりゃまたミステリーワールドかなぁ・・
と最初思ったのですがいやいや奥深い意味があったんですね。
「くらげなす」は古事記に出てくる、形が定まらないさまを表す言葉で、
砂や泥の堆積によって現在の姿になる前の、古代の大阪を象徴している。
とあるニュースで見ましたが、もう少し検索してみると、

≪『古事記』における日本神話≫
http://bbs7.sekkaku.net/bbs/?id=koumyou2&mode=res&log=1882
「久羅下(くらげ)なす漂える」と表現。
”久羅下”は漢字を、発音を表現するカナ代りに使用しているので、
漢字としては意義がないが、クラゲは”暗気(くらげ)”を意味するので、
「くらげなすただよえる」は
「創世記」の「黒暗淵(やみわだ)の面にあり」
と同工異曲(どうこういきょく)の表現であり、
「宇宙の真理」の共通普遍性をあらわしている。
「ただよえる」は「淵の面」の不定形なるにピッタリした表現。

≪「食あれば 楽あり」著者: 小島 武夫≫
http://homepage2.nifty.com/kunimi-yaichi/hobby/jelly-fish.htm
クラゲ の語源説
「海の中をクラクラと浮遊しているので、その「クラ」から来た説」
「暗やみにいる化け物のようだから「くらばけ」がクラゲになったという説」
「「暗ぐれ」「輪笥(くるげ)」「繰上(くりあげ)」などの説」























