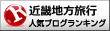義務教育を終えてかれこれ50年目となる。校歌は小学校でも、さらには進学したさきで耳にし、かつ歌った。歌っている当時、その意味を解していたかといえば、確かな記憶はない。それでも、級友が一同に会すると、その結びに合唱するということはママあった。長じて内容や旋律を解するようになり、合唱することで「同じ釜の飯をたべた」一体感を感ずることができるから、不思議でもあった。
『校歌はこうして誕生した』は、「学校の願い、作者の思い」という副題をもつ。この本を頂戴して顧みるに、自然に歌い、意味も解さずに歌いつづけてきたものの、「学校の願い、作者の思い」などは、ついぞ説明されぬまま、ただ《大きく口をあけて、腹から声を出す》連続であったことに、いささか恥じ入る思いであった。
教育の世界では、「校章、校歌、校旗」を学校教育の《三本柱》と位置づけている、とある。教育の理念、地域の風景と期待。学校開設時に、関係者の意気込みを散文に託して、一体感を醸成する営為には、百の歌に百の物語がこめられているものであることを、実感する。採録された校歌に、採録された以上のエピソードが記載されていて、実に興味深い。
戦前、その校歌自体が国の検定認可によるものであった。市街地の中心に位置する学校の校歌は、その検定認可がえられぬまま七十有余年にわたり、歌いつがれた。その秘密は、著名な作詞家による歌詞の一部を問題視しながらも、作詞家が著名であるゆえに「役人も訂正などできない」(60ページ)ところにあったと推察する。
著者は、前著『わが母校わが校歌』(2003年3月)を、すでにおおやけにされている。自治体合併がすすむいっぽうで、学校は統合、そして廃校の局面にある。そのときに、『新版 わが母校わが校歌』を刊行される作業の途次で、本書は生まれた。
今日、教育の世界では、学校と教師への《期待》が大きい。それではこれまで、教育に情熱と展望がなかったのかといえば、それはもとよりあたらない。教育関係者のなかに現在にも増して、熱い情熱と深い思い入れがあった。そのことを本書は、校歌の制定を通じて示している。(2007年9月発行 非売品)