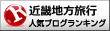著者の青地久恵さんが、御尊父の生涯を描いた『大工の神様』を出版されたのは、旧臘12月のことであった。越後の宮大工に弟子入りし、のちに弟子屈町川湯温泉を足場に昭和40年代までにかけて、多くの作品を残した名工の軌跡を、「愛情を込めて書いた」と紹介させていただいたのは、つい先日であったような気がする。
この3月17日、洲崎町「藏」を再生させる会の講演会に招かれてでかけていったところ、著者から「続編です」と、本書を頂戴した。写真集である。師匠の田島与一郎翁の元気なお姿が紹介され、師匠の作品にくわえてご一家の姿やお父上の田村由松翁参加の一門、そしてその作品の数々が紹介されている。副題に、「大工の神様」出版記念写真集とあり、暮れに出版された『大工の神様』の姉妹編、追録のビジュアル版、関係写真が一書にまとめられた。
おおまかに数えて100点ほどの写真に挿図(川湯温泉絵地図)が一点。ベースに『田島与一郎日記』の記載事項を配置し、そこに前述の写真が配置されている。作品を通じて温泉旅館、寺院建築、民家・事務所に及ぶ匠の誇りが表明されている。木造のせめて二階建て、三階建ての建物ながら風格やぬくもりを感じさせてくれる作品群は読む者ならずとも、「ホットさせてくれる」落ち着きを記憶とともに呼び覚ませてくれる。他方で、時代をうつす作業着に包まれた、技術者の誇りと誠意をおもわせる職人集団、つまり一門の写真も盛り込まれて、力強い。
時代はうつり川湯温泉のたたずまいは、鉄筋・高層の建築物にかわり、往事のおもかげは歴史の舞台から消えている。
宿泊したなーと思わせる第一旅館の風情や、一度は泊まってみたいとあこがれた老舗たる橘屋の容姿。そして「火災で焼失」と『大工の神様』に紹介されてあった瑞龍寺本堂。いずれも失われた栄光が豊かによみがえる。
本書は、「『大工の神様」』出版記念写真集」のサブタイトルがつけられている。
今日からみると決して豊かではないが、そこに込められた一市井人の誇りと存在感を存分に伝えている。本書は時代を読み取ることの楽しさを提示する。しかも、工匠の粋と意気を形にしたところに、本書の意義と提案がこめられている。そう感じたのであるが。