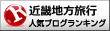温排水は選炭場、Co2は坑道に蓄積、残滓は坑道充填 釧路火発210207.
旧臘師走に営業発電を開始した「釧路石炭火発」。「脱炭素社会」の要請のなか、非難ゴウゴウの船出でもある。
その稼働状況を道内配布紙が伝えた。2月7日のことである。
環境への配慮。
1965年頃、このマチで立ち上げられた電力会社の火発構想は、予定地を変更して立地した。
そういうことであったと、記憶する。
2017年9月、「音別火発が発電し、ブラックアウトに貢献」、その報は市民を安堵させた。
しかし、ほどなく伝えられたことは、「老朽化による休眠中だった施設は、機能せず」「発電中止」の報が伝わった。
2015年、「環境問題をどう、クリアするのか」。
「地元産石炭で、地元消費向け火力発電」の報が伝わったとき、往時の火発議論を思い出した。
当時、要因は温排水が漁業資源と漁村漁業に与える要因が、まず提起されたと記憶する。
「北電野球場」。釧路町域に位置する広い土地は、確か、「火発予定地」とされた「釧路川べりの要地」。
旧臘師走に営業発電を開始した「釧路石炭火発」。「脱炭素社会」の要請のなか、非難ゴウゴウの船出でもある。
その稼働状況を道内配布紙が伝えた。2月7日のことである。
環境への配慮。
1965年頃、このマチで立ち上げられた電力会社の火発構想は、予定地を変更して立地した。
そういうことであったと、記憶する。
2017年9月、「音別火発が発電し、ブラックアウトに貢献」、その報は市民を安堵させた。
しかし、ほどなく伝えられたことは、「老朽化による休眠中だった施設は、機能せず」「発電中止」の報が伝わった。
2015年、「環境問題をどう、クリアするのか」。
「地元産石炭で、地元消費向け火力発電」の報が伝わったとき、往時の火発議論を思い出した。
当時、要因は温排水が漁業資源と漁村漁業に与える要因が、まず提起されたと記憶する。
「北電野球場」。釧路町域に位置する広い土地は、確か、「火発予定地」とされた「釧路川べりの要地」。