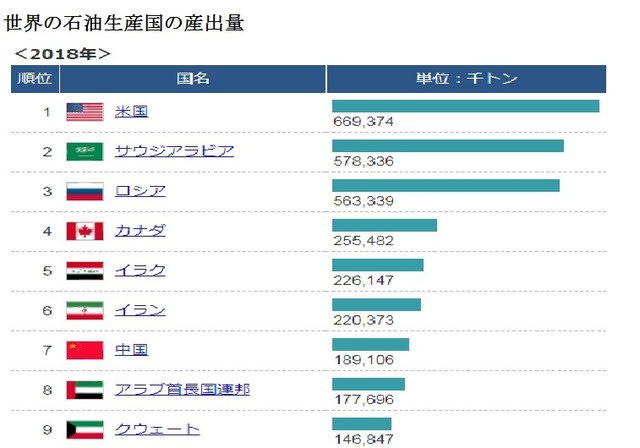「DaaS」を中心とした新たなトレンドにより、システム屋はデバイスの多様な選択肢をエンドユーザーに提供できるようになった。そして、MSは「Windows Virtual Desktop」でDaasを、Windows端末に加えMac、Chromebook で実現出来るようになった。端末の垣根が取り払われた事になる。
DaaSとは、クラウドサービスの一つで、コンピュータのデスクトップ操作画面をネットワークを通じて遠隔の端末へ提供するサービス。利用者ごとにフル機能のコンピュータ一式を揃えなくても簡易な端末などを通じてデスクトップ環境を利用できる。
以下、IT 専門誌TechTargetJapan誌による:::::::::::::::::::
仮想デスクトップをサービスとして提供するDaaS(Desktop as a Service)と、ノート型デバイス「Chromebook」や「MacBook」、さらにはタブレット「iPad」は、ぴったりの組み合わせだ。これらのデバイスはいずれも、それ自体の成熟度が高いだけでなく、アプリケーション仮想化やデスクトップの仮想化と組み合わせることが可能だ。この組み合わせを生かせば、企業はエンドユーザーに対して多様なデバイスの選択肢を提供しやすくなる。
Mac、Chromebookの導入を促進するトレンド
「リモートのWindowsデバイスで稼働するアプリケーションやデスクトップを、Windows以外のOSを搭載したデバイスで利用できるようにする」という考え方は、新しくはない。この考え方は常に、リモートコンピューティング(遠隔のデバイスからコンピューターを利用する仕組み)の“中心原理”となってきた。特にオンプレミスのVDI(仮想デスクトップインフラ)またはDaaSと、Chromebookを組み合わせるという考え方に基づいて、これまでにベンダーが他社との提携などの取り組みを進めてきた。
現在、幾つかの動きがこの考え方に新風を吹き込んでいる。主要なトレンドを紹介しよう。
トレンド1.「Windows Virtual Desktop」の登場
1つ目は、DaaSの実用性がこれまで以上に高まっていることだ。MicrosoftがDaaS「Windows Virtual Desktop」を発表し、DaaS市場は活気付いた。ユーザー企業がDaaSを利用すると、デスクトップ仮想化とアプリケーション仮想化の利点を取り入れながら、インフラの運用管理とホスティングをサービス提供事業者に任せられる利点がある。DaaSの特に大きな利点は、オンプレミスのインフラにVDIを構築する際にかかる多大な初期コストを必要としない点と、簡単にスケールできる点にある。
トレンド2.Chromebook、MacBookの管理機能
2つ目は、WindowsではないOSを搭載したデバイスの管理機能が充実してきたことだ。IT担当者はVMwareの「VMware Workspace ONE」やCitrix Systemsの「Citrix Endpoint Management」といった統合エンドポイント管理(UEM)製品を使って、Chromebookを管理できる。PCベンダーは、「Chrome OS」を搭載した新しい法人向けChromebookである「Chromebook Enterprise」シリーズを市場に投入し始めている。
MacBook管理の分野も急速に成長している。MacBookのOSである「macOS」が、デバイス管理用のAPI(アプリケーションプログラミングインタフェース)を拡充したことで、MacBookを管理より簡単に管理できるようになった。iPad用のOS「iPadOS」はマルチタスク機能を強化し、ビジネスでiPadを利用する魅力を高めた。
トレンド3.Windowsへの依存度の低下
3つ目は、企業におけるSaaS(Software as a Service)の導入が進むことで、Windowsへの依存度が下がる点だ。SaaSは多様なクライアント環境での動作を重視しており、一般的にはWindowsに加えて「iOS」およびmacOS、「Android」といった各種OSで利用できる。オフィススイート「Microsoft Office」もモバイルデバイスでの利用を重視し、例えばmacOS向けのクライアントアプリケーションが、公式アプリケーションストアの「App Store」で提供されている。
この動向を受け、VMwareやCitrixはUEMとデスクトップ仮想化製品の機能を統合し、あらゆるタイプのデバイスをサポートするコンセプトを具現化している。
トレンド4.エンドユーザー主体のIT環境の重視
4つ目は、IT部門ではなく、事業部門の担当者が積極的にシステム構築や運用に関わる、エンドユーザー主体のIT環境整備に、より多くの注意を払う企業の動きがある点だ。エンドユーザーが自分の望むデバイスを選べるようにすることは、エンドユーザー主体のIT環境整備を推進する企業の顕著な取り組みだと言える。
多様なデバイスが必要とされる
IT部門は今、デバイス管理製品を利用することで、これまで以上に簡単に多様なデバイスを管理し、DaaSによってWindowsアプリケーションの配信を容易にすることが可能になった。企業はデバイス導入の方針を慎重に検討し、自社にとってどのようなアプローチが理にかなっているかを見極めなければならない。結論がどうなるにせよ、今こそそれを議論すべきときだ。