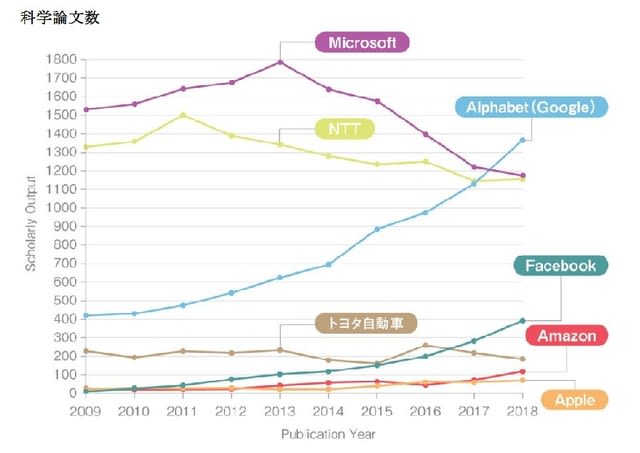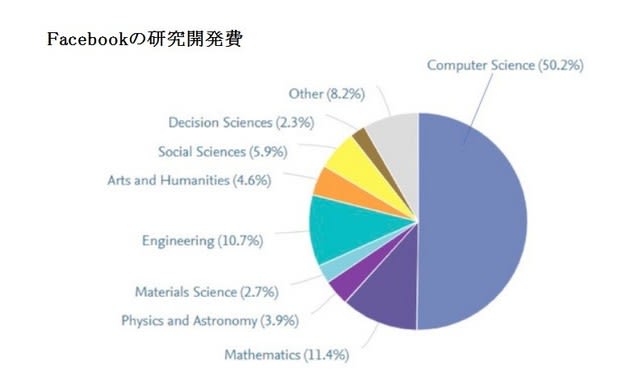産経新聞が『「巨大NTT復活」に待った auやソフトバンクなど30社、共同調達に反対 意見書提出へ』と言うニュースを出しているが、NTTが巨大化してでも、日本は、再度技術先進国入りを果たすべきだと思う。NTT 巨大化を恐れるSoftBank、au等30社は大同団結して、巨大グループを作って、対抗しかつ先端技術開発にまい進すべきでは? 2大グループなら、競争が働き寡占による弊害を無くせるだろうし、巨大化による弊害をない様にする政策を取るべきであろう。
総務省が昨年末に打ち出したNTTグループによる通信関連機器などの共同調達を認める方針を受け、KDDI(au)やソフトバンクなど通信約30社が近く、反対の意見申出書を高市早苗総務相に提出することが26日、分かった。総務省は規制緩和による調達コスト低減で、先進技術への投資やデジタル変革などを促す考えだが、競合企業は公正な競争が阻害されることなどを懸念し、“巨大NTTの復活”に待ったをかける。
KDDIやソフトバンクなど約30社は意見申出書を27日にも提出する。公正競争確保のために必要な議論の実施や、共同調達にかかる審査や認可基準を定めることを求めるほか、これらが完了するまでは共同調達を開始しないように指導するよう要求する。
旧電電公社が前身のNTTは昭和60年の民営化まで通信市場を独占し、関連機器メーカーに対して巨大な購買力を誇った。このため、NTTドコモ、NTTデータ、NTTコミュニケーションズの3社が分社化される際は、競合がコストで太刀打ちできないとして、NTT持ち株会社とNTT東日本、NTT西日本との共同調達が行政上の方針で禁止された。
だが近年、NTT持ち株会社とNTT東西を合わせた調達額のグループ全体に占める割合は、かつての8割程度から2割程度に下がった。総務省の有識者会議は昨年12月にまとめた将来の通信ルールづくりの最終答申で「資材調達を取り巻く環境が大きく変化し市場に与える影響は小さくなっている」として共同調達の容認を盛り込んだ。
この流れに競合各社は警戒感を強める。NTTグループの通信機器の発注量が増えて価格交渉力が強まれば、NTTグループがコストで有利になるだけでなくNTT仕様が通信機器の事実上の標準になる可能性もあるためだ。関係者は今春の第5世代移動通信システムの商用サービス開始を踏まえ、「新たな通信網整備などが進む時期だからこそ、公正競争が担保される環境が非常に重要になる」と語る。
有識者会議の最終答申では「公正競争を阻害しない範囲で認める」としながらも、「対象品目や規模など具体的な内容は何も示されていない」(関係者)。競合各社からは「ルール変更の際の根拠や影響などがほぼ議論されないまま、方向性だけが出た」という不満の声が上がっている。