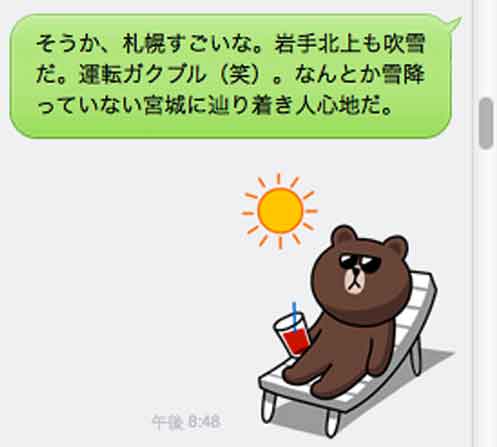今回の広島出張では、
休日を利用して、わたしの家系探訪をしておりました。
わたしの家は、大正年間の初年ころに広島県福山市近郊から
一家を挙げて移住してきた家系なのです。
わたしの父親はまだ3歳の時に北海道に移住したので
訛りなどはほとんどなかったのですが、
年長の叔父たちには濃厚な広島弁訛りがあって、耳に焼き付いている部分がある。
そういった幼少期の記憶が、自分の中から消えないうちに
ルーツの土地に対する肉体体験を多少は持っておきたいと考えるもの。
手掛かりは次兄が調べてくれた先祖の過去帳などの調査資料です。
そのなかに鞆の浦という古い街の福禅寺という寺に縁があったとされていて、
その手掛かりをあてに、100年を超えてなお残る空気感を感じたいと思ったのです。
そのように逍遙してみた次第。
広島というのは、県の西側にあるのですが、
福山は東側の外れのような位置で、鞆の浦はいまは福山市の一部。
西隣には尾道があります。
これらの都市集落は、いずれも瀬戸内海に面していて、
ずっと歴史年代、アジア世界と畿内地域を結ぶ大動脈の役割を担ってきた。
海運が最大の交通手段であった時代に栄華を誇った地域。
厳島とか、鞆の浦とか、尾道とか
こういった瀬戸内海岸線地域を歩いてみると、
そのような時代の雰囲気と空気感が良く理解出来る。
なかでも尾道は、海上交通によって商業が栄え、
急峻な坂道と暮らしが寄り添うように紡いできた文化を良く伝えてくれています。
坂の街で、古い住宅に手を入れて「猫の細道」という街づくりに取り組んでいる
園山春二さんという方と偶然に知り合ったりしました。

こんな猫の造形物を作ったりしている。
もと電通社員の方で、たのしくお話させていただけました。
で、そんな語らいの中で、ふと目に留めた「あなごのねどこ」の情報を聞いた次第。
わたしも実は尾道の駅周辺商店街のなかに面白い一角を発見して
写真に納めていたものだったのです。
お話では、若い年代の方が古い「町家」形式の商家を借りて
それを宿泊施設として再生利用しているのだそう。
こういった古いニッポン的な場末感を楽しませる仕掛けを行って
それがある程度、訴求力を持っているようなのです。

内部はこんな感じで、欧米系のみなさんを中心に
どうも海外からのみなさんにも、ウケているようなのであります。
まぁわたしとしては、住文化としての部分で面白みを感じる次第ですが
欧米のみなさんには、東アジア的なエキゾチシズムとして了解可能なのでしょう。
そしてニッポン人としても、こうした人間くささの積層した文化に対して
そのいごこちや性能面は度外視した部分で
いわば暮らし文化のようなものに、ある価値観を見出しつつあるように思います。
このブログの読者のみなさんはおおむねご存知のように
わたし自身も、こういった趣味傾向は持っているのですが、
さて、こういった部分が大きな住宅デザイン領域にまで表出していくモノかどうか、
店舗などの「非日常性」空間としてはおもしろさとして了解可能でしょうが、
暮らし方や、ふつうの生活デザインパターンの一種として
受け入れられていくのかどうか、
ちょっと、興味を抱かせられた次第であります。
ふ~~~む、さて。