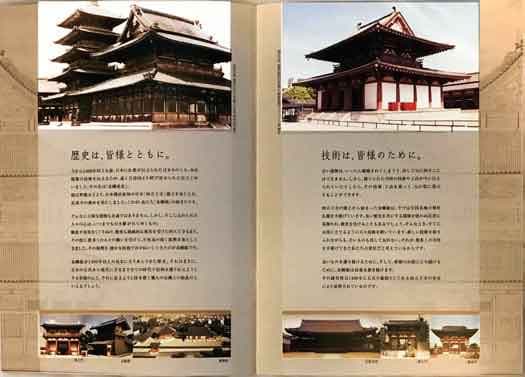写真は先週日曜日に見学していた姫路林田の方の「三木家住宅」です。
こっちの家も、先日来ご紹介している「福崎・三木家住宅」と同様に
わが家の伝承にかかわっている家系のようなのであります。
で、見ていて驚いたというか、見たことがない光景を発見。
写真のように大きな根曲がりの梁が渡されているのですが、
その梁には、ご覧のように土が塗り込められているのです。
奥の方に行くと、2枚目の写真のような状況でした。
わたしもたくさんの「古民家」建築を見てきていますが、
こんなふうに横架材が塗り土で被覆されているというケースは見たことがない。
この建物は兵庫県の指定有形文化財であり、
公費を使って保存修理された建物ですから、きちんと考証され、
こういった内装仕上げも、きちんとした調査の上で復元施工されている。
見たことがなかったので、ボランティアの説明員さんに聞いたところ、
「くどで火を扱うので、そのために防火仕様にしている」ということ。
「くど」というのは、Wikipediaの記述では以下の通り。
〜京都などでは、竈(かまど)そのものを意味し、「おくどさん」と呼ぶ。
また、土間など住居の中で、煮炊きを行う空間そのものを意味することもある。
山陰地方などでは、煮炊きの設備を「かまど」、空間そのものを
「くど」と呼んで区別している地域も存在する。〜
ようするに台所空間のことのようです。
現代住宅では、法令で台所は「防火処置」がいろいろに義務づけられますが、
目的としては同じような機能を果たせるように工夫しているようなのです。
現代のように「不燃建材」などがあるわけではなく、
燃える木材を素地のまま使う建築材料しかない。
そこで「難燃性」を確保するためにこのように土塗りを施したようなのです。
ふつう、土塗り施工は脱落しないようにするために
小舞いといわれる下地の構成が不可欠になるのではないかと思われるのですが、
このような素地のままの自然木、根曲がり材に対してどのように土を展着させるのか、
そこまでは説明を確認できませんでした。
この住宅は「大庄屋」の住居であり、公的な施設としての側面もあって
多くのひとが参集する建物なので、
くど、かまども大人数のための大型のものが備えられている。
そういう意味で火災への備えもしっかりされていた、ということなのでしょう。
効果のほどや、施工方法などに興味を持った次第。
それと、ほかではあんまり見たことがないので、
なぜこの住宅でこんな技法が採用されたのか、理由にも興味を持ちました。