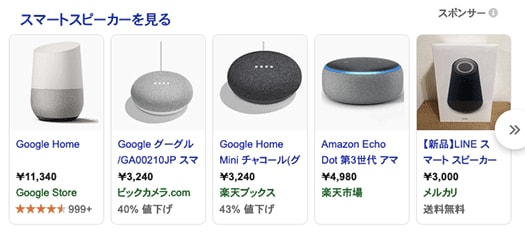本日も総歩数4000歩超の散歩から帰還。
で、きのうの北海道神宮「西鳥居」を興味深く建築工事観察。
きのうの状況は以下のようでした。

<昨日の写真に若干の画像補正しています>
違いが明らかなのは「貫」が入れられたことです。
上部の「笠木」と2本の柱だけだった昨日から、
この貫が加えられたことで、目にも見慣れた鳥居の外観。
貫というのはWikipediaで見ると
「貫(ぬき)とは木造建築で柱等の垂直材間に通す水平材。
日本には鎌倉時代の俊乗坊重源が中国から大仏殿建造のための
最新技術として伝え、その構造の強固さから急速に日本全国に広まった。
木造建築では、水平方向の固定に用いる。」とされている。
次の写真は貫と柱の接合部のアップです。

貫はそれこそ柱に「貫通」させるので、
柱間よりも長さが長いことになる。
それを柱に予め穴を空けておいてから、貫入させる。
木の貫を入れる場合には木材を曲げたり滑らせたりして
なんとか施工するのでしょう。
こちらの北海道神宮の西鳥居は鉄柱素材なので、
さてどうやって貫入させたのか、興味深く感じた。
工事の終わった今朝の段階では、クローズアップで見ると
1箇所に「コミ栓」のようなものを確認することができました。
これがどういうことであるのか、
やがて取り払われるのだと思われますが、
この施工のプロセスをなにか暗示しているように思われる。
現代の建築の構造の考え方では、
この貫は建築力学的に整合性を持って説明されないとされます。
鎌倉時代の重源さんという人物は、
平家の焼き討ちで灰燼に帰した奈良の東大寺大仏殿を再建すべく、
頼朝など全国の有力者から資金を勧進してみごと再建した方ですが、
そういったいわば、プロデューサーであると同時に
この貫について、最先端技術として中国から導入したというのは
初めて知った。建築者として語られ続けるべき人物だと。
まぁこれは一個人のスーパーマン的な活躍ということではなく、
この時代の建築のすべての先端的なひとびとの協働の結果なのでしょう。
戦乱からの復興に於いて、それがまた新技術の発展につながっている。
ニッポンの先人の知恵と努力の上で
今日のわたしたち社会が存在するのだと強く感じさせられますね。
で、きのうの北海道神宮「西鳥居」を興味深く建築工事観察。
きのうの状況は以下のようでした。

<昨日の写真に若干の画像補正しています>
違いが明らかなのは「貫」が入れられたことです。
上部の「笠木」と2本の柱だけだった昨日から、
この貫が加えられたことで、目にも見慣れた鳥居の外観。
貫というのはWikipediaで見ると
「貫(ぬき)とは木造建築で柱等の垂直材間に通す水平材。
日本には鎌倉時代の俊乗坊重源が中国から大仏殿建造のための
最新技術として伝え、その構造の強固さから急速に日本全国に広まった。
木造建築では、水平方向の固定に用いる。」とされている。
次の写真は貫と柱の接合部のアップです。

貫はそれこそ柱に「貫通」させるので、
柱間よりも長さが長いことになる。
それを柱に予め穴を空けておいてから、貫入させる。
木の貫を入れる場合には木材を曲げたり滑らせたりして
なんとか施工するのでしょう。
こちらの北海道神宮の西鳥居は鉄柱素材なので、
さてどうやって貫入させたのか、興味深く感じた。
工事の終わった今朝の段階では、クローズアップで見ると
1箇所に「コミ栓」のようなものを確認することができました。
これがどういうことであるのか、
やがて取り払われるのだと思われますが、
この施工のプロセスをなにか暗示しているように思われる。
現代の建築の構造の考え方では、
この貫は建築力学的に整合性を持って説明されないとされます。
鎌倉時代の重源さんという人物は、
平家の焼き討ちで灰燼に帰した奈良の東大寺大仏殿を再建すべく、
頼朝など全国の有力者から資金を勧進してみごと再建した方ですが、
そういったいわば、プロデューサーであると同時に
この貫について、最先端技術として中国から導入したというのは
初めて知った。建築者として語られ続けるべき人物だと。
まぁこれは一個人のスーパーマン的な活躍ということではなく、
この時代の建築のすべての先端的なひとびとの協働の結果なのでしょう。
戦乱からの復興に於いて、それがまた新技術の発展につながっている。
ニッポンの先人の知恵と努力の上で
今日のわたしたち社会が存在するのだと強く感じさせられますね。