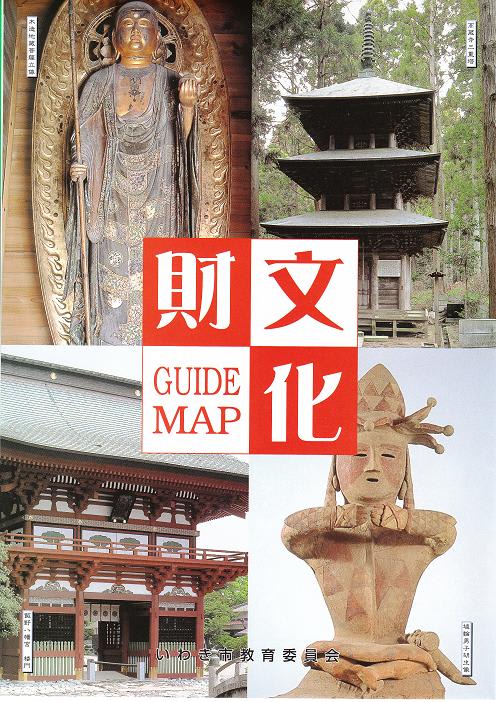いわき市教育委員会発行の「文化財GUIDE MAP」です。
指定文化財一覧表とそれが地図に落としこまれて
ひと目でわかるようになったパンフレットです。

3・11、4・11、4・12による地震や津波で被害を受けた
いわき市の「指定文化財」の被害状況がまとめられています。
先日
いわきヒューマンカレッジいわき学部4回目の講座に参加しました。
東日本大震災といわきの指定文化財
ー被災状況の今後の対応ー
講師は
樫村 友延先生(いわき市考古資料館館長)でした。
1)定義
①文化財とは
②指定文化財とは
③登録有形文化財とは・・・平成8年に創設された新しい概念です。
2)いわき市の文化財体系・・・有形文化財・無形文化財
3)いわき市の指定文化財その被害状況
92枚のスライドで紹介されました。
4)震災時と今後の対応
①国での文化財レスキュー
②県内の文化財レスキュー
③市内の文化財レスキュー
④今後の対応
5)まとめ
と多岐にわたる項目を講義いただきました。
特に
3)のいわき市の指定文化財その被害状況では
92枚のスライドをパワーポイントで紹介いただき
画像で現在の被害状況が見られましたので、
わかりやすい講義になったのではと思います。
被害状況では
建造物は約72%に被害が出ています。
彫刻では37%が、史跡では26%に被害が。
4)の今後の対応について
①今やれる事を行うことが大事。
②指定・未指定にかかわらず
修復などへの官・民での支援が大事。
③旧家や史料所蔵者情報の収集の実施と所在マップの作成。
④地域を越えた地方自治体との連携・強化。
⑤文化財レスキュー市民ボランティアの創出。
⑥放射能汚染の問題
が今大事ではないのかと。
最後にまとめとして、
1)「なぜ、文化財を保護・保存するのか」を
再考する絶好のチャンスでもあるのではと。
☆今回の震災・原発事故発生による地域コミュニティの崩壊の危機。
☆地域の人々に支えられ、地域の人々を支えてきた数々の文化財。
今、地域コミュニティや地域の存在を確かめるためにも、
文化財を通して地域が長い間育んできた歴史を知ることや、
その歴史内容を正確に残すことが大事ではないのかと。
☆地域に残るこれらの文化財は、
その地域を示す大切な歴史遺産。
従って、被災を受けた文化財の保全活動は
今に生きる私達の重要な仕事ではないのかと。
2)震災と原発事故によるいわきの被災の特性把握と
後世へ伝える責務があるのではないか。
☆岩手県・宮城県と福島県の違い、
会津地方・中通り地方と浜通り地方の違い、
相双地区といわきの違いを明確にしておくことも大事と。
☆いわき地区の津波マップの検証・・・3月11日
☆いわき地区の活断層マップの検証・・・4月11日
が今後私達が
早急にやらなければいけないのではと結ばれました。
樫村先生、
貴重な映像と共に、
今後・私達が後世に残さなければいけない課題を示され
ありがとうございました。
地震・津波でいわき市では
310名の方々が亡くなられ(行方不明者は38名の方々が。)、
被害も甚大ですが、
亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに
今後、どのように復興させていくのか
文化財からの貴重な講義になりました。