個人的評価: ■■■■■□
[6段階評価 最高:■■■■■■、最悪:■□□□□□]
THE NORTH FACE のキャップ、MAMMUTのフリースジャケット、CASIOのPRO TREKを腕にまいて、MERRELLのカメ2履いてと・・・低山の日帰りトレッキングスタイルで映画館に向かった。中々の気合いで挑んだ「127時間」は期待を裏切ること無く楽しませてくれた。
主人公のアーロンが行きトラブルになるのは山ではないけれど、彼のクライマーグッズ満載の装備にはもちろん親近感。ヘッドランプ、プラティパス、カラビナ、山でおなじみの装備。そして落石によるトラブル発生は北アルプスにも当然起こりえることで、彼の失敗と成功の両方から遭難対策のあれこれを学ぶことができて山好きな男女を楽しませるだけでなく、いい参考資料になるだろう。
だから「127時間」は山が舞台ではないけれども、「劔岳 点の記」以来の山好きな映画好きを楽しませる「山映画」に認定したい。(2011年に公開された北アルプスが舞台のあの日本映画は美しい空撮映像以外はあんま楽しめなかったので、余計にうれしい作品だ)
しかし、単なる山好きのための山映画ではなく、映画好きを楽しませる要素もいっぱいだ。
映画の歴史を振り返ると時々「独りぼっちもの」映画が作られて評価されていることを思い出す。
裕次郎と市川崑の「太平洋ひとりぼっち」(見てないけど)
ビリー・ワイルダーの「翼よあれが巴里の灯だ」
最近だとロバート・ゼメキスの「キャスト・アウェイ」
「127時間」もまた独りぼっちものの成功作の一つに数えられるだろうし、さらにほとんど身動きができないまま127時間を過ごした男という普通に考えればおよそ映画向きではない企画を見事に成功させた。
身動きできない系映画としては「フォーンブース」とか「潜水服は蝶の夢を見る」とかを思い出す。独りぼっちで身動きできないという二重の困難にかかんに立ち向かい、成功させた映画として高く評価したい。
話し相手がいないため説明台詞に頼れない「ひとりぼっちもの」では、それでも独りぼっちの主人公に台詞を喋らせるために脚本家と監督は色々と作戦を考える。
一般的な作戦としては回想シーンを挿んで、台詞、会話、説明を主にそこで片付けてしまう方法。「キャスト・アウェイ」はボールのウィルソンを相手に喋らせた。
「127時間」も回想シーンなどは勿論あるが、「翼よあれが・・・」みたいに回想シーンに頼りきった物語構成にはしていない。主人公はビデオカメラに自分の状況を記録することで独りぼっちにもかかわらず台詞を喋る。
中でも面白かったのは主人アーロンが一人でトークショーごっこをしてMCとゲストの一人二役する場面。
一人二役の会話で思い出すのは、「ロード・オブ・ザ・リング」の二作目でスメアゴルの二重人格独り言をイマジナリーラインをまたいで切り返すことで会話のようにしてしまった秀逸なカット割りだ。
「127時間」ではビデオカメラというアイテムをうまく使って、アーロンの生映像とビデオのモニターを切り返すことで独り言の会話化に成功させた。
そしてこの映画が映画好きを喜ばせるのは、もちろん監督がダニー・ボイルであるということだ。
妄想の中での感情爆発が得意なダニー・ボイルにとって、極限状態で行動不能に陥った男という物語は、そもそも困難どころか創作意欲をかき立てまくる格好の題材だったのかもしれない。
動けないからこそ、動的な記憶の数々が蘇り、水が無いからこそ水に関する妄想が凶暴なまでに暴走し、命が削られていくからこそ生きることへの執着が強く激しくなっていく。
動けない誰もいないは主人公の感情も欲望もどんどん加速させていく。
そしてダニー・ボイルの好きな渇望は汚物を越えてシーン。トレスポの便所の場面とか、スラムドッグ・ミリオネアの肥だめの場面とかダニー・ボイルの名シーンはいつもくそ汚い。
しかし今回はこれまでのように、ドラッグとかスターのサインとかそんな物欲が渇望対象ではなく、生命そのものへの渇望だ。
チューブの中を吸い上げられる小便の映像も、泥と雑菌が政府の基準値の2億倍くらいありそうな泥水をガブ飲みする場面も、ダニー・ボイル節全開だ。
ああ、そして痛みを伴う場面が自分はつくづく好きなんだと思い知る。
スプラッターホラーの切断シーンや粉砕シーンは想像力が追いつかなくて逆に痛くないのだが、ミザリーの足を折る場面とか、ブラック・スワンの生えてきた黒い羽を引き抜く妄想とかは、想像できて痛い。
本作の神経を切るシーンの痛みは今思い返してもヒィィと恐怖が走る痛さだ。激痛名シーンの一つに認定しよう。
そんな激痛場面を盛り上げたのが「スラムドッグ・ミリオネア」に引き続いてダニー・ボイル作品の音楽を担当したインドのA.R. ラフマーンだ。かつて「ムトゥ 踊るマハラジャ」のころは「インドの小室哲哉」などと紹介されていた作曲家だ。
前作は内容からいってラフマーンの起用は違和感なかったが、インドと縁もゆかりも無い今作でも音楽を任せてしまうのだからダニー・ボイルはよっぽどラフマーンの音楽が気に入ったのだろう。
前述の激痛シーンでの神経を伝達する激痛信号の効果音のような音楽といい、127時間ぶりに他人に出会いついに助かったときの魂からの歓喜を表現しまくる音楽とか、いちいち心を揺さぶってくる。人によってはやかましいと嫌われるかもしれないが、彼の音楽は魂に直接響く。
*******
[山映画として・・・彼の失敗から学ぶこと]
『居場所を教えることが遭難者の生存率をあげる上で非常に重要である』
アーロンの場合携帯電話を持っていても圏外だったに違いないが、北アルプス辺りならけっこう効果的だろう。圏外だとしても留守電のメッセージに行き先や行動予定を吹き込んでおけば誰かが気づいてくれるかもしれない。
しかしそれよりも何よりも、事が起きる前からの対応が一番大切だ。彼の最大の失敗は本人も話していた通り、トレッキングの計画を誰にも話していなかったことだ。だから登山計画書の提出はやはり絶対に必要な事だし、さらに家族や知人に行き先を伝えておけば遭難時の捜索の重要な手がかりになるのだ。
[山映画として・・・彼の成功から学ぶもの]
『刃物とロープの使い方は学んでおこう』
刃物に関してはもっとよく切れる物ならどれだけ楽だったか判らないけど。スイス製のナイフ俺も買おうかなと思った。
ロープの使い方、ほどけない縛り方はサバイバルでとっても重要だ。体に巻き付けて寒さ対策にもなるとは。結果うまくはいかなかったが岩を動かすリフト装置にしたり、何より最後の水たまりへの下降はロープの扱いに精通していたからだ。あそこでロープが無ければ崖の上でのたれ死にか転落死のどちらかだった。
8の字結び、もやい結び、本結び、あれこれあるけどちゃんとマスターしておこう・・・と本作を見て思った。
[追記]
それにしてもアーロンさんは強いクライマーになったのでしょうな。
無くした腕にピッケルが装着されていた姿を見て、とても頼もしい感じがした
[追記の追記]
前回のアカデミー作品賞候補作はこれでやっと5本目の鑑賞。
「英国王」がこれや「ブラック・スワン」や「ソーシャル・ネットワーク」より上だとはどうしても思えないなあ
********
ブロガーによる00年代(2000~2009)の映画ベストテン
↑この度、「ブロガーによる00年代(2000~2009)の映画ベストテン」を選出しました。映画好きブロガーを中心とした37名による選出になります。どうぞ00年代の名作・傑作・人気作・問題作の数々を振り返っていってください
この企画が講談社のセオリームックシリーズ「映画のセオリー」という雑誌に掲載されました。2010年12月15日発行。880円
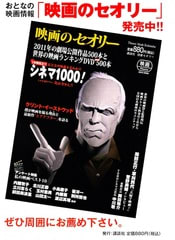
------------
↓面白かったらクリックしてね
 にほんブログ村
にほんブログ村
人気blogランキング
自主映画撮ってます。松本自主映画製作工房 スタジオゆんふぁのHP
[6段階評価 最高:■■■■■■、最悪:■□□□□□]
THE NORTH FACE のキャップ、MAMMUTのフリースジャケット、CASIOのPRO TREKを腕にまいて、MERRELLのカメ2履いてと・・・低山の日帰りトレッキングスタイルで映画館に向かった。中々の気合いで挑んだ「127時間」は期待を裏切ること無く楽しませてくれた。
主人公のアーロンが行きトラブルになるのは山ではないけれど、彼のクライマーグッズ満載の装備にはもちろん親近感。ヘッドランプ、プラティパス、カラビナ、山でおなじみの装備。そして落石によるトラブル発生は北アルプスにも当然起こりえることで、彼の失敗と成功の両方から遭難対策のあれこれを学ぶことができて山好きな男女を楽しませるだけでなく、いい参考資料になるだろう。
だから「127時間」は山が舞台ではないけれども、「劔岳 点の記」以来の山好きな映画好きを楽しませる「山映画」に認定したい。(2011年に公開された北アルプスが舞台のあの日本映画は美しい空撮映像以外はあんま楽しめなかったので、余計にうれしい作品だ)
しかし、単なる山好きのための山映画ではなく、映画好きを楽しませる要素もいっぱいだ。
映画の歴史を振り返ると時々「独りぼっちもの」映画が作られて評価されていることを思い出す。
裕次郎と市川崑の「太平洋ひとりぼっち」(見てないけど)
ビリー・ワイルダーの「翼よあれが巴里の灯だ」
最近だとロバート・ゼメキスの「キャスト・アウェイ」
「127時間」もまた独りぼっちものの成功作の一つに数えられるだろうし、さらにほとんど身動きができないまま127時間を過ごした男という普通に考えればおよそ映画向きではない企画を見事に成功させた。
身動きできない系映画としては「フォーンブース」とか「潜水服は蝶の夢を見る」とかを思い出す。独りぼっちで身動きできないという二重の困難にかかんに立ち向かい、成功させた映画として高く評価したい。
話し相手がいないため説明台詞に頼れない「ひとりぼっちもの」では、それでも独りぼっちの主人公に台詞を喋らせるために脚本家と監督は色々と作戦を考える。
一般的な作戦としては回想シーンを挿んで、台詞、会話、説明を主にそこで片付けてしまう方法。「キャスト・アウェイ」はボールのウィルソンを相手に喋らせた。
「127時間」も回想シーンなどは勿論あるが、「翼よあれが・・・」みたいに回想シーンに頼りきった物語構成にはしていない。主人公はビデオカメラに自分の状況を記録することで独りぼっちにもかかわらず台詞を喋る。
中でも面白かったのは主人アーロンが一人でトークショーごっこをしてMCとゲストの一人二役する場面。
一人二役の会話で思い出すのは、「ロード・オブ・ザ・リング」の二作目でスメアゴルの二重人格独り言をイマジナリーラインをまたいで切り返すことで会話のようにしてしまった秀逸なカット割りだ。
「127時間」ではビデオカメラというアイテムをうまく使って、アーロンの生映像とビデオのモニターを切り返すことで独り言の会話化に成功させた。
そしてこの映画が映画好きを喜ばせるのは、もちろん監督がダニー・ボイルであるということだ。
妄想の中での感情爆発が得意なダニー・ボイルにとって、極限状態で行動不能に陥った男という物語は、そもそも困難どころか創作意欲をかき立てまくる格好の題材だったのかもしれない。
動けないからこそ、動的な記憶の数々が蘇り、水が無いからこそ水に関する妄想が凶暴なまでに暴走し、命が削られていくからこそ生きることへの執着が強く激しくなっていく。
動けない誰もいないは主人公の感情も欲望もどんどん加速させていく。
そしてダニー・ボイルの好きな渇望は汚物を越えてシーン。トレスポの便所の場面とか、スラムドッグ・ミリオネアの肥だめの場面とかダニー・ボイルの名シーンはいつもくそ汚い。
しかし今回はこれまでのように、ドラッグとかスターのサインとかそんな物欲が渇望対象ではなく、生命そのものへの渇望だ。
チューブの中を吸い上げられる小便の映像も、泥と雑菌が政府の基準値の2億倍くらいありそうな泥水をガブ飲みする場面も、ダニー・ボイル節全開だ。
ああ、そして痛みを伴う場面が自分はつくづく好きなんだと思い知る。
スプラッターホラーの切断シーンや粉砕シーンは想像力が追いつかなくて逆に痛くないのだが、ミザリーの足を折る場面とか、ブラック・スワンの生えてきた黒い羽を引き抜く妄想とかは、想像できて痛い。
本作の神経を切るシーンの痛みは今思い返してもヒィィと恐怖が走る痛さだ。激痛名シーンの一つに認定しよう。
そんな激痛場面を盛り上げたのが「スラムドッグ・ミリオネア」に引き続いてダニー・ボイル作品の音楽を担当したインドのA.R. ラフマーンだ。かつて「ムトゥ 踊るマハラジャ」のころは「インドの小室哲哉」などと紹介されていた作曲家だ。
前作は内容からいってラフマーンの起用は違和感なかったが、インドと縁もゆかりも無い今作でも音楽を任せてしまうのだからダニー・ボイルはよっぽどラフマーンの音楽が気に入ったのだろう。
前述の激痛シーンでの神経を伝達する激痛信号の効果音のような音楽といい、127時間ぶりに他人に出会いついに助かったときの魂からの歓喜を表現しまくる音楽とか、いちいち心を揺さぶってくる。人によってはやかましいと嫌われるかもしれないが、彼の音楽は魂に直接響く。
*******
[山映画として・・・彼の失敗から学ぶこと]
『居場所を教えることが遭難者の生存率をあげる上で非常に重要である』
アーロンの場合携帯電話を持っていても圏外だったに違いないが、北アルプス辺りならけっこう効果的だろう。圏外だとしても留守電のメッセージに行き先や行動予定を吹き込んでおけば誰かが気づいてくれるかもしれない。
しかしそれよりも何よりも、事が起きる前からの対応が一番大切だ。彼の最大の失敗は本人も話していた通り、トレッキングの計画を誰にも話していなかったことだ。だから登山計画書の提出はやはり絶対に必要な事だし、さらに家族や知人に行き先を伝えておけば遭難時の捜索の重要な手がかりになるのだ。
[山映画として・・・彼の成功から学ぶもの]
『刃物とロープの使い方は学んでおこう』
刃物に関してはもっとよく切れる物ならどれだけ楽だったか判らないけど。スイス製のナイフ俺も買おうかなと思った。
ロープの使い方、ほどけない縛り方はサバイバルでとっても重要だ。体に巻き付けて寒さ対策にもなるとは。結果うまくはいかなかったが岩を動かすリフト装置にしたり、何より最後の水たまりへの下降はロープの扱いに精通していたからだ。あそこでロープが無ければ崖の上でのたれ死にか転落死のどちらかだった。
8の字結び、もやい結び、本結び、あれこれあるけどちゃんとマスターしておこう・・・と本作を見て思った。
[追記]
それにしてもアーロンさんは強いクライマーになったのでしょうな。
無くした腕にピッケルが装着されていた姿を見て、とても頼もしい感じがした
[追記の追記]
前回のアカデミー作品賞候補作はこれでやっと5本目の鑑賞。
「英国王」がこれや「ブラック・スワン」や「ソーシャル・ネットワーク」より上だとはどうしても思えないなあ
********
ブロガーによる00年代(2000~2009)の映画ベストテン
↑この度、「ブロガーによる00年代(2000~2009)の映画ベストテン」を選出しました。映画好きブロガーを中心とした37名による選出になります。どうぞ00年代の名作・傑作・人気作・問題作の数々を振り返っていってください
この企画が講談社のセオリームックシリーズ「映画のセオリー」という雑誌に掲載されました。2010年12月15日発行。880円
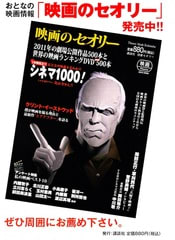
------------
↓面白かったらクリックしてね
人気blogランキング
自主映画撮ってます。松本自主映画製作工房 スタジオゆんふぁのHP

























