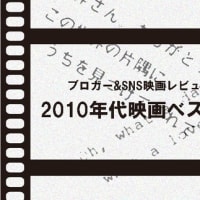グリフィスだエイゼンシュテインだと、原始的映画ばかり続けて観たので、口直しに「新作」を観ようと思いヒッチコックの「見知らぬ乗客」を鑑賞。
良い、面白い、興味深い・・・と思ったところは、トリュフォー著「ヒッチコック映画術」でほぼ語られていたので、同書の193ページから200ページをもって私の感想の代わりとする、と言ってしまうと身も蓋もないので、頑張って「ヒッチコック映画術」のパクリにならないように映評をしたためてみようと思う。
----
本作のスタッフで一際目を引くのは、共同脚本でクレジットされるレイモンド・チャンドラーである。
2人のビッグネームの共同作業。ワクワクドキドキもの・・・だが、できあがった作品は「ヒッチコック映画」以外の何物でもなく、レイモンド・チャンドラーの立場がない感じだ。
実際、「ヒッチコック映画術」によると、チャンドラーとの共作はうまくいかなかったとヒッチコックは述懐し、チャンドラーもクレジットに名前を出さないでほしかったと言っていたらしい。
大物同士が一緒に仕事をするのは注目を集めるにはいいのだが、たいていの場合は、どちらか一方の色が非常に強くなって他方が損する形になる。
一方が他方をヨイショすることでいいカンジになる(「第三の男」でキャロル・リードをたてたグレアム・グリーンとか、「インディ」でルーカスをたてたスピルバーグとか)か、一方がブチブチ文句を言って険悪になる(「シャイニング」でキューブリックに文句を言うスティーブン・キングとか)か、ほぼこの二つに一つだ。ビッグネーム二人の味が50:50で出てしかも傑作になったものって・・・少ないような気がする。
スタッフで他に注目したいのは、音楽のディミトリ・ティオムキンである。
迫力があり格調高い楽曲を得意とするこの作曲家は、「ジャイアンツ」「ナバロンの要塞」「アラモ」のような大作映画に引っ張りだことなり、ハワード・ホークスの西部劇などでも知られ(全て「見知らぬ乗客」より後の作品だが)、映画音楽史に名を轟かしている。今でいえばジョン・ウィリアムズの位置に近いような映画音楽の巨匠だった。
「見知らぬ乗客」でもダイナミックかつクラシカルな高級感のある音楽をつけ、作品を盛り上げている。だが、主張が強い割にメロディが残らないティオムキンの音楽(2000年代以降のウィリアムズも技巧にこりだしてメロディメーカーでなくなってしまった)を、恐らくヒッチコックはあまり気に入らなかったのではないだろうか?
といってもこの後の2作「私は告白する」と「ダイヤルMを回せ」もティオムキンと組んでいるから、そうでもないかもしれない。
名パートナーとなるバーナード・ハーマンとの邂逅は、まだ後のことである。
----
映画構成で興味深いのはクライマックスの壮絶アクションである。
暴走したメリー・ゴー・ラウンドの中で、主人公と殺人犯が壮絶な格闘をする。
「ヒッチコック映画術」でトリュフォーはこのクライマックスについて「正直、首を傾げたくなった」とムッシュ・ヒッチコックに堂々と苦言を呈していた。たしかに、それまでの一級サスペンスの香りはメリー・ゴー・ラウンドの超速回転の遠心力でぶっ飛ばされていくようだ。しかもアクション的にも、主人公が遠心力で吹っ飛ばされそうになったかと思えば、遠心力など関係ないねと駆け回ったりで、突っ込みどころが多い。
だが、クライマックスをここまで壮絶なアクションで飾ったヒッチコック映画は本作くらいではなかろうか。
「逃走迷路」の自由の女神像での対決、「北北西に進路を取れ」のラシュモア山での対決、「救命艇」でドイツのスパイをリンチにするクライマックス、「裏窓」の犯人との対決、「レベッカ」の屋敷が炎上するクライマックス、「バルカン超特急」のチェイスシーン・・・と物語の終結部をアクションやスペクタクルで締めくくった映画は沢山あるが、いずれも主人公と悪人の動きは少なく、カメラの動きも少なく、舞台設定と編集の緩急で盛り上げる、上品なアクションシーンであった。
しかしながら「見知らぬ乗客」のクライマックスは明らかに毛色が違う。ところどころにヒッチコック流のユーモア(メリー・ゴー・ラウンドの暴走で大はしゃぎする子供が主人公に加勢して悪人をポカポカたたく)、ヒッチコック流のテクニック(「メリー・ゴー・ラウンド上の主人公と悪人の対決」と「回転するメリー・ゴー・ラウンドの下の狭い隙間を這っていって暴走を止めようとする老人」とをパラレル編集する)が見られはするものの、このあまりに急激に壮絶アクションへ移行し強引に話を締めくくってしまう展開は、80年代以降のハリウッドアクションサスペンスの定番である。なんとなくロン・ハワードとかトニー・スコットとかがやりそうなクライマックスという印象。
とすると、ヒッチコックベストは「サイコ」だ「裏窓」だ「汚名」だ「めまい」だ・・・と、はやし立てておきながら、それらは継ごうとするものは誰も無く、ヒッチコック作品としてはそれほど完成度は高くなく知名度も低い「見知らぬ乗客」が、ハリウッドスタンダードとして選ばれていたことになるのかもしれない。
今でこそ知名度は低いが当時「見知らぬ乗客」は大ヒットしたらしい。「見知らぬ乗客」をスタンダードにして、「めまい」や「裏窓」を誰も撮ろうとしないのは、芸術より実利をとるハリウッドらしさの現れという気がする。
ハリウッドらしいがヒッチコックらしくないといえば、この映画はヒッチコックにしては珍しく二種類のラストシーンを撮っていたという(ハリウッドでは常識)。
何作か失敗が続いた後(「ロープ」→「山羊座のもとに」→「舞台恐怖症」→「見知らぬ乗客」)の作品だったので是が非でもヒットさせたかったのだろう。レイモンド・チャンドラーのような大物を担ぎ出したのも、大ヒットを最優先課題としていたからではなかろうかと思えてくるのだった。
-------
などと「やや否定的」なことばかり書いてきたが、そうはいってもヒッチコック。冒頭から結末に至るまで、いちいち面白い。
二人の靴のアップを交互に映して、それがこつんとぶつかりあって主人公と殺人者が顔をあわせるオープニングの素晴らしさは言わずもがな。
殺人者のキャラクターはヒッチコック作品の悪人ベスト3に入りそうなくらい印象的だ。
殺人者が主人公の妻を殺そうと、トンネルの中でボートで近づき妻の影と殺人者の影が重なると、カメラがトンネルの外に移り妻の悲鳴・・・と思ったら、男友達とふざけ合っている声だったりするじらしの上手さ。
主人公が殺人者の父を殺そうとしているかのように、屋敷に忍び込み、観客すべてに「ホントにいいのか?おい?」と思わせておきながら、階段の踊り場に番犬を登場させることで、今度は観客に「なんとか犬をやり過ごせ~」っとさっきまでとは真逆のドキドキ感を抱かせる展開とか、なんだってヒッチコックの映画はこんなに面白いんだろうと、その偉大さをあらためて思い知るのであった。
逃げた主人公を追う刑事がバッジをかざして車を停めて乗り込むと、お金持ちのマダムがいて「あの車を追っている」と言われたマダムが、好奇心と驚きの入り混じった顔をするところが大好きだ。
なんとなくイギリス流のユーモアだと思う。
********
↓面白かったらクリックしてね
 にほんブログ村
にほんブログ村
良い、面白い、興味深い・・・と思ったところは、トリュフォー著「ヒッチコック映画術」でほぼ語られていたので、同書の193ページから200ページをもって私の感想の代わりとする、と言ってしまうと身も蓋もないので、頑張って「ヒッチコック映画術」のパクリにならないように映評をしたためてみようと思う。
----
本作のスタッフで一際目を引くのは、共同脚本でクレジットされるレイモンド・チャンドラーである。
2人のビッグネームの共同作業。ワクワクドキドキもの・・・だが、できあがった作品は「ヒッチコック映画」以外の何物でもなく、レイモンド・チャンドラーの立場がない感じだ。
実際、「ヒッチコック映画術」によると、チャンドラーとの共作はうまくいかなかったとヒッチコックは述懐し、チャンドラーもクレジットに名前を出さないでほしかったと言っていたらしい。
大物同士が一緒に仕事をするのは注目を集めるにはいいのだが、たいていの場合は、どちらか一方の色が非常に強くなって他方が損する形になる。
一方が他方をヨイショすることでいいカンジになる(「第三の男」でキャロル・リードをたてたグレアム・グリーンとか、「インディ」でルーカスをたてたスピルバーグとか)か、一方がブチブチ文句を言って険悪になる(「シャイニング」でキューブリックに文句を言うスティーブン・キングとか)か、ほぼこの二つに一つだ。ビッグネーム二人の味が50:50で出てしかも傑作になったものって・・・少ないような気がする。
スタッフで他に注目したいのは、音楽のディミトリ・ティオムキンである。
迫力があり格調高い楽曲を得意とするこの作曲家は、「ジャイアンツ」「ナバロンの要塞」「アラモ」のような大作映画に引っ張りだことなり、ハワード・ホークスの西部劇などでも知られ(全て「見知らぬ乗客」より後の作品だが)、映画音楽史に名を轟かしている。今でいえばジョン・ウィリアムズの位置に近いような映画音楽の巨匠だった。
「見知らぬ乗客」でもダイナミックかつクラシカルな高級感のある音楽をつけ、作品を盛り上げている。だが、主張が強い割にメロディが残らないティオムキンの音楽(2000年代以降のウィリアムズも技巧にこりだしてメロディメーカーでなくなってしまった)を、恐らくヒッチコックはあまり気に入らなかったのではないだろうか?
といってもこの後の2作「私は告白する」と「ダイヤルMを回せ」もティオムキンと組んでいるから、そうでもないかもしれない。
名パートナーとなるバーナード・ハーマンとの邂逅は、まだ後のことである。
----
映画構成で興味深いのはクライマックスの壮絶アクションである。
暴走したメリー・ゴー・ラウンドの中で、主人公と殺人犯が壮絶な格闘をする。
「ヒッチコック映画術」でトリュフォーはこのクライマックスについて「正直、首を傾げたくなった」とムッシュ・ヒッチコックに堂々と苦言を呈していた。たしかに、それまでの一級サスペンスの香りはメリー・ゴー・ラウンドの超速回転の遠心力でぶっ飛ばされていくようだ。しかもアクション的にも、主人公が遠心力で吹っ飛ばされそうになったかと思えば、遠心力など関係ないねと駆け回ったりで、突っ込みどころが多い。
だが、クライマックスをここまで壮絶なアクションで飾ったヒッチコック映画は本作くらいではなかろうか。
「逃走迷路」の自由の女神像での対決、「北北西に進路を取れ」のラシュモア山での対決、「救命艇」でドイツのスパイをリンチにするクライマックス、「裏窓」の犯人との対決、「レベッカ」の屋敷が炎上するクライマックス、「バルカン超特急」のチェイスシーン・・・と物語の終結部をアクションやスペクタクルで締めくくった映画は沢山あるが、いずれも主人公と悪人の動きは少なく、カメラの動きも少なく、舞台設定と編集の緩急で盛り上げる、上品なアクションシーンであった。
しかしながら「見知らぬ乗客」のクライマックスは明らかに毛色が違う。ところどころにヒッチコック流のユーモア(メリー・ゴー・ラウンドの暴走で大はしゃぎする子供が主人公に加勢して悪人をポカポカたたく)、ヒッチコック流のテクニック(「メリー・ゴー・ラウンド上の主人公と悪人の対決」と「回転するメリー・ゴー・ラウンドの下の狭い隙間を這っていって暴走を止めようとする老人」とをパラレル編集する)が見られはするものの、このあまりに急激に壮絶アクションへ移行し強引に話を締めくくってしまう展開は、80年代以降のハリウッドアクションサスペンスの定番である。なんとなくロン・ハワードとかトニー・スコットとかがやりそうなクライマックスという印象。
とすると、ヒッチコックベストは「サイコ」だ「裏窓」だ「汚名」だ「めまい」だ・・・と、はやし立てておきながら、それらは継ごうとするものは誰も無く、ヒッチコック作品としてはそれほど完成度は高くなく知名度も低い「見知らぬ乗客」が、ハリウッドスタンダードとして選ばれていたことになるのかもしれない。
今でこそ知名度は低いが当時「見知らぬ乗客」は大ヒットしたらしい。「見知らぬ乗客」をスタンダードにして、「めまい」や「裏窓」を誰も撮ろうとしないのは、芸術より実利をとるハリウッドらしさの現れという気がする。
ハリウッドらしいがヒッチコックらしくないといえば、この映画はヒッチコックにしては珍しく二種類のラストシーンを撮っていたという(ハリウッドでは常識)。
何作か失敗が続いた後(「ロープ」→「山羊座のもとに」→「舞台恐怖症」→「見知らぬ乗客」)の作品だったので是が非でもヒットさせたかったのだろう。レイモンド・チャンドラーのような大物を担ぎ出したのも、大ヒットを最優先課題としていたからではなかろうかと思えてくるのだった。
-------
などと「やや否定的」なことばかり書いてきたが、そうはいってもヒッチコック。冒頭から結末に至るまで、いちいち面白い。
二人の靴のアップを交互に映して、それがこつんとぶつかりあって主人公と殺人者が顔をあわせるオープニングの素晴らしさは言わずもがな。
殺人者のキャラクターはヒッチコック作品の悪人ベスト3に入りそうなくらい印象的だ。
殺人者が主人公の妻を殺そうと、トンネルの中でボートで近づき妻の影と殺人者の影が重なると、カメラがトンネルの外に移り妻の悲鳴・・・と思ったら、男友達とふざけ合っている声だったりするじらしの上手さ。
主人公が殺人者の父を殺そうとしているかのように、屋敷に忍び込み、観客すべてに「ホントにいいのか?おい?」と思わせておきながら、階段の踊り場に番犬を登場させることで、今度は観客に「なんとか犬をやり過ごせ~」っとさっきまでとは真逆のドキドキ感を抱かせる展開とか、なんだってヒッチコックの映画はこんなに面白いんだろうと、その偉大さをあらためて思い知るのであった。
逃げた主人公を追う刑事がバッジをかざして車を停めて乗り込むと、お金持ちのマダムがいて「あの車を追っている」と言われたマダムが、好奇心と驚きの入り混じった顔をするところが大好きだ。
なんとなくイギリス流のユーモアだと思う。
********
↓面白かったらクリックしてね