永 :美井さん、いよいよ年末ですね。新年を迎える準備は整いましたか?
美井:ええ、ほぼ終えましたよ。ところで、なぜ大晦日というのでしょうね。
永 :晦日とは30日という意味で、かつて日本で陰暦が使われた頃は、ひと月の最終日
である30日を晦日(みそか)と言っていたようです。「晦」という字は三十路
(みそじ)のみそと同じで、30という意味があるんですよ。
1年のうち、12月の最終日を大晦日と言っていた名残ですが、太陽暦になってか
らは12月31日が大晦日ですね。
美井:なるほど。私たちの生活の中には年末恒例の習慣がいくつかあって、大掃除もそ
のひとつですね。
永 :そうそう、1年間にたまった埃や汚れをきれいに掃除して、清々しくなった家に
「年神さま」をお迎えするのですよ。ホコリを払うといえば、6月の終わりに「夏
越しの大祓い(おおはらい)」、年末に「年越しの大祓い」と呼ばれる風習があり
ますよね。私たちの祖先はこの大祓いで半年のあいだに身に付いてしまった邪気
を祓おうとしたのでしょうね。もしかしたら、半年ごとにエネルギーが衰えるこ
とを感じて、エネルギーの再生を願ったのかもしれませんね。
美井:なるほど。大晦日には年越しソバも欠かせませんよ。
永 :そうですね。ソバのように細く長く生きたいとの願いを込めて食べるのだとか、
いくつかの説がありますね。地域によってはソバではなくウドンを食べるとか。
そういえば、お雑煮の具や味付けも地域によって様々だと聞いています。餅の形
もね。
美井:もうひとつ、大晦日と言えば除夜の鐘ですね。大晦日の真夜中に、鐘を108回撞
くんですが、人間が持つ108つの煩悩を取り払うためだとか、これまた諸説あり
ますね。私は108回のうち、107回は大晦日のうちに撞いて、108回目は新年に
なる零時ちょうどに鳴らすのだとばかり思っていましたが、寺院によって異なる
ようです。
永 :年末には年賀状書きもありますね。明治5年の郵便配達制度と明治39年の年賀
郵便制度の開始、更に昭和24年のお年玉付き年賀ハガキの発売によって、年賀
状を交換し合う習慣は一気に日本全国へ広まりましたね。
最近は電子メールなどの普及で年賀ハガキの売り上げは減り続けているようで
す。もちろん私は年賀状派ですが。
美井:私も年賀状派です。12月25日までにちゃんと投函しましたよ。通信面はパソコン
で作成して、プリンターで印刷しましたが、宛名はひとりひとりのお顔を脳裏に
浮かべながら、手書きしました。私たちの世代は今日、話に出てきたような行事
を全て行わないと、何となく一年が収まらない気分ですね。
永 :同感です。それでは良いお年をお迎えください。
美井:ハハハ、そのセリフも年末の定番ですね。
永 :ホントだ。では、来年もよろしくお願いします。良いお年を!
美井:ええ、ほぼ終えましたよ。ところで、なぜ大晦日というのでしょうね。
永 :晦日とは30日という意味で、かつて日本で陰暦が使われた頃は、ひと月の最終日
である30日を晦日(みそか)と言っていたようです。「晦」という字は三十路
(みそじ)のみそと同じで、30という意味があるんですよ。
1年のうち、12月の最終日を大晦日と言っていた名残ですが、太陽暦になってか
らは12月31日が大晦日ですね。
美井:なるほど。私たちの生活の中には年末恒例の習慣がいくつかあって、大掃除もそ
のひとつですね。
永 :そうそう、1年間にたまった埃や汚れをきれいに掃除して、清々しくなった家に
「年神さま」をお迎えするのですよ。ホコリを払うといえば、6月の終わりに「夏
越しの大祓い(おおはらい)」、年末に「年越しの大祓い」と呼ばれる風習があり
ますよね。私たちの祖先はこの大祓いで半年のあいだに身に付いてしまった邪気
を祓おうとしたのでしょうね。もしかしたら、半年ごとにエネルギーが衰えるこ
とを感じて、エネルギーの再生を願ったのかもしれませんね。
美井:なるほど。大晦日には年越しソバも欠かせませんよ。
永 :そうですね。ソバのように細く長く生きたいとの願いを込めて食べるのだとか、
いくつかの説がありますね。地域によってはソバではなくウドンを食べるとか。
そういえば、お雑煮の具や味付けも地域によって様々だと聞いています。餅の形
もね。
美井:もうひとつ、大晦日と言えば除夜の鐘ですね。大晦日の真夜中に、鐘を108回撞
くんですが、人間が持つ108つの煩悩を取り払うためだとか、これまた諸説あり
ますね。私は108回のうち、107回は大晦日のうちに撞いて、108回目は新年に
なる零時ちょうどに鳴らすのだとばかり思っていましたが、寺院によって異なる
ようです。
永 :年末には年賀状書きもありますね。明治5年の郵便配達制度と明治39年の年賀
郵便制度の開始、更に昭和24年のお年玉付き年賀ハガキの発売によって、年賀
状を交換し合う習慣は一気に日本全国へ広まりましたね。
最近は電子メールなどの普及で年賀ハガキの売り上げは減り続けているようで
す。もちろん私は年賀状派ですが。
美井:私も年賀状派です。12月25日までにちゃんと投函しましたよ。通信面はパソコン
で作成して、プリンターで印刷しましたが、宛名はひとりひとりのお顔を脳裏に
浮かべながら、手書きしました。私たちの世代は今日、話に出てきたような行事
を全て行わないと、何となく一年が収まらない気分ですね。
永 :同感です。それでは良いお年をお迎えください。
美井:ハハハ、そのセリフも年末の定番ですね。
永 :ホントだ。では、来年もよろしくお願いします。良いお年を!











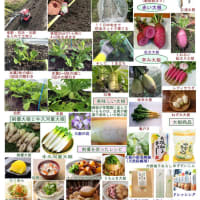

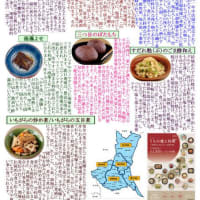
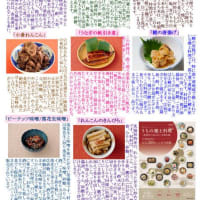

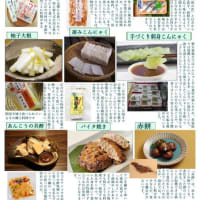


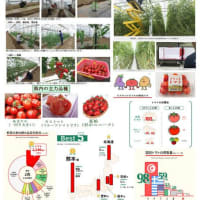
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます