けさ撮ったばかりの六葉の写真です!
わが家の庭にやっと開花したあじさいの古種「城ヶ島の雨」。
本来の花の色は青紫。最近はアルカリの土壌で栽培してピンク色も出回っているようですが、これは邪道。
もともと静岡県の城ヶ島で発見された自生種です。
誰がつけたか知りませんが『城ヶ島の雨」とはステキな銘ですよね。
雨に咲く花 雨に映える花、
まあ…ごゆっくりとご覧ください。






2017 06 17 午前 6時 撮影
けさ撮ったばかりの六葉の写真です!
わが家の庭にやっと開花したあじさいの古種「城ヶ島の雨」。
本来の花の色は青紫。最近はアルカリの土壌で栽培してピンク色も出回っているようですが、これは邪道。
もともと静岡県の城ヶ島で発見された自生種です。
誰がつけたか知りませんが『城ヶ島の雨」とはステキな銘ですよね。
雨に咲く花 雨に映える花、
まあ…ごゆっくりとご覧ください。






2017 06 17 午前 6時 撮影

ブラジルの奥地を旅行すれば必ず蟻の山が見える
この演劇のタイトルになっている『白蟻の巣』とは一体何を意味しているのであろうか。
まず、上掲の画像を見ていただきたい。
そもそも白蟻といっても日本のものとは種類がまったく違う蟻で、大地に土と自らの排泄物によって、ときには人の背丈ほどの巨大な蟻
塚を築くのである。
一つの蟻塚には数百万の蟻がおり、その蟻が居を移し空になった塚には二度と戻ることはないという。

『白蟻の巣』の初版本
わたしは若いころから「戯曲」を読むのが好きで、あるとき本屋さんで手にしたのが三島由紀夫の『白蟻の巣』という単行本だ。高校生の
ころだった。
奥付をみると、昭和31年1月25日発行の版元は新潮社で、定価220円とある。
もちろん、むさぼるように読み耽った。そしてこの戯曲の上演を待ち望んでいた。強い感銘を受けたからだ。
のちに青年座が『白蟻の巣』を1955年に初演したことを知った。

長い間、再演を待っていたが、やっと今年になって、34歳の新鋭演出家谷賢一で、しかも日本の現在演劇の本丸といわれる新国立
劇場でこの戯曲が上演される。
青年座の上演以来、じつに62年ぶりの上演である。
地元の兵庫県芸術文化ホールでも巡演されるらしいが、やはり、あの呼吸感まで伝わる新国立劇場で観たいと、わたしの心は躍った。

ブラジルのコーヒー農園を舞台に、元華族の農園主・刈谷義郎(平田満)と妻妙子 (安蘭けい)、同じ屋敷に住む運転手の百鳥健次
(石田佳史)と妻啓子(村山絵梨)の物語である。
妙子と健次はかつて心中末遂を起こしたが、主人刈谷の"寛大さ”で、二人を許し、同居させていた。
刈谷の”寛大さ”が、逆にじわじわと皆を絡めとり、真綿でくるんだように締めつけてゆく。
平たくいえば、三島好みの”不倫”のおはなし。




(上段・安蘭けい 下段・平田満 村川絵梨 石田征史)
「寛容な主人」の苅屋が逆に見えない檻 を作り、奇妙な崩れそうなバランスを保っている。そんな難役を平田満がことさら力まず
懸命に好演。無気力、無関心な刈谷の役作りをしている。
対する妻妙子を演じる安蘭けいは、高貴で美しいが、一見、生ける屍と三島戯曲にあるが、「生ける屍」の下に熱いマグマと情熱を感
じさせたのはさすが。
とはいえ、長セリフになると、宝塚調が見え隠れするのは是非もないが、夫への不満から、いろんな過ちを犯し、挙げ句にお抱え運転手
と心中未遂をするような女性には見えてこない。
百島健次の石田征史は、つか劇団を皮切りに蜷川の舞台に数多く立っているベテランだが、妙子が夢中になるだけの説得力がない
のがいちばんの欠点。

ブラジル生まれの運転手夫婦。生まれ出る新しい血を演じる妙子(村川絵梨)は、感情が一気に溢れ出す終幕は圧巻。
ブラジルの強烈な太陽が昇ってくるあたりから、台詞のテンポが昂ってくる、計算された演技に感心した。
難を云えば、三島独特のレトリッツクがいささか会得されてないためか、啓子という人物像があまり伝わってこない。
「『日本に帰りたいと云っていたのに』と葬式で言われたい」という雇用人・大杉(半海一晃)が、本作品いちばんの出来。
三島がおおよそイメージしたであろう大杉になっていた。芝居に「ウソ」を感じさせないところがよい。
意表をついたのは土岐研一の舞台美術。
舞台奥の紗幕と、ベット、食卓などの家具だけのシンプルなもの。
紗幕が劇の進行によって血を流したように真っ赤になったり、ブラジルの照りつける太陽光線に変化する。
ひりひりと焼きつくような見苦しい空気の中、ブラジル農園の表現が、照明や音響でそれなりに効果をあげていた。
芸術監督である宮田慶子さんが、三島由紀夫の戯曲は、「最後のセリフのためにあるような気がする」と語った。
これはまさしく「正論」だとわたしも同感である。
のちの三島の大作『サド侯爵夫人』、『鹿鳴館』、そして『黒蜥蜴』も鋭く磨かれ、凝縮された台詞で幕になる.
この『白蟻の巣』では
刈屋 :(呟くごとく) ………とてもそんなことが……
これは「許し」に関わることであり、そこには「決められない日本」「他者依存」など、いまの日本人として受け止めなければならない
"三島からのメッセージ”が込められているような思いがしてならない。
(2017・3・16 新国立劇場 小劇場で所見)


画像 上段左より 風間杜夫 大倉孝二 早乙女太一 広瀬アリス 青木さやか
下段左より 和田正人 福田転球 赤堀雅秋 梅沢昌代 鈴木砂羽
誰が云ったか知らないが、今いちばん油がのっている赤堀雅秋の芝居のことを「赤堀ワールド」という。
赤堀は劇作家、演出家、俳優、そして映画監督として、暗く澱んだ人間の深淵を見据えながら、どちらかというとシニカルなユーモア
をまじえた作品が多く、独自の世界を築き上げる。
今回の『世界』について、赤堀は「原点に立ち帰り”市井の人々とその暮らしを描くことだ”」。そんな新たな心境のもとに取り組んだコク
―ン第3弾だ。
繊細で丁寧な人間描写、陰影のあるキャラクター、そして溢れだす生々しい人間関係…。
赤堀が描き出す”やるせない喜劇”を観ていて本来なら笑うはずだが、笑えない自分がいることに気ずく。
ともあれ3弾目にして「赤堀ワールド」の真骨頂をみせる舞台に仕上がった。

ストーリーらしいストーリーはない。
どこにでもありそうな、地方都市で小さな工場を営む家族を中心に描き出される、街、安アパート、それに寂れたカラオケスナック、そし
て家族…。
逃れられない”普通の人々”のミニマムな人間関係、様々な波紋が広がるなかで、日々の営みが続いて行く…
けれど彼らの日常は、細い糸で結び合い絡まっていくのである。
『世界』は、自身の回り3メートルほどのの世界でもある。何気ない日常の風景を描きながら、気がつけば結構な毒気をはらんだ言葉と思
いが錯綜しているのに気づくのは私だけか。

『世界』には事件が起こらない。だから加害者も被害者もいない。
あがく人、また状況を変えようとする人がいるが、いずれも不発、末遂に終わる。
この芝居には、どことなく”空気感”というか”呼吸感”がある。そこがまた面白い。いままでの赤堀作品なら、ひとりの人間の内面に、
ピンポイントにとらえることに執心していたけれど、今回は俯瞰の位置から人間なり人生を捉えようとした。
つまり「距離感」である。その距離感が作品に厚味ができ、成果をあげたのだと思う。

風間杜夫が赤堀作品に初参加をはじめ、常連組の大倉孝二、鈴木砂羽などベテラン勢が顔をそろえているが、特に印象深かった2人
がいる。
まず、和田正人演じる諸星というバイトさんが切ない。年下にバカにされ、年寄リに罵倒される気の毒な役だが、諸星の抱える孤独
、焦燥感をみごとに表現した。、
特に、故郷の親元から送ってきた蜜柑箱に入っていた茶封筒の手紙の中に、1万円札がカオをみせたのには、ホロッとした。
もう1人は、足立家の息子の嫁を演じる青木さやか。口うるさい老夫婦(風間杜夫、梅沢昌代)の世話から、家事、おまけに近くのコンビ
ニのパートと忙しい。そのコンビニで義父が万引きをする。同じ夜のこと、万引きのことを口にせず、ことさら明るく振る舞い、ラストにい
たたまれず後ろ向きになって肩だけをふるわすシーンは印象にのこった。

回り舞台に4つのセット。
むきだしの換気扇のある足立家の台所をメインに、ありがちな町工場、ありきたりなスナック、どこにでもあるコンビニの事務室。風呂も
便所もない安アパート。登場するのは”普通”を煮詰めた人々。舞台上半分を真横に陸橋が貫く。
新国立劇場で上演された『負傷者16人』の土岐研一の美術。リフォーム寸前のセットをこさえるのは大変な仕事だと察するに余りある。
(2017・2・4 森ノ宮ピロティホールにて所見)

2004年の初演から12年。
初演は岩松 了が蜷川幸雄さんのために書き下ろした戯曲である。
物語の鍵を握る青年、ナオヤ役を、初演では嵐の二宮和也が演じたが、今回は『書を捨て街に出よう』で話題を呼んだ村上虹郎がナオ
ヤ役に挑戦。不思議な女マリー役には初演と同じく小泉今日子が続投する。



私、成長してない? そう見える…成長をとめなきゃ。
現実と虚構の狭間を生きる、孤独な人たち。観客の心を揺さぶるミステリアスなストリー。
廃墟になった家に思いを残す青年と、蝕まれはじめたわが身をもてあます女の現前化しない「愛」の物語でもある。
村上虹郎のナオヤは、子供でもなく、大人にもなりきれず、重い過去を抱えつつ揺れる、危うく、脆い感じをストレートに演じた。
ただ発声に難があり、聞き取りにくい台詞も多い。
小泉今日子は、マリーという退廃的な役柄。ナオヤに対する想い、アオヤギに対する想い。あれこれ考えるが、まとまらず。
この妖精的なというか、魔性のおんなというか、ミステリアスな女に存在感があり、ゾッとするようなエロを匂わせたのはさすが。
トシミ役の南乃彩希は平凡。可もなし不可もなし。ケンイチの鈴木勝大は役が持つメッセージに誠実に向き合っている。
橋本じゅん、豊原功補らのベテラン陣がワキを固めた。岩松 了はセリフ無しのご馳走役。





『シブヤ~』は、蜷川幸雄さんが「こんなのどう?」と、岩松了さんに見せた『チェルノブイリの写真集』だった。そもそもその一冊の写真
集が『シブヤ~』の発端である。
蜷川さんのアタマの中に何らかの構想があったのではないか。
初演は半ば廃墟化している邸宅に、それを取り囲むように黑いヒマワリが咲いていたそうだ。
さらに言えば、この作品はヴェルディのオペラ『椿姫』が下敷きになっており、暗い記憶の狭間を浮遊する青年と、すべてから逃れよ
うとする不思議な女マリーの静かではあるが、力強い愛が描かれている。
12年前とはまた別の命をもって生まれたんじゃない、と再演した演出家はいう。
たしかに、難解といえば難解だが、この芝居から、時間とはなにか、人間が成長するとはどういうことか、廃墟のアパートの内部をみ
せないように、なんだかよくわからないが、観客にそんな質問を投げかけているように思えてならない。
皆さん良いお年をお迎えください。


900回をこえる、昭和の傑作喜劇『三婆』が、よみがえった。
しかも今回は、大竹しのぶ、渡辺えり、キムラ緑子という芸達者な3女優が顔を揃え、いずれも初役だ。
ことさら”喜劇”と銘打たなくても、まさしく「現代のブラック・ユーモア」とでもいおうか、その喜劇性は、現代社会の仕組みなり、世相
風俗そのものが内包しているタチのもので、上演を重ねるごとに、舞台自体も成長つづけたということだ。
世に謂う”喜劇”と銘打ったものに碌なものはない。
昭和の喜劇黄金期に東宝の菊田一夫作『雲の上団五郎一座』は、圧倒的に面白かったが、それから、なりをひそめている。
いまでは、この領域で三宅裕司が『熱海五郎一座』と一人気を吐いているが、しょせんコントに毛が生えたもの。

もともと、この『三婆』は喜劇ではなかった。
1961年2月号の『新潮』に載った有吉佐和子の70枚ばかしの短編である。
高齢化時代を先取りした社会性をそなえておリ、3人の老女の孤独を生み出す心理をえぐった、どちらかといえばシリアスな小
説であった。

( 初演の舞台 日比谷・芸術座 )
小幡欣治はこれを、『脚色」でなく、「劇化」した。それが予想をこえる大当たりとなったのである。
初演はヒビヤ芸術座で、本妻松子は新派の市川翆扇、駒代は一の宮あつ子、タキは民芸の北林谷栄、重助は有島一郎の布
陣。演出は小幡欣治だった。
本妻松子だけでも、赤木春恵、正司歌江、池内淳子、波乃久里子、水谷八重子が演じてている。
中でも池内淳子の松子が決定版とされ、定評があったという。

ストーリーは、金融業者の社長が、妾宅で急死したところからはじまる。
お相手の妾・駒代(キムラ緑子)があたふたしている所へ本妻の松子(大竹しのぶ)、社長の妹タキ(渡辺えり)が駆けつける。
すったもんだの末、行き場のない駒代とタキが本宅に居候と決め込んだため、てんやわんやの大騒ぎ。
おまけに社長の専務をしていた重助(段田安則)までがころがりこんで、三婆と元専務の奇妙な「共同生活」がはじまるのだ
が…

本妻・松子の大竹しのぶが新橋演舞場に出演するのは、30年ぶりとか。
今回は全幕、和装で通すという新境地を見せる。動きにエネルギシュな破調をにじませながら、軸足をしっかり保っているの
は、さすがである。
この奇妙な「共同生活」にイヤ気がさし、追い出すところのコミカルさ。追い出しに成功した後、”孤独”のしじまを深々と見せる
芝居運びのうまさ。
老け役になっても、沈み込まない、明るく、前向きな面があるのは、大竹しのぶしかできない独特の強みだ。
余談だが、第一幕の幕切れは、初演の市川翠扇が演じた松子が絶品だったそうだ。
演劇評論家の矢野誠一さんは「ひと言の台詞も口にしない妖気漂うがごときお芝居には、圧倒された」と『小旙欣治の歳月』で
評している。


お妾さん役のキムラ緑子はどちらかというと淡路出身の関西の女優さん。
コミカルな芝居から、シュールな海外戯曲、シリアスなウエルメイドプレイまで、説得力を持たせる女優さんだ。
平成5年のNHKの朝ドラ『ごちそうさん』でヒロインの小姑役で人気が急上昇した。
看板にある日本髪こそ舞台ではみせないが、和装もしっくりと板についている。あっけらかんとしたところが、この人の持ち味。
本家に上がり込む厚かましさに、関西人らしいねちっこいねばりがほしい。
それと、旦那に出してもらってお店をやっている、もと水商売風の匂いが希薄。
本妻になんとか気に入られようとする一生懸命さが、哀しくもあり可愛らしくもある流れが、実にうまい。


「電気クラゲ」とアダ名のある、小姑のタキ役の渡辺えりは、少女趣味なのかオモロイ衣装で登場する(上段・画像)。
登場しただけで、ワッと客席から爆笑の渦。
女宇野重吉といいたいような、いつもながらのこの人のぶっきらぼうな物言いが、不思議に異彩を放ち、舞台に立っているだ
けで存在感がある。
それでいて、出過ぎず退かず、ぎりぎりまで踏みとどまっているところが、この人ならではの演技の伎倆 なのだ。
渡辺えりは劇作家でもある。
「喜劇と悲劇は紙一重なの、今回のホン(台本のこと)は、その部分が色濃く出ていて、やればやるほど滑稽で残酷。
今の社会問題が笑ちゃうううちに浮き上がってくる芝居なのよ。この「三婆」は…」
老いてゆく女の淋しさを見据えた劇作家らしいまなざしがあった。

さて、このへんで本妻松子の亡夫金融業者に永年つかえていた専務重助(段田安則)について語っておきたい。
有吉佐和子の原作には、重助なる人物は登場しない。劇化した小幡欣治が新たにつくりだした役である。
重助は、老婆3人の潤滑油であり、この人がいればこそ3人の姿が明確になる。いわば反射板の役目を担っている。
初演の有島一郎いらい曾我廼家明蝶、金子信雄、いかりや長介、菅野菜保之、鶴田忍、最近になって 佐藤B作、笹野高史がつとめてい
る。こうしてみると、いずれも個性派俳優ばかりである。
今回の段田安則は受けの芝居が舞台のおさえにななって好演。この人のユーモラスな面が、重助役にうまくハマっている。
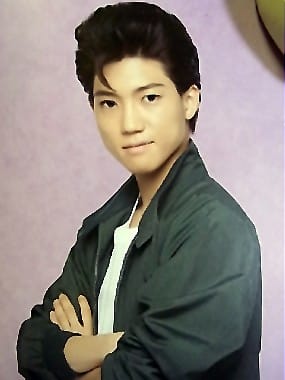

昭和の八百屋の店員役だと云われてもピンと来ないという、今回抜擢されたジャニーズの安井謙太郎。初舞台は、平成18年「滝沢歌
舞伎」で南郷力丸に扮した。
八百屋の御用聞きというのがあったのは、昭和のまっただ中であった。
大事なことは、八百屋にせよ豆腐屋にしても当時は地域とのつながりがあった。平成のいま、それがどうなのか考えさせられる舞台
でもあった。
20代の若者に、昭和の匂いを出せというのは是非もないが、ジェームス・ディーンに憧れ、当時流行したリーゼントにして、カッコつけた
がる若者を、平成の若者が素直に演じたのは、うれしい。

舞台中央に小体な庭を作り、回り舞台を生かした松井るみの美術は、見事だった。
商業演劇の美術はおそらく初めてだと思うが、初演からの新派風で旧弊な装置を排し、今様の舞台美術をつくりあげた。
幕開きの、神楽坂の妾宅の応接室を見て、ワタシは目を見張った。
障子にうつる笹竹の影。駒代の芸者時代のあでやかな日本髪姿の屏風。旦那のゴルフの数々のトロフィー。
これはまさしく神楽坂だと、ひと目でわかる。松井るみの仕事の中でも、屈指のものだった。
(2016.11.17 東銀座・新橋演舞場で所見)