幕末史において、津藤堂家の戊辰戦争における『裏切り』が幕府の敗北を決定付けた、という表現がよく見られる。その行為に関しては、『幕府軍が不利とみるやいなや転向した』とか『高虎以来寝返りの家風であるから』などというのが一般の風評だ。
しかし、これは単眼的な偏った見方で誤解である。
幕末は結局、薩長と幕府の政権交代の戦いでしかなかった。そこに攘夷だとか、尊王だとか、もっともらしい理由をつけてはいるが、早い話、現在の政権争いとまったく変わらない。攘夷やら尊王というのは、彼らにとっては思想というよりも政策であった。
多くの藩が勝ち組につきたいのは人情である。だが、雄藩、幕府どちらが勝つのか分からない。
戊辰戦争の時期はまさにそういった混沌とした時であり、どの藩も、どちらに就くのか鮮明にしていない。
津藩はその最たるものであったかも知れない。
津は、外様ではあったが、準譜代の扱いを受けており佐幕であったが、長州征伐の頃から局外中立に転じている。
一応ニュートラルなポジションを置いていたわけで、すぐに倒幕に傾いたわけではない。
もともと、津は勤皇思想の強い土地であり、しかも、開明派も多かった。
公武合体はこの藩のもっとも望むところであったが、攘夷は本心ではなかった。
山崎奉勅と言われ、幕府軍に砲撃を加えた津藩ではあるが、この時、藩主の高猷の指示は、「砲門は開くな」との厳命であった。
これには伏線がある。
当時、砲門を指揮していたのは藤堂采女と吉村長兵衛であった。
この両名のところには、幕府、薩軍双方から、味方になるようにと使者が来た。
幕府の使者としてやってきたのは、滝川播磨守であった。
この人選は、まったくの誤りであった。
天誅組の際、津藩も制圧に当たっていて、采女、長兵衛の両名も出動している。その際に総指揮をとったのが滝川であった。
津は勤皇思想の強い土地柄で、天誅組にも同情し、捕らえた後も厚遇している。幕府に渡す際も、寛大な処置を依頼している。それなのに、滝川は津藩の意向をまったく無視、全員を極刑に処している。
ただでさえ、滝川憎しの感情のあるところに加え、孤立する砲台に幕府軍を少人数でも送りこんでくれれば、旗色も鮮明にできると申し出たのに、幕府軍は一人もやってこない。多分、滝川はその場では、いい返事をする人間だったのであろう。
天誅組の時も、砲門の時も、返事はいいが、実行が伴わなかったため、反感は大きくなる。
そうこうしているうちに、薩軍が錦の御旗を持ち、再度接触してきたので、采女、長兵衛もそれ以上は、要請を拒めなかった。
この時、両名は高猷の許可を得ておらず、切腹の覚悟だったという。
これはかなり苦渋の判断であったわけだが、現場を預かる指揮官としては、ぎりぎりの選択であったのだろう。
↓よろしかったら、クリックをお願いします。

しかし、これは単眼的な偏った見方で誤解である。
幕末は結局、薩長と幕府の政権交代の戦いでしかなかった。そこに攘夷だとか、尊王だとか、もっともらしい理由をつけてはいるが、早い話、現在の政権争いとまったく変わらない。攘夷やら尊王というのは、彼らにとっては思想というよりも政策であった。
多くの藩が勝ち組につきたいのは人情である。だが、雄藩、幕府どちらが勝つのか分からない。
戊辰戦争の時期はまさにそういった混沌とした時であり、どの藩も、どちらに就くのか鮮明にしていない。
津藩はその最たるものであったかも知れない。
津は、外様ではあったが、準譜代の扱いを受けており佐幕であったが、長州征伐の頃から局外中立に転じている。
一応ニュートラルなポジションを置いていたわけで、すぐに倒幕に傾いたわけではない。
もともと、津は勤皇思想の強い土地であり、しかも、開明派も多かった。
公武合体はこの藩のもっとも望むところであったが、攘夷は本心ではなかった。
山崎奉勅と言われ、幕府軍に砲撃を加えた津藩ではあるが、この時、藩主の高猷の指示は、「砲門は開くな」との厳命であった。
これには伏線がある。
当時、砲門を指揮していたのは藤堂采女と吉村長兵衛であった。
この両名のところには、幕府、薩軍双方から、味方になるようにと使者が来た。
幕府の使者としてやってきたのは、滝川播磨守であった。
この人選は、まったくの誤りであった。
天誅組の際、津藩も制圧に当たっていて、采女、長兵衛の両名も出動している。その際に総指揮をとったのが滝川であった。
津は勤皇思想の強い土地柄で、天誅組にも同情し、捕らえた後も厚遇している。幕府に渡す際も、寛大な処置を依頼している。それなのに、滝川は津藩の意向をまったく無視、全員を極刑に処している。
ただでさえ、滝川憎しの感情のあるところに加え、孤立する砲台に幕府軍を少人数でも送りこんでくれれば、旗色も鮮明にできると申し出たのに、幕府軍は一人もやってこない。多分、滝川はその場では、いい返事をする人間だったのであろう。
天誅組の時も、砲門の時も、返事はいいが、実行が伴わなかったため、反感は大きくなる。
そうこうしているうちに、薩軍が錦の御旗を持ち、再度接触してきたので、采女、長兵衛もそれ以上は、要請を拒めなかった。
この時、両名は高猷の許可を得ておらず、切腹の覚悟だったという。
これはかなり苦渋の判断であったわけだが、現場を預かる指揮官としては、ぎりぎりの選択であったのだろう。
↓よろしかったら、クリックをお願いします。










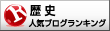
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます