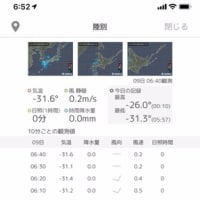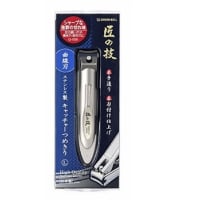水を無駄遣いするな!と聞くと、水道水のことだけを想像しがちですが、輸入牛肉や農産物を大量に消費する事と、衣類を大量に買い続け消費し廃棄する事が、どれほどめちゃくちゃにエネルギーを浪費し続けているか、なかなか実感できないですよね。
以下、丹保 憲仁 北大名誉教授の講演録からの抜粋です。
インドも、中国の一部もまだ草を食っているが、中国の東側は豚を食っており、これが牛の方がうまいと食いだしたら大変なことになる。どれくらい大変なのか。米1kg作るのに3tの水がいる。牛肉100gを作るのに平均すると15tの水がいる(草だけ食わしている牛<飼料を食わしている牛)。世界では水が少なくなってきている中で、和牛は安全だが、これを食うのは最大の犯罪行為である。
(中略)
世界中の水は大半の97.3%が海にあるわけで、淡水は残りの2.7%しかなく、その内使えるのは河川などの0.01%程しかない。しかも10日に1度の割合で蒸発して雨として降ってくる。
使われている水の量は、農業用水、産業用水、都市用水とあるが、農業用水以外の水は、人間が直接使う物は別としていくらでも置き換えられる。例えば、下水道がなくても死ぬ人はいない。ところが農業はアルコールや石油があっても、水がなければだめ。従って最後の最後までキープしなければならないのは、農業用水ということになる。日本は、徳川時代からの慣行農業水利権を未だに維持している。この状況下で農業構造改善をいろいろとやってはいるが、最新の科学を取り入れた農業は全くやっていない。本当の意味での構造改善、例えば農薬を使わなくても済むようなことはやっていない。農学の世界でも工学の世界でもやらなければならないことはたくさんある。
世界で水が少ないところはどこか。アラビア半島、エジプトなど1人当たりの水賦存量が1000t/年以下である地域を渇水地帯といっている。実は日本でも関東平野が渇水地帯である。これは、水は来るものの、滅茶苦茶に水を使用している結果。こういう状況が起こっているから、群馬県にダムを造らないともたない、ということになる。関西も水の大消費地であるが琵琶湖のおかげでまだましな状況であり、ダム不要論も成立するが関東では成立しない。関東でダム不要論を言う奴はクレイジー。ダムが要らないというならば、便所で水を流すな!と言ってやれば良い。安全な水を使うためにダムを造る造らないという議論はあるが、じゃあウンコはどうするのか、というような原点に返った議論はされていない。これは近代文明という肩書社会とヨーロッパで始まった習慣の延長線上にある問題だ。これを切り替えないと我々は次へ行けない。
(抜粋終わり)
どうですか?みなさんすでにご存知の部分もあるでしょうが、そろそろ我々日本人は欲望にまかせた大量消費をやめ、「モノを大量に買って廃棄しない、食べ物は近くのものを少しづつ食べる」習慣を付けなくてはいけない時代にすでに突入しています。そういう私もなかなか「欲を押さえる」のは容易ではなく、欲と戦って何とか踏ん張っている感じです。
服を大量に買う事がなぜ行けないのか。衣類のメイン素材である綿花はものすごい量の水を消費する上、その土壌も相当痩せてしまう植物です。飲み水がどれほど限られているかは、上の抜粋の通り。泥水をすすって生きている人がいる中、我々は服を買いまくっているんですね。着るものはいいものを長く着る。これにつきます。
以前、私の本家HPで書きましたが、水洗トイレから水を使わないバイオトイレの普及も考えなくてはならないでしょう。
これまでの大量消費生活をやめ(生活レベルを下げるということ)、質素な暮らしの中にも満足を得る方法を我々先進国の者が率先して実行しなくてはならない時代だと思います。
以下、丹保 憲仁 北大名誉教授の講演録からの抜粋です。
インドも、中国の一部もまだ草を食っているが、中国の東側は豚を食っており、これが牛の方がうまいと食いだしたら大変なことになる。どれくらい大変なのか。米1kg作るのに3tの水がいる。牛肉100gを作るのに平均すると15tの水がいる(草だけ食わしている牛<飼料を食わしている牛)。世界では水が少なくなってきている中で、和牛は安全だが、これを食うのは最大の犯罪行為である。
(中略)
世界中の水は大半の97.3%が海にあるわけで、淡水は残りの2.7%しかなく、その内使えるのは河川などの0.01%程しかない。しかも10日に1度の割合で蒸発して雨として降ってくる。
使われている水の量は、農業用水、産業用水、都市用水とあるが、農業用水以外の水は、人間が直接使う物は別としていくらでも置き換えられる。例えば、下水道がなくても死ぬ人はいない。ところが農業はアルコールや石油があっても、水がなければだめ。従って最後の最後までキープしなければならないのは、農業用水ということになる。日本は、徳川時代からの慣行農業水利権を未だに維持している。この状況下で農業構造改善をいろいろとやってはいるが、最新の科学を取り入れた農業は全くやっていない。本当の意味での構造改善、例えば農薬を使わなくても済むようなことはやっていない。農学の世界でも工学の世界でもやらなければならないことはたくさんある。
世界で水が少ないところはどこか。アラビア半島、エジプトなど1人当たりの水賦存量が1000t/年以下である地域を渇水地帯といっている。実は日本でも関東平野が渇水地帯である。これは、水は来るものの、滅茶苦茶に水を使用している結果。こういう状況が起こっているから、群馬県にダムを造らないともたない、ということになる。関西も水の大消費地であるが琵琶湖のおかげでまだましな状況であり、ダム不要論も成立するが関東では成立しない。関東でダム不要論を言う奴はクレイジー。ダムが要らないというならば、便所で水を流すな!と言ってやれば良い。安全な水を使うためにダムを造る造らないという議論はあるが、じゃあウンコはどうするのか、というような原点に返った議論はされていない。これは近代文明という肩書社会とヨーロッパで始まった習慣の延長線上にある問題だ。これを切り替えないと我々は次へ行けない。
(抜粋終わり)
どうですか?みなさんすでにご存知の部分もあるでしょうが、そろそろ我々日本人は欲望にまかせた大量消費をやめ、「モノを大量に買って廃棄しない、食べ物は近くのものを少しづつ食べる」習慣を付けなくてはいけない時代にすでに突入しています。そういう私もなかなか「欲を押さえる」のは容易ではなく、欲と戦って何とか踏ん張っている感じです。
服を大量に買う事がなぜ行けないのか。衣類のメイン素材である綿花はものすごい量の水を消費する上、その土壌も相当痩せてしまう植物です。飲み水がどれほど限られているかは、上の抜粋の通り。泥水をすすって生きている人がいる中、我々は服を買いまくっているんですね。着るものはいいものを長く着る。これにつきます。
以前、私の本家HPで書きましたが、水洗トイレから水を使わないバイオトイレの普及も考えなくてはならないでしょう。
これまでの大量消費生活をやめ(生活レベルを下げるということ)、質素な暮らしの中にも満足を得る方法を我々先進国の者が率先して実行しなくてはならない時代だと思います。