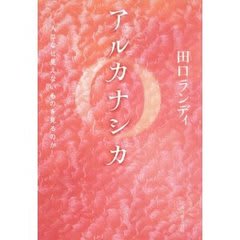
田口ランディさんの「アルカナシカ 人はなぜ見えないものを見るのか」(角川学芸出版)を読んだ。
すごく面白かった・・・。衝撃だった。鳥肌たった。
少し前に出た「マアジナル」(→『田口ランディ「マアジナル」』(2011-06-19))をフィクションだとすると、「アルカナシカ」は便宜的にノンフィクションとされている。
ただ、このフィクション、ノンフィクションというわけ目自体に、すでに仕掛けがあるような気がした。
フィクション世界はノンフィクション世界を侵食しているし、ノンフィクション世界はフィクション世界へと侵食しているようで。
ふたつは一つのはっきりした境界線で仕切られるものではなくて、紙の表と裏のようなものだ。その境界(マージナル)、分けようとする線引きの行為そのものに、何か大事なことが隠れているのだろう。
この現実世界もおなじようなものだ。
どこまでが自分の脳の神経細胞が作り出した電気的な発光現象の産物のフィクションなのか、それともあるがままのノンフィクションなのか、そう容易く線引きできないものだ。
===============
<内容紹介>(Amazonより)
人はなぜ、不思議な現象を怖れ、憧れ、求めるのか?
偶然に導かれるように出会った、UFO遭遇者、超能力者、霊能力者――。
体験者たちの圧倒的な現実から人間の意識と精神の根源に迫る、渾身のノンフィクション!
===============
■小林秀雄「信ずることと知ること」
この「アルカナシカ」にも一部引用されている、小林秀雄の「信ずることと知ること」という講演がある。
この文章が収録された小林秀雄「人生について」(新潮文庫)という本。
この本はとても好きだ。見返すと、赤線引きまくり、付箋もはりまくられている。
自分の心深くにひっかかるものがたくさんあった。
ちなみに、「信ずることと知ること」というタイトルには、<信ずることと知ることは一体のものであって分けることができないものだ。ふたつでひとつなのだ>という考えが込められていると、小林秀雄本人が語っている。

まず、ユリ・ゲラーのスプーン曲げに関する記述がある。
----------------------------------
小林秀雄「信ずることと知ること」
『今度のユリ・ゲラーの実験にしても、これを扱う新聞や雑誌を見ていますと、不思議を不思議と受け取る素直な心が、何と少ないかに驚く。
テレビで不思議を見せられると、これに対して嘲笑的態度をとるか、スポーツでも見て面白がるのと同じ態度をとるか、どちらかでしょう。
・・・・・・
今日の知識人にとって、己の頭脳によって理解できない声は、みんな調子が外れているのです。
その点で、彼らは根底的な反省を書いている、と言っていいでしょう。』
----------------------------------
そして、ある女性の夫が戦争で死んだとき、その戦場で夫が殺された生々しい幻をまったく同じ時間に違う場所で見たという話しが出てくる。<精神感応>の例として。
そのことに対する知識人の発言で「幻の中にも、結果的に正しかった幻と、結果的に正しくなかった幻を見ているのでしょう。前者の方が印象深いので単にそのことだけを覚えているだけでしょう。精神感応とか念力とか、そういう未知の力による現象ではなくて単なる偶然でしょう。」というような発言が紹介されていて、その態度を小林秀雄は批判する。
----------------------------------
小林秀雄「信ずることと知ること」
『その夫人はそういう問題(=夫人が夢を見た時に確かに夫は死んだのか、生きていたかという問題)を話したのではなく、自分の経験を話したのです。
夢は余りにもなまなましい光景であったから、それをそのまま人に語ったのです。
それは、その夫人にとって、たった一つの経験的事実の叙述なのです。
そこで結論はどうかというと、夫人の経験の具体性をあるがままに受け取らないで、これをはたして夫は死んだか、死ななかったかという抽象的な問題に置き換えてしまう。
そこに根本な間違いが行われているというのです。』
----------------------------------
『近代科学の本質は計量を目指すが、精神の本質は計量を許さぬ所にある。』
----------------------------------
『私がこうして話しているのは、極く普通の意味で理性的に話しているのですし、ベルクソンにしても、理性を傾けて説いているのです。
けれども、これは科学的理性ではない。僕らの持って生まれた理性です。
科学は、この持って生まれた理性というものに加工をほどこし、科学的方法とする。
計量できる能力と、間違いなく働く智慧とは違いましょう。学問の種類は非常に多い。近代科学だけが学問ではない。
その狭隘な方法だけでは、どうにもならぬ学問がある。』
----------------------------------
小林秀雄のこの発言は重い。
確かに、未知な現象や神秘的な現象、よくわからない現象を見せられると、
「これはトリックに違いない。」
「これは騙そうとしているに違いない。」
「聞こえたのは幻聴。見えたのは妄想。きっとそのひとの頭がすこしおかしいに違いない。自分は正しく、向こうは間違っている。」
という思考が最初に頭によぎってしまう。
でも、「正しいか、正しくないか」「うそか、ほんとか」などの前に、<驚くべきことに素直に驚く態度>が先に来るべきなのだろう。その「驚き」の態度に、正しいとか間違っているか、そういう抽象的な話題は付け入る隙はないはずだ。
驚くこと、信じられないこと。
そんな現実を自分に取り入れるとき、「そんなものはないはずだ」と切り捨てて取り込まない人もいるし、その現象を加工してねじまげて自分に取り入れる人もいる。
でも、大事なことは、起きた現象を素直に全体のまま受け取めることだと思う。
矛盾は矛盾のまま。わからないことはわからないま。
そうすると、矛盾がほどけることや「わからない」ことが「わかる」ことは本質的な問題ではなくなる。
多様なものを排除せずに受け入れる、自分の生きていく態度そのものが醸成されていくのだと思う。
きっと、その態度は<科学的思考>(=対象を計量化して数値化することで客観的に調べていく態度。言い換えれば、計量化して数値化できる世界だけを扱っていく態度)とも矛盾なく両立するのではないだろうか。
この小林秀雄の指摘には、当初この文章を読んだ時にドキッとしたものだ。それほど、自分は科学的思考を絶対的なドグマとして疑いすらしなかったということなのだろう。
この小林秀雄の文章の一部が、「アルカナシカ」の中で紹介されていて(引用箇所は一部違うけれど)、この謙虚な態度こそ通底低音として流れている音だと感じました。
・・・・・・・・
ちなみに、この「信ずることと知ること」の中では、柳田國男が見たおばあさんの「魂」の話が出てくる。
自分はこの話が一番好き。(詳細は本を買って読んでみてください。文庫は660円で買えるのですから!高い喫茶店のコーヒー一杯や高い居酒屋のビール一杯と同じような値段で読めるのです。)
柳田國男が「魂」を見た体験を話しながら、「そういう体験がベースにないと民俗学なんてできませんよ」と語る。
そして、「魂はあるかないか・・・ あるに決まっているじゃないですか。」
とピシャリと言うくだりもあって、痛快だ。
(本の活字では省略されているけど、講演集のCDには出てくる。小林秀雄の講演集『信ずることと考えること―講義・質疑応答』(新潮CD講演 小林秀雄講演 第2巻))

その簡潔な言い方の中には、
「何を言っているの?アルカナイカではないでしょ。魂はあるに決まってるじゃない。そんなの昔からいろんな人が言ってるんだから。観念的に頭の中でグルグル考えてる暇があったら、アルカナイカではなくて、アルとして素直に自分の頭で考えてみなさいよ。」
という小林秀雄の叱咤が聞こえてきそうだ。
ちなみに、この「人生について」(新潮文庫)の中には『感想』という別のエッセイがあって、彼自身の「童話的経験」と称して、亡くなった母の魂が蛍の光となり、その魂(蛍)と出会ったエピソードも紹介されているのです。
・・・・・・
この「魂」の下りまでは『アルカナシカ』の中では紹介されていませんが、驚くべき不思議なことに対して、かっこつけずに素直に驚く態度を大切にしましょうと聞こえる。
近代科学は歴史が浅く多くの学問の中のひとつに過ぎないのだから、近代科学だけで全てを無理やり説明しなさんな、と。
科学的理性だけではなく、<僕らの持って生まれた理性>を、素直なこころをもっと大切にしなさいよ、と。
そう聞こえた。
そんな小林秀雄自身の率直な態度にも感じ入ったのです。
そして、こういう素直な態度こそ『アルカナシカ』の本を読んでいくうえで、この世に溢れているわからないことをわからないまま考えていく上で、とても大事で基本的な態度になるのだと思うのです。
■カント
『アルカナシカ』の本の中で、哲学者イマヌエル・カント(1724-1804年)のことが紹介されている。
カントは人間の認識の限界というものを、自分自身の認識や知性の限界まで使い抜いて考えた人だ。
抽象的な思考をする前に、まず理性(知的な能力)が扱える限界を考えてみましょうよと言った。
それがかの有名な『純粋理性批判』に通じていく。
その過程の中で、人間は「そのもの自体」を感知することはできないと、カントは指摘する。
なぜなら、人間は五感をもっていて、その五感(見る、聞く、匂う、触る、味わう)という窓を通して世界を認識しているから。そのものの限界が内在されているから。
「あなたがそのように見るから、そのような現実である」
人間の認識態度こそが世界を構成して作り出している。
そのことを指摘したのがカントだ。
自分たち(観察者側)の態度や意思が、この世界に影響を与えている。
そして、この世界がどのように見えるかを規定して枠を設定してしまっている。
自分で霊界を直接見たという神秘思想家のスウェーデンボルグについても、『視霊者の夢』(1766年)という本の中で触れられていて、スウェーデンボルグの千里眼(遠いストックホルムの火事を同じ時間に違う場所で幻視した)という当時を揺るがせた超常現象について、基本的には激しく批判している。ただ、それが存在するのか幻覚であるのか、判断はできないという感想も併記している。
カントの壮大な学問のきっかけになったのは、カント自身が神秘思想家スウェーデンボルグの幻視体験が持つリアリティーに圧倒され、自分の理性が揺らぎ、日常の崩壊を疑似体験したからではないかと、「アルカナシカ」で語られる。
カントは、理性で扱う限界を考えて、その枠組みを設定した。
その上で、形而上学(抽象的な学問)を作りあげようとした。
この考えは、むしろ近代科学に通じるのだ思う。
計量化して数値化できるものを科学では扱いましょう。それ以外は原理上扱えませんよ。あるともないとも言えません、と。
近代科学は、客観化して数値化できるものに対して「how?」の説明をする。例えば、どのようにして物体が坂を転がるのか。どのようにして人は心臓が止まり、脳が機能停止し、死んでいくのか。・・・
ただ、客観化できないものや数値化できないものに対して「Why?」の説明はできない。なぜ、そもそもこの物体が存在しているのか、重力・宇宙・・・なぜ存在しているのか、なぜ人は死ぬのか・・・。
■窓
よくわからないことに遭遇した時の態度。
その態度や意識(無意識もふくめて)そのものが、すでにその現実を規定していく。
好きな人に対しては「あばたもエクボ」という言葉がある。
好きな人は、欠点も長所のように見えてしまうということだ。それくらい現実認識は脆い。
このことは、不思議な現象やよくわからない現象に接するときにも戒めとして知っておかないといけないことだと思う。
自分の外界と内界を連結する「窓」を考える。
自分がオープンで開かれた態度でものごとに接していれば、ものごとは開かれた状態に展開されて見える。
自分がクローズドで閉じた態度で接していれば、ものごとはその閉じた世界での整合性に従って展開されて見える。
ただ、あまりに自分の窓を不用心に全開にすると何でもかんでも無条件に入ってくる。自分の手に負えなくなる。
だから、適度に窓を開けたり閉めたりして、網戸を使ったりして、夜寝てる時は安全のために鍵を閉めたりして、意識的にも無意識的にも、自分の中に入ってくるものを窓の開け閉めで調節しているのだろう。
でも、そういう開け閉めしている自分の窓のサイズによって、僕らが見ている世界は規定されている。
見たくないものは見てないし、見たいものだけを見ている。
そのことに自覚的でありなさい。ということだろう。
それは、ごく当たり前のことのようだけれど、なかなか改めて気づけないことでもある。
自分の外界と内界の間にある窓の存在を知るためには、外も内もそれなりに知っている必要があるからだ。
それは、この世界のことを学び、自分自身のことをよく知ることだ。
そのことへの自覚が自分の「窓」への理解となる。
■「情報」
認識や理性の限界を丁寧に踏まえ論証した上で、「情報」の概念も触れられる。
物質とエネルギーに次いで、近代科学が扱う重要な第三の存在としての「情報」。
本書ではかかれなかったが、おそらく物理学者マクスウェルが提唱した「マクスウェルの悪魔」という思考実験の知識も根底にあるのだと思う。
すごく簡単に言うと、物理学にとっての観測問題(=<見る>という行為)のこと。見ることが、すでにその系に影響を与える。
量子論、統計力学、熱力学だけではなく、<情報>の概念が導入されることである解決を見た。
パソコンで使われるビットなどのメモリー(記憶)は、エントロピーやエネルギーと変換される。
アインシュタインの<E=MC2>で、物質はエネルギーに変換される。そして、エネルギーは「情報」へと変換される!
<参考>
都筑卓司「マックスウェルの悪魔」ブルーバックス (2002/9/20)

■占星術
最後は、ランディさんのシンクロニシティー(=意味のある偶然の一致)を読み手も追体験しながら、大宇宙とこの生きている世界との相関を考え続けた占星学の知識も結集されていく。
カントの墓に記されている有名な言葉。
「我が上なる星空と、我が内なる道徳法則、我はこの二つに畏敬の念を抱いてやまない」『実践理性批判』
時空を超えて追体験した気がする。
この本で紹介されている鏡リュウジさんにもすごく親近感がわいた。
・・・・・・
『アルカナシカ』はUFOという不可解な事柄を入り口として話が進んでいくのだけど、そのランディさんが行こうとする旅は果てしない旅だ。
量子論、カント、スウェーデンボルグ、占星学・・・様々なシンクロニシティー(共時性)と遭遇しながら、人間の知性や認識の限界に迫っていく。
迫力のある本だった。その辺の学術書よりも数倍深いことが書いてあると思った。自分の認識そのものを改めて考えさせられる。
「ありえないものをありえないと決めつける信念、わからないものは存在しないと決めつける信念・・・そういうものは、果たしてどこからやってくるのだろう。」という、理性や知性そのものへの壮大な問いだ。
虚心坦懐に、素直にものごとを見ることは大事だ。
赤ん坊のように偏見もなく素直にものごとを見ること。
そして、自分たちがどのように世界をとらえていこうとするか、希望を持つか・絶望するか、そのこと自体でこの世界は変容していく。
それは、キルケゴールが現代に特徴的な<絶望>をあげ、そのことを<死に至る病>と名づけたこととも関連するのかもしれない(Soren Kierkegaard「死にいたる病」(ちくま学芸文庫))
ランディさんの「アルカナシカ」の射程はおそろしく深くて広い。
自分も改めていろいろ考えさせられることが多かった。
この世界は僕らの生きる態度と感応して存在している。
真面目に素直に正直に、希望や愛情を持ってこの世界に接していけば、この世界はそのように反応して変容していくし、そのような世界が展開されていく。
逆もまた然りだ。
自分がどういう態度でこの世界を生きていくか、それは自分の意思で決めていくこと。
善意を持って、無私の精神で、利他のこころで、奉仕の精神で、思いやりと優しさを持ってこの世界を生きていくのか。
悪意を持って、自意識過剰に自分勝手な欲望で、暴力と支配と統治の精神で生きていくのか。
それは誰かが決めるのではない。自分で決めることだ。
どんな環境でも自分で決めることだ。
たしかに、この世界には自分で決めれないこともあるけれど、自分で決めれることも同じ程度に多い。
それは、生き方そのものの問題になる。
ある意思を持ち、生きていくことを引き受けること。いま生きているということは、すでに前向きだ。生命はそういうものだ。
その重みを引き受ければ、世界はそのように展開していくのだと、思う。
・・・・・・・
高度な哲学的で形而上的な問題を、この世界の神秘や不思議さと織り交ぜながら圧倒的な筆力で文章が展開していく様は、圧巻。
いろいろ深く考えるように刺激する本はいい本です。書き手のエネルギーが、読み手の中に移動して反応する。
そういうものこそが時代の流れと無関係に残るのでしょう。
不易と流行。
名著です。おすすめです。是非とも、読んでみてください。
(このブログは1万文字までしか入らないのですが、ぎりぎり9900文字くらいで納まったー)
すごく面白かった・・・。衝撃だった。鳥肌たった。
少し前に出た「マアジナル」(→『田口ランディ「マアジナル」』(2011-06-19))をフィクションだとすると、「アルカナシカ」は便宜的にノンフィクションとされている。
ただ、このフィクション、ノンフィクションというわけ目自体に、すでに仕掛けがあるような気がした。
フィクション世界はノンフィクション世界を侵食しているし、ノンフィクション世界はフィクション世界へと侵食しているようで。
ふたつは一つのはっきりした境界線で仕切られるものではなくて、紙の表と裏のようなものだ。その境界(マージナル)、分けようとする線引きの行為そのものに、何か大事なことが隠れているのだろう。
この現実世界もおなじようなものだ。
どこまでが自分の脳の神経細胞が作り出した電気的な発光現象の産物のフィクションなのか、それともあるがままのノンフィクションなのか、そう容易く線引きできないものだ。
===============
<内容紹介>(Amazonより)
人はなぜ、不思議な現象を怖れ、憧れ、求めるのか?
偶然に導かれるように出会った、UFO遭遇者、超能力者、霊能力者――。
体験者たちの圧倒的な現実から人間の意識と精神の根源に迫る、渾身のノンフィクション!
===============
■小林秀雄「信ずることと知ること」
この「アルカナシカ」にも一部引用されている、小林秀雄の「信ずることと知ること」という講演がある。
この文章が収録された小林秀雄「人生について」(新潮文庫)という本。
この本はとても好きだ。見返すと、赤線引きまくり、付箋もはりまくられている。
自分の心深くにひっかかるものがたくさんあった。
ちなみに、「信ずることと知ること」というタイトルには、<信ずることと知ることは一体のものであって分けることができないものだ。ふたつでひとつなのだ>という考えが込められていると、小林秀雄本人が語っている。

まず、ユリ・ゲラーのスプーン曲げに関する記述がある。
----------------------------------
小林秀雄「信ずることと知ること」
『今度のユリ・ゲラーの実験にしても、これを扱う新聞や雑誌を見ていますと、不思議を不思議と受け取る素直な心が、何と少ないかに驚く。
テレビで不思議を見せられると、これに対して嘲笑的態度をとるか、スポーツでも見て面白がるのと同じ態度をとるか、どちらかでしょう。
・・・・・・
今日の知識人にとって、己の頭脳によって理解できない声は、みんな調子が外れているのです。
その点で、彼らは根底的な反省を書いている、と言っていいでしょう。』
----------------------------------
そして、ある女性の夫が戦争で死んだとき、その戦場で夫が殺された生々しい幻をまったく同じ時間に違う場所で見たという話しが出てくる。<精神感応>の例として。
そのことに対する知識人の発言で「幻の中にも、結果的に正しかった幻と、結果的に正しくなかった幻を見ているのでしょう。前者の方が印象深いので単にそのことだけを覚えているだけでしょう。精神感応とか念力とか、そういう未知の力による現象ではなくて単なる偶然でしょう。」というような発言が紹介されていて、その態度を小林秀雄は批判する。
----------------------------------
小林秀雄「信ずることと知ること」
『その夫人はそういう問題(=夫人が夢を見た時に確かに夫は死んだのか、生きていたかという問題)を話したのではなく、自分の経験を話したのです。
夢は余りにもなまなましい光景であったから、それをそのまま人に語ったのです。
それは、その夫人にとって、たった一つの経験的事実の叙述なのです。
そこで結論はどうかというと、夫人の経験の具体性をあるがままに受け取らないで、これをはたして夫は死んだか、死ななかったかという抽象的な問題に置き換えてしまう。
そこに根本な間違いが行われているというのです。』
----------------------------------
『近代科学の本質は計量を目指すが、精神の本質は計量を許さぬ所にある。』
----------------------------------
『私がこうして話しているのは、極く普通の意味で理性的に話しているのですし、ベルクソンにしても、理性を傾けて説いているのです。
けれども、これは科学的理性ではない。僕らの持って生まれた理性です。
科学は、この持って生まれた理性というものに加工をほどこし、科学的方法とする。
計量できる能力と、間違いなく働く智慧とは違いましょう。学問の種類は非常に多い。近代科学だけが学問ではない。
その狭隘な方法だけでは、どうにもならぬ学問がある。』
----------------------------------
小林秀雄のこの発言は重い。
確かに、未知な現象や神秘的な現象、よくわからない現象を見せられると、
「これはトリックに違いない。」
「これは騙そうとしているに違いない。」
「聞こえたのは幻聴。見えたのは妄想。きっとそのひとの頭がすこしおかしいに違いない。自分は正しく、向こうは間違っている。」
という思考が最初に頭によぎってしまう。
でも、「正しいか、正しくないか」「うそか、ほんとか」などの前に、<驚くべきことに素直に驚く態度>が先に来るべきなのだろう。その「驚き」の態度に、正しいとか間違っているか、そういう抽象的な話題は付け入る隙はないはずだ。
驚くこと、信じられないこと。
そんな現実を自分に取り入れるとき、「そんなものはないはずだ」と切り捨てて取り込まない人もいるし、その現象を加工してねじまげて自分に取り入れる人もいる。
でも、大事なことは、起きた現象を素直に全体のまま受け取めることだと思う。
矛盾は矛盾のまま。わからないことはわからないま。
そうすると、矛盾がほどけることや「わからない」ことが「わかる」ことは本質的な問題ではなくなる。
多様なものを排除せずに受け入れる、自分の生きていく態度そのものが醸成されていくのだと思う。
きっと、その態度は<科学的思考>(=対象を計量化して数値化することで客観的に調べていく態度。言い換えれば、計量化して数値化できる世界だけを扱っていく態度)とも矛盾なく両立するのではないだろうか。
この小林秀雄の指摘には、当初この文章を読んだ時にドキッとしたものだ。それほど、自分は科学的思考を絶対的なドグマとして疑いすらしなかったということなのだろう。
この小林秀雄の文章の一部が、「アルカナシカ」の中で紹介されていて(引用箇所は一部違うけれど)、この謙虚な態度こそ通底低音として流れている音だと感じました。
・・・・・・・・
ちなみに、この「信ずることと知ること」の中では、柳田國男が見たおばあさんの「魂」の話が出てくる。
自分はこの話が一番好き。(詳細は本を買って読んでみてください。文庫は660円で買えるのですから!高い喫茶店のコーヒー一杯や高い居酒屋のビール一杯と同じような値段で読めるのです。)
柳田國男が「魂」を見た体験を話しながら、「そういう体験がベースにないと民俗学なんてできませんよ」と語る。
そして、「魂はあるかないか・・・ あるに決まっているじゃないですか。」
とピシャリと言うくだりもあって、痛快だ。
(本の活字では省略されているけど、講演集のCDには出てくる。小林秀雄の講演集『信ずることと考えること―講義・質疑応答』(新潮CD講演 小林秀雄講演 第2巻))

その簡潔な言い方の中には、
「何を言っているの?アルカナイカではないでしょ。魂はあるに決まってるじゃない。そんなの昔からいろんな人が言ってるんだから。観念的に頭の中でグルグル考えてる暇があったら、アルカナイカではなくて、アルとして素直に自分の頭で考えてみなさいよ。」
という小林秀雄の叱咤が聞こえてきそうだ。
ちなみに、この「人生について」(新潮文庫)の中には『感想』という別のエッセイがあって、彼自身の「童話的経験」と称して、亡くなった母の魂が蛍の光となり、その魂(蛍)と出会ったエピソードも紹介されているのです。
・・・・・・
この「魂」の下りまでは『アルカナシカ』の中では紹介されていませんが、驚くべき不思議なことに対して、かっこつけずに素直に驚く態度を大切にしましょうと聞こえる。
近代科学は歴史が浅く多くの学問の中のひとつに過ぎないのだから、近代科学だけで全てを無理やり説明しなさんな、と。
科学的理性だけではなく、<僕らの持って生まれた理性>を、素直なこころをもっと大切にしなさいよ、と。
そう聞こえた。
そんな小林秀雄自身の率直な態度にも感じ入ったのです。
そして、こういう素直な態度こそ『アルカナシカ』の本を読んでいくうえで、この世に溢れているわからないことをわからないまま考えていく上で、とても大事で基本的な態度になるのだと思うのです。
■カント
『アルカナシカ』の本の中で、哲学者イマヌエル・カント(1724-1804年)のことが紹介されている。
カントは人間の認識の限界というものを、自分自身の認識や知性の限界まで使い抜いて考えた人だ。
抽象的な思考をする前に、まず理性(知的な能力)が扱える限界を考えてみましょうよと言った。
それがかの有名な『純粋理性批判』に通じていく。
その過程の中で、人間は「そのもの自体」を感知することはできないと、カントは指摘する。
なぜなら、人間は五感をもっていて、その五感(見る、聞く、匂う、触る、味わう)という窓を通して世界を認識しているから。そのものの限界が内在されているから。
「あなたがそのように見るから、そのような現実である」
人間の認識態度こそが世界を構成して作り出している。
そのことを指摘したのがカントだ。
自分たち(観察者側)の態度や意思が、この世界に影響を与えている。
そして、この世界がどのように見えるかを規定して枠を設定してしまっている。
自分で霊界を直接見たという神秘思想家のスウェーデンボルグについても、『視霊者の夢』(1766年)という本の中で触れられていて、スウェーデンボルグの千里眼(遠いストックホルムの火事を同じ時間に違う場所で幻視した)という当時を揺るがせた超常現象について、基本的には激しく批判している。ただ、それが存在するのか幻覚であるのか、判断はできないという感想も併記している。
カントの壮大な学問のきっかけになったのは、カント自身が神秘思想家スウェーデンボルグの幻視体験が持つリアリティーに圧倒され、自分の理性が揺らぎ、日常の崩壊を疑似体験したからではないかと、「アルカナシカ」で語られる。
カントは、理性で扱う限界を考えて、その枠組みを設定した。
その上で、形而上学(抽象的な学問)を作りあげようとした。
この考えは、むしろ近代科学に通じるのだ思う。
計量化して数値化できるものを科学では扱いましょう。それ以外は原理上扱えませんよ。あるともないとも言えません、と。
近代科学は、客観化して数値化できるものに対して「how?」の説明をする。例えば、どのようにして物体が坂を転がるのか。どのようにして人は心臓が止まり、脳が機能停止し、死んでいくのか。・・・
ただ、客観化できないものや数値化できないものに対して「Why?」の説明はできない。なぜ、そもそもこの物体が存在しているのか、重力・宇宙・・・なぜ存在しているのか、なぜ人は死ぬのか・・・。
■窓
よくわからないことに遭遇した時の態度。
その態度や意識(無意識もふくめて)そのものが、すでにその現実を規定していく。
好きな人に対しては「あばたもエクボ」という言葉がある。
好きな人は、欠点も長所のように見えてしまうということだ。それくらい現実認識は脆い。
このことは、不思議な現象やよくわからない現象に接するときにも戒めとして知っておかないといけないことだと思う。
自分の外界と内界を連結する「窓」を考える。
自分がオープンで開かれた態度でものごとに接していれば、ものごとは開かれた状態に展開されて見える。
自分がクローズドで閉じた態度で接していれば、ものごとはその閉じた世界での整合性に従って展開されて見える。
ただ、あまりに自分の窓を不用心に全開にすると何でもかんでも無条件に入ってくる。自分の手に負えなくなる。
だから、適度に窓を開けたり閉めたりして、網戸を使ったりして、夜寝てる時は安全のために鍵を閉めたりして、意識的にも無意識的にも、自分の中に入ってくるものを窓の開け閉めで調節しているのだろう。
でも、そういう開け閉めしている自分の窓のサイズによって、僕らが見ている世界は規定されている。
見たくないものは見てないし、見たいものだけを見ている。
そのことに自覚的でありなさい。ということだろう。
それは、ごく当たり前のことのようだけれど、なかなか改めて気づけないことでもある。
自分の外界と内界の間にある窓の存在を知るためには、外も内もそれなりに知っている必要があるからだ。
それは、この世界のことを学び、自分自身のことをよく知ることだ。
そのことへの自覚が自分の「窓」への理解となる。
■「情報」
認識や理性の限界を丁寧に踏まえ論証した上で、「情報」の概念も触れられる。
物質とエネルギーに次いで、近代科学が扱う重要な第三の存在としての「情報」。
本書ではかかれなかったが、おそらく物理学者マクスウェルが提唱した「マクスウェルの悪魔」という思考実験の知識も根底にあるのだと思う。
すごく簡単に言うと、物理学にとっての観測問題(=<見る>という行為)のこと。見ることが、すでにその系に影響を与える。
量子論、統計力学、熱力学だけではなく、<情報>の概念が導入されることである解決を見た。
パソコンで使われるビットなどのメモリー(記憶)は、エントロピーやエネルギーと変換される。
アインシュタインの<E=MC2>で、物質はエネルギーに変換される。そして、エネルギーは「情報」へと変換される!
<参考>
都筑卓司「マックスウェルの悪魔」ブルーバックス (2002/9/20)

■占星術
最後は、ランディさんのシンクロニシティー(=意味のある偶然の一致)を読み手も追体験しながら、大宇宙とこの生きている世界との相関を考え続けた占星学の知識も結集されていく。
カントの墓に記されている有名な言葉。
「我が上なる星空と、我が内なる道徳法則、我はこの二つに畏敬の念を抱いてやまない」『実践理性批判』
時空を超えて追体験した気がする。
この本で紹介されている鏡リュウジさんにもすごく親近感がわいた。
・・・・・・
『アルカナシカ』はUFOという不可解な事柄を入り口として話が進んでいくのだけど、そのランディさんが行こうとする旅は果てしない旅だ。
量子論、カント、スウェーデンボルグ、占星学・・・様々なシンクロニシティー(共時性)と遭遇しながら、人間の知性や認識の限界に迫っていく。
迫力のある本だった。その辺の学術書よりも数倍深いことが書いてあると思った。自分の認識そのものを改めて考えさせられる。
「ありえないものをありえないと決めつける信念、わからないものは存在しないと決めつける信念・・・そういうものは、果たしてどこからやってくるのだろう。」という、理性や知性そのものへの壮大な問いだ。
虚心坦懐に、素直にものごとを見ることは大事だ。
赤ん坊のように偏見もなく素直にものごとを見ること。
そして、自分たちがどのように世界をとらえていこうとするか、希望を持つか・絶望するか、そのこと自体でこの世界は変容していく。
それは、キルケゴールが現代に特徴的な<絶望>をあげ、そのことを<死に至る病>と名づけたこととも関連するのかもしれない(Soren Kierkegaard「死にいたる病」(ちくま学芸文庫))
ランディさんの「アルカナシカ」の射程はおそろしく深くて広い。
自分も改めていろいろ考えさせられることが多かった。
この世界は僕らの生きる態度と感応して存在している。
真面目に素直に正直に、希望や愛情を持ってこの世界に接していけば、この世界はそのように反応して変容していくし、そのような世界が展開されていく。
逆もまた然りだ。
自分がどういう態度でこの世界を生きていくか、それは自分の意思で決めていくこと。
善意を持って、無私の精神で、利他のこころで、奉仕の精神で、思いやりと優しさを持ってこの世界を生きていくのか。
悪意を持って、自意識過剰に自分勝手な欲望で、暴力と支配と統治の精神で生きていくのか。
それは誰かが決めるのではない。自分で決めることだ。
どんな環境でも自分で決めることだ。
たしかに、この世界には自分で決めれないこともあるけれど、自分で決めれることも同じ程度に多い。
それは、生き方そのものの問題になる。
ある意思を持ち、生きていくことを引き受けること。いま生きているということは、すでに前向きだ。生命はそういうものだ。
その重みを引き受ければ、世界はそのように展開していくのだと、思う。
・・・・・・・
高度な哲学的で形而上的な問題を、この世界の神秘や不思議さと織り交ぜながら圧倒的な筆力で文章が展開していく様は、圧巻。
いろいろ深く考えるように刺激する本はいい本です。書き手のエネルギーが、読み手の中に移動して反応する。
そういうものこそが時代の流れと無関係に残るのでしょう。
不易と流行。
名著です。おすすめです。是非とも、読んでみてください。
(このブログは1万文字までしか入らないのですが、ぎりぎり9900文字くらいで納まったー)









