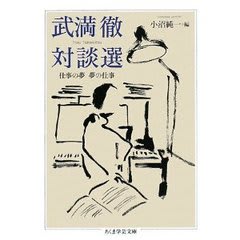
最近、作曲家であり、現代音楽の巨匠である武満徹さんの言葉にしびれている。
「武満徹対談選―仕事の夢 夢の仕事」(ちくま学芸文庫)、武満徹エッセイ選―言葉の海へ」(ちくま学芸文庫)は、とてもすばらしい本。
言葉の端々がメタファーに富んでいるのだけど、それはメタファーのためのメタファーではない。
伝えたい言葉が、ある領域とある領域との間にあって、そこに適切な言葉が存在しないから、メタファーで紡がざるを得ないんだと思う。村上春樹さんがインタビュー時に話すときと同じような(たとえば、「夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです」(文藝春秋)とか。)、流れるようなメタファーの自然さを感じる。
その中で、武満徹さんとジャズピアニストのキース・ジャレットとの対談。
優雅な禅問答のように刺激的だった。
キース・ジャレットは、ジャズピアノでの即興音楽の名手だから、話は自然に「即興」(improvisation)に関する話題になる。
「即興」について考えてみると、日常はすべて、即興の連続なのだと思う。予定調和なものではなくて。
人間を扱う仕事をしていると、そんなことを強く思う。
その場で感じ、考え、その場で対応する。
正解があるのかないかわからないけど、即興で暫定的な解答を置いて行かないといけない。
そういうことで、キース・ジャレットのジャズにおける「即興」は、自分の仕事に引き付けても、いろいろ考えることが多かった。
====================
武満
(即興が一般的に陥りやすい点について語る)
「うっかりすると、その即興が単に自分を繰り返し模倣する自己模倣におちいってしまって、そこに何ら新しい自分を発見するということがないようなことになってしまう。」
ジャレット
「そういう意味で、本当の即興者というのは少ないですね。機械的なイミテーションばかりで、内容は同じまま。わたしにとって、それはもはや音楽とは言えないんです。」
====================
====================
ジャレット
(演奏について語る)
「楽器に秘められた可能性を引き出し、音楽によって与えられるはずの快適な状態を闇の中から引き出すことです。」
====================
ジャレット
「芸術のできることというのは、ほんの瞬間、人の内側に入り込むことだけ。そして、これは特に音楽において可能なことだと思う。」
====================
====================
武満
(ジャレットの演奏を評して)
「たいへんパーソナルでありながら、ユニヴァーサルというか、いやもっと宇宙的(コズミック)な、ジャレットさんが弾いてるってことを忘れちゃうような世界ですね。
つまりそれは、音楽が満ち溢れていて、音楽が見えなくなっている状態というか」
====================
ジャレット
「即興というのは、何か頭の上にあるものを指す言葉として使われているけれども、それはまったく正反対のこと。
即興というのは、逆に大変深いもので、一番底をきわめたその瞬間に音楽がやってくるようなものだと思うんです。」
====================
ジャレット
「わたしは自分で即興をする時に、自分ではリスニング(listening)と呼んでいます。たとえば、即興をグループでやるときは、皆お互いに聴き合わなくてはならないですから。」
====================
ジャレット
「私自身のサウンドを聴きたい、私の音楽を所有したいという欲望は、今はもうなくなりました。
今は、他の人の音楽の中で欠けていると思われるものを取り戻したいと思っているのです。彼らに音楽を返してあげたいのです。」
====================
ジャレット
「わたしの音楽との関係は、正に正直なもので、それを今まで演奏している間ずっと見つめてきたんです。
だから、音楽はいつもわたしに欠けているもの、わたしが次にしなくてはならないことを教えてくれました。」
====================
武満
(キース・ジャレットとの対談を終えて)
「キース・ジャレットの感性は、訓練された筋肉のようにしなやかで、そこに余分な、あいまいな感情というものは無い。ダイレクトに事物の核心を獲物を狙う豹のような素早さで把握する。音楽的未熟児が多いジャズの領域で、かれは止まることのない成長を続ける幼児(イノセント)のように見える。かれは、いつでも、最小限の音で、世界の全体を顕してしまう。」
====================
キース・ジャレットも、武満徹さんも、すでにクラシックとか、ジャズとか、そういう人工的な縛りや囲いは眼中にないようだ。
そんな小さきものよりも、もっと大きな「音楽」そのもの、「美」そのものと、ダイレクトに向き合い、そこに寄り添うように仕事の仕方をしていると感じた。
それは、どんな領域の仕事でも言えると思う。
小さいものの仕事に追われるのではなくて、その背後に隠れている巨大なものを見つめること。
自分の仕事や生活の背後に隠れる、巨大な畏敬すべき対象と、一対一でダイレクトに結びつくこと。
それは、「即興」と呼ばれる、ほんの些細な一瞬一瞬の積み重ね。
「一瞬」という時間は、手のひらでパンと叩くと、実感できる。
それは、ほとんど「音」そのものだ。
そんな一瞬の一瞬の積み重ねの中に、「時」は生まれる。
「時」は、そんな些細なディテールの積み重ねだと思う。
そのことを、「音楽」そのものが、教えてくれるのだろう。
「武満徹対談選―仕事の夢 夢の仕事」(ちくま学芸文庫)、武満徹エッセイ選―言葉の海へ」(ちくま学芸文庫)は、とてもすばらしい本。
言葉の端々がメタファーに富んでいるのだけど、それはメタファーのためのメタファーではない。
伝えたい言葉が、ある領域とある領域との間にあって、そこに適切な言葉が存在しないから、メタファーで紡がざるを得ないんだと思う。村上春樹さんがインタビュー時に話すときと同じような(たとえば、「夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです」(文藝春秋)とか。)、流れるようなメタファーの自然さを感じる。
その中で、武満徹さんとジャズピアニストのキース・ジャレットとの対談。
優雅な禅問答のように刺激的だった。
キース・ジャレットは、ジャズピアノでの即興音楽の名手だから、話は自然に「即興」(improvisation)に関する話題になる。
「即興」について考えてみると、日常はすべて、即興の連続なのだと思う。予定調和なものではなくて。
人間を扱う仕事をしていると、そんなことを強く思う。
その場で感じ、考え、その場で対応する。
正解があるのかないかわからないけど、即興で暫定的な解答を置いて行かないといけない。
そういうことで、キース・ジャレットのジャズにおける「即興」は、自分の仕事に引き付けても、いろいろ考えることが多かった。
====================
武満
(即興が一般的に陥りやすい点について語る)
「うっかりすると、その即興が単に自分を繰り返し模倣する自己模倣におちいってしまって、そこに何ら新しい自分を発見するということがないようなことになってしまう。」
ジャレット
「そういう意味で、本当の即興者というのは少ないですね。機械的なイミテーションばかりで、内容は同じまま。わたしにとって、それはもはや音楽とは言えないんです。」
====================
====================
ジャレット
(演奏について語る)
「楽器に秘められた可能性を引き出し、音楽によって与えられるはずの快適な状態を闇の中から引き出すことです。」
====================
ジャレット
「芸術のできることというのは、ほんの瞬間、人の内側に入り込むことだけ。そして、これは特に音楽において可能なことだと思う。」
====================
====================
武満
(ジャレットの演奏を評して)
「たいへんパーソナルでありながら、ユニヴァーサルというか、いやもっと宇宙的(コズミック)な、ジャレットさんが弾いてるってことを忘れちゃうような世界ですね。
つまりそれは、音楽が満ち溢れていて、音楽が見えなくなっている状態というか」
====================
ジャレット
「即興というのは、何か頭の上にあるものを指す言葉として使われているけれども、それはまったく正反対のこと。
即興というのは、逆に大変深いもので、一番底をきわめたその瞬間に音楽がやってくるようなものだと思うんです。」
====================
ジャレット
「わたしは自分で即興をする時に、自分ではリスニング(listening)と呼んでいます。たとえば、即興をグループでやるときは、皆お互いに聴き合わなくてはならないですから。」
====================
ジャレット
「私自身のサウンドを聴きたい、私の音楽を所有したいという欲望は、今はもうなくなりました。
今は、他の人の音楽の中で欠けていると思われるものを取り戻したいと思っているのです。彼らに音楽を返してあげたいのです。」
====================
ジャレット
「わたしの音楽との関係は、正に正直なもので、それを今まで演奏している間ずっと見つめてきたんです。
だから、音楽はいつもわたしに欠けているもの、わたしが次にしなくてはならないことを教えてくれました。」
====================
武満
(キース・ジャレットとの対談を終えて)
「キース・ジャレットの感性は、訓練された筋肉のようにしなやかで、そこに余分な、あいまいな感情というものは無い。ダイレクトに事物の核心を獲物を狙う豹のような素早さで把握する。音楽的未熟児が多いジャズの領域で、かれは止まることのない成長を続ける幼児(イノセント)のように見える。かれは、いつでも、最小限の音で、世界の全体を顕してしまう。」
====================
キース・ジャレットも、武満徹さんも、すでにクラシックとか、ジャズとか、そういう人工的な縛りや囲いは眼中にないようだ。
そんな小さきものよりも、もっと大きな「音楽」そのもの、「美」そのものと、ダイレクトに向き合い、そこに寄り添うように仕事の仕方をしていると感じた。
それは、どんな領域の仕事でも言えると思う。
小さいものの仕事に追われるのではなくて、その背後に隠れている巨大なものを見つめること。
自分の仕事や生活の背後に隠れる、巨大な畏敬すべき対象と、一対一でダイレクトに結びつくこと。
それは、「即興」と呼ばれる、ほんの些細な一瞬一瞬の積み重ね。
「一瞬」という時間は、手のひらでパンと叩くと、実感できる。
それは、ほとんど「音」そのものだ。
そんな一瞬の一瞬の積み重ねの中に、「時」は生まれる。
「時」は、そんな些細なディテールの積み重ねだと思う。
そのことを、「音楽」そのものが、教えてくれるのだろう。









