日本近代文学の森へ (189) 志賀直哉『暗夜行路』 76 ただのプロスティチュート 「前篇第二 十四」 その1
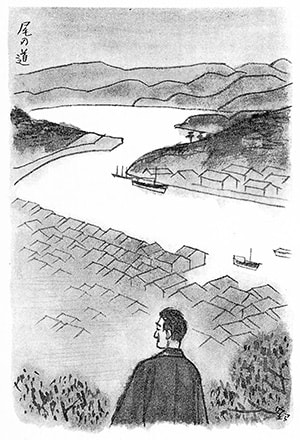
2021.4.13
いよいよ第一部の最終章である。前の「十三」は、とめどない自己嫌悪の感情が描かれたが、この「十四」に入ると、一転して遊郭の一室らしい場面となる。
やけになって、遊郭へ行ったということなのだろうか、その説明はない。いかにも唐突である。
小さい女は髪結いの処で丁度解いた所を呼ばれたのだといって、その沢山ある髪の毛を紅い球(たま)のついた髪差(かんざし)で襟首の上に軽く留めておいた。「朝鮮の女のようでしょう?」こんな事をいって横を向いて見せたりした。戸外(そと)はまだ明るかったが、天井の電燈がひとりでについた。風の音がして、それで部屋の中は甚<蒸々している。
この「小さい女」がそっけないので、謙作が外へ出ようと階段を降りてくると、「美しい女」が坐っていた。
彼は起ち上った。そして部屋を出ようとすると、小さい女は「失敬」といって手を挙げた。彼もちょっと手を挙げて、一人先に段々を降りて来た。そして出ようとすると、彼は其処(そこ)に若い女が坐っているのを見た。美しい女だった。何処(どこ)か感じのいい処があると彼は思った。
戸外(そと)へ出た。そして電車路の方へ歩きながら、今からならお栄にいって来たように、明るい内に帰れそうだと思った。それはそうと、何故あの女はあんな処に坐っていたろう。客が来ていてあんな処にいるのも変だと思った。この次行けば、あの女を自分は望むだろう、と彼は思った。どんな人でしたと訊(き)かれる。その時どういえばいいか。いうような事は何もない。実際何の特徴らしい特徴も自分は見ていなかった。俺が帰る時、下に坐っていた女だ。美しい女だ。せいは? それは分らない。肥っていましたか? 脊せた方ではなかった。こんな事で結局要領を得そうもない。
彼はこのまま電車に乗ってしまうのが惜しい気がした。今の小さい女がまだいるかも知れない。あるいは近所で会うかも知れない。「忘れ物をした」こういえばいい。そう思って彼はまた、前の家へ引きかえして行った。
「特徴らしい特徴」も見ていなかったのに、ただ「美しい女」だと思った女のことが気になって、謙作は女の家に引き返す。
彼は格子の中に立って女中と話した。
「今、其処にいたのはお客さんで来ているのか?」
女中にはこれだけで通じた。
「今、上に一人呼んでいるんです。それと交代で上るんです。直ぐですから、お上がりなさい」
「俺を先にしないか」
女中は顔をしかめて見せた。そしてまた、「直ぐです」といった。
彼は下駄を脱いだ。次の間を通る時、その襖のかげに今の会話を聴いていた女が隠れるようにして立っていた。彼は見ないようにして二階へ上って行った。が、上ると直ぐやはり後は困ると思って、彼は手を叩いて女中を呼んだ。隣りにはその客というのがいるので彼は小声でいった。
「隣りは別の奴を呼べばいいじゃないか」
「いいえ、名ざしなんです。それに先刻顔を見ちゃったんです」
「困るな」彼は気六(きむず)ヶしい顔つきをして黙ってしまった。
彼は別に根拠もなしにその女をおとなしい、素人臭い、善良な女という風に何時か心で決めてしまっていた。
隣りから一人の女が出て行った。間もなくその女がその部屋に入って行った。彼はじっとしていられない気持になった。そしてまた手を叩いた。
女中は入って来て、彼が何もいわない先に、
「今入った所です。直ぐです」と、なだめ顔にいった。彼は、
「硯を貸してくれ」といった。
懐(ふところ)から白紙を出し、それを餉台(ちゃぶだい)の上に延べて彼は下腹に力を入れて習字を始めた。慈眼視衆生、福聚海無量、こんな文句を書いた。が、こんな文句をこんな場所で書くのは勿体ない気がしてそれは直ぐやめたが、とにかく彼は隣りを頭に浮べたくなかったのである。
目当ての女にはすでに先客がいたのだが、謙作は、オレを先にしろという。ほんとにどうしようもないワガママ男だ。「美しい女」だと思い込んでいた女をこんどは「別に根拠もなしにその女をおとなしい、素人臭い、善良な女という風に何時か心で決めてしまっていた」というのも、とにかく自分本位で、思い込みが激しい性格がよく分かる。
その女が、隣の部屋で別の男と過ごしている様子を想像したくないのは分かるけど、だからといって、硯を持ってこさせて、信行から聞いた禅語だかを書くなんてことするものだろうか。しかも挙げ句に、「こんな文句をこんな場所で書くのは勿体ない気がして」とくる。気持ちは分からないでもないが、それなら初めからしなければいいのに。
やがて、女が来る。
女が入って来た。笑い顔をした。いやな顔ではなかったが、彼が勝手に決めていた顔とは大分異(ちが)っていた。
「ありがとう」少し斜めに向いて膝を突き、彼の顔を見ながら高いお辞儀をした。それが如何にもただのプロスティチュートだった。先刻の神妙らしい様子とは別人だった。
「プロスティチュート」は娼婦のこと。娼婦を呼んでおきながら、それがいかにも娼婦らしい女だからといってガッカリしている。それは相手がたとえ娼婦であろうと、その裏に隠れた人間性をこそ謙作が求めているからだと言えないこともないが、しかし、謙作の傲慢な態度からは侮蔑の念しか感じられない。「一緒に旅をしないか」だとか言ってみたり、女の家族のことを聞いてみたり、嘘かほんとか分からない答を聞いて、その後どうしたのか、まあ、なるようになったのだろうが、謙作は「何もはっきりした話はせずに、間もなく彼は其処を出て、真直ぐに自家(うち)へ帰って来た。
こういう書き方からすると、「なるようにはならなかった」のかもしれない。まあ、その辺のことはよく分からない。
翌日になり、夕方になると、また女のもとへ出かけて行く。
謙作は、信行が尋ねてくるのを実は待っているのだが、その信行もいっこうにやってこない。きっと自分の家を前を素通りして、本郷の父の家に行っているのだろうと思うと、不愉快な気分になるのだった。
















