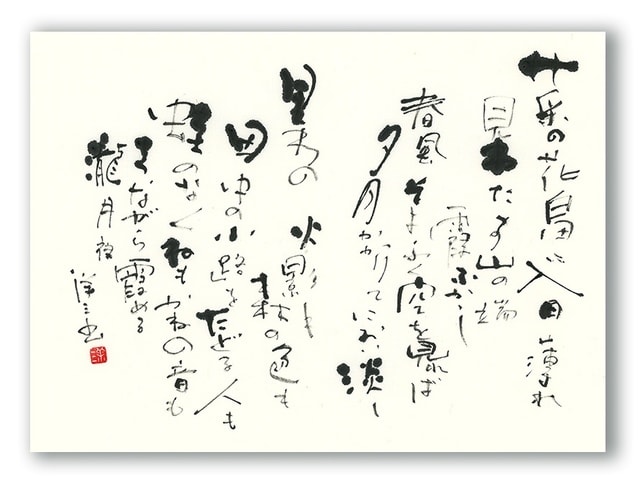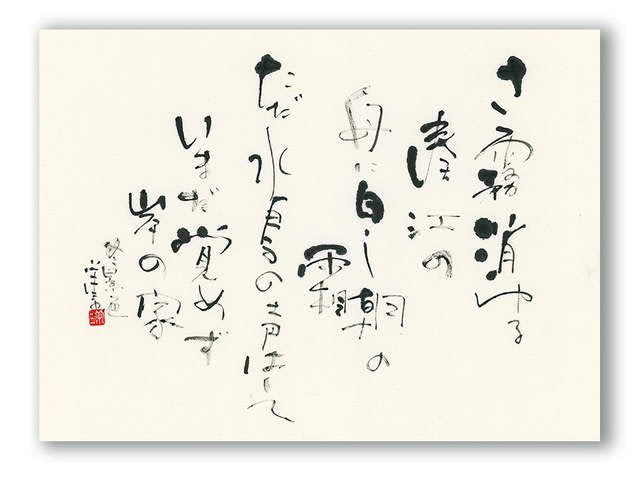日本近代文学の森へ (148) 志賀直哉『暗夜行路』 35 「放蕩まで」 「前篇第一 十」

2020.3.22
日記を書き終わった謙作は、妹の咲子に恋文を送ってよこした男に会おうとして氷川神社に出かけたのだが、それらしい男は現れなかった。
そこにいたのは妙にみすぼらしい若い男である。ひょっとしてコイツかと思って声をかけると、謙作を掲示と間違えてひどくおびえた。
とうとう謙作は前へ行って、
「誰か待ってるのか?」と訊いてみた。
若者は直ぐ返事が出来ないほどの恐怖を現わした。
その急にキョトキョトし出した様子で、謙作はやはりこの男だな、という気になった。
「何故、此処にいるんだ」
「まま待って……」と息を切らしながら、頭を振る事で後をおぎないながら、「いるんじゃない」と漸く続けた。自然に身体が震えている。眼がおびえ切っていた。二寸位に延びた薄い髪の毛は栄養不良から、まるで光沢がなく、手や足の皮膚はカサカサになって、白い粉を吹いていた。
「家はあるんです。箪笥町十九番地です」若者は謙作の怒ったような顔を凝っと見上げながら、あえぎあえぎいった。そしてほとんど無意識に親指の《ささくれ》をむしり出した。《ささくれ》からは血がにじみ出て来た。それでも痛さを感じないようになお無闇とむしった。若者は浮浪罪に問われる事から、すっかりおびえてしまったのだ。謙作を刑事と思ったのだ。
「浮浪罪」って初めて聞いたが、本当にあったのだ。昭和23年に廃止されたらしいけど、「一定の住居または生業なくして諸方に徘徊する者は、30日未満の拘留に処せられる」という規定で、かなり悪用・濫用されたらしい。こわいことだ。
結局男は現れず、迎えにきたお栄と一緒に家に帰った。家で待っていた宮本としばらく将棋をさす。
また霧のような雨が降り出した。二人は将棋をさした。そして五、六度さして、もう疲れ、盤の上も薄暗く、少し不愉快になった時に電気が来た。暫く考えて、いい考も出ずにいた謙作は「よそうか」といった。
「電気が来た」というのが面白い。この当時は、電気は時間制だったようだ。
「趣味家」(趣味人)の宮本と一緒に、「溜池から電車に乗って、新橋から銀座へ出た」。宮本は「袋物」に興味を持って、ウインドショッピングをする。この「袋物」って何のことだろう。紙入れとか、タバコ入れとかそういったものだろうか。そういうものに趣味がある男っていうのも、最近ではほとんどいないだろう。
途中にあった「台湾喫茶店」に、謙作は緒方がいそうな気がしたが、ほんとうにいたので、彼をひっぱりだして、三人で京橋の方へ歩いていった。まったく呑気な連中である。
謙作は、さっき氷川神社で見たみすぼらしい男がいったいどんな悲惨な生活を余儀なくされているかを想像すらできないのだ。
結局三人は他に行くところがなくて、またぞろ「清賓亭」へ行くことにした。
お加代は、仲間の女たちと、運送屋の「いい男」がどうのこうのと、「品のない」話をしている。
「Oさん、この間ね」といってお加代は笑い出した。「お清さんが露月町の方にそれはそれはいい男の散髪屋さんがいるっていうのよ。それをまた、よくきかずにこの人と出かけちゃったものよ。ところがどうしても家が知れなくて、一軒一軒散髪屋を覗いて歩いちゃった……」女二人は横眼を見合せ、顔を真赤にして笑った。その時のお加代の顔には、変に下等な感じが出ていた。謙作は或る不安から宮本の方を見た。宮本も謙作の方を見ていた。その顔には意地悪いような同情するような笑いを浮べていた。
お加代とお牧は図に乗って界隈の「いい男」の噂を始めた。運送屋の番頭もその一人だった。八百屋の息子というのもあった。自動車の運転手というのもあった。それを聴きながら宮本は露骨ににがにがしい顔を女たちに見せていた。
謙作の抱いた「或る不安」というのは、自分が「下等な女」と付き合っていると宮本に軽蔑されるんじゃないだろうかという不安だろう。
「西緑」や「清賓亭」にいる女たちは、そもそも「上等」な女ではないだろう。それでも、謙作は、そういう女たちにどこか「上等」さを求めていた、あるいは「上等な付き合い方」を求めていたのだといえるだろう。だからこそ、簡単には女たちと深い関係に入れなかったのだ。しかし、そんな謙作の拘りは、客観的にみれば馬鹿らしい拘りでしかなく、人間の欲望の前では、「上等」も「下等」もないのだが、謙作は、ギリギリそこに拘ることで、自分の矜持を保とうとしているかのようだ。
お加代は毎日昼前十時頃銭湯に行くと丁度空いている時で、誰もいないと両方に留桶を抱えてよく泳ぐというような話をした。
「この人はそりゃあ上手なんですよ」と傍からお牧がいった。
肉づきのいいこの大きな女が留桶を抱えて風呂の中で泳ぐ様子が謙作にはかなり不恰好な形で想像された。そしてその不恰好さがいやに肉感的に感じられた。お加代は瓦斯会社の工夫が大きな脚立を流しへ持ち込んで、損じた瓦斯燈が直ってからも何時までもぐずぐずしているので湯槽を出られなかったというような話を自身でも興味を持って話していた。
謙作は最初からお加代を品のいい女とは考えなかった。ただ投げやりな生々した所や、変にコケティッシュな所などに惹きつけられていた が、今日の余りに安価な感じから、すっかり気持を冷やされた。近よれば近よるほどこの感じは強くなりそうに思われた。
この点では初めて会った時が一番よかった。
「いい男」の話題で同僚と盛り上がったり、銭湯で泳いだりするというだけで、「下品」だとか「安価」だとか感じる謙作の感受性は、どうもよく分からないところだが、近寄れば近寄るほど相手のアラが見えてくるのは当然なことで、「初めて会った時が一番よかった。」なんて感想は、あまりに幼稚で笑えるほどだ。
そしてこの「十」は唐突に終わり、「十一」に入る。その冒頭は、「謙作が自分から放蕩を始めたのはそれから間もなくであった。」という一文である。
つまり、ここまでの謙作は「放蕩」をしてなかったのだ。つまり女と一度も「寝てない」のだ。(という解釈でいいのかしら。ちょっと不安だ。)「放蕩」の一歩手前で踏みとどまり、そこで「上等」だの「下等」だのと拘っていたにすぎないのだ。
ぼくがあまりにゆっくりと読んできたせいもあるだろうが、それにしても、長い長い「放蕩まで」である。岩野泡鳴なら一行でおわりだ。