前座無し。客は「気軽に笑おう!」のノリの人より、「芸を吟味する」タイプの人多し。そんな中、若手は頑張っていたと思います。
「粗忽の釘」林家たい平
引っ越したばかりの若夫婦。箒をかけるための釘を打ってくれと、女房が大工の旦那に頼む。この大工が粗忽者で、柱を逸れて壁に八寸釘を壁に打ち込んでしまった。薄い長屋の壁。先が隣家に突き出してしまったと思われるので謝りに行くが・・・。
オチは「明日からここに箒を・・・」まで。「粗忽な」「江戸っ子」の雰囲気が良く出ていました。本編も面白いが、マクラもやっぱり面白い。古典が板に付いてきたなあ。
「片棒」柳家花緑
金持ちの旦那が、身代を3人の息子のうち誰に継がせるかを悩み、「父(自分)の弔いをどうだすか」を提案させ、それで決めようとする。長男・次男は金のかかる葬儀を提案。そして三男は・・・。
前回は緊張気味だった花緑は、今日は落ち着いて会場を沸かせました。もうちょっとオチをスパッと決められるといいかもなあ。次男の「山車」のあたりが賑やかで面白かっただけに。
「道具屋」林家木久蔵
与太郎が叔父の勧めで道具屋を始める・・・。
前二人よりゆったりめのペース。違う席なら、この、ほのぼの加減も楽しいと思うけど、今日はそれが裏目に出たかなあ。噛み噛みだったこともあり、話が進まずもどかしい気分。今年の歌丸さんのあだ名は「生手羽先」だそうだ。
「稽古屋」桂小米朝
女にもてたい男が横丁の隠居に相談に行く。隠居は金がなければ芸の一つでも身につけた方がいい、踊りの師匠を紹介する。
人間国宝・米朝の息子。初めて聞きましたが、声も口跡も良く、とても聞きやすかったです。三味線との掛け合いも良く、音楽的(笑)。「蛍の踊り」がイイねえ。
「子は鎹」林家正蔵
吉原の女郎に入れあげ酒に酔い身なりも崩れ仕事もおろそかになった熊五郎は、女房子供に手を上げたあげく二人を追い出し女郎を後妻としたが、いまは改心し、後妻を追い出し仕事に精を出す日々。思い出すのは女房子供。ある日偶然子供に出会う・・・。
末広亭四月上席で聞きましたが、格段に上手くなっていました。狭い小屋より広めの舞台の方が良いのかなあ。いままで「こぶ」「こぶへー」「こぶちゃん」と言われていたのが、手のひらを返したように「正蔵師匠」と奉られる。でも、立場が人を作る場合もあるから、それも良いと思います。一層の精進を期待。
「粗忽の釘」林家たい平
引っ越したばかりの若夫婦。箒をかけるための釘を打ってくれと、女房が大工の旦那に頼む。この大工が粗忽者で、柱を逸れて壁に八寸釘を壁に打ち込んでしまった。薄い長屋の壁。先が隣家に突き出してしまったと思われるので謝りに行くが・・・。
オチは「明日からここに箒を・・・」まで。「粗忽な」「江戸っ子」の雰囲気が良く出ていました。本編も面白いが、マクラもやっぱり面白い。古典が板に付いてきたなあ。
「片棒」柳家花緑
金持ちの旦那が、身代を3人の息子のうち誰に継がせるかを悩み、「父(自分)の弔いをどうだすか」を提案させ、それで決めようとする。長男・次男は金のかかる葬儀を提案。そして三男は・・・。
前回は緊張気味だった花緑は、今日は落ち着いて会場を沸かせました。もうちょっとオチをスパッと決められるといいかもなあ。次男の「山車」のあたりが賑やかで面白かっただけに。
「道具屋」林家木久蔵
与太郎が叔父の勧めで道具屋を始める・・・。
前二人よりゆったりめのペース。違う席なら、この、ほのぼの加減も楽しいと思うけど、今日はそれが裏目に出たかなあ。噛み噛みだったこともあり、話が進まずもどかしい気分。今年の歌丸さんのあだ名は「生手羽先」だそうだ。
「稽古屋」桂小米朝
女にもてたい男が横丁の隠居に相談に行く。隠居は金がなければ芸の一つでも身につけた方がいい、踊りの師匠を紹介する。
人間国宝・米朝の息子。初めて聞きましたが、声も口跡も良く、とても聞きやすかったです。三味線との掛け合いも良く、音楽的(笑)。「蛍の踊り」がイイねえ。
「子は鎹」林家正蔵
吉原の女郎に入れあげ酒に酔い身なりも崩れ仕事もおろそかになった熊五郎は、女房子供に手を上げたあげく二人を追い出し女郎を後妻としたが、いまは改心し、後妻を追い出し仕事に精を出す日々。思い出すのは女房子供。ある日偶然子供に出会う・・・。
末広亭四月上席で聞きましたが、格段に上手くなっていました。狭い小屋より広めの舞台の方が良いのかなあ。いままで「こぶ」「こぶへー」「こぶちゃん」と言われていたのが、手のひらを返したように「正蔵師匠」と奉られる。でも、立場が人を作る場合もあるから、それも良いと思います。一層の精進を期待。

























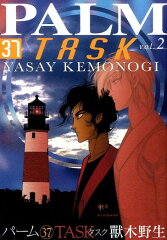

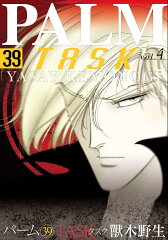
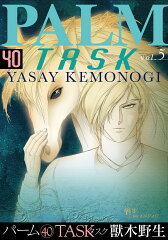
![Wings (ウィングス) 2013年 06月号 特別付録 永久保存版小冊子「プチ・パームブック」[雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61in8ViynvL._SL160_.jpg)


