 昨日、何かの媒体で見つけて気になっていた「長谷検校記念 くまもと全国邦楽コンクール」とやらを覗いてみようと熊本市民会館(僕はこの名でしか呼ばない)に行ってみた。すぐに僕の認識不足も甚だしいことに気がついた。イベント名に「くまもと」が付いているので、地元の手だれの奏者たちが集まって全国大会の地区予選でもやるのかな、くらいの気持だった。とんでもない!日本の邦楽界で既に第一線で活躍している人も全国各地から参加してくるほどの凄いレベルの大会だったのだ。参加者の力量の高さは素人の僕にでもよ~くわかった。そもそも長谷検校(ながたにけんぎょう)なる人物、名前だけはどこかで聞いた覚えがあったが、どういう人物なのか知らなかった。なんでも熊本出身で幕末から明治・大正時代に活躍し、九州系地歌を全国に普及させた、邦楽界では伝説的な人らしい。この人をリスペクトして熊本でこのコンクールが開かれているというわけだ。地歌とは上方で生まれた座敷音楽で、三味線を伴奏とする歌曲のことをいうのだそうだ。このコンクールは「箏曲の部」、「尺八・笛音楽の部」、「三味線音楽の部」、「琵琶楽の部」、「三曲等合奏の部」の五つの部門が行われ、全体のナンバー1が選ばれる。昨日は「箏曲の部」の佐藤亜美さん(東京)が最優秀賞に選ばれた。ただ、見ていて僕が気になったのは、こんな全国レベルの大会にもかかわらず観客が少ないことだ。なんだかもったいない気がする。基本的には邦楽そのものに対する市民の関心の低さがあると思うが、イベントのプロデュースのしかたにも問題があるような気がした。
昨日、何かの媒体で見つけて気になっていた「長谷検校記念 くまもと全国邦楽コンクール」とやらを覗いてみようと熊本市民会館(僕はこの名でしか呼ばない)に行ってみた。すぐに僕の認識不足も甚だしいことに気がついた。イベント名に「くまもと」が付いているので、地元の手だれの奏者たちが集まって全国大会の地区予選でもやるのかな、くらいの気持だった。とんでもない!日本の邦楽界で既に第一線で活躍している人も全国各地から参加してくるほどの凄いレベルの大会だったのだ。参加者の力量の高さは素人の僕にでもよ~くわかった。そもそも長谷検校(ながたにけんぎょう)なる人物、名前だけはどこかで聞いた覚えがあったが、どういう人物なのか知らなかった。なんでも熊本出身で幕末から明治・大正時代に活躍し、九州系地歌を全国に普及させた、邦楽界では伝説的な人らしい。この人をリスペクトして熊本でこのコンクールが開かれているというわけだ。地歌とは上方で生まれた座敷音楽で、三味線を伴奏とする歌曲のことをいうのだそうだ。このコンクールは「箏曲の部」、「尺八・笛音楽の部」、「三味線音楽の部」、「琵琶楽の部」、「三曲等合奏の部」の五つの部門が行われ、全体のナンバー1が選ばれる。昨日は「箏曲の部」の佐藤亜美さん(東京)が最優秀賞に選ばれた。ただ、見ていて僕が気になったのは、こんな全国レベルの大会にもかかわらず観客が少ないことだ。なんだかもったいない気がする。基本的には邦楽そのものに対する市民の関心の低さがあると思うが、イベントのプロデュースのしかたにも問題があるような気がした。
実行委員長の幸山熊本市長から表彰を受ける最優秀賞の佐藤亜美さん











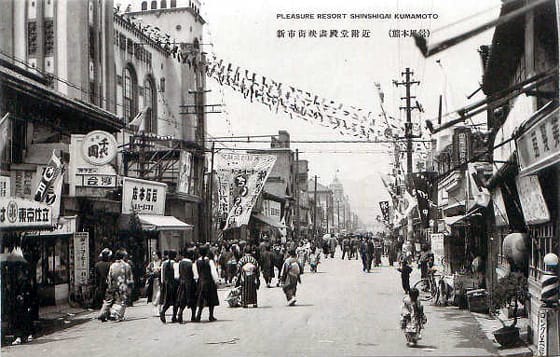




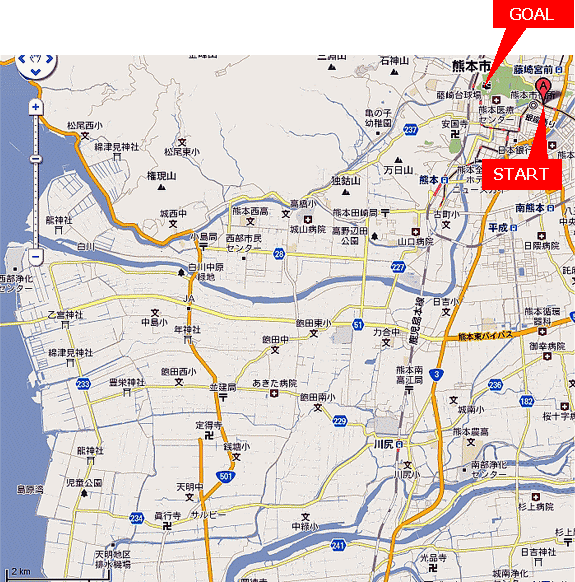
 昨日はテレサ・テンの十七回忌(没後16年)にあたる日だった。これまでも彼女の忌日には何度かブログに書き込んだ覚えがあるが、僕にとって80年代の想い出は彼女の歌とともにあると言っても過言ではない。彼女が日本デビューしたのは1973年で、日本レコード大賞新人賞を受賞した「空港」などのヒットもあったが、テレサ・テンの評価を確立したのは「つぐない」、「時の流れに身をまかせ」、「愛人」、「別れの予感」などのヒットを連発した84年以降で、なかでも「つぐない」がなければ今日のテレサ・テンの評価はなかっただろう。そして、この4曲を含め、テレサ・テンのヒット曲の多くを手がけたのが、作詞:荒木とよひさ(熊本市出身)、作曲:三木たかしのコンビだ。「つぐない」の「窓に西陽があたる部屋は いつもあなたの・・・」という有名な歌い出しは、今聞いても斬新で見事な情景描写だ。「自虐の詩」という映画で名取裕子が、西日のあたる部屋を「貧乏くせぇ~ッ!」と叫ぶシーンがあったが、まさにそんな生活の匂いがただよってきそうな秀逸な歌詞だと思う。
昨日はテレサ・テンの十七回忌(没後16年)にあたる日だった。これまでも彼女の忌日には何度かブログに書き込んだ覚えがあるが、僕にとって80年代の想い出は彼女の歌とともにあると言っても過言ではない。彼女が日本デビューしたのは1973年で、日本レコード大賞新人賞を受賞した「空港」などのヒットもあったが、テレサ・テンの評価を確立したのは「つぐない」、「時の流れに身をまかせ」、「愛人」、「別れの予感」などのヒットを連発した84年以降で、なかでも「つぐない」がなければ今日のテレサ・テンの評価はなかっただろう。そして、この4曲を含め、テレサ・テンのヒット曲の多くを手がけたのが、作詞:荒木とよひさ(熊本市出身)、作曲:三木たかしのコンビだ。「つぐない」の「窓に西陽があたる部屋は いつもあなたの・・・」という有名な歌い出しは、今聞いても斬新で見事な情景描写だ。「自虐の詩」という映画で名取裕子が、西日のあたる部屋を「貧乏くせぇ~ッ!」と叫ぶシーンがあったが、まさにそんな生活の匂いがただよってきそうな秀逸な歌詞だと思う。 今日は水前寺競技場で行なわれる「熊本レディース陸上大会」を観に行きたかったが、朝からいろんな用事が重なり行けなかった。そのかわりというわけでもないのだが、午後から「セイコーゴールデングランプリ川崎」がテレビで放送されたのでじっくり観戦した。期待の江里口匡史クンは、世界陸上の参加標準記録突破を期待したのだが、残念ながら今回もそれはならなかった。一方、女子の短距離陣は元気が良い。日本Aチーム(北風沙織、高橋萌木子、福島千里、市川華菜)は43秒39という日本新記録で走った。世界陸上や来年のロンドンオリンピックに期待をもてる。ただ、エースの福島千里がその後行なわれた100mで足に違和感を感じて途中で力を抜いたのが気になる。深刻な怪我でなければよいが。
今日は水前寺競技場で行なわれる「熊本レディース陸上大会」を観に行きたかったが、朝からいろんな用事が重なり行けなかった。そのかわりというわけでもないのだが、午後から「セイコーゴールデングランプリ川崎」がテレビで放送されたのでじっくり観戦した。期待の江里口匡史クンは、世界陸上の参加標準記録突破を期待したのだが、残念ながら今回もそれはならなかった。一方、女子の短距離陣は元気が良い。日本Aチーム(北風沙織、高橋萌木子、福島千里、市川華菜)は43秒39という日本新記録で走った。世界陸上や来年のロンドンオリンピックに期待をもてる。ただ、エースの福島千里がその後行なわれた100mで足に違和感を感じて途中で力を抜いたのが気になる。深刻な怪我でなければよいが。


 一昨日、映画「浮雲」のデジタルリマスター版がBSプレミアムで放送された。何度見てもこの映画は僕の心をとらえて離さない。この映画が公開されたのは昭和30年(1955)。僕がこの映画を初めて見たのは成人してからだからずっと後のことだ。しかし、小学4年生だった、この昭和30年のことは今でもよく思い出す。この年の7月、アメリカの進駐軍が上熊本駅から列車で帰って行った。僕はそれを上熊本駅の線路脇の立て杭越しに眺めていた。プラットフォームでは米兵とオンリーさんたちの泣き別れが繰り広げられていた。
一昨日、映画「浮雲」のデジタルリマスター版がBSプレミアムで放送された。何度見てもこの映画は僕の心をとらえて離さない。この映画が公開されたのは昭和30年(1955)。僕がこの映画を初めて見たのは成人してからだからずっと後のことだ。しかし、小学4年生だった、この昭和30年のことは今でもよく思い出す。この年の7月、アメリカの進駐軍が上熊本駅から列車で帰って行った。僕はそれを上熊本駅の線路脇の立て杭越しに眺めていた。プラットフォームでは米兵とオンリーさんたちの泣き別れが繰り広げられていた。


 この映画は観たことがなく、今回、デジタルリマスター版を放送するというので初めて観た。さすがに和田三造氏による衣裳デザインがアカデミー賞を受賞したという色彩は素晴らしい。美術的価値の高い映画であることは間違いない。1953年の公開時の映像を復元したというデジタルリマスター技術も素晴らしいが、それよりも何よりも、あの見事な衣装の数々を見ていると、今から800年も昔に、日本人が既にこんな色彩感覚を持っていたことはなんとも凄いとしか言いようがない。いったい日本人はいつ頃からこんな色彩感覚を持つようになったのだろうか。
この映画は観たことがなく、今回、デジタルリマスター版を放送するというので初めて観た。さすがに和田三造氏による衣裳デザインがアカデミー賞を受賞したという色彩は素晴らしい。美術的価値の高い映画であることは間違いない。1953年の公開時の映像を復元したというデジタルリマスター技術も素晴らしいが、それよりも何よりも、あの見事な衣装の数々を見ていると、今から800年も昔に、日本人が既にこんな色彩感覚を持っていたことはなんとも凄いとしか言いようがない。いったい日本人はいつ頃からこんな色彩感覚を持つようになったのだろうか。