
翻訳:有働薫
ジャン=ミッシェル・モルポア:1952年フランス生まれ。
青の歴史を誰かが書くかもしれません。(リルケ)
そして人々は山々の頂きや、海の波、川のゆったりした流れ、大洋の循環、そして天体の運行を感嘆して眺め、自分自身を忘れてしまうのです。(聖アウグスティヌス)
この上記の二文は、この詩集の扉にあたかも「予言」のように置かれています。「リルケ」の言葉は「クララ」に送った手紙の1節です。訳者の解説によれば、それに応えるかのようにジャン=ミッシェル・モルポアの「青の物語」は書かれたようです。このように時を越えた詩人の出会いがとても嬉しい。そしてこのようにして「詩」が引き継がれてゆくことも。この詩集は海と人間との絶え間ない対話なのだと思えます。そしてその「海」に青の言葉を捧げ続ける詩人の絶えることのない作業の連続であるように思えます。その作業はとても勤勉であり、大変美しく均衡のとれた言葉の構築でありました。そしてモルポアは「人間が生きる。」ということのすべてを書き尽くしてみようと試みたのではないか?とさえ思えます。(以下、抜粋&引用です。)
* * *
海はわれらの内で文章を書こうとする。
この青のすべてが苦悩なしとは思うな。
空の本質は不思議なやさしさでできている。
明日という日は、こんなに野蛮な身振りをし、こんなに汗をかき、青白く期待をかける価値が十分あるのだから。
どこまでも青は逃亡する。
おまえは海に行き、おのれの憂愁で洗われる。/その青と折り合いをつける。
言葉はときおり身を投げる。
海の上に、長い斜めの縞になって降ってくる温かい、灰色の雨。ほんのお湿りほどの雨で、雨音は聞こえない。彼女は、雨を避ける場所を探しもせず、顔を雨に差しのべる。雨が静かなので、彼女は自分がここにいることを知り、感じる。彼女は言う――雨は彼女にみずからを捧げてくれ、あるいは彼女自身気づかなかったこの優しさを、単調で自由なこの落下運動を、そして哀しみで彼女から潮が退いていらい、もはや彼女のものではなくなっているこのような軽やかな波立ちを呼び戻してくれるのだと。(註:ここがエピローグです。)
* * *
リルケのソネットについて考える日々のなかで、大分以前に読んだこの詩集を思い出したのでした。しかし数年後にまたこの詩集を開く時、きっとわたくしは別の詩行を選ぶかもしれません。「青の物語」とはそのように永い時間を息づくであろうと思われる詩集なのです。
モルポアの「青」とは、ラヴレターの色、エンマ・ボヴァリーが行きずりの行商人から買うリボンの色、あるいは彼女がルドルフとともに出発することを夢みた幌付二輪馬車の日除けの色、海の色、処女マリアの色、そして西洋的内面性のキー・カラーだとされる。
(1999年・思潮社刊)










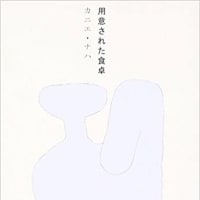









日本の夏の稲の色を「青田」という感覚でみると意味は同じですね。
最後に「イザベラ」への手紙のなかでは「こうして書いている間にも、海の響きが僕の所までのぼって来ます。」と書かれていますね。
トニオ・クレーガーの最後も、同じ終わりかたをします。主人公は、友達のロシア人の画家、リザヴェータ・イヴァノーヴナに手紙を書きます。そうして、
「こうして手紙を書いていると、海の音が、わたしのところまで響いてきます。そうして、わたしは眼を閉じるのです。....」
不思議な符合。
Nun, wie das Gruene, das Blaue heisse,
duerfen wir frange: sie kanss, sie kanns!
さて、こういうわけで、緑のものが、青いものを意味するとしようか、そのように、わたしたちは質問することがゆるされる(大地に、それができるのだろうか?):大地は、それができる、大地は、それができる。
これを田口、生野、ご両名は、どのように訳しているのでしょうか。目暗ら、蛇におぢずのわたくしです。
実は、この意味はまだ思案中なのです。でも、青つながり。
いまぼくらは あの緑 あの青が何なのかと
たずねてもいい。彼女にはできる、できるとも!
生野訳
今こそ、緑は何か、青は何か、と、
ぼくたちは訊いていい。彼女はできる、彼女はできるさ!
とりあえず、これだけ書いておきます。
「彼女」は「大地」のこと。明日にでも、この全訳を掲載します。
構文の理解は、おふたりの方が正しい。
そこで、わたしの散文訳は、次のようになります。
さて、こういうわけで、緑のものの名前は何か、青いものの名前は何か、そのように、わたしたちは質問することがゆるされる(大地に、それができるのだろうか?):大地は、それができる、大地は、それができる。
この「名前」という訳はステキだと思います。