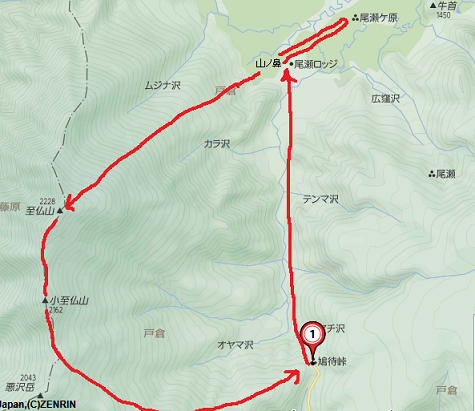8月30日(金)
【続き】
3.自然と人間の対峙

▲ ツール・ド・フランス 2007 307X218.9
ツールドフランスとは毎年7月にフランスで行なわれる世界的に有名な自転車ロードレース。この映像画は山岳コースにさしかかった時のもののようだ。見物者、報道陣の人とクルマが延々と下から上に伸びているのが良く見える。一般的には、自然の雄大さvs人間のちっぽけさが、我々の好む感動的絵画のテーマによくなる。しかし人間の歴史は、物理的に自然を克服してきた歴史でもある。しかし、その克服・対峙の有り様は、現代の人間群集が一斉に行動を起こすと、神の目といおうか俯瞰(ふかん)的視点からは、なんかこっけいな姿に見えないだろうか?

▲ ライン川Ⅱ 1999 42.9X71.4
大型の映像画が多い中、これは比較的小ぶりの作品。しかし、この作品は2011年11月クリスティーズ・ニューヨークで、現役作家の写真作品としては史上最高額の約433万ドル(当時のレートで約3億4千万円)で落札された!!もの。
水量を一杯にさざ波を立てきらめきながら流れるライン川。緑の土手とコンクリートの道が横に走る。上には薄灰色の空が雲とともに広がる。これも人間の自然との対峙(治水)の有り様を描いたといえる。
グルスキーは、より美しい画面を作りあげるために川の対岸に密集する建築物をデジタル技術によって消し去ったとか。それにより抽象度の高い、グルスキーが到達した崇高な世界が広がったと、パンフレットに書いてある。
しかし、オレだってと思って今日の帰り道に撮った、お茶畑と道路と向こうに小学校と空。これだってグルスキー風だろう? え、自然との対峙が足りないって? じゃ、小学校を削除しようか(笑)。
 お茶畑(拡大クリック)
お茶畑(拡大クリック)
4.幾何学的な美しさ

▲ カミオカンデ 2007 228.2X367.2
これは、岐阜県飛騨市の神岡鉱山の地下1000mにあるニュートリノ検出装置、スーパーカミオカンデを題材にしている。地下深く埋められた巨大な円筒形のタンクは、純水を蓄え、内側は光電子倍管とよばれる無数のセンサーで覆われている。円形の空間の中で、黄金色の光が均質的に広がっていく無機質な眺めは、最先端の科学に導かれる現代社会のこれからの有り様を示唆するものではないか。
しかし、圧倒的な幾何学的文様は、それだけで美しい。結晶とか、分子、原子等の自然界の根本的有り様も、幾何学的フォルム。美は幾何学に戻る?

▲ バーレーンⅠ 2005 306X221.5
金に飽かして砂漠の地に作り上げた高速道路。幾何学的文様の極致。しかし、本線と幅広い路肩が複雑に織なし過ぎて、どこがどうなのか判らない。ここを走ったら、ナビも絶対混乱する(笑)。

▲ スキポール空港 1994 61.5X76.4
私も利用したことのある非常に機能的なオランダの空港。空港ビルに入っている顧客との商談のために、日本から日帰り!で往復したことがある。 遠近法が強調された構図。平坦な内部のグリッド状の床。外部に拡がる芝生と滑走路、さらに遠くの風景も自然に右側に収れんしていく。明るく透明感の満ち溢れた空間で、私の大好きなイメージだ。
****************
■ グルスキー画・魅力の秘密
彼の映像画の特徴として、1.パノラマ的細密性、2.人間集団の重視、3.自然と人間の対峙、4.幾何学的美しさ、の4つに私が便宜的に分類。そのうえで、それぞれの特徴を表す代表的な映像画を、今回展示された65作品の内、公開画像を用いて示してみた。
しかし、彼の映像画が「写真のようであって写真ではない」所以は、写真の被写体(題材)の選び方のユニーク性はもとよりなのだが、むしろそのデジタル処理にある。ネタバレ的になるため、この話題はこの後半に持ち越した。その秘密とは。
1.複数の焦点を持つ写真の合成
我々の目は、一点を見つめるとそこに焦点が集中して、その周りの対象物は意識に上らないようになっている。カメラは、焦点を合わせたところ以外の周りは映らないわけではないが、焦点はぼけてくる。グルスキーの映像画は、近くも遠くも焦点があっている。即ち細部までが均等にクリアなのだ。これは、おそらく複数のカメラで左右、遠近を同時に撮って、のちに一つに合成しているはずだ。
バンコクでの家具作りの作業場の画像も、実際の作業場はあんなに大きい必要はないし、おそらく巧妙に張り合わせていったのだろうと思う。
2.まったく無いもの追加、有るものの削除、の修正
ストップピットの中央のレースクイーンの二人は恐らく、他のシーンからの切り抜き追加だろう。ストップピットに彼女達が待機している必要性がないからだ。いた方が、もちろん画像としては面白いが。
コレクションでのモデルさん達も、顔、髪型等を子細に眺めると同一人物とみなされる者が数名いる。恐らく、違う写真での同一人物を貼り付けたのだろう。
写真の合成、修正で作り出された画像は現実ではない。恐ろしく手間暇を掛けて作り出された虚構なのだ。「アートは現実をそのまま写し出すべきではない」というグルスキーの言葉は正しいだろう。
3.最終映像画へ至る自らのイメージの独創性
しかし、デジタル写真の合成、修正のコンピューター技術を持っていたところで、彼のような映像画を制作できたであろうか。無理だ。できない。例えば、カミオカンデの制作では、もとの写真には水は張ってなかったという。そこへ、コンピューター技術で水を張り、船頭の乗る船まで浮かばせる思いつきが必要だ。そのことにより、単なるグラフイックアートではない、深淵、神秘的なイメージの物語性を持った画像ができた。
1.俯瞰的センス、2.集団的人間への感度、3.自然の撮りこみ方のセンス、4.幾何学的な美意識等の、事前イメージングセンスがなければできない。
余談ではあるが、グルスキーの集団的人間へのセンス、幾何学的な構造への美意識などは、ドイツ的な特徴ではないかと思う。先日NHKのBS歴史館で、ヒットラーのもとで、ベルリンオリンピックの記録映画等を制作したレニ・リーフェンシュタールの伝記を観た。ナチスの宣伝映画には違いないがその美術的映像の価値は今でも評価が高い。空を背景に躍動する選手へのカメラの追い方は、計算された構図そのものだった。
 民族の祭典
民族の祭典
************
最後に、アンドレアス・グルスキー氏にご登場願おう。

▲ 1955年に旧東ドイツのライプツイヒで生まれ、幼少期に西ドイツへ移住。
1977年から1980年まで、エッセンのフォルクヴァング芸術大学でヴィジュアル・コミュニケーションを専攻し、その後、1980年から1987年まで、デュッセルドルフ芸術アカデミーで写真界の巨匠ベルトン・ベッヒャーに師事した。
グルスキーは2001年にニューヨーク近代美術館で大規模な個展を開催し、一躍世界にその名が知られるようになった。
現在、ポンピドウセンター(パリ)、テート(ロンドン)、ニューヨーク近代美術館をはじめとする世界の主要美術館が彼の作品を所蔵している。
*************
さあ、全部観た。出よう。

▲ 出口には、カミオカンデの複製画像が同一サイズで掲げてあり、ここの前だけは写真が撮ることができた。
「そう、そのポーズで・・」
(となりの若者が言っていた)

▲ 出口の前には、休憩用のチェアが並んでいる。。
縦・横の無機質の構図に、集団で無言で休む人間たち。背景に青い空がのぞく。
うん、グルスキー的シーンだ!! パシャ。
2階に上ってみる。見下ろすと。。

▲ 点在する丸テーブル。幾何学的文様だ。そこにおもいおもいに座る個々の人間たち。
食事を買い求めるために列をなす人達。上下の距離を感じさせる立体的構図。
うん、これもグルスキー的だ!! パシャ。
オレの感性もインスパイヤーされて、なんか磨かれてきたなあー (笑)

▲ 国立新美術館を出る。日本で5番目の国立美術館として2007年1月に開館。
黒川紀章の最後の設計だった。
ありがとうよ。初めての美術館、そしてアンドレアス・グルスキーさん。
精進するよ。
了
アンドレアス・グルスキー展 HP
関連日記 :写真展「梅佳代展 UMEKAYO」を観て
【続き】
3.自然と人間の対峙


▲ ツール・ド・フランス 2007 307X218.9
ツールドフランスとは毎年7月にフランスで行なわれる世界的に有名な自転車ロードレース。この映像画は山岳コースにさしかかった時のもののようだ。見物者、報道陣の人とクルマが延々と下から上に伸びているのが良く見える。一般的には、自然の雄大さvs人間のちっぽけさが、我々の好む感動的絵画のテーマによくなる。しかし人間の歴史は、物理的に自然を克服してきた歴史でもある。しかし、その克服・対峙の有り様は、現代の人間群集が一斉に行動を起こすと、神の目といおうか俯瞰(ふかん)的視点からは、なんかこっけいな姿に見えないだろうか?

▲ ライン川Ⅱ 1999 42.9X71.4
大型の映像画が多い中、これは比較的小ぶりの作品。しかし、この作品は2011年11月クリスティーズ・ニューヨークで、現役作家の写真作品としては史上最高額の約433万ドル(当時のレートで約3億4千万円)で落札された!!もの。
水量を一杯にさざ波を立てきらめきながら流れるライン川。緑の土手とコンクリートの道が横に走る。上には薄灰色の空が雲とともに広がる。これも人間の自然との対峙(治水)の有り様を描いたといえる。
グルスキーは、より美しい画面を作りあげるために川の対岸に密集する建築物をデジタル技術によって消し去ったとか。それにより抽象度の高い、グルスキーが到達した崇高な世界が広がったと、パンフレットに書いてある。
しかし、オレだってと思って今日の帰り道に撮った、お茶畑と道路と向こうに小学校と空。これだってグルスキー風だろう? え、自然との対峙が足りないって? じゃ、小学校を削除しようか(笑)。
 お茶畑(拡大クリック)
お茶畑(拡大クリック)4.幾何学的な美しさ


▲ カミオカンデ 2007 228.2X367.2
これは、岐阜県飛騨市の神岡鉱山の地下1000mにあるニュートリノ検出装置、スーパーカミオカンデを題材にしている。地下深く埋められた巨大な円筒形のタンクは、純水を蓄え、内側は光電子倍管とよばれる無数のセンサーで覆われている。円形の空間の中で、黄金色の光が均質的に広がっていく無機質な眺めは、最先端の科学に導かれる現代社会のこれからの有り様を示唆するものではないか。
しかし、圧倒的な幾何学的文様は、それだけで美しい。結晶とか、分子、原子等の自然界の根本的有り様も、幾何学的フォルム。美は幾何学に戻る?

▲ バーレーンⅠ 2005 306X221.5
金に飽かして砂漠の地に作り上げた高速道路。幾何学的文様の極致。しかし、本線と幅広い路肩が複雑に織なし過ぎて、どこがどうなのか判らない。ここを走ったら、ナビも絶対混乱する(笑)。

▲ スキポール空港 1994 61.5X76.4
私も利用したことのある非常に機能的なオランダの空港。空港ビルに入っている顧客との商談のために、日本から日帰り!で往復したことがある。 遠近法が強調された構図。平坦な内部のグリッド状の床。外部に拡がる芝生と滑走路、さらに遠くの風景も自然に右側に収れんしていく。明るく透明感の満ち溢れた空間で、私の大好きなイメージだ。
****************
■ グルスキー画・魅力の秘密
彼の映像画の特徴として、1.パノラマ的細密性、2.人間集団の重視、3.自然と人間の対峙、4.幾何学的美しさ、の4つに私が便宜的に分類。そのうえで、それぞれの特徴を表す代表的な映像画を、今回展示された65作品の内、公開画像を用いて示してみた。
しかし、彼の映像画が「写真のようであって写真ではない」所以は、写真の被写体(題材)の選び方のユニーク性はもとよりなのだが、むしろそのデジタル処理にある。ネタバレ的になるため、この話題はこの後半に持ち越した。その秘密とは。
1.複数の焦点を持つ写真の合成
我々の目は、一点を見つめるとそこに焦点が集中して、その周りの対象物は意識に上らないようになっている。カメラは、焦点を合わせたところ以外の周りは映らないわけではないが、焦点はぼけてくる。グルスキーの映像画は、近くも遠くも焦点があっている。即ち細部までが均等にクリアなのだ。これは、おそらく複数のカメラで左右、遠近を同時に撮って、のちに一つに合成しているはずだ。
バンコクでの家具作りの作業場の画像も、実際の作業場はあんなに大きい必要はないし、おそらく巧妙に張り合わせていったのだろうと思う。
2.まったく無いもの追加、有るものの削除、の修正
ストップピットの中央のレースクイーンの二人は恐らく、他のシーンからの切り抜き追加だろう。ストップピットに彼女達が待機している必要性がないからだ。いた方が、もちろん画像としては面白いが。
コレクションでのモデルさん達も、顔、髪型等を子細に眺めると同一人物とみなされる者が数名いる。恐らく、違う写真での同一人物を貼り付けたのだろう。
写真の合成、修正で作り出された画像は現実ではない。恐ろしく手間暇を掛けて作り出された虚構なのだ。「アートは現実をそのまま写し出すべきではない」というグルスキーの言葉は正しいだろう。
3.最終映像画へ至る自らのイメージの独創性
しかし、デジタル写真の合成、修正のコンピューター技術を持っていたところで、彼のような映像画を制作できたであろうか。無理だ。できない。例えば、カミオカンデの制作では、もとの写真には水は張ってなかったという。そこへ、コンピューター技術で水を張り、船頭の乗る船まで浮かばせる思いつきが必要だ。そのことにより、単なるグラフイックアートではない、深淵、神秘的なイメージの物語性を持った画像ができた。
1.俯瞰的センス、2.集団的人間への感度、3.自然の撮りこみ方のセンス、4.幾何学的な美意識等の、事前イメージングセンスがなければできない。
余談ではあるが、グルスキーの集団的人間へのセンス、幾何学的な構造への美意識などは、ドイツ的な特徴ではないかと思う。先日NHKのBS歴史館で、ヒットラーのもとで、ベルリンオリンピックの記録映画等を制作したレニ・リーフェンシュタールの伝記を観た。ナチスの宣伝映画には違いないがその美術的映像の価値は今でも評価が高い。空を背景に躍動する選手へのカメラの追い方は、計算された構図そのものだった。
 民族の祭典
民族の祭典************
最後に、アンドレアス・グルスキー氏にご登場願おう。

▲ 1955年に旧東ドイツのライプツイヒで生まれ、幼少期に西ドイツへ移住。
1977年から1980年まで、エッセンのフォルクヴァング芸術大学でヴィジュアル・コミュニケーションを専攻し、その後、1980年から1987年まで、デュッセルドルフ芸術アカデミーで写真界の巨匠ベルトン・ベッヒャーに師事した。
グルスキーは2001年にニューヨーク近代美術館で大規模な個展を開催し、一躍世界にその名が知られるようになった。
現在、ポンピドウセンター(パリ)、テート(ロンドン)、ニューヨーク近代美術館をはじめとする世界の主要美術館が彼の作品を所蔵している。
*************
さあ、全部観た。出よう。

▲ 出口には、カミオカンデの複製画像が同一サイズで掲げてあり、ここの前だけは写真が撮ることができた。
「そう、そのポーズで・・」
(となりの若者が言っていた)

▲ 出口の前には、休憩用のチェアが並んでいる。。
縦・横の無機質の構図に、集団で無言で休む人間たち。背景に青い空がのぞく。
うん、グルスキー的シーンだ!! パシャ。
2階に上ってみる。見下ろすと。。

▲ 点在する丸テーブル。幾何学的文様だ。そこにおもいおもいに座る個々の人間たち。
食事を買い求めるために列をなす人達。上下の距離を感じさせる立体的構図。
うん、これもグルスキー的だ!! パシャ。
オレの感性もインスパイヤーされて、なんか磨かれてきたなあー (笑)

▲ 国立新美術館を出る。日本で5番目の国立美術館として2007年1月に開館。
黒川紀章の最後の設計だった。
ありがとうよ。初めての美術館、そしてアンドレアス・グルスキーさん。
精進するよ。
了
アンドレアス・グルスキー展 HP
関連日記 :写真展「梅佳代展 UMEKAYO」を観て
























 iPodとiTunes画面
iPodとiTunes画面
 (←トラックじゃ・笑)
(←トラックじゃ・笑)




 柔らかい肉塊と固めの肉皮の部分が舌の上で軽やかに交互に感じられるのが、目新しい食感。
柔らかい肉塊と固めの肉皮の部分が舌の上で軽やかに交互に感じられるのが、目新しい食感。

 (ここをクリックしてもだめだよ・笑)
(ここをクリックしてもだめだよ・笑)