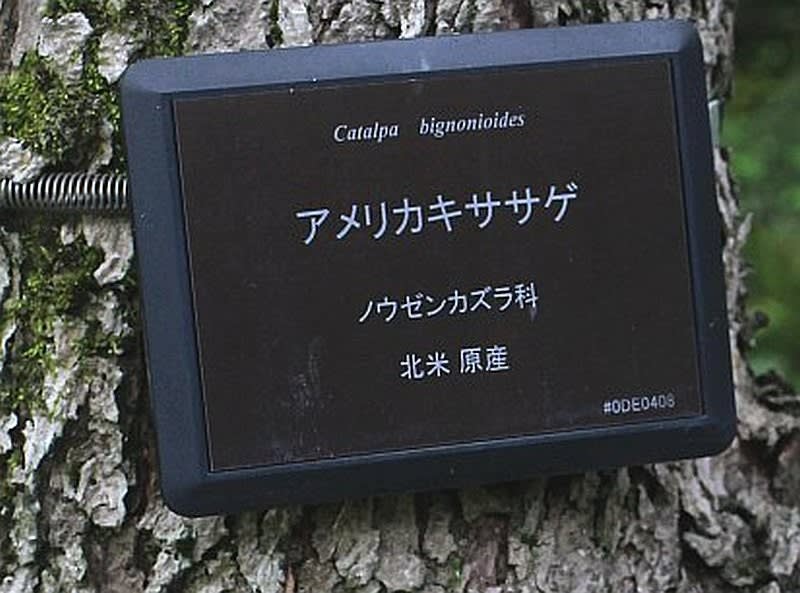午前と午後2回の散歩で出会ったカヤツリグサの仲間です。
「イネ科とカヤツリグサ科は風媒花として進化し、そのため互いに似た点が多い。それは花が地味なこと、小穂を形成することなどである。そのため、見た目の派手な特徴に乏しく、その割に種類が多くて同定が難しい。植物観察では相手にされることが少なく、敬遠されることが多い点でも共通している。」(wiki 「カヤツリグサ科」)
名前は とりあえず Google Lens で確認しました。
タマガヤツリ

タマガヤツリは「くす玉のような穂」から。

「花序は花茎の先端に一つだけつく。穂の単位は軸に小穂が並んだ形であるが、軸がごく短縮しているので、全体は丸っこいくす玉のように見える。」(wiki 「タマガヤツリ」)


「小穂は線形、長さ3-10mm、幅1mmと小さく、暗紫褐色を帯びる。個々の鱗片ではその竜骨が黄緑なので、全体では暗紫褐色のものに緑の縁取りがあるように見え、花序全体の色合いを複雑に見せている。」(同上)

コアゼガヤツリ

小穂は扁平、線形、長さ5〜10mm、紅色を帯び、10〜25個の花を密につける。鱗片は広倒卵形、褐色、長さ約1.5mm、鈍頭、中肋は緑色、凸頭で外反しない。そう果は長さ約0.7mm。花柱の長さはそう果の半分以下。柱頭は3個。(岡山県カヤツリグサ科植物図譜)(松江の花図鑑「コアゼガヤツリ」)

「花序は長さ5-10cmくらいの枝が10-20も出て、それらは時に花茎の先端からくす玉のように広がる。この数は小型のカヤツリグサの中では多いものである。それぞれの枝の先端に2-3個ほど頭状に集まり、あるいはさらに短く枝が出てその先に小穂をつける。」(wiki 「コアゼガヤツリ」)



カヤツリグサ

「小穂は平らで細長く、多少褐色を帯びる。小穂が小軸からやや大きい角度で突き出し、それがずらりと並んでブラシのようになったものが茎の先端から伸びた柄の先にいくつかついて、そういう柄が茎の先端から数本伸びたものが花序を形成している。茎の先端に直についた穂もある。」(wiki 「カヤツリグサ」)

「花は小穂の鱗片の中に収まり、雌しべを雄しべが取り囲むだけの簡単なもの。雌しべは成熟して果実になると、鱗片とともに脱落する。」(同上)



ヒメクグ

「花茎の先端に、丸っこいくす玉のような穂を、1個つけるのが特徴である。」(wiki 「ヒメクグ」)

「花序は多数の小穂が頭状に集まったもので、ほぼ球形のものが一つだけ(まれに2~3個)である。」(同上)



ハマスゲ

「ハマスゲは単子葉植物カヤツリグサ科カヤツリグサ属の植物である。スゲと名が付いているがスゲ属ではない。乾燥したところにもよく育つ多年草である。」(wiki 「ハマスゲ」)

「小穂は線形で長さ1.5-3cm程度、互いにやや寄り合って数個ずつの束を作る。小穂の鱗片は血赤色で艶があるが、やや色が薄い場合もある。」(同上)

「乾燥に強く、日ざしの強い乾いた地によく成育する。砂浜にも出現し、名前もこれによるものであるが、実際には雑草として庭や道端で見かけることの方が多い。」(同上)


ヒデリコ

「カヤツリグサ科テンツキ属の植物」(wiki 「ヒデリコ」)

「花序は散状になり、長さは8cmになる。何度も枝分かれして非常に多くの小穂をつける。」(同上)

「小穂は2.5-3mm程度と小さく、球形に近い楕円形で、錆褐色。鱗片は卵形で長さ1mm。」(同上)


.
「イネ科とカヤツリグサ科は風媒花として進化し、そのため互いに似た点が多い。それは花が地味なこと、小穂を形成することなどである。そのため、見た目の派手な特徴に乏しく、その割に種類が多くて同定が難しい。植物観察では相手にされることが少なく、敬遠されることが多い点でも共通している。」(wiki 「カヤツリグサ科」)
名前は とりあえず Google Lens で確認しました。
タマガヤツリ

タマガヤツリは「くす玉のような穂」から。

「花序は花茎の先端に一つだけつく。穂の単位は軸に小穂が並んだ形であるが、軸がごく短縮しているので、全体は丸っこいくす玉のように見える。」(wiki 「タマガヤツリ」)


「小穂は線形、長さ3-10mm、幅1mmと小さく、暗紫褐色を帯びる。個々の鱗片ではその竜骨が黄緑なので、全体では暗紫褐色のものに緑の縁取りがあるように見え、花序全体の色合いを複雑に見せている。」(同上)

コアゼガヤツリ

小穂は扁平、線形、長さ5〜10mm、紅色を帯び、10〜25個の花を密につける。鱗片は広倒卵形、褐色、長さ約1.5mm、鈍頭、中肋は緑色、凸頭で外反しない。そう果は長さ約0.7mm。花柱の長さはそう果の半分以下。柱頭は3個。(岡山県カヤツリグサ科植物図譜)(松江の花図鑑「コアゼガヤツリ」)

「花序は長さ5-10cmくらいの枝が10-20も出て、それらは時に花茎の先端からくす玉のように広がる。この数は小型のカヤツリグサの中では多いものである。それぞれの枝の先端に2-3個ほど頭状に集まり、あるいはさらに短く枝が出てその先に小穂をつける。」(wiki 「コアゼガヤツリ」)



カヤツリグサ

「小穂は平らで細長く、多少褐色を帯びる。小穂が小軸からやや大きい角度で突き出し、それがずらりと並んでブラシのようになったものが茎の先端から伸びた柄の先にいくつかついて、そういう柄が茎の先端から数本伸びたものが花序を形成している。茎の先端に直についた穂もある。」(wiki 「カヤツリグサ」)

「花は小穂の鱗片の中に収まり、雌しべを雄しべが取り囲むだけの簡単なもの。雌しべは成熟して果実になると、鱗片とともに脱落する。」(同上)



ヒメクグ

「花茎の先端に、丸っこいくす玉のような穂を、1個つけるのが特徴である。」(wiki 「ヒメクグ」)

「花序は多数の小穂が頭状に集まったもので、ほぼ球形のものが一つだけ(まれに2~3個)である。」(同上)



ハマスゲ

「ハマスゲは単子葉植物カヤツリグサ科カヤツリグサ属の植物である。スゲと名が付いているがスゲ属ではない。乾燥したところにもよく育つ多年草である。」(wiki 「ハマスゲ」)

「小穂は線形で長さ1.5-3cm程度、互いにやや寄り合って数個ずつの束を作る。小穂の鱗片は血赤色で艶があるが、やや色が薄い場合もある。」(同上)

「乾燥に強く、日ざしの強い乾いた地によく成育する。砂浜にも出現し、名前もこれによるものであるが、実際には雑草として庭や道端で見かけることの方が多い。」(同上)


ヒデリコ

「カヤツリグサ科テンツキ属の植物」(wiki 「ヒデリコ」)

「花序は散状になり、長さは8cmになる。何度も枝分かれして非常に多くの小穂をつける。」(同上)

「小穂は2.5-3mm程度と小さく、球形に近い楕円形で、錆褐色。鱗片は卵形で長さ1mm。」(同上)


.