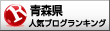先日行われたカブの収穫の様子です。
とはいっても大きな畑ではなくプランターです。
3〜4人の班を作り、一班に10個ぐらいのプランターを貸し出し
好きな品種のカブを栽培してもらいました。
農業高校なのにプランターとはまるで小学生の体験学習のようですが
環境システム科は施設園芸を学ぶ学科。
つまり彼らの学習の舞台は温室なのです。
そんなこともあって生物生産科のように大きな畑を持っていません。
カブの栽培は春に一度体験し、秋は2回目。
作業も慣れているはずですが、秋は思ったより大きくなりませんでした。
おそらくこの秋は、いつもより気温が低かったからかもしれません。
もし生物生産科だったら減収は大きなダメージだと思いますが
この科目ではあまり気にしません。
なぜなら欲しいのはお金ではなく、生産販売に関するデータだからです。
この科目は、売上原価や販売管理費などの経費と売上高の関係など
経営や商業的な知識を学ぶのが目的。
座学で学ぶこともできますが、それではなかなかピンときません。
そこで実際に生産販売してもらい、
そのデータを使って具体的に学べるようにしているのです。
したがって栽培するものは何でもOK。
今年はたまたまカブだったというわけです。
収穫したカブやダイコンを洗う作業はこたえます。
気がつくときれいに色づいていた木々の葉も落ち始め
冬に向かおうとしています。
とはいっても大きな畑ではなくプランターです。
3〜4人の班を作り、一班に10個ぐらいのプランターを貸し出し
好きな品種のカブを栽培してもらいました。
農業高校なのにプランターとはまるで小学生の体験学習のようですが
環境システム科は施設園芸を学ぶ学科。
つまり彼らの学習の舞台は温室なのです。
そんなこともあって生物生産科のように大きな畑を持っていません。
カブの栽培は春に一度体験し、秋は2回目。
作業も慣れているはずですが、秋は思ったより大きくなりませんでした。
おそらくこの秋は、いつもより気温が低かったからかもしれません。
もし生物生産科だったら減収は大きなダメージだと思いますが
この科目ではあまり気にしません。
なぜなら欲しいのはお金ではなく、生産販売に関するデータだからです。
この科目は、売上原価や販売管理費などの経費と売上高の関係など
経営や商業的な知識を学ぶのが目的。
座学で学ぶこともできますが、それではなかなかピンときません。
そこで実際に生産販売してもらい、
そのデータを使って具体的に学べるようにしているのです。
したがって栽培するものは何でもOK。
今年はたまたまカブだったというわけです。
収穫したカブやダイコンを洗う作業はこたえます。
気がつくときれいに色づいていた木々の葉も落ち始め
冬に向かおうとしています。