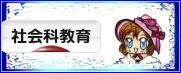約2年ぶりの,「新☆歴史模擬授業」の再開です。
お待たせして,失礼いたしました。
新☆歴史模擬授業です。産業革命2です。
詳細は、この前の記事(ご注意)をご覧ください。
*わかりやすく解説したいので、「こういう説もある!」という専門的なことを
引き合いに出されてもお答えできないことがあるかもしれません。申し訳ありません。
不快な気持ちになった方には申し訳ありません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
キンコーンカンコーン
 「さて,今回で市民革命の授業は終了です。」
「さて,今回で市民革命の授業は終了です。」
 「はい!長かったなぁ。」
「はい!長かったなぁ。」
 「市民革命とは,簡単に言えば,社会の主役が,一般の人(市民)に変わった,ということだと前に話したね。
「市民革命とは,簡単に言えば,社会の主役が,一般の人(市民)に変わった,ということだと前に話したね。
一部の特権階級(貴族)だけが政治をするのでなく,市民が政治に参加できるように変えたのが,
イギリスの清教徒革命(ピューリタン革命)と名誉革命,そして,フランスのフランス革命。
イギリスという国の支配から,その国に住むアメリカ人が自分の国の政治をする形にしたアメリカ独立戦争。
そして,機械の発明や改良によって,それまでは各地域で主に手作業で生産し,そこでずっと暮らしていた生活から,
機械工場に各地に住んでいたみんなが集まって都市に人口が集中するような生活形態に変わったのが産業革命だったね。」
 「そうだったね。」
「そうだったね。」
 「前回は,産業革命の光の部分をお話しました。今日は,闇の部分をやります。」
「前回は,産業革命の光の部分をお話しました。今日は,闇の部分をやります。」
 「え?闇?」
「え?闇?」
 「世の中,良いことの裏には,かならず,裏があり,栄光をつかむ人の裏では犠牲になった人がいる。」
「世の中,良いことの裏には,かならず,裏があり,栄光をつかむ人の裏では犠牲になった人がいる。」
 「たしかに・・。」
「たしかに・・。」
 「産業革命で汽船や機関車により輸送能力を高まり,大量に外国に輸出することも楽になった。
「産業革命で汽船や機関車により輸送能力を高まり,大量に外国に輸出することも楽になった。
それにより,製鉄業・造船業・機械工業などの重工業がさかんになり,
そこで働く人々が必要となるので、工場がある場所に人口が増える。
そのように人口が増えた場所が都市(都会)になって・・・とね、
そして、工場で作った製品を外国に売って儲けて、
どんどんイギリスは豊かになっていく,と前回お話したね。」
 「そうだったね。」
「そうだったね。」
 「では,それにより,苦しい生活に変わった人もいることを,これから話します。」
「では,それにより,苦しい生活に変わった人もいることを,これから話します。」
 「ついに産業革命の闇の部分が登場か・・。」
「ついに産業革命の闇の部分が登場か・・。」
 「まず,資本家と労働者,という言葉を説明します。そうした方が,後々分かりやすくなるから。
「まず,資本家と労働者,という言葉を説明します。そうした方が,後々分かりやすくなるから。
資本家は,簡単に言うと,社長や会長などの,会社や工場の経営者のことです。(細かいことを言うと,異なる点もあります。)
そして,その資本家に雇われて,その人の会社(工場)で働く人を労働者,と言います。」
 「資本家が会社や工場のトップで,そこで働く人が労働者ってことね。」
「資本家が会社や工場のトップで,そこで働く人が労働者ってことね。」
 「そういうことね。」
「そういうことね。」
 「では本題にいきますね。
「では本題にいきますね。
産業革命が起こったあと,機械を使って大きな工場を経営する資本家が,どんどん力を持つようになった。
たとえば,仮にAという製品を工場で大量生産し,それで儲けることができるようになった,とするね。
それでその工場の資本家は金持ちになる。
でもさ,よく考えて。
Aという製品は,産業革命が起こる以前から,人々には使われていた。
ということは,産業革命で工場で新たにAを作り始める前からAを作っていた人はどうなるんだろうね?」
 「あー,たしかに。」
「あー,たしかに。」
 「産業革命前,だから,おそらく動力を使う機械でAは作ってないよね?
「産業革命前,だから,おそらく動力を使う機械でAは作ってないよね?
ということは,手(や足などの身体)だけか,簡単な道具も使ってAを生産する人(手工業者)はいたはずだ。」
 「そうか!そうだよね。」
「そうか!そうだよね。」
 「工場で作ったAは安く大量生産できるけど,手作業だと作る量は限られるし,値段も高くなってしまう。
「工場で作ったAは安く大量生産できるけど,手作業だと作る量は限られるし,値段も高くなってしまう。
そうすると,それを買ってくれる人は少なくなってしまう。」
 「・・ということは,そのように生産していた人(手工業者)は,お金を稼げなくなって,失業してしまうよ!」
「・・ということは,そのように生産していた人(手工業者)は,お金を稼げなくなって,失業してしまうよ!」
 「そのとおり!」
「そのとおり!」
 「それで,職を失った手工業者は,自分を失業に追い込んだ工場で,労働者として働くことになっていく。」
「それで,職を失った手工業者は,自分を失業に追い込んだ工場で,労働者として働くことになっていく。」
 「なんか・・時代の流れだよね・・。」
「なんか・・時代の流れだよね・・。」
 「工場では,職を失った手工業者や農民が働くようになった。
「工場では,職を失った手工業者や農民が働くようになった。
でも,その労働条件が,とてつもなく悪いものだった。」
 「どんな風に悪かったのかな?」
「どんな風に悪かったのかな?」
 「まずは,賃金(働いてもらえるお金)が十分でなかった。」
「まずは,賃金(働いてもらえるお金)が十分でなかった。」
 「それは問題だ!」
「それは問題だ!」
 「さらに,働く時間。
「さらに,働く時間。
1日10数時間にのぼる労働時間。
今は,1日8時間くらいが一般的(休み時間含む)。」
 「そう考えると,長い・・。」
「そう考えると,長い・・。」
 「僕のお父さんが,仮に朝9時から仕事を初めて,10時間労働だと考えると,夜7時まで・・。うーん,長いよ。」
「僕のお父さんが,仮に朝9時から仕事を初めて,10時間労働だと考えると,夜7時まで・・。うーん,長いよ。」
 「それでは,仕事に行って,家で寝て,また仕事・・になって休む暇がないよ。」
「それでは,仕事に行って,家で寝て,また仕事・・になって休む暇がないよ。」
 「さらに,賃金の安い女性や子供まで働かせていた。」
「さらに,賃金の安い女性や子供まで働かせていた。」
 「え!子供まで!」
「え!子供まで!」
 「しかも,炭坑など,いつ上が崩れてくるかわからない,とっても危ない場所で働かせて,事故も多発。」
「しかも,炭坑など,いつ上が崩れてくるかわからない,とっても危ない場所で働かせて,事故も多発。」
 「ひどい!」
「ひどい!」
 「労働者が住んでいる場所も,せまくて不衛生な住宅だった。
「労働者が住んでいる場所も,せまくて不衛生な住宅だった。
他のところに引っ越したくても,安い賃金しかもらえない。
だから,そこに住み続けるしかなかった。」
 「生きるために働いているのか,働くために生きているのかわからない状態だね・・。」
「生きるために働いているのか,働くために生きているのかわからない状態だね・・。」
 「そこで,我慢の限界に達した労働者は立ちあがった!」
「そこで,我慢の限界に達した労働者は立ちあがった!」
 「おおお!」
「おおお!」
 「労働者は,労働組合という労働者たちで組織した団体をつくって,
「労働者は,労働組合という労働者たちで組織した団体をつくって,
賃金の引き上げや労働時間の短縮など労働条件の改善を求める労働運動を始めたのです。」
 「がんばれ!労働者!」
「がんばれ!労働者!」
 「この労働問題は,すぐ,簡単に解決はしなかったけど,徐々によくなっていきます。」
「この労働問題は,すぐ,簡単に解決はしなかったけど,徐々によくなっていきます。」
 「不満があるなら戦うことで,良くなることもあるんだね。」
「不満があるなら戦うことで,良くなることもあるんだね。」
 「そうね。私は,このように,弱い立場の人たちが戦う歴史は好きよ。
「そうね。私は,このように,弱い立場の人たちが戦う歴史は好きよ。
自分が辛い立場にあるときに私も負けずにがんばろ!って思えるから。」
 「歴史は,人が集まってつくったものだから,自分と同じ気持ちを持った歴史人物(人々)から勇気がもらえるよね。」
「歴史は,人が集まってつくったものだから,自分と同じ気持ちを持った歴史人物(人々)から勇気がもらえるよね。」
 「そうね。歴史は,私のカウンセラー!」
「そうね。歴史は,私のカウンセラー!」
 「では,お話を元に戻しますね。先ほどまで話したのは,国内のお話。今度は国外のお話。
「では,お話を元に戻しますね。先ほどまで話したのは,国内のお話。今度は国外のお話。
産業革命はイギリスだけで起こったものではなく,
イギリスのあと,ヨーロッパ諸国のさまざまな国に産業革命が起こります。(日本も)
産業革命に成功した国々は,もっと稼げないか?を考える。
1つの製品で儲けを出すには,売った値段(と売れた量)から,
その製品の原料や諸経費,労働者への賃金,などを差し引いたもの。
儲けを出すために,労働者の賃金を低くして,労働問題が起こったことはさっき話したね。」
 「はい。」
「はい。」
 「さらに,その製品をつくる原料も安く作れないか?と考えた。
「さらに,その製品をつくる原料も安く作れないか?と考えた。
さらさらさらに,自分たちが工場で大量生産したものを,自分の国の住人に売るには人口の限界がある。
そこで,他の国に自分の国で作ったものを売ったら,さらに儲かる!と思った。」
 「たしかに!」
「たしかに!」
 「しかも,彼らは,自分たちの言うことを聞くような国をつくって,さらに儲けようとする。
「しかも,彼らは,自分たちの言うことを聞くような国をつくって,さらに儲けようとする。
自分たちが有利になるように設定した価格で,ほぼ強制的に買わせれ,儲けはさらにアップするから。」
 「・・・・。」
「・・・・。」
 「このように,強制的に自分たちの言うこと聞かせる国(地域)を植民地と言います。
「このように,強制的に自分たちの言うこと聞かせる国(地域)を植民地と言います。
詳しく言うと,植民地を支配している国(本国)に原料を供給したり,本国が生産したものを買う市場,であり,
かつ,政治をする権利は本国にあり自分たちにはないところになります。」
 「つまり,植民地とは,経済的にも政治的にも力がなく,本国の奴隷,・・。」
「つまり,植民地とは,経済的にも政治的にも力がなく,本国の奴隷,・・。」
 「そうね。理解力があるね。」
「そうね。理解力があるね。」
 「えへへ。」
「えへへ。」
 「産業革命に成功した国は,アジア・アフリカ・中南米に次々と植民地を作っていきます。
「産業革命に成功した国は,アジア・アフリカ・中南米に次々と植民地を作っていきます。
植民地を作る,と言っても,「今日から,ここはうちの植民地」と言うだけで植民地をつくるわけではありません。
もしそうしたら,植民地になった国の国民の反発だけでなく,自分もそこを植民地にしたい,とねらっていた他の国も反対するから・・。
そこで,彼らは,国内での反乱などをおさえる目的で国に入り,そのまま,徐々にその国を支配して・・,という形をとっていきます。」
 「こわい・・。」
「こわい・・。」
 「植民地化されていった国は,とてもたくさんあります。
「植民地化されていった国は,とてもたくさんあります。
その中で,かつては大国であった国も植民地になっていく。
その大国であった国の植民地化,について,次回お話していきますね。」
 「はい。」
「はい。」
 「今回は,言葉では労働組合・労働運動,の2語くらいしか,あまり試験には出ないけど,
「今回は,言葉では労働組合・労働運動,の2語くらいしか,あまり試験には出ないけど,
理解してもらうために色々お話しました。また,この部分から次回に続く内容は,現代の我々が反省すべき内容がたくさんあります。」
 「色々と考えさせられたな~。」
「色々と考えさせられたな~。」
 「ではでは,今日はここまで。起立・礼!」
「ではでは,今日はここまで。起立・礼!」


 「ありがとうございました!」
「ありがとうございました!」
キンコーンカンコーン
ーーーーーーーー
わかりやすく解説したいので、「こういう説もある!」という専門的なことを
引き合いに出されてもお答えできないことがあるかもしれません。申し訳ありません。
不快な気持ちになった方には申し訳ありません。
ーーーーーーーーー
ランキングに参加しております。ぽちっと押して頂けるとうれしいです。