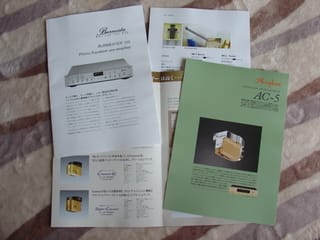今回試聴できた機器の中で印象に残ったものを挙げていきたい。まずはデンマークの
RAIDHO ACOUSTICS社のスピーカー、
X Monitor。広帯域リボン型トゥイーターユニットと、セラミック製のコーンによる中低音ユニットによるコンパクト型2ウェイだが、とにかく音場の広さには圧倒させられた。スピーカーの周りの空間までもが朗々と歌いまくるという、得難い再現性を持つ機種だ。定価は約55万円だが、一度気に入ったら長く鳴らし込みたくなる製品だと思う。
X Monitorをドライヴさせていたアンプが
APRIL MUSIC社の
Stello Ai500という機種。何と韓国のメーカーである。 他のスピーカー群と繋げて聴いたわけではないのでアンプ単体のキャラクターは把握しきれてはいないが、なかなか駆動力のある製品であることは確かだ。洗練されたデザインも相まって、所有欲をくすぐる機器である。
米国
ANTHONY GALLO ACOUSTICS社のスピーカー、
The Reference 3.5も面白い製品だ。まるでオブジェのようなスタイリッシュな外観。低音ユニットが横向きに付けられているせいか、音場の展開が巧みだ。左右に棚引く音響空間の創造性には、誰もが聴き入ってしまうだろう。
独
MUSIKELECTRONIC GEITHAIN社のスピーカーは昨年(2010年)秋のオーディオフェアでも試聴したが、今回はスタジオモニター用の高級機である
RL 901に接することが出来た。前回聴いた比較的低価格の民生用機はあまり印象に残らなかったが、このRL 901は優れ物だ。バランスの良いモニター的サウンドなのだが、音の一つ一つが芳醇で楽器や声の響きが味わい深い。パワーアンプ内蔵型のアクティヴ・スピーカーで、意外と使いこなしは難しくなさそうである。民生用として本機を元にした
ME901KAという機種もリリースされる予定とのことで、それも機会があれば聴いてみたい。
英国
Harbeth社のスピーカーは毎回試聴しているが、今回は勝手が違う。例年ではスウェーデンの
PRIMARE社のアンプでドライヴしていたのだが、同社の日本での販売権が切れたせいか、国産の
ACCUPHASEのアンプを使用していた。ところが、印象が前回までと全然違うのである。奥ゆかしい柔らかさに、パッと明るい積極性が加わった。アンプをチェンジしただけでこうも変わるものかと驚いた次第。これならばジャズやクラシックはもちろん、ロック系でもイケそうだ。考えてみると私のメイン・システムのアンプもACCUPHASEだし、Harbeth社のスピーカーは次のグレードアップの有力候補になりそうである。
米国
McIntosh社は古くから高級アンプ類の作り手として知られているが、珍しく今回はスピーカーを大々的にアピールしていた。最近リリースしたXRT2Kである。中高音ユニットを縦にズラッと並べた奇態なデザインで、正直サランネットを外した様子は見ていて“引く”ものがある(笑)。しかし、音は実に正攻法だ。明るく開放的だが、余計なケレン味はない。聴感上はフラットで、十分な分解能を確保している。
昔からMcIntoshのアンプは色彩感のあるパワフルな音というイメージがあるが、それは同社のアンプが
JBLや
ALTECといった典型的な西海岸サウンドのスピーカーとペアで鳴らされることが多かったからだと思う。McIntosh自体は元々は東部のメーカーだ。XRT2Kのキャラクターも含めて、明朗なハイスピード系の音は、
THIELや
MAGICOといった最近のアメリカの“主流派”(?)にも通じるものがある。McIntoshのアンプも汎用性は高い。いつか欧州ブランドのスピーカーを繋げて聴いてみたいものだ。
ハリウッドにある世界屈指のレコーディングスタジオ「オーシャンウェイ・レコーディング」のオーナー兼エンジニアが開発したモニターシステムが、
OCEAN WAY MONITORSである。フェア会場ではそのハイエンドモデル
HR-2が展示されていた。
高さが190センチほどある大型スピーカーに加え、専用イコライザーとクロスオーバーを含めて800万円強にも達する高額商品。ユニットごとのマルチ駆動に必要なアンプと、それに見合ったプレーヤーなどを用意すると2千万円は軽く超えるシステムになる。音の方だが、カラリと晴れ渡ったウエストコースト・サウンドだ。しかも圧迫感や特定周波数帯域の不自然な強調感もない。屈託のない押し出しの良さに加え、音場の奥行きは恐ろしく深く、音楽情報の全てを引き出そうという感じのサウンド・デザインである。これを一般家庭に入れようというユーザーはめったにいないだろうが(笑)、今回聴けただけでも有意義だった。
イタリアの
SONUS FABER社のスピーカーの音は、明るくて色気がある。新製品の
AMATI futuraを試聴することが出来たが、本当に魅力的だ。ドイツ・オーストリア系のオーケストラの音色が、いつの間にか指揮者だけイタリア人に交替したような感じになってしまうのは御愛嬌だが(爆)、それも許してしまえるほどの吸引力がある。仕上げも実に美しい。
独
QUADRAL社のスピーカーは以前のフェアでハイエンド機の
TITANや上級機の
ORKANなどを試聴したことがあったが、今回聴いたのはそれらより安い
WOTANである(とはいってもペアで50万円だが ^^;)。ORKANよりもユニットサイズが小さい分だけ低域の量感は抑えられるが、その代わりに中高域の小気味良さが印象付けられる。このメーカーの製品を聴いていつも思うのだが、真の意味で“万人向き”というのは、こういう音ではないだろうか。広いレンジ感を持ち、明るく滑らか。絶対にイヤな音を出さない。音場展開も自然そのものだ。同じドイツ製の
ELACと比べると知名度では相当に落ちるが、もっと知られて良いブランドだ。
国産のスピーカーの新製品としては、
SONYが2010年末にリリースした
SS-NA2ESのデモが行われていた。重量が1本32kgのトールボーイ型で、ユニットにも筐体にも作りに手間暇を掛け、にもかかわらずペア40万円弱という、それだけ聞くとかなりのコストパフォーマンスを確保していると言える。しかし、出てくる音にはまったく感心しない。全体的にキッチリと作られてはいるのだが、まろやかさや艶・色気・温度感・空気感・明るさといった音楽鑑賞に必要なファクターは皆無(おまけに、高域にヘンな強調感がある)。もちろん“色気だの何だの、そんなのは不要だ! 解像度と情報量とレンジの広さだけがあれはばいい!”と切って捨てるユーザーも多いことは想像に難くないが、少なくとも私は家庭でこの音を聴きたくはない。
別のブースで鳴っていた
PIONEER(およびそのハイエンドブランドの
TAD)のスピーカーも、同様に無機的で楽しくない音しか出ていない。日本の大手メーカーのスピーカー開発者は、もっとコンサートに足繁く通ったり、自分で楽器を手にするなどして、音楽に接する機会を多く持つべきである。
(この項つづく)