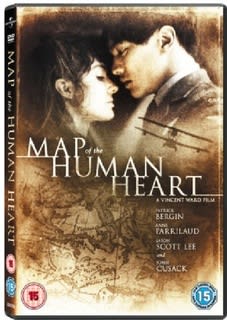(原題:WONDER WOMAN)予想を上回る面白さで、鑑賞後の満足度は高い。矢継ぎ早に作品を投入し、駄作はあるが快作も確実に存在するMARVEL陣営に比べ、DCコミック側は感心しない展開が目立っていたのだが、本作の登場によって状況が変わってきた。次なる「ジャスティス・リーグ」のシリーズにもいくらか期待が持てる。
古代より女性だけのアマゾン族が暮らすパラダイス島で、ようやく誕生したプリンセスのダイアナは、快活で好奇心旺盛だが島の外の世界を知らずに育った。そんなある日、彼女は島に漂着したアメリカ人パイロットのスティーヴを助ける。折しも外界では第一次大戦の真っ最中。スティーヴを追って島に侵攻しようとしたドイツ軍を撃退したダイアナ達だが、彼からドイツが大量破壊兵器を開発して世界を脅かそうとしていることを聞き、ダイアナはこれは軍神アレスの仕業だと確信。世界を救うため、二度と島には戻れないと知りながら彼女はスティーヴと共にロンドンへ赴く。
まず、舞台を戦時中に持ってきたのが勝因だ。各国が自前の正義を振りかざし、殺戮行為を正当化していた時代。そんな混迷の中にあって、ダイアナの“アレスを倒せばすべて解決する”という考え方も、結局は戦争当事者達の(表向きの)スローガンと一緒である。そんな一面的な考え方から、戦争および人間の行動様態の実相が解明されていくという筋書きは、ヒロインの“成長”ともシンクロし、かなりの効果を上げている。
そして何と言っても主演のガル・ガドットだ。堂々とした体躯と群を抜くルックス。しかも、若干の天然ぶりと可愛らしさをも感じさせ、これ以上には無いと思える起用である。アクション場面も文句なしで、特に塹壕から飛び出してドイツ軍に向かって突撃していくシークエンスは、胸が躍った。
スティーヴに扮するクリス・パインも絶好調。“パッと見た感じは軽量級だが、実は熱血漢”という役柄を上手く表現していた。そしてパトリック卿を演じたデイヴィッド・シューリスもさすがの海千山千ぶりだ。監督のパティ・ジェンキンスは何と「モンスター」(2003年)以来の仕事になるが、かなり上達した様子が窺える。
まあ、終盤の敵の首魁とのバトルが他のヒーロー映画とあまり変わらない展開になったり、マッドサイエンティストの女性化学者(エレナ・アナヤ)の掘り下げが浅かったりと欠点もあるのだが、勢いのある作劇の前にあっては気にならなくなってくる。
マシュー・ジェンセンのカメラによる戦場のリアルで寒々とした光景や、ルパート・グレグソン=ウィリアムズの音楽も要チェック。今後の「ジャスティス・リーグ」の出来がどうなるかは分からないが、ワンダーウーマンに限っては心配御無用といったところだろう。