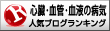MICS=側方小開胸アプローチでは、特有のリスクがありますが、心筋保護についても注意しなくてはならない点があります。これはMICSに限ったことではありませんが、この心筋保護が不十分だったせいで術後のLOSになる可能性について議論になったことから、筆者なりの考察をまとめてみました。
①MICS、とくにMICS-MVPにおいては、大動脈遮断が必ずしも理想的な位置を選べない可能性があり、遮断鉗子の先端を術者の手で位置確認できずブラインドになっている状態で遮断することになります。これによって遮断が不十分になる可能性があり、この場合、ルートカニューラから心筋保護液を注入しても遮断から漏れた血液と混合されて不十分な心筋保護となる可能性があります。この現象は何度か経験し、遮断鉗子を追加したり遮断位置を変更することで解決できました。これを各地することは、なかなか心筋保護が聞かず、心電図上の心静止が得られない、一度心静止しても直ぐに心電図波形が出てしまうなどの現象で築きますが、それ以前に遮断鉗子をかけた心筋保護液を注入する前に、ルートカニューラの側枝から逆流がないかを確認することが重要です。側枝のないシングルルーメンのルートカニューラを採用してる施設では一度連結をはずして、逆流がないかを確認する必要があり、やはり側枝のあるカニューレを採用すべきと思いました。大動脈弁閉鎖不全症など、大動脈切開を最初から行う手術では、遮断不十分に関してはすぐに判明しますが、その場合でもできれば遮断が十分か確認してから大動脈切開したいものです。遮断不十分に関しては、経食道エコーで判明する可能性もありますがちょうど見えにく位置にあるため必ず同定できるものではありません。慣れた麻酔科医なら言わずとも指摘してくれることがあります。
②大動脈弁逆流があると、冠動脈に十分に心筋保護液が行かずに左室内に逃げてしまう。特に左房左室ベントを引きすぎるとこの大動脈弁逆流が増加しやすいのでベント流量を下げるなどの対応が必要です。術前に大動脈弁逆流が指摘されていなくとも遮断するとバルサルバ洞が変形して逆流が起こることもあります。これに関しては経食道エコーでも観察可能です。当院ではMICSにおいては初回は通常量の2倍の心筋保護液を注入することで確実な心筋保護を行っています。
③僧帽弁手術の場合、リトラクターをかけて僧帽弁視野を確保したまま心筋保護液を注入すると、バルサルバ洞が変形していて大動脈弁逆流が増加し、十分な心筋保護液が冠動脈に注入されないリスクがあります。毎回リトラクターをゆるめるなどの工夫が必要です。また、僧帽弁の手技に時間がかかり、毎回の注入間隔を適切に行えないと、これもまたLOSの原因となるリスクがあります。注入間隔の管理はME(CE)さんが担当していることが多いと思いますが、外科医とME(CE)さんとのコミュニケーションがうまくいっていない施設ではトラブルが起こりやすい印象があります。
④特に僧帽弁手術では、水テストを行う際にエアーがバルサルバ洞にたまり、そのエアーが注入されて冠動脈内にエアーブロックが起きて十分な心筋保護液が注入されない、不均等な灌流となる可能性があります。特に右冠動脈口周辺のバルサルバ洞にエアーがたまりやすいので注入のたびにエアー抜きを十分行う必要がありますが、側枝のないルートカニューラを採用している施設では、エアー抜きが出来ない可能性があり注意が必要です。
⑤冠静脈洞から逆行性心筋保護を併用してする場合では、逆行性心筋保護を過信しないことが重要です。冠静脈洞から注入される心筋保護液の血流分布はかならずしも均等ではなく、亜型が多く一定の割合で左室領域には灌流できない症例があると言われています。かならず一定の間隔で順行性を併用すべきです。多くの施設に手術のお手伝いに伺う機会がありますが、なかなかこの逆行性だけで手術を乗り切ろうとする施設が時々遭遇し、このことをお伝えしても改善しない施設があり、術後のLOSの原因と思われるのに想起できない外科医も少なくないことを経験しています。
⑥特に、PLSVC(左上大静脈遺残)がある症例では、逆行性心筋保護は無効です。必ず術前のCTでPLSVCがないことを確認する必要があります。正中開胸では、このPLSVCを遮断して逆行性心筋保護注入を行うことがありますが、遮断してもその遮断部位から冠静脈洞合流部までの間の部分がリザーバーのように拡張して十分な心筋保護液が灌流されないリスクもあり、ましてや右小開胸アプローチからはPLSVC遮断は不可能です。
⑦こうした心筋保護のトラブルが発生した場合の対処としては、麻酔科、ME(CE),外科医のコミュニケーションが重要です。ナースも含めた手術チーム全体のコミュニケーションが普段から良好な関係を作っていないと適切な対処が困難です。昔気質の怒鳴る外科医は最近は減っているようですが、このような外科医のチームではそれだけでリスクを抱えている、と考えられます。